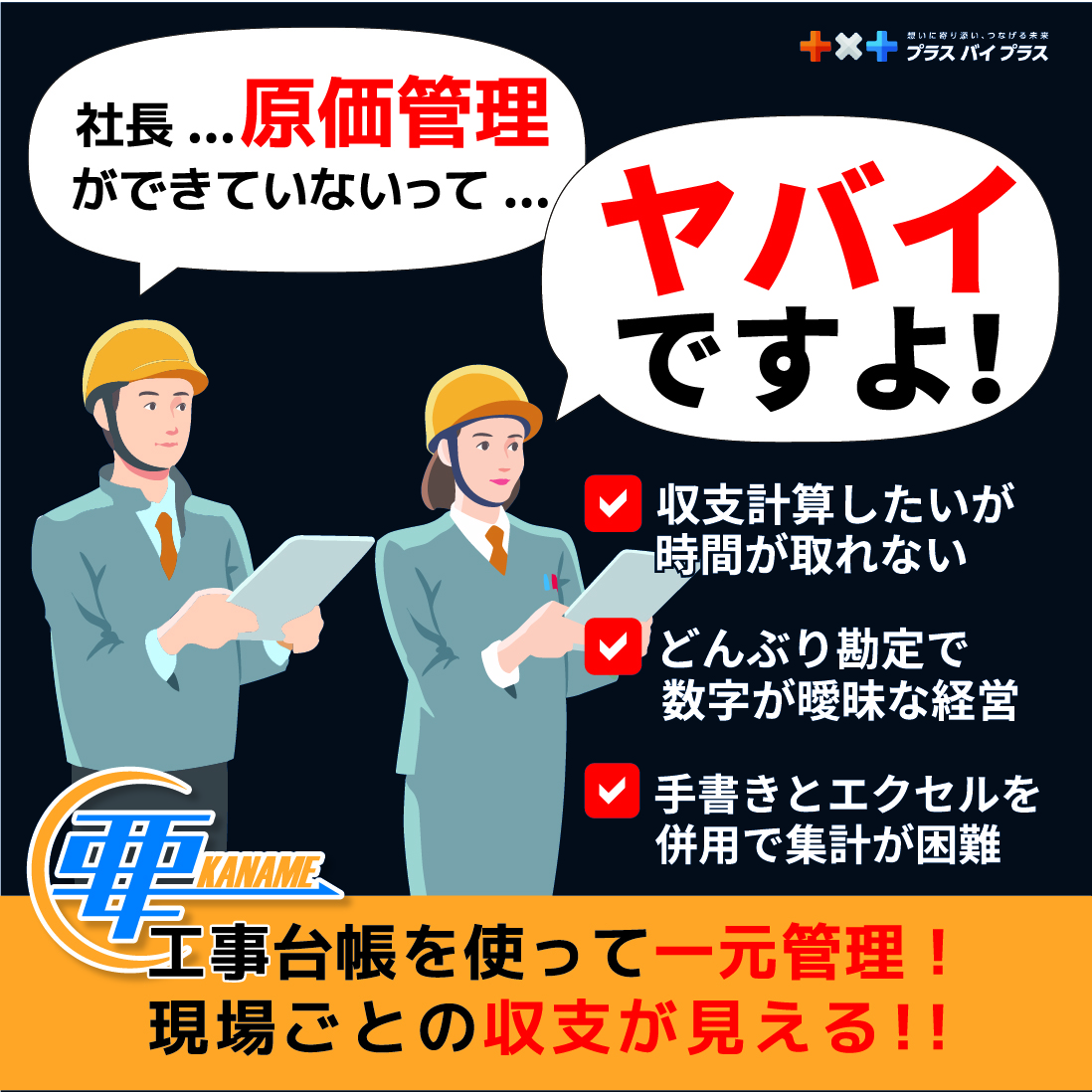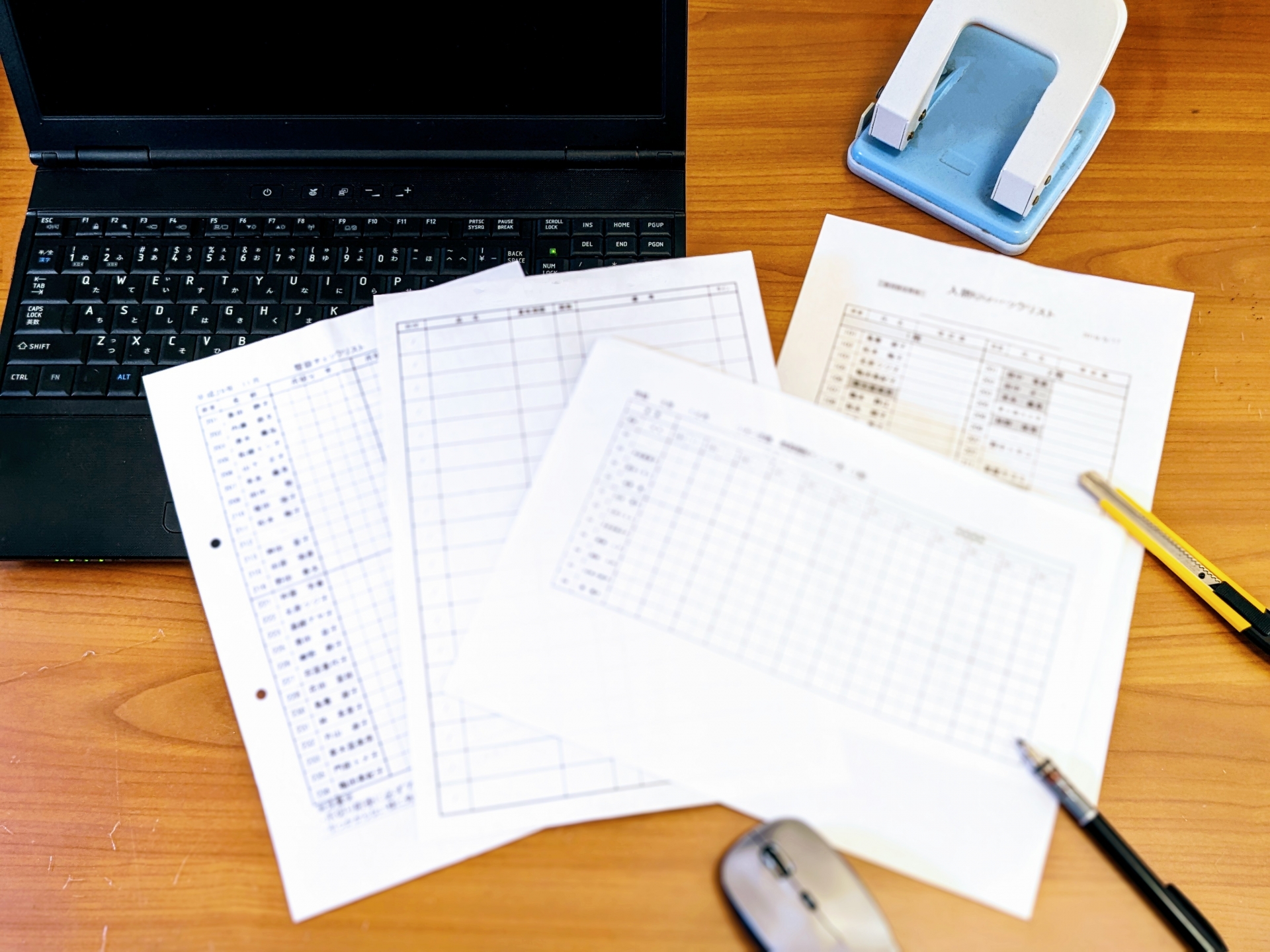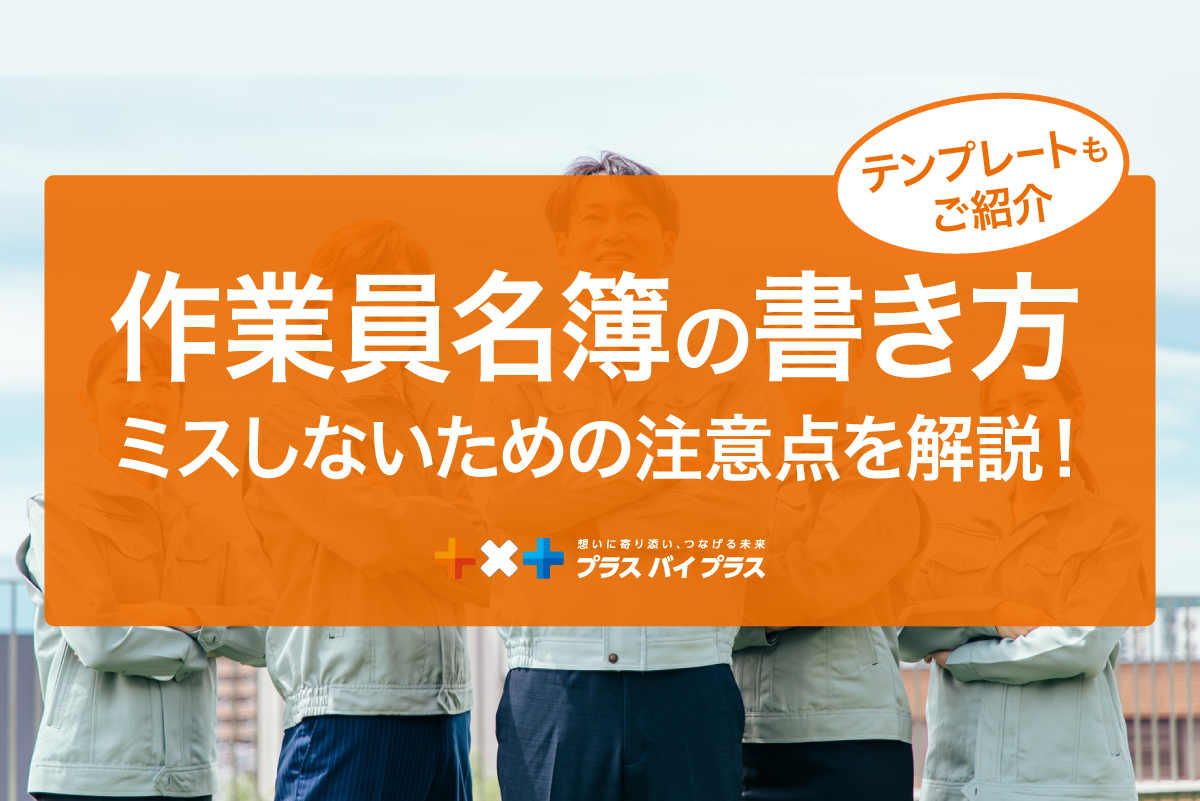- 2025年11月07日
原価管理と会計の違い・関係を経理目線で徹底解説|利益改善につながる実務の仕組みづくり

企業の利益を最大化する上で、原価管理は極めて重要な経営活動です。
しかし、案件やプロジェクトごとに正確な原価計算を行うためには多大な手間がかかり、多くの経理担当者が課題を抱えています。
適切な原価管理は経営判断の質を直接左右するため、経営層からの要求水準も高く、その複雑な業務をいかに効率化するかが問われます。
本記事では、経理の視点から原価管理と会計の関係性を整理し、利益改善につながる実務的な仕組みを構築するための具体的な方法を解説します。
コンテンツ
経理部門を苦しめる“コスト把握の非効率” ── 真の原因と改善の方向性
多くの経理担当者が、コスト把握の複雑さと日々の非効率な業務に頭を抱えています。その背景には、原価を正確に計算するためのプロセスが煩雑であること、そして生産管理システムや会計システムが十分に連携していないという構造的な問題があります。
手作業によるデータ入力や転記作業が発生するたびに、ミスのリスクと作業時間は増加し、迅速な意思決定が難しくなります。
このような状況は、経理部門の負担を増大させるだけでなく、経営判断に必要な“リアルタイムな原価情報”の把握をも妨げています。
今、求められているのは「正確でスピーディーに原価を把握できる仕組みづくり」です。会計と現場をつなぐ情報の流れを再設計することで、経理部門はようやく“数字を作る仕事”から“経営を支える仕事”へと進化できるのです。
原価管理とは? ― 経理担当が押さえるべき基本概念
原価管理とは、製品やサービスの提供に要した費用(原価)を正確に計算・把握し、その分析を通じてコストの維持や低減を図る一連の活動を指します。設定した「目標原価」と実際に発生した「実際原価」を比較し、その差を分析して改善する活動と言えるでしょう。その目的は、財務諸表を適正に作成する財務会計の側面と、経営者の意思決定に資する情報を提供する管理会計の側面の双方にあります。経理的に見れば、単なる費用管理ではなく「コスト構造を明らかにする会計的手法」です。
原価は主に「材料費」「労務費」「経費」の3要素から構成されており、材料費は直接製品に使われる原材料の費用、労務費は製造・サービス提供に直接関わる人件費、経費は設備・光熱・減価償却など間接的な費用を指します。
これらを正確に把握・配賦することが、原価管理の第一歩です。
現場のみで行われる原価計算では、複数の製品にまたがる間接費の見落としといった問題が生じがちであり、企業全体の利益を正確に把握するためには、経理部門が主導し、全社的な視点で管理体制を構築することが不可欠となります。
関連記事:
【すぐ実践できる】原価管理とは?目的やメリット、管理方法の全体の流れをわかりやすく解説
建設業の工事原価管理のやりやすい方法|難しい理由と実践メリットを紹介
原価計算・原価管理が必要な理由とは
原価計算と原価管理は、企業の利益確保と成長に不可欠な活動です。その主な目的は、原価計算基準にも示されており、財務会計、管理会計の双方で重要な役割を果たします。まず財務会計の側面では、正確な財務諸表を作成し、利害関係者に企業の財政状況を適切に報告するために、売上原価の算出が必要となります。これにより、企業の経済活動が客観的に評価され、投資家や金融機関からの信頼を得ることに繋がります。
一方、管理会計の側面では、経営者や現場管理者が適切な意思決定を行うための情報を提供することが主な目的です。例えば、製品やサービスの価格を適正に設定するための資料提供、原価情報の分析による無駄の排除、予算編成や経営計画策定に必要な資料の作成などが挙げられます。
このように、原価計算と原価管理は、企業全体の経営活動において多角的な目的を持ち、単なる費用計算に留まらない問題解決と成長を促すための重要なツールなのです。
経理部門がこれらの活動を主導することで、現場視点だけでは見過ごされがちな間接費なども含めた全社的な原価構造を把握し、企業の真の利益を可視化することが可能になります。
会計と原価管理の関係 ― 財務会計と管理会計の違い
原価管理は財務会計と管理会計の両方に密接に関連していますが、それぞれの目的や対象期間、出力、法的義務には明確な違いがあります。財務会計は、外部報告、特に税務や株主への報告を目的として過去の期間を対象とし、財務諸表の作成が主な出力となります。これには法的義務が伴います。
一方で管理会計は、経営判断や内部管理を目的とし、現在から未来の期間を対象として部門別損益や原価差異分析などを出力します。
これには法的義務は伴わず、社内任意で運用されます。つまり、原価管理は管理会計の中核に位置づけられ、財務会計で「費用を記録」し、原価計算で「コストを分類・集計」し、原価管理で「分析・改善を行う」という3ステップが、経理が経営を支える会計の流れとなるのです。
この一連の流れにより、経理部門は損益計算書の売上原価や貸借対照表の棚卸資産価額を正確に算定し、企業全体の財政状態と経営成績を適切に報告できるだけでなく、経営判断に必要な情報を提供し、製品別の収益性分析やコスト削減施策の立案、適正な販売価格の設定といった具体的な経営判断の基礎情報を提供できるようになります。
経理担当が直面する「原価管理の壁」
経理担当者は原価管理の実務において、複数の壁に直面します。一つは「情報の収集」です。
製造現場や営業部門など、各部署から原価計算に必要な情報を正確かつタイムリーに集めることは容易ではありません。
各部署で管理されているデータの形式が異なっていたり、情報共有のルールが徹底されていなかったりすることが、作業の遅延や不正確さを招きます。
二つ目はその「複雑な計算手順」です。
原価計算では、発生した費用を費目別に分類し、それをさらに製造部門や間接部門といった部門別に集計する「部門別原価計算」、そして最終的に製品ごとに原価を算出する「製品別原価計算」という3つのステップを踏みます。
特に、間接費を適切に配賦するプロセスは、複数の配賦基準の中から適切なものを選択する必要があり、経理担当者にとって大きな負担となることがあります。
三つ目は「手作業による負担」です。
収集したデータを表計算ソフトなどに手入力し、複雑な配賦計算を行うプロセスは、膨大な時間を要する上にヒューマンエラーのリスクも高くなります。
これらの壁が、本来の目的である分析や改善活動へリソースを割くことを困難にしています。
経理担当が直面する「原価管理の壁」①情報の収集
原価管理の最初の「壁」となるのが、必要な情報の収集です。正確な原価計算を行うためには、原材料の購入費、製造に関わる労務費、消耗品や光熱費などの経費といった多岐にわたる費目を網羅的に把握する必要があります。これらの情報は、生産部門、購買部門、人事部門など、企業内の様々な部署に散在しており、それぞれの部署で異なる形式で管理されていることが少なくありません。例えば、生産現場では作業時間や投入量を手書きの帳票で管理している場合もあれば、購買部門ではサプライヤーからの請求書をそのまま保管しているケースもあります。このように情報が点在し、形式が統一されていない状況では、経理担当者が手作業で情報を集約し、入力する手間が発生します。この集約作業は膨大な時間を要するだけでなく、手入力によるミスや抜け漏れが発生するリスクも高まります。正確な原価計算を行うためには、全ての原価情報をタイムリーかつ正確に収集することが必須であり、この情報の粒度や鮮度が、後の原価計算や差異分析の精度を大きく左右します。
収集した情報をもとに、適切な原価計算を行い、目標と実績の差異を分析するためには、情報収集の段階でいかに漏れなく、そして効率的にデータを集められるかが成功の鍵となります。この初期段階での課題をクリアすることが、原価管理の目的達成に向けた第一歩となるのです。
経理担当が直面する「原価管理の壁」②計算方法の複雑さ
原価管理が難しいとされる第一の理由は、原価計算の方法そのものが持つ複雑性にあります。原価は材料費、労務費、経費といった費目別に分類され、さらに特定の製品に直接紐づく「直接費」と、複数の製品に共通して発生する「間接費」に分けられます。
特に間接費は、どの製品にどれだけ負担させるかを決定するための「配賦」という手続きが不可欠です。
この配賦基準の選定や計算が非常に煩雑であり、客観的で合理的な基準を設けること自体が一つの課題となります。
経理担当者は、これらの複雑な計算ルールを正確に適用しなければならず、関連部門が増えるほどその負担は増大します。
1.費目別
原価計算基準では、原価を「材料費」「労務費」「経費」の3つの要素、すなわち費目別に分類すると定められています。材料費は製品の製造に直接用いられる原材料の費用、労務費は製造作業に携わる従業員の人件費、経費はそれ以外の製造活動に必要な光熱費や減価償却費などを指します。これらの費目ごとに原価を把握することで、どこでどのくらいのコストが発生しているのかを具体的に特定することが可能になります。
しかし、この費目別の分類だけでは、それぞれの費用がどの製品にどれだけ貢献しているのか、あるいはどの部門で発生しているのかといった詳細な情報までは把握できません。
特に、間接的な労務費や経費などは複数の製品や部門にまたがって発生するため、費目別の集計だけでは正確な原価を算出する上で問題が生じることがあります。
そのため、費目別の原価をさらに直接費と間接費に分け、間接費については適切な配賦基準を用いて製品や部門に割り振る必要があります。
2.部門別
部門別原価計算では、費目別に分類された間接費をさらに細分化し、企業内の各部門で発生したコストを集計して分析します。製造部門や販売部門、管理部門といった各部署で発生する労務費や経費、その他費目を明確に区分することで、部門ごとの責任範囲を明確にし、コスト発生源を特定することが可能になります。例えば、製造部門で発生する機械の減価償却費や間接的な労務費、販売部門で発生する広告宣伝費や営業担当者の人件費などが該当します。
この部門別原価計算では、各部門に共通して発生する共通費や、経理や総務といった間接部門で発生する費用を、適切な配賦基準を用いて各製造部門や直接部門に配賦する作業が重要となります。
部門共通費の配賦では、水道光熱費であれば床面積比、間接部門費であれば各部門の従業員数や売上高比などを考慮して配賦します。
これにより、製品の製造やサービスの提供に直接関わる部門の原価をより正確に把握できるため、原価計算の精度を向上させることができます。
また、部門ごとのコストを可視化することで、各部門のコスト管理意識を高め、無駄の排除や効率化に向けた改善活動を促進することも期待されます。
部門別原価計算は、費目別と製品別原価計算の中間に位置し、より詳細な原価情報を得る上で不可欠な手法と言えます。
3.製品別
製品別原価計算は、費目別や部門別で集計された原価情報を基に、最終的に個々の製品やサービスごとに原価を算出する方法です。この方法によって、特定の製品がどれだけの材料費や労務費、経費を要して製造されたのかを具体的に把握できます。
例えば、ある自動車メーカーであれば、車種ごとに発生した直接材料費(部品代など)や直接労務費(組立作業員の賃金など)を直接集計し、さらに複数の車種に共通して発生する間接費(工場の賃借料や管理部門の費用など)を適切な方法で配賦することで、その車種の正確な原価を算出するのです。
この製品別の原価計算は、製品ごとの利益率を正確に把握し、価格設定の妥当性を評価したり、不採算製品の特定や生産中止の判断材料としたりする上で非常に重要な費目となります。
特に、多品種少量生産を行う企業や、個別受注生産を行う企業では、この製品別原価計算が不可欠な原価計算の方法となります。
各製品の原価を詳細に把握することで、より具体的なコスト削減目標を設定し、経営戦略に役立てることが可能になるのです。
経理担当が直面する「原価管理の壁」③手作業・手入力の負担
経費の管理は部門ごとにExcelや専用のシステムで行われることが多く、経理担当者は各部門から異なる形式で送られてくる原価情報を会計システムへ手入力する必要があります。特に間接費については、適切な配賦基準に基づいて複雑な計算を行い、さらに手入力で仕訳を行うため、多大な時間と労力がかかるのが実情です。多くの中小企業では、経理部門が少人数で運営されているため、このような手作業の負担は他の重要な業務にまで影響を及ぼし、業務全体の遅延を招く可能性があります。
費目別に細分化された原価情報やプロジェクト情報の入力は、非常に手間がかかる作業です。また、市販されている原価管理システムの中には、現場での収益性管理に重点を置いたものが多く、直接原価の管理はできても、間接費の管理や管理会計、財務会計上の原価管理まで適切に対応できないケースがあります。
結果として、システムを導入しても経理担当者の手作業や手入力による負担が軽減されず、非効率な状態が継続してしまうという悪循環に陥ることが少なくありません。
この課題を解決するためには、会計システムと連携し、費目の自動取り込みや配賦計算の自動化が可能なシステムの導入が不可欠です。
原価管理を会計視点で進めるステップ
原価管理を形骸化させず実務に活かすには、会計視点に基づいた体系的なアプローチが求められます。これは単なる現場のコスト管理に留まらず、財務会計の要請に応えつつ、管理会計に資する情報を創出する仕組みを構築することを意味します。
具体的には、まず自社の原価構造を可視化し、次に原価計算のルールを標準化、そして会計システムと連動させて効率化を図るというステップを踏むことが有効です。
経理部門が主導し、各費目を正確に捉え、全社的な視点で管理体制を整えることが肝要です。
Step1:原価構造の可視化
最初のステップは、自社の製品やサービスにかかるコストの全体像を把握し、その構造を可視化することです。まず、発生した費用を「材料費」「労務費」「経費」といった費目ごとに分類します。
次に、それぞれの費目を、特定の製品に直接賦課できる「直接費」と、複数の製品に共通して発生する「間接費」に仕分けます。
このプロセスで特に問題となるのが間接費の扱いです。
どの製品にどれだけ配賦するかの基準が曖昧なままでは、正確な製品別原価を算出できません。
各費目の内容を精査し、直接費と間接費の分類基準を明確に定義することが、精度の高い原価管理の第一歩となります。
Step2:原価計算のルール化
原価構造を可視化した後は、原価計算の具体的な手順と基準を全社的なルールとして定めます。特に、複数の部門や製品にまたがる間接費(共通の労務費や経費など)を、いかに公平かつ合理的に各々に負担させるかという「配賦基準」の策定が核心です。
例えば、工場の賃借料は各製品の生産ラインが占める面積比で、管理部門の人件費は各事業部門の売上高比で配賦するなど、事業の実態に即した基準を設定します。
経理部門は、これらの費目ごとの配賦ルールを文書化して関係部署と共有し、属人性を排除することで、継続的で一貫性のある原価計算を実現します。
Step3:管理会計との連動
ルールに基づいて算出された原価データを、経営の意思決定に活用するために管理会計と連動させます。製品別や事業部別の損益を詳細に分析し、不採算事業の特定や価格設定の見直し、コスト削減施策の検討などに役立てるのです。
例えば、特定の製品にかかる労務費や各費目の原価が当初の予算を上回っている場合、その原因を深掘りし、製造プロセスの改善や外注先の見直しといった具体的なアクションにつなげます。
このように、原価計算の結果を単なる数値として終わらせず、経営課題の発見と解決に結びつける方法を確立することが、原価管理の価値を最大化します。
Step4:経営層・現場との共有
構築した原価管理の仕組みと、それによって得られた分析結果は、経営層および現場の関係者と定期的に共有する必要があります。経営層には、全社的な収益構造や事業別の採算性をまとめたレポートを提供し、戦略的な意思決定を支援します。
一方、製造や営業といった現場の各部門には、自部門のコスト発生状況や予算との差異などを分かりやすくフィードバックし、コスト意識の向上と具体的な改善活動を促します。
この双方向のコミュニケーションを通じて、原価管理が単なる経理部門の業務ではなく、全社的な経営改善活動の一環であるという認識を醸成することが重要です。
経理が知っておくべき原価管理システム・ツールの選び方
効率的かつ正確な原価管理を実現するためには、適切なシステムやツールの活用が欠かせません。手作業での管理には限界があり、業務の属人化やヒューマンエラーを招きやすくなります。
市場には多様な原価管理システムが存在しますが、自社の事業規模や業態、そして経理部門の実務フローに合致したものを選ぶことが肝要です。
特に、会計システムとの連携性は、データの一元管理と二重入力を防止する観点から極めて重要な選定基準となります。
費目別の原価計算を自動化する機能や、柔軟な配賦設定が可能な製品を選ぶことが業務効率化に直結します。
原価管理を成功させるための「経理マインドセット」
優れたシステムを導入しても、それを扱う経理担当者の意識が旧来のままであれば、原価管理は成功しません。求められるのは、単なる「計算担当者」から、データを分析して経営に示唆を与える「ビジネスパートナー」への意識改革です。
原価データを集計して終わりにするのではなく、「なぜこのコストが増加したのか」「どの製品の利益率が低下しているのか」といった問いを立て、その背景にある事業活動に関心を持つ視点が不可欠です。
また、現場部門とのコミュニケーションを密にし、数字の裏にある実態を理解しようと努める姿勢も求められます。
このような能動的なマインドセットが、経理部門の価値を高めます。
まとめ:原価管理は経理の「次のステージ」
原価管理は、単にコストを計算するだけの作業ではなく、企業の利益構造を深く理解し、改善へと導くための経営管理手法です。その本来の目的を達成するためには、現場の視点に加え、財務会計と管理会計をつなぐ経理部門の視点が不可欠となります。
煩雑な原価計算やデータ収集は、会計と連携した適切なシステムを活用することで効率化を図るべきです。
これにより、経理担当者は定型的な作業から解放され、データの分析や経営への提言といった、より付加価値の高い業務へシフトすることが可能となります。
正確な原価管理体制の構築は、経理部門が企業の戦略的意思決定に貢献するための重要な一歩です。
経理の“視える化”から、経営の“判断力強化”へ。
原価管理システムの「要 ~KANAME~」は、現場の数字をリアルタイムで原価に反映できる原価管理システムです。
煩雑なExcel作業から解放され、原価の把握・分析・改善までをスムーズに。
次のステージへ進む経理業務に、「要 ~KANAME~」を導入してみませんか?
原価管理システム「要 ~KANAME~」の詳細はこちら ▶︎▶︎▶︎
よくある質問
Q1. 原価管理と会計はどう違うのですか?
A1. 原価管理は、製品やサービスの提供にかかった費用(原価)を把握・分析し、コスト削減や利益改善につなげるための社内向けの活動です。
一方、会計は財務諸表を作成し、税務や株主など外部に報告することを目的とした外部向けの仕組みです。
つまり、会計が「外に見せる数字」を作るのに対し、原価管理は「経営判断に使う数字」を作るものです。
Q2. なぜ原価管理が企業経営にとって重要なのですか?
A2. 原価管理を行うことで、製品やサービスごとの正確な利益を把握でき、価格設定・コスト削減・不採算事業の見直しなど、経営判断の精度が高まります。
また、財務会計の観点では正確な財務諸表の作成につながり、管理会計の観点では経営戦略の立案や意思決定を支援します。
**原価管理は「企業の利益構造を見える化する仕組み」**と言えます。
Q3. 経理担当者が原価管理で直面する主な課題は何ですか?
A3. 主に3つの課題があります。
- 情報収集の難しさ(部署ごとに形式が違い、データが点在)
- 計算方法の複雑さ(間接費の配賦や基準の設定が難しい)
- 手作業・手入力の多さ(Excel入力などに時間がかかり、ミスのリスクが高い)
Q4. 原価計算の方法にはどのような種類がありますか?
A4. 原価計算は大きく3つのステップで行われます。
- 費目別原価計算:材料費・労務費・経費に分類してコストを把握。
- 部門別原価計算:どの部門でコストが発生しているかを明確化。
- 製品別原価計算:最終的に製品やサービスごとに原価を算出。
Q5. 原価管理を効率化するには、どんなシステムを導入すればよいですか?
A5. 効率的な原価管理には、会計システムと連携できる原価管理ツールの導入が効果的です。
ポイントは以下の3つです。
- 費目別の原価計算を自動化できる機能がある
- 間接費の配賦設定を柔軟に行える
- 会計データを自動で取り込み、二重入力を防げる