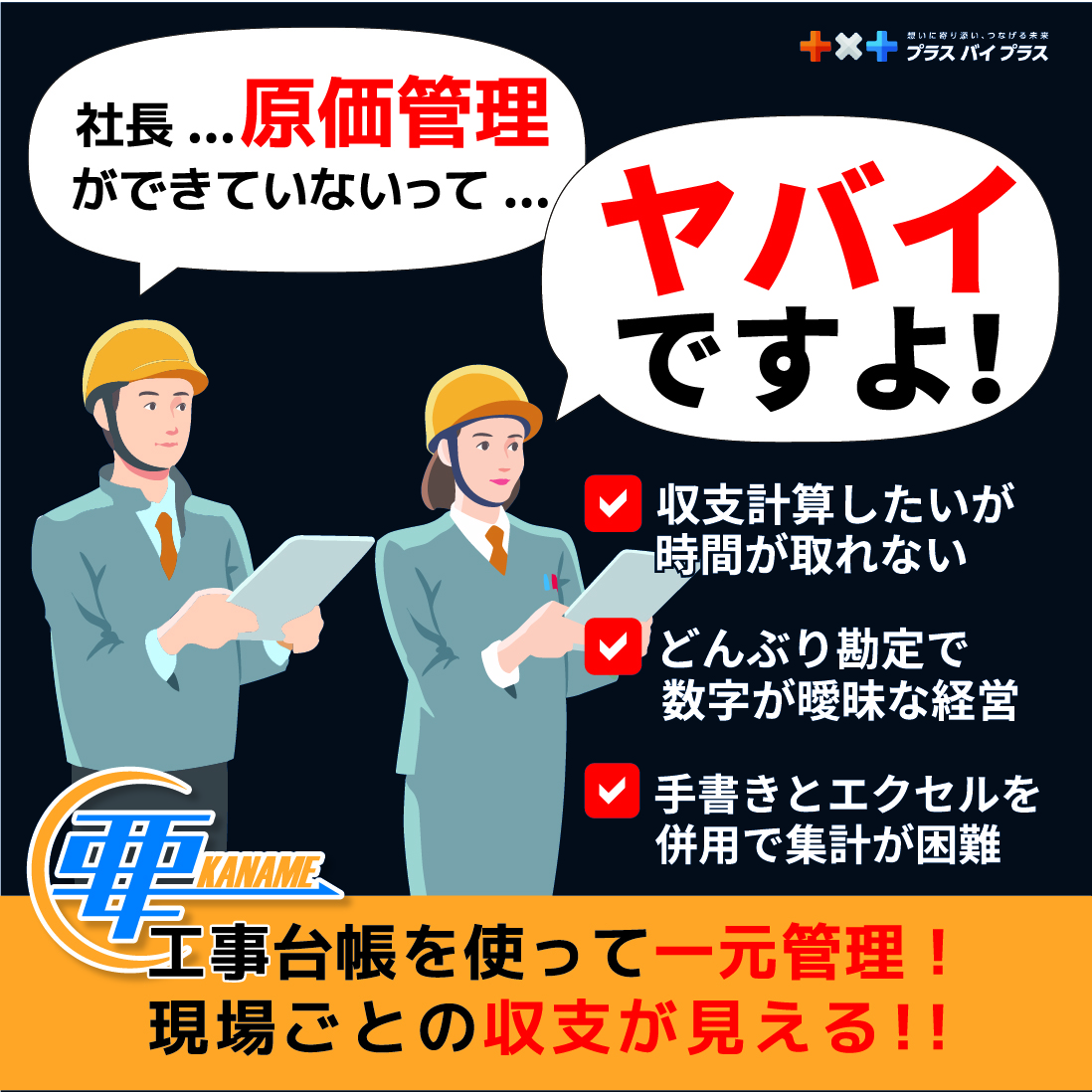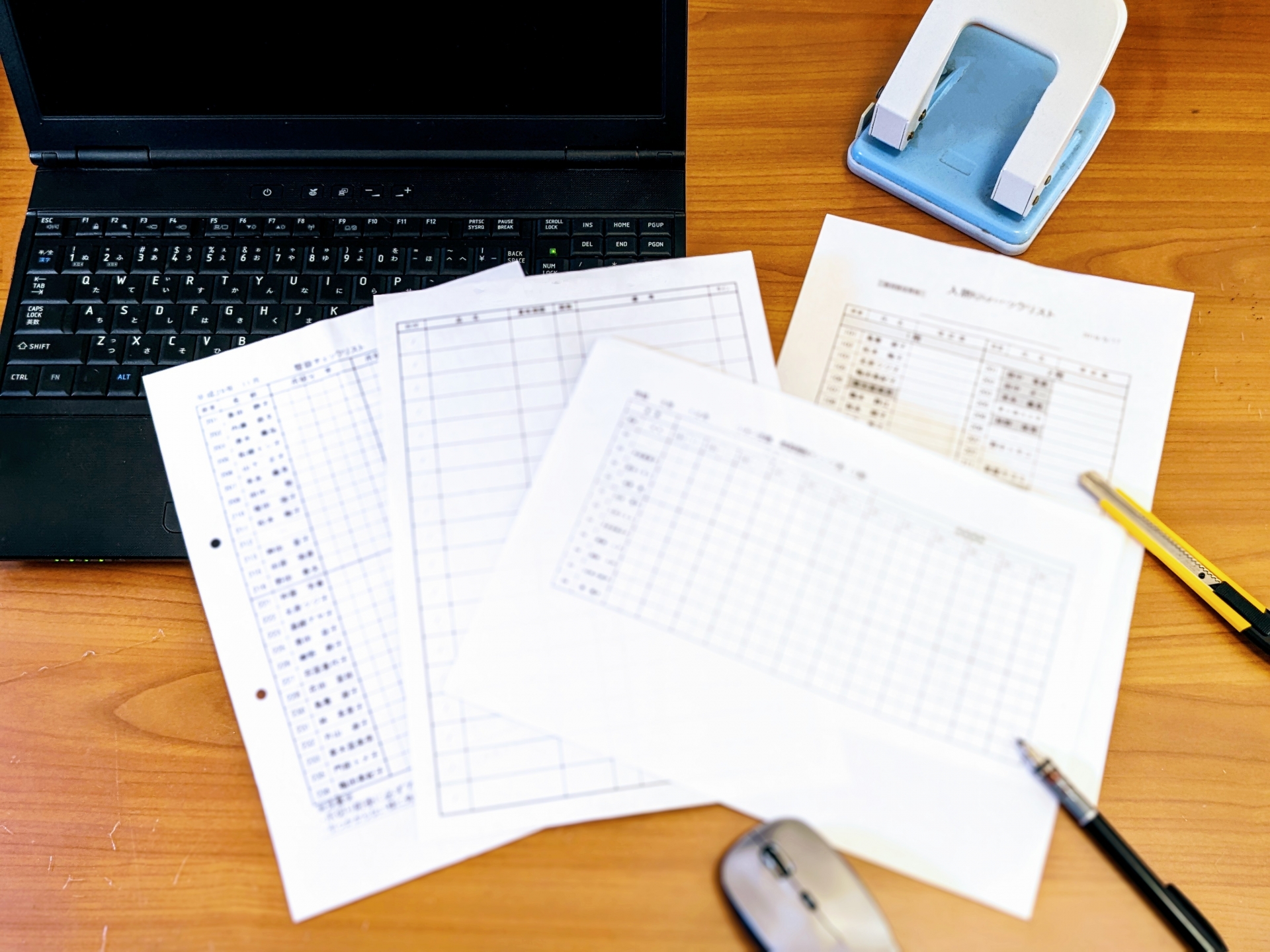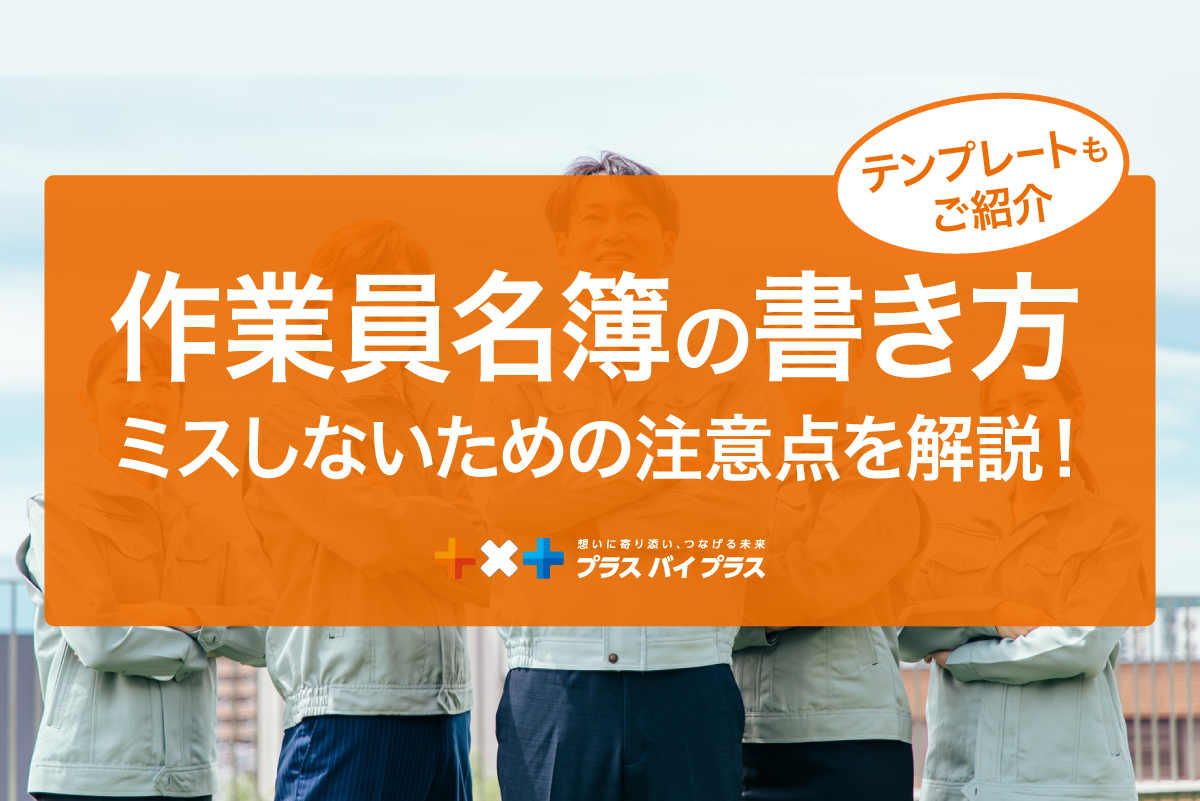- 2026年02月05日
施工管理が行う原価管理とは?役割と目的、経営との違いを整理

施工管理として現場を任されるようになると、「原価管理」という言葉を耳にする機会が増えてきます。
ただ実際には、経営や事務の仕事というイメージが強く、「施工管理がどこまで関わるべきなのか」「何を把握していれば十分なのか」と戸惑う方も少なくありません。
原価管理は、数字を細かく計算することが目的ではなく、現場での判断が工事全体にどのような影響を与えているかを把握するための考え方です。
本記事では、施工管理が行う原価管理の役割や目的を整理しながら、経営者が行う原価管理との違い、現場で押さえておきたいポイントを解説します。
コンテンツ
施工管理における原価管理の基本を解説
施工管理における原価管理とは、工事を進める中で発生する費用の動きを把握し、想定していた予算と大きなズレが生じていないかを確認することを指します。施工管理が行う原価管理の目的は、細かな数字を分析することではなく、現場の判断が原価にどのような影響を与えているかを把握することにあります。
まずは、工事原価がどのような費用で構成されているのかを理解し、「どこで原価が動きやすいのか」を意識できるようにすることが、原価管理の第一歩となります。
関連記事:
・原価管理とは?目的やメリット、管理方法の全体の流れを分かりやすく解説
工事原価を構成する4つの主な費用(材料費・労務費・外注費・経費)
工事原価は、主に「材料費」「労務費」「外注費」「経費」の4つに分類されます。材料費は、木材、鉄筋、コンクリートといった工事に使用する資材の購入費用です。
労務費は、自社で雇用している職人や現場作業員へ支払う賃金、給与、賞与、各種手当などを指します。
外注費は、鳶工事や電気工事といった専門的な作業を協力会社や下請け業者に依頼した際に支払う費用です。
経費は、これら3つに含まれない全ての費用を指し、現場事務所の賃料や水道光熱費、重機・車両のリース代、保険料などが該当します。
これらの費用を正確に分類し把握することが、的確な原価管理の基礎となります。
施工管理が行う原価管理と経営者が行う原価管理の違いとは?
施工管理と経営者の間では、同じ原価管理という言葉を使っていても、その目的や視点が異なるため認識のズレが生じがちです。施工管理者は現場ごとの収支に責任を持ち、実行予算に対して実際の材料費や外注費をいかに抑えるかというミクロな視点で管理を行います。一方で経営者は、会社全体の利益や資金繰り、投資判断といったマクロな視点で原価を捉えています。
この視点の違いを整理できていないと、現場では利益が出ているはずなのに会社全体では赤字になるといった混乱を招きます。双方の役割における目的の違いを正しく理解し、共通の指標で数字を共有することが、現場と経営の認識を揃え、スムーズに連携していくための鍵となります。
関連記事:
・建設業における原価管理の難しさと、実践するメリットを詳しく解説
経営者が行う原価管理の役割
経営者は、個別の現場における細かなコスト抑制よりも、会社全体の収支バランスや将来の事業方針を決定するためのマクロな視点で原価管理を行います。各工事の利益率を俯瞰することで、どの事業に注力すべきか、あるいは設備投資や人員採用にどれほどの予算を割けるかといった、経営の根幹に関わる判断を下すことが主な役割です。
現場から上がってくる数字を基に、会社全体の資金繰りや年度計画との整合性を確認し、組織として持続的な成長が可能かどうかを見極めます。
つまり、経営者にとっての原価管理は、単なる支出の把握ではなく、企業の生存と発展を確かなものにするための戦略的な意思決定ツールといえます。
施工管理が行う原価管理の役割
施工管理における原価管理の主な役割は、現場で日々刻々と変動する原価を正確に把握することにあります。天候の変化や予期せぬトラブル、仕様変更などによって発生する費用の増減をリアルタイムで監視し、予算との乖離を防ぐことが求められます。現場での迅速な意思決定は、常に原価と直結しています。資材の発注タイミングや人員配置の変更といった日々の工事判断が、最終的な収支にどのような影響を及ぼすかを常に意識しなければなりません。
ただし、施工管理が行う原価管理は、個々の工事を予算内に収め、利益を確保することを目的としています。
会社全体の利益確保や利益率向上を目的とする経営者の原価管理とは役割が異なりますが、施工管理の原価管理が会社全体の利益に貢献する重要な要素であることに変わりはありません。
予算の範囲内でいかに効率よく工事を進めるかに集中し、健全な現場運営を実現することが重要です。
よくある混乱ポイント
原価管理の実践において、まず直面するのが見積と実行予算の混同です。見積はあくまで受注を目的とした顧客への提示金額であり、そこには営業的な判断や利益が含まれています。対して実行予算は、実際に工事を完遂するために必要な原価の目標値であり、現場を管理する上での真の基準となります。
両者の役割を明確に区別できていないと、正しい利益管理は行えません。
また、原価管理を事務部門や経営層だけの仕事だと捉えてしまう点も、現場でよくある誤解の一つです。
実際には、日々の資材発注や人員配置を決定する施工管理者の判断こそが原価を左右します。
現場の動きと数字が結びつかなければ、原価管理は形骸化し、適切な収益確保を阻害する要因となります。
施工管理が原価管理を徹底する3つのメリット
施工管理者が原価管理を徹底することは、現場の円滑な運営だけでなく、自身の業務負担を軽減し、周囲との信頼関係を築く上でも多くの利点があります。単にコストを抑えるための作業と捉えず、現場をコントロールするための強力な武器として活用することが重要です。原価管理を適切に行うことで得られる具体的なメリットについて、以下の3つの観点から解説します。
現場判断がしやすくなる
現場の原価状況を把握していると、日々の工事判断がしやすくなります。材料の選定や人員の追加配置を検討する場面でも、原価の目安が頭に入っていれば、その判断が工事全体にどのような影響を与えるかを整理しながら考えられるためです。
特に、追加工事や急な仕様変更が発生しやすい現場では、原価の考え方が整理されているかどうかで、対応のスピードや判断の迷いに差が出ます。
感覚だけに頼らず、数字を一つの判断材料として持っておくことで、現場での意思決定が安定し、工事を落ち着いて進めやすくなります。
後からのトラブルや指摘を減らせる
原価を工事の進捗に合わせて把握しておくことで、想定とズレが出始めた段階で状況に気づきやすくなります。工事完了後になって初めて問題が表面化する、といった事態を避けやすくなる点も大きなメリットです。
また、日々の原価の動きを記録しておくことで、「なぜその費用が発生したのか」「どの判断が影響したのか」を説明しやすくなります。
根拠をもとに状況を共有できれば、事後の確認や指摘による混乱を減らし、現場としても納得感のある対応がしやすくなります。
経営・事務との会話が噛み合う
原価管理を通じて共通の数字を把握しておくと、現場と経営・事務との会話が噛み合いやすくなります。感覚的な説明ではなく、同じ数値を前提に話ができるため、現場の状況や判断の背景が伝わりやすくなるためです。
これにより、「現場では何が起きているのか」「どこで想定と違いが出ているのか」といった点を、余計なやり取りを挟まずに共有できます。
原価を共通言語として使えるようになることで、現場とバックオフィスの連携がスムーズになり、調整にかかる負担も軽減されます。
施工管理が行う原価管理の流れ
施工管理が関わる原価管理は、決まった作業手順をこなすことではありません。工事の各場面で、原価が動くポイントを意識し、必要なタイミングで状況を把握することが重要です。
以下は、施工管理が原価管理に関わる主なタイミングの整理です。
工事前に、原価の前提を把握する 工事を始める前に、見積や実行予算の内容を確認し、どこに原価がかかる想定になっているのかを把握しておきます。
工事中に、原価が動く場面を意識する 資材の発注変更や人員配置の調整、外注作業の追加など、現場判断が原価に影響する場面を意識しながら工事を進めます。
ズレが出そうなときに、原価の状況を共有する 想定していた原価から乖離が生じそうな場合は、早めに関係者と情報を共有し、判断をすり合わせます。
工事後に、原価の動きを振り返る 完工後に、原価がどのように動いたのかを確認し、次の工事に活かせる気づきを整理します。
まとめ
施工管理における原価管理で最も大切なのは、単なる計算手法を学ぶことではなく、現場と経営における役割の違いを整理し、正しい考え方を持つことです。現場での日々の判断が工事全体にどのような影響を与えるのかを理解することで、初めて数字に基づいた確実な現場運営が可能となります。
しかし、個人の記憶やExcelによる手入力に頼った管理では、入力漏れや計算ミスといったヒューマンエラーによる数字のズレを完全に防ぐことは困難です。
こうした課題を根本から解決するためには、誰が担当しても正確な数字が算出される仕組み作りが欠かせません。
原価管理をシステム化できるツールを活用し、現場と経営がリアルタイムで同じ数字を共有できる環境を整えることで、施工管理が判断しやすい現場運営につなげることができます。
原価管理を強化するなら「要 〜KANAME〜」で現場と経営をつなぐ
現場と経理をつなぐ原価管理を本当に機能させるには、属人的なExcel管理から脱却し、数字をリアルタイムで「視える化」できる仕組みが必要です。建設業向け原価管理システム「要 〜KANAME〜」なら、実行予算と実績原価を自動で突合し、予算超過や赤字の兆候を即時に把握。
日報・出面・発注・出来高管理も一元化し、現場から経営までの判断をスピードアップします。
小規模工事から元請け対応まで幅広く対応可能で、誰でも使いやすい設計。
「要 〜KANAME〜」の商材ページで、導入効果や事例をご覧ください。
よくある質問
Q1. 施工管理が行う原価管理とは何ですか?
施工管理が行う原価管理とは、工事を進める中で発生する費用の動きを把握し、現場での判断が原価にどのような影響を与えているかを確認することです。施工管理の原価管理は、会社全体の利益を確定させることが目的ではなく、工事中に原価のズレが起きていないかを把握し、必要に応じて調整や共有を行う役割を担います。
現場の進捗や判断と数字を結びつけて考えることが、施工管理に求められる原価管理の基本といえます。
Q2. 建設業で原価管理が重要視される理由は何ですか?
建設業では、資材価格の高騰や人件費の上昇、人手不足などにより利益率が低下しやすいため、原価管理が重要視されています。原価管理を徹底することで、予算超過や赤字工事の発生を防ぎ、利益を確保しやすくなります。
また、過去の工事データを活用して次の見積もり精度を高めるなど、経営判断にも役立ちます。
Q3. 施工管理者が原価管理を行うメリットは何ですか?
施工管理者が原価管理を行うことで、現場での判断がしやすくなり、工事中の変更や調整にも落ち着いて対応しやすくなります。また、原価の動きを把握しておくことで、後から状況を説明する必要が生じた場合でも、判断の背景を数字をもとに整理しやすくなります。
原価管理はコスト削減のためだけのものではなく、現場を安定してコントロールするための考え方として活用できる点が、施工管理にとっての大きなメリットです。
Q4. 工事原価管理が難しいとされる理由は何ですか?
建設業では、会計処理や費用構造が特殊であり、材料費・労務費・外注費・共通費などを正確に分類・計上する必要があります。さらに、工事進行基準による売上や原価の分割計上、新収益認識基準への対応などが求められるため、経理担当者には専門知識が必要です。これらの要因が原価管理を難しくしています。
Q5. 原価管理の精度と効率を上げるにはどうすれば良いですか?
原価管理の精度を上げるには、まず社内で統一された仕訳ルールや報告フォーマットを定めることが重要です。さらに、原価管理システムを導入することで、データ入力の自動化や情報の一元管理が可能となり、リアルタイムで原価状況を把握できます。自社の規模や目的に合ったシステムを選定し、運用体制を整えることが成功の鍵です。