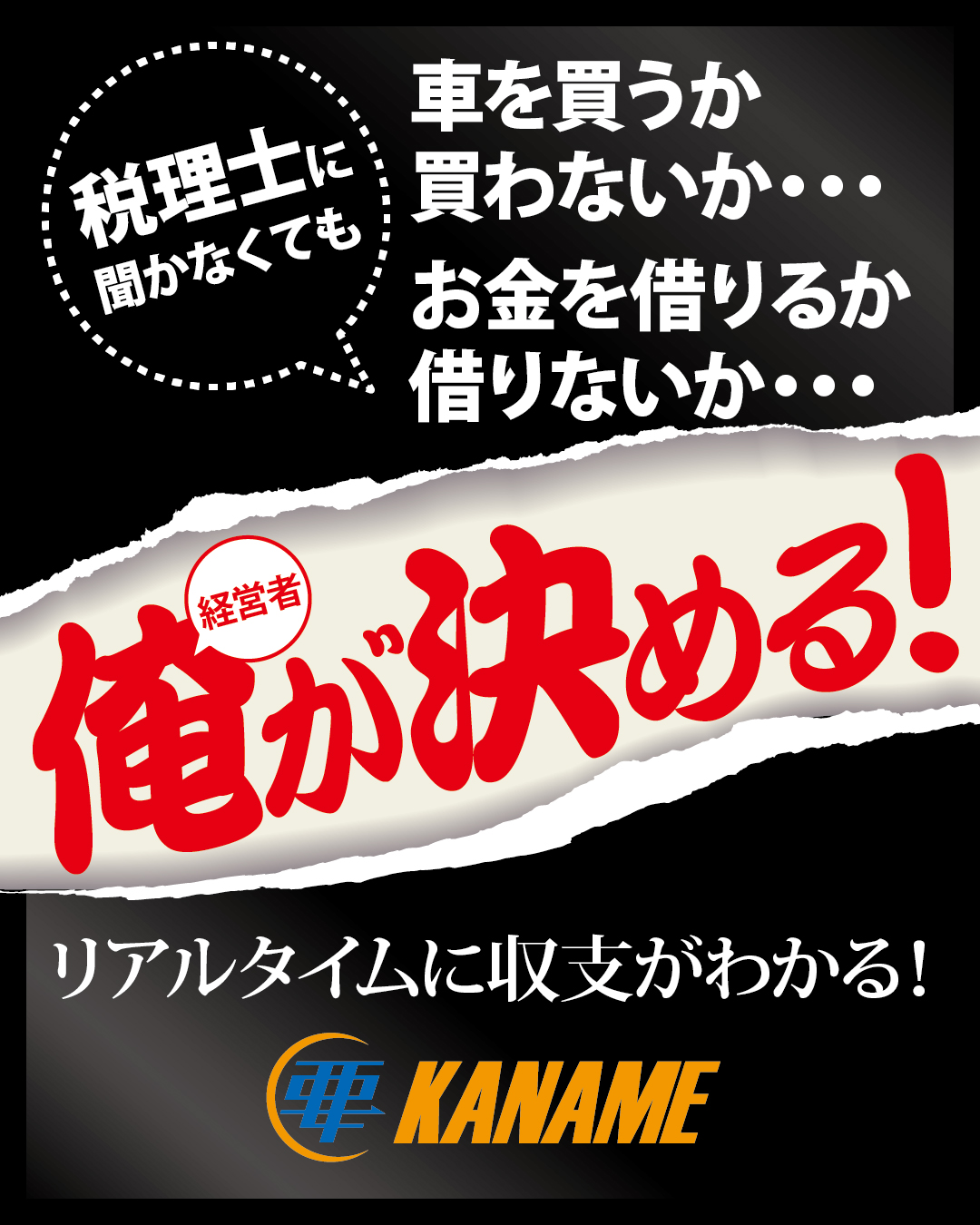- 2025年09月22日
なぜ水道工事は赤字になりやすいのか?原因と対策を解説
経営に役立つ知識

地域社会に不可欠なライフラインを支える水道工事。その社会的意義は大きいものの「赤字」という厳しい経営課題に直面している事業者は少なくありません。
水道工事は、予期せぬコスト増や利益圧迫要因が多く、赤字に陥りやすい傾向があります。この記事では、水道工事で赤字が発生してしまう背景や具体的な原因、そして赤字を防ぐための管理・業務改善ポイント、利益確保のための戦略的アプローチまでを解説します。
コンテンツ
水道工事で赤字が発生する背景とは?
水道工事が赤字になってしまう背景には、以下のような業界特有の構造的な要因があります。中小施工業者が直面する経営課題
日本の水道工事業界は、多くが地域密着型の中小施工業者によって支えられています。これらの事業者は、重要な役割を果たす一方で、経営面では多くの課題を抱えています。経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の制約が大きく、限られた人員で現場作業から事務、営業までをこなし、経営管理に十分なリソースを割けないケースもあります。最新ツールの導入や情報収集をするにも資金的・時間的な制約から難しい場合もあるでしょう。
また、価格競争の激化も深刻です。特に公共工事の入札では低価格競争が常態化し、民間工事でも相見積りによる価格競争で適正利益の確保が難しくなっています。
さらに、元請け・下請け構造における立場の弱さも収益性を圧迫します。元請けからの厳しい価格交渉や一方的な仕様変更、長い支払サイトなども経営を不安定にさせる要因です。
加えて、後継者不足や職人の高齢化といった事業承継の問題も、多くの中小施工業者が抱える共通の悩み。これらの複合的な経営課題が、水道工事業者の収益性を圧迫し、赤字リスクを高める要因となっています。
利益率が低くなりがちな構造的要因
水道工事は、業務内容や市場環境から、いくつか利益率が低くなりがちな構造的要因を抱えています。第一に、工事単価の低迷傾向です。公共工事の予定価格や積算基準が実勢価格や労務費上昇に追いつかず、厳しい価格競争を強いられることが少なくありません。民間工事でも価格競争や値引き要求で、十分な利益を見込んだ価格設定が難しい状況です。
第二に、工事内容の変動要素の多さです。特に地中埋設管工事などは、掘削してみないと地中の状況が正確に分からず、予期せぬ障害物や悪条件下での作業が工期遅延や追加コストを招き、利益を圧迫します。
第三に、季節や天候による影響の受けやすさです。悪天候による工事中断は工期遅延だけでなく、待機時間中の人件費や機材レンタル費を増加させます。凍結対策や熱中症対策など季節に応じた追加コストが発生する場合もあります。
第四に、小規模・短納期案件の多さも利益率を圧迫します。緊急修繕や小規模改修などは、案件規模が小さいため移動や準備・片付け時間の割合が大きくなり、実質的な作業効率が上がりにくく、利益確保が難しい傾向があります。
材料費・人件費の高騰による利益の圧迫
近年の経済状況は、水道工事事業者の経営にとってさらなる逆風となっています。世界的な資源価格上昇や円安の影響で、水道工事に不可欠な主要材料費が高騰しています。仕入れコスト増加が直接的に工事原価を押し上げています。これに加え、建設業界全体で深刻化している人件費の上昇も利益を圧迫しています。熟練工不足は賃金相場を押し上げ、働き方改革関連法による労務コスト増も重なっています。若年層確保のための賃金水準引き上げや福利厚生充実も必要です。
問題は、これらの材料費・人件費高騰分を、受注価格に十分に転嫁できていないケースが多いことです。既存契約では価格改定が難しく、新規案件でも厳しい価格競争のなかでコスト上昇分の上乗せが困難なため、自社の利益を削らざるを得ない状況に陥っています。
水道工事が赤字になってしまう具体的な原因
水道工事が赤字に陥りやすい背景に加え、日々の業務運営のなかに潜む具体的な問題点が、直接的な赤字の原因となっているケースも少なくありません。ここでは典型的な原因を4つご紹介します。原価管理の不備・見積りの甘さ
赤字発生の最も直接的かつ根本的な原因の一つが、原価管理の不備と、それに起因する見積りの甘さです。工事開始前にコストを正確に見積り、期間中は予算内でコストを管理し、完了後に実績と比較分析するという、原価管理の基本サイクルが回っていない場合、赤字リスクは必然的に高まります。「どんぶり勘定」と呼ばれる曖昧な原価管理では、日々のコストを正確に把握せず、工事終了まで実際の費用が分かりません。
次に、見積りの甘さも大きな原因です。過去の実績データや最新の単価動向を考慮せず、安易に見積りを作成すると、受注できても利益が出なかったり、赤字になってしまったりする可能性が高まります。実行予算を作成していなかったり、作成しても形骸化していたりする場合も問題です。実行予算は現場が守るべきコスト目標であり、これと実績を比較することで初めて原価管理が可能になります。
追加工事・設計変更によるコスト増
水道工事では、当初計画に含まれていなかった「追加工事」や、途中で仕様が変わる「設計変更」が頻繁に発生します。これらの理由は顧客要望や予期せぬ現場状況、他工事との調整など。問題は、これらに伴うコスト増を適切に管理できていない場合、顧客に適正価格の請求ができず、当初の利益が損なわれ、赤字に転落するリスクが高まることです。追加・変更の発生時、まずはそれに関わる作業内容や必要材料、工数などを正確に見積り、追加費用を算出する必要があります。しかし「現場を混乱させたくない」「顧客との関係性を崩したくない」といった配慮から、追加見積り作成が後回しになったり、どんぶり勘定で行われたりすることも。根拠を明確に示せないと価格交渉で不利になり、十分な費用を請求できないケースもあるでしょう。
さらに、追加・変更工事の費用負担について、事前に顧客と明確な合意がない場合、工事完了後にトラブルとなり、施工業者側がコスト負担せざるを得なくなるケースも少なくありません。
また、追加・変更工事は全体の工期を遅延させ、待機時間中の人件費や機材費増加、場合によっては遅延損害金発生といった、さらなるコスト増を招く可能性もあります。
これらのリスクを回避するためには、契約段階で追加・変更時の費用負担や手続きを明確に取り決めておくことが重要です。そして、追加・変更発生時には、速やかに内容と影響を正確に把握・記録し、根拠ある見積りを作成したうえで、必ず顧客に書面などで合意を得てから作業に着手する必要があります。原価管理システムなどを活用し、追加・変更工事の原価も当初予算と区別して正確に管理・追跡できる体制整備も有効です。
人員計画ミス・作業効率の低下
水道工事の原価構成において人件費は大きな割合を占めるため、現場作業員の配置計画ミスや、現場での作業効率低下は、直接的に労務費を増加させ、赤字の大きな原因となります。人員を過剰に配置してしまうと無駄な人件費が発生し、不足すると残業増や工期遅延で結果的に労務費が増加します。必要なスキルを持つ職人が適切なタイミングで配置されない場合も、作業効率低下の原因となるでしょう。
現場での作業効率低下の例としては、段取り不足があげられます。現場内の整理整頓不足により資材や工具を探す時間が発生することや、作業スペースが狭いことなども効率が落ちる要因です。また、天候による作業中断や、他工事業者との連携不足による手待ちも頻発しがちな要因です。従業員のモチベーション低下も、作業の質・スピードに悪影響を与えます。
これらの労務費の無駄をなくすには、まず過去データなどを参考に適切な人員計画を立てることが重要です。現場では、作業開始前の段取りを徹底し、作業内容・手順・役割分担・必要資材等を明確にします。現場の5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)徹底も基本です。日報などを活用し、日々の作業時間・進捗・問題点を正確に記録・分析し、継続的に改善活動を行います。
原価管理システムと勤怠管理システムなどを使い、リアルタイムで労務費発生状況を把握・比較することも有効です。
下請け業者への過度な依存・単価の圧迫
水道工事業者のなかでも元請け企業の場合、施工の一部または大部分を協力会社(下請け業者)に依頼しています。適切な連携は有効ですが、協力会社への過度な依存により、自社の利益を圧迫し、赤字リスクを高める場合があります。自社の施工能力が低く、多くの業務を下請けに依存せざるを得ない状況は、コスト面でリスクとなるでしょう。外注費は内製の人件費より高くなるのが一般的で、外注比率が高いほど利益幅は小さくなります。複数下請けが関わることで、指示系統の複雑化や連携ミスによる効率低下の可能性もあるでしょう。
次に、協力会社との価格交渉力も重要です。常に言い値で発注したり、特定業者に依存したりすると、市場価格より高い単価で支払っている可能性があります。逆に、元請けの立場を利用し、下請けに過度に厳しい価格を要求すると、短期的にはコストを抑えられても、長期的には品質低下や協力会社の経営圧迫リスクを招きます。
これらの問題を回避するには、まず自社のコア技術・施工能力を高め、可能な範囲で内製化を進める努力が重要です。外注時には、複数の業者から見積りを取り、価格だけでなく技術力・実績・信頼性等を総合評価し、適正価格で発注しましょう。
また、協力会社との間で契約内容・仕様・責任範囲を明確にし、良好なパートナーシップを構築することも大切。原価管理システムなどで協力会社ごとの実績やコストパフォーマンスをデータ分析することも有効です。
赤字を防ぐための管理・業務改善ポイント
水道工事で赤字を発生させないためには、日々の管理体制と業務プロセスに潜む問題点を特定し、具体的な改善策を講じる必要があります。ここでは、赤字防止に特に重要な4つの管理・業務改善ポイントを解説します。現場の原価管理を徹底する
赤字を防ぐための最も基本的かつ重要な取り組みは、現場レベルでの原価管理の徹底です。「どんぶり勘定」から脱却し、発生コストを正確に把握・管理する仕組みの構築・運用が不可欠です。まず、工事ごとに正確な実行予算を作成します。これは現場が守るべきコスト目標値。過去データや最新単価を基に、材料費、労務費、外注費、経費などを詳細に予算化しましょう。
次に、日々発生する実績原価を正確かつタイムリーに記録・集計します。材料仕入伝票、使用記録、作業日報、外注費支払記録、経費領収書などを漏れなく収集し、データ化しましょう。
そして、原価管理システムを活用し、集計した実績原価と実行予算を定期的に比較・分析し、予算に対する実績進捗、超過しそうな費目、原因などをモニタリングします。
予算超過の兆候が見られたら、速やかに原因究明と対策を講じましょう。材料費が超過しているなら仕入れ価格の見直し、使用方法の改善、追加請求の検討など、具体的なアクションを起こします。問題が小さいうちに対策することで赤字拡大を防げます。
この「実行予算作成 → 実績原価把握 → 予算実績比較・分析 → 対策実行」という原価管理のPDCAサイクルを全工事で徹底することが、水道工事で赤字を防ぐ最も確実な方法です。
見積り精度を上げる
水道工事における赤字の原因の多くは、工事開始前の「見積り」段階に潜んでいるといって良いでしょう。安易な価格提示やコスト見落としのある「甘い見積り」は赤字に直結します。赤字防止には、見積り精度を可能な限り高める努力が不可欠です。第一歩は、過去の類似工事における正確な実績原価データを蓄積・活用することです。経験や勘だけでなく、客観的データに基づき積算することで、見積りのブレが減り精度が高まります。そのためには、日々の原価管理を徹底し正確な実績データを蓄積することが前提となります。
次に、常に最新の材料単価や労務単価情報を反映させることも重要です。古い単価情報での見積りは、実際のコストとの乖離を生み利益を圧迫します。仕入れ先からの最新見積りや公表されている物価・労務単価情報を常にチェックし反映させるように習慣化しましょう。
また、直接工事費だけでなく、現場経費や一般管理費といった間接コストも適切に見積りに計上します。これらの計上漏れや過小見積りは、最終的な利益を圧迫します。諸経費の計上ルールを社内で明確化することが重要です。
さらに、見積り作成プロセスを標準化し、ダブルチェック体制を導入することも有効です。社内で統一された積算基準やフォーマットを整備することで、担当者による精度のばらつきを防げます。作成された見積りは、必ず別の担当者が内容をチェックするプロセスを設けることで、ヒューマンエラーリスクを低減できます。
「plusCAD水道」のように、水道工事専用の積算見積ソフトやCADソフトの活用も、精度向上と効率化に大きく貢献します。「自動材料拾い出し」「最新単価マスタ連携」「諸経費自動計算」などの機能が手作業によるミスを減らし、迅速かつ正確な見積り作成を支援します。
日報・進捗管理で工数の「見える化」
水道工事の原価構成において労務費は大きな割合を占めるため、「誰が」「どの工事に」「どれだけの時間」を費やしたかを正確に把握・管理することは、赤字防止に極めて重要です。これを実現する基本ツールが「日報」であり、日報を活用した進捗管理による工数の「見える化」が求められます。従来の手書き日報では、記入内容のばらつき、記録の曖昧さ、提出遅れといった問題があり、正確な労務費の把握や進捗評価が困難でした。
改善策として、まず日報フォーマットを標準化し、作業日、作業者、工事名、コード、作業内容、作業時間、使用材料、機材、問題点といった記録項目を明確に定義します。そして、全作業員が毎日、作業終了時に必ず日報を作成・提出するルールを徹底します。
さらに効率化と精度向上には、日報作成のデジタル化が有効です。施工管理アプリや勤怠管理システム、原価管理システムの日報機能などを活用し、スマホからでも簡単に入力・提出できるようにしておくとよいでしょう。これにより手書きの手間や判読不能リスクがなくなり、提出漏れも防ぎやすくなります。
重要なのは、日報を記録で終わらせず「進捗管理」に活用することです。日報データを集計し、各工事への投入工数を把握したうえで、予定工数と比較して「予定より大幅に工数がかかっている工事はないか?」「特定の作業で時間がかかりすぎていないか?」といった問題点を早期に発見しましょう。
日報を活用して日々の工数を正確に「見える化」し、予定工数や出来高と比較・分析することで、労務費の無駄遣いを早期に発見し、作業効率改善に繋げられるのです。
無駄な作業・待機時間の排除
水道工事の現場では、直接的な施工作業以外にも、さまざまな「無駄な作業」や「待機時間」が発生しがちです。これらは積み重なると大きなコスト増となり、赤字の原因となります。「無駄な作業」の典型例は、手戻り作業、資材・工具の探索、非効率による過剰な移動などです。
また、「待機時間」としては、段取り不足による手待ち、他工事業者との連携不足による待ち、悪天候による作業中断などが挙げられます。
これらの無駄を排除するには、事前準備と段取りを丁寧に行うことが重要です。作業開始前に関係者全員で作業内容、手順、必要資材、役割分担、安全注意点などを確認・共有するとともに、図面や指示書も事前に十分確認し、疑問点を解消しておきましょう。
次に、現場の5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を徹底し、常に資材・工具が所定場所にあり、作業スペースが確保された状態を維持します。これにより探索時間を削減し、安全で効率的な作業環境を実現できるでしょう。
また、工程管理の精度を高め、関連業者との綿密な連携を行うことも不可欠です。各工程の予定を明確にし、進捗状況をリアルタイムで共有することで、手待ち時間を最小限に抑えられます。
さらに、日報や作業記録を通じて、どのような無駄が発生しているかを「見える化」し、原因を分析して継続的に改善策を実施することも重要です。「なぜ手戻りが発生したか?」「なぜ材料が足りなくなったか?」といった問いを繰り返し、根本原因にアプローチしましょう。
利益を確保するための戦略的アプローチ
赤字を防ぐ守りの管理・改善に加え、積極的に利益を確保し事業を成長させる「攻め」のアプローチも重要です。ここでは、水道工事事業者が持続的に利益を上げていくための戦略的な考え方と具体的な取り組みを解説します。高収益案件の選定と受注管理
全ての水道工事案件が同じように利益を生むわけではありません。利益を安定確保するには、自社にとってどのような案件が高収益に繋がりやすいかを分析・特定し、そうした案件を戦略的に選定・受注していく視点が重要です。まず、過去の工事実績データを分析し、高い利益率をもたらした工事の種類・規模・条件等の傾向を把握して、自社ならではの「勝ちパターン」を見つけ出します。
次に、分析結果に基づき、自社の強みを活かせる高収益が見込める案件領域を特定して、そこに営業リソースを重点投入します。「選択と集中」により受注活動の効率と質を高められるでしょう。
また、新規案件受注時には、単価だけでなく採算性を十分に吟味します。精度の高い見積りはもちろん、潜在リスクも考慮し、十分な利益が見込めるか、将来の優良顧客となる可能性などを総合的に判断します。ときには「安すぎる」「リスクが高すぎる」案件を断る決断も必要です。
さらに、受注案件情報を一元管理し、進捗状況や採算性を継続的にモニタリングする体制も重要です。原価管理システムなどを活用し、どの案件が順調か、注意が必要かを常に把握し、問題の早期発見・早期対応に繋げます。
ITツールによる業務効率化
水道工事業者が利益確保と競争力強化を図るうえで、ITツール活用による業務効率化は不可欠な戦略です。人手不足やコスト上昇圧力が強まるなか、限られたリソースを最大限活用し生産性を向上させるには、デジタル技術の活用が鍵となります。ITツール導入の目的は主に「時間の創出」「ミスの削減」「情報の可視化・共有」です。
水道工事専用CADソフトの「plusCAD水道V」を使用することで、図面作成から材料拾い出し、見積書作成までを連動し、作業時間を劇的に短縮でき、「時間の創出」「ミスの削減」「情報の可視化・共有」という3つの点で有力です。
外注とのバランスと職人の育成
水道工事事業の運営において、内製化と外注化のバランスは経営戦略上の重要な判断事項です。利益確保と持続的成長のためには、このバランスを戦略的に考え、同時に自社の核となる「職人」育成にも注力する必要があります。まず自社の「コア業務」と「ノンコア業務」を見極めます。自社の強みであり品質・利益に直結する基幹工事は、できる限り内製化を目指し、自社職人の技術力向上に注力します。これによりコスト競争力と品質安定化、技術ノウハウ蓄積を図ることができるでしょう。
「自社職人の育成」においては、OJTに加え、資格取得支援、社内勉強会、外部研修などで技術・知識向上をサポートし、仕事への誇りや責任感、コミュニケーション能力といった人間的成長も促す環境を整えることで、定着率向上や将来のリーダー育成が期待できます。
そのうえで、専門性が特に高い工事や一時的な業務ピークには、信頼できる協力会社を厳選し、良好なパートナーシップの下で戦略的に外注を活用することが理想的です。
支出の見直しと固定費の最適化
水道工事で利益を確保するには、売上増だけでなく、日々の「支出」を徹底的に見直し、無駄を削減する地道な努力も不可欠です。特に、売上に関わらず発生する「固定費」の最適化は、損益分岐点を下げ、利益を出しやすい体質を作るうえで非常に重要です。
まず、全ての支出項目を洗い出し、必要性やコスト削減の余地を見直します。例えば、材料仕入れでは、特定業者に依存せず複数社から相見積りを取り価格交渉を行ってみましょう。
原価管理ソフトで業務を可視化・改善するのもおすすめ!
水道工事の赤字原因の多くは、「原価が見えない」「管理が効率的でない」ことに起因します。これらの課題を解決し、赤字を防ぎ、利益を確保するための強力な武器が「原価管理ソフト」の導入・活用です。専用ソフトを用いることで、煩雑で曖昧になりがちな原価管理業務を劇的に可視化・改善できます。現場ごとの採算をリアルタイムで把握
原価管理ソフト導入の最大のメリットの一つが、現場ごとの採算状況を、リアルタイムかつ正確に把握できる点です。従来のExcelや手作業では、コストデータを集計し実行予算と比較するのに時間がかかり、月次や工事完了後にならないと最終損益が分からないのが一般的でした。これでは問題の早期発見・早期対応が困難です。原価管理ソフトを導入し、日々の実績データをシステムに反映する仕組みを構築すれば、ソフトウェアが自動でデータを集計・計算し、現時点での各現場の実行予算に対する原価進捗率、想定利益、予算超過リスクなどをいつでも即座に確認できます。ダッシュボードやグラフで視覚的に表示され、経営者や管理者は直感的に各現場の採算状況を把握できるのです。
過去の工事データからコストの傾向分析
原価管理ソフトは、現在のコスト状況把握だけでなく、過去に実施した膨大な工事データを蓄積・分析し、将来の経営に役立つ貴重な知見を引き出すデータベースとしても機能します。手作業やExcel管理では埋もれてしまいがちだった過去データも、原価管理ソフトなら構造化された形で蓄積され、容易に検索・分析が可能になります。これにより、過去データをさまざまな切り口で検索・抽出し、分析することが可能になります。職人の稼働状況・工数配分の最適化
水道工事の原価で大きな割合を占める労務費管理において、職人の稼働状況を正確に把握し、各工事へ適切に工数を配分し、無駄な時間を削減することは、赤字防止と利益最大化に極めて重要です。原価管理ソフトは、勤怠管理システムや日報機能との連携を通じて、この職人稼働状況と工数配分の「見える化」と「最適化」を支援します。従来の日報管理では困難だった、複数現場掛け持ち時の工数割り振りなども、システムを活用すれば正確に行えるようになります。職人自身がスマホ等で日々の作業時間や従事工事を記録すれば、データは自動的に原価管理ソフトに集約され、「どの工事に」「どの職人が」「どれだけ工数」を投入したかがリアルタイムで把握可能に。これにより、各工事の予定工数に対する実績工数の進捗を正確にモニタリングでき、「予定より大幅に工数がかかっている工事」や「特定の作業に時間がかかりすぎている職人」などを早期に特定し、原因究明と必要なサポート・改善策を講じられます。
まとめ|赤字工事を防ぐカギは「可視化」と「先手の対応」
本記事では、水道工事における赤字発生の背景と原因、そしてそれを防ぎ、着実に利益を確保するための管理・改善ポイントと戦略的アプローチについて解説しました。赤字を防ぐ最大のカギは「現状を正確に把握すること」と「問題の兆候を早期に捉え、先手を打って対応すること」。これを実現する最も有効な手段が、原価管理の徹底であり、それを支えるITツールの戦略的活用です。
そこでお勧めしたいのが、建設業向け原価管理ソフト「要 〜KANAME〜」です。原価と利益の「見える化」を通じてどんぶり勘定からの脱却を支援し、全社的なコスト意識向上を促進。データに基づいた客観的な経営判断を可能にし、企業の収益力強化と持続的成長をバックアップします。分かりやすいインターフェースで、ITに不慣れな方でも導入・運用しやすい点も魅力です。
▼建設業向け原価管理ソフト「要 〜KANAME〜」の詳細・資料請求はこちら▼ https://www.pluscad.jp/products/kaname/