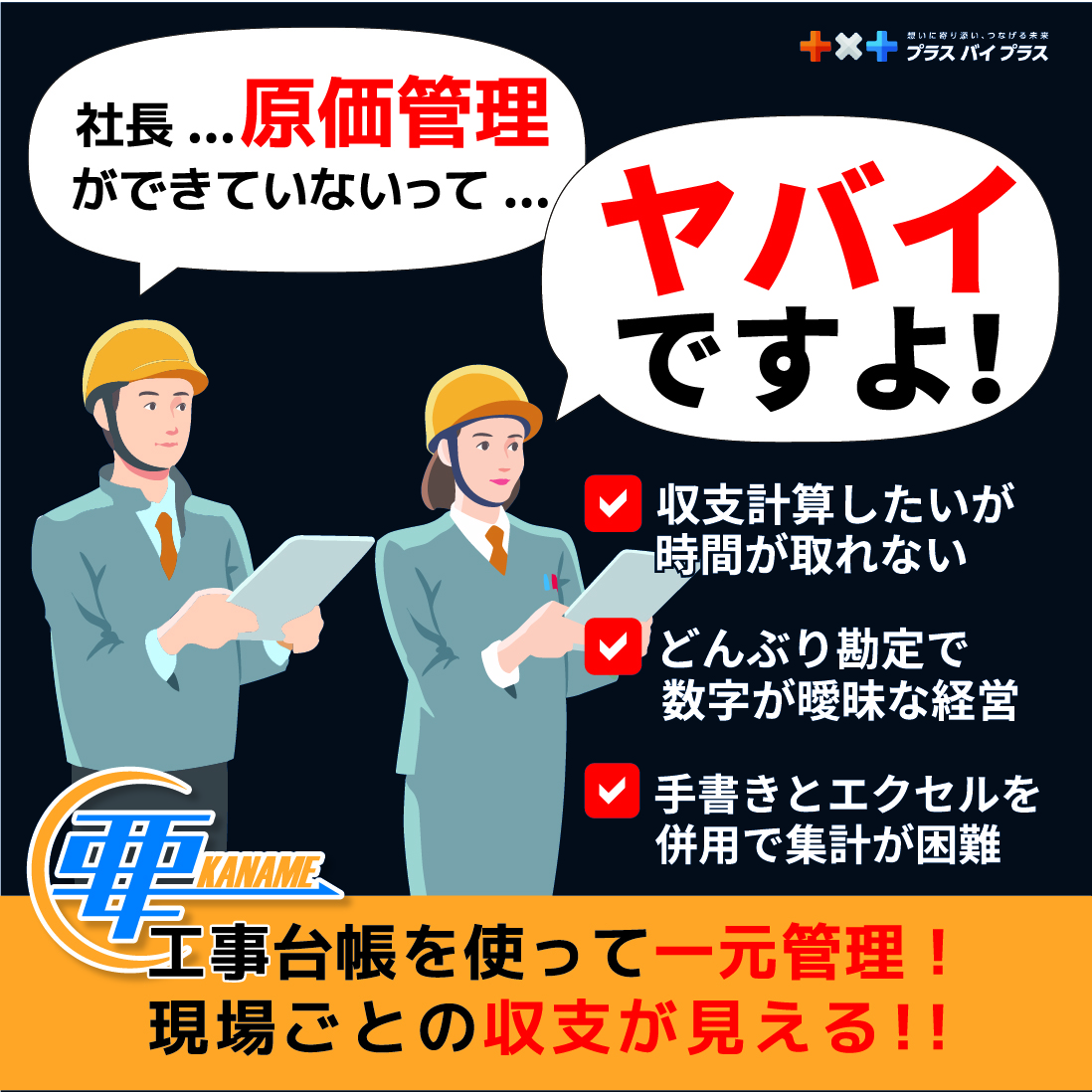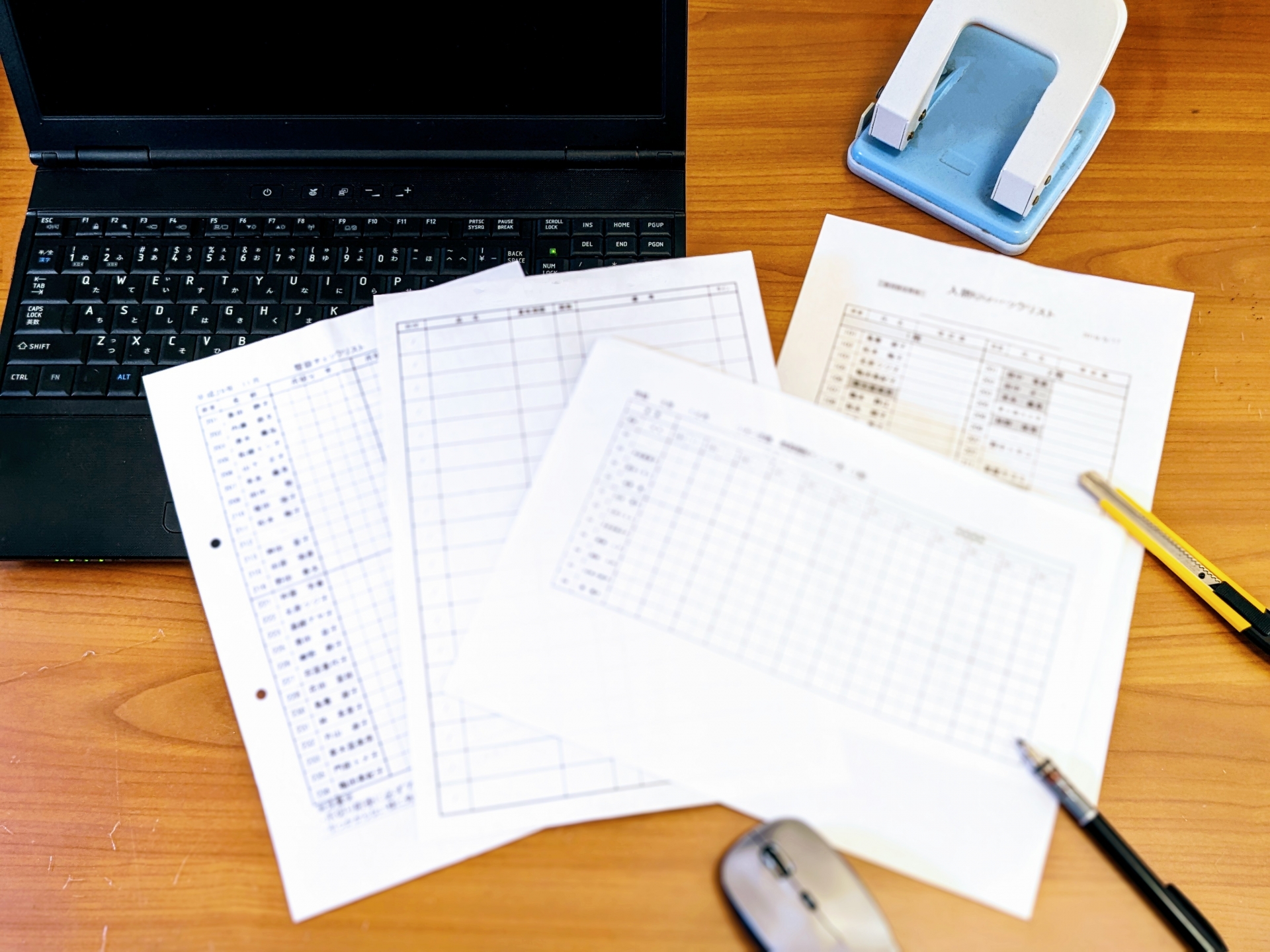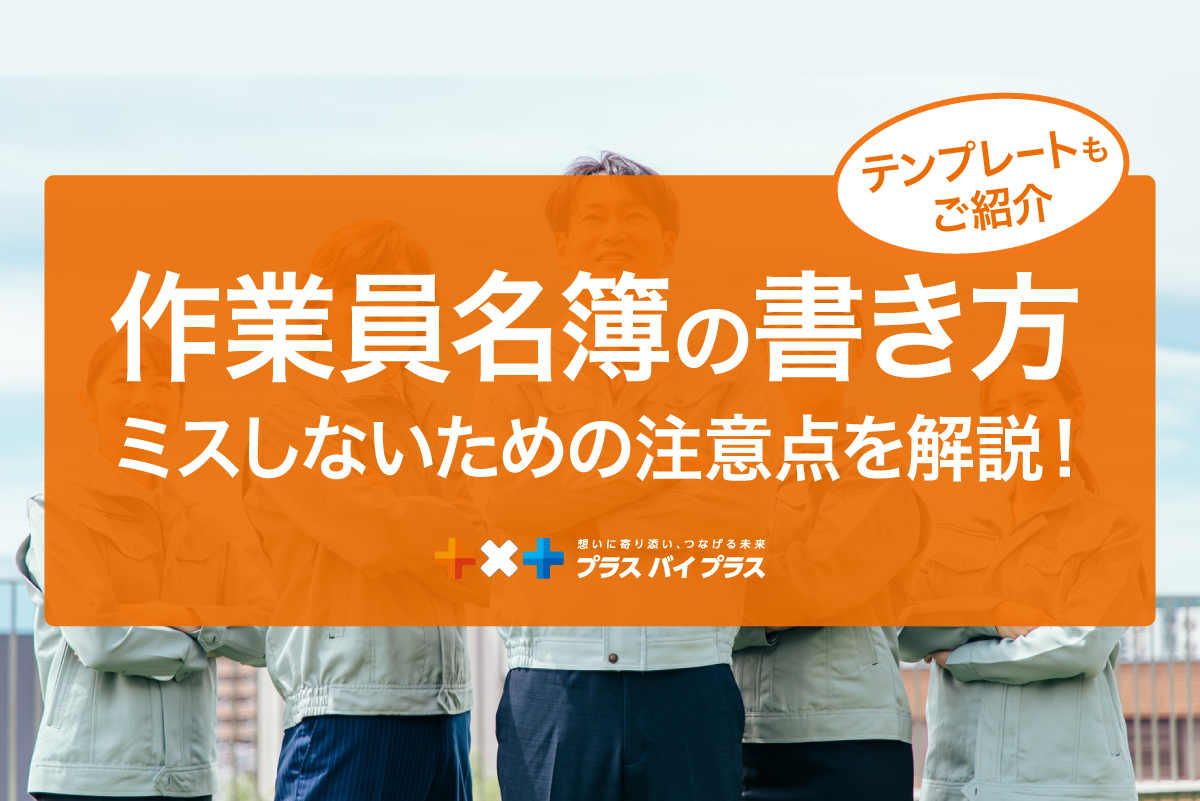- 2025年10月16日
建設現場の書類電子化で業務効率アップ!メリットと課題を徹底解説

近年、DX化が急速に進むなかで、建設業においても業務効率化や生産性向上が喫緊の課題として求められています。特に電気、空調、水道、屋根、リフォーム業、技能工(外装・左官・内装工事)といった29工種に携わる企業は、取り扱う書類が膨大であるにもかかわらず、従来の紙媒体での書類作成や管理が大きな業務負担となってきました。
この「現場 書類電子化」の遅れは、書類の紛失リスクや情報共有の遅延といった深刻な課題を業界全体に生み出しています。
この記事では、なぜ今建設現場で電子化が必要とされているのか、電子化がもたらす具体的なメリット、そしてシステム導入後に直面しがちな課題を解説します。
コンテンツ
なぜ建設業の現場で書類電子化が求められるのか
建設業の現場で書類電子化が求められる背景には、法律によるデータ保存の義務化という外部要因や、業界特有の非効率な「紙文化」の限界があります。紙文化の限界と非効率性
建設業における「帳票」とは、一般的な会計における請求書・領収書・契約書などの伝票の総称に加え、施工体系図、施工計画書、現場点検表といった膨大な資料の総称です。これらの帳票を紙ベースで管理する方法は依然として普及しており、帳票作成なども紙ベースで実施している企業が多い傾向にあります。しかし、紙の運用は、これらの書類の作成や管理にかかる業務量が非常に多く大変な作業となります。書類の作成・管理に多くの工数が割かれているのが現状であり、紙の書類では、設計変更時や見積り内容変更時の修正、さらには印刷に要する手間が大きく、業務効率化の大きな妨げとなっていました。また、紙ベースでの管理は誰でもかんたんにできる反面、現場で記録した情報を事務所に戻ってからデータ化する手間など、後処理工数が多く発生し、非効率になっています。
書類紛失リスクと管理負担
国税に関係する書類は、紙で扱う場合は紛失のリスクがあるため丁重に保管されてきましたが、紙ベースで管理している場合、帳票の移動や移し替えなどにより紛失するリスクが伴います。電子化によって、書類の持ち運びや保管で紛失するリスクを抑えることができます。また、建設業者は建設業法に基づき、帳簿及び営業に関する図書を定められた期間保存しなければなりません。電子帳簿保存法においては、原則、事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存義務が定められています。一方、建設業法においては、建設工事の目的物の引渡しをしたときから原則5年間(住宅を新築する建設工事に係るものにあっては10年間)と定められており、法律によって保存期間や起算点が異なるため注意が必要です。
単純に保管する資料が多いことに加え、紙媒体での長期保管は、国税関係帳簿等の保存のために社内に書庫スペースを確保する必要が生じるなど、事業者にとって大きな課題となっています。
情報共有のスピード不足
従来の紙ベースでのやり取りでは、情報共有のスピードに限界がありました。現場で作成した帳票を事務所に戻ってからデータ化する作業が発生したり、必要な資料を探す際に時間と人的コストがかかったりします。工事請負契約書や請求書などの取引書類を書面で取り交わす場合、押印や郵送に要する時間と手間が発生し、顧客とのスムーズな取引を妨げる要因となります。電子化システムを導入することで、取引先とのやりとりをシステム上で完結できるため、関連書類なども迅速に探せるようになり、業務全体が効率よく進むでしょう。
業界全体のデジタル化推進
近年、建設業界のDX化が進展し、帳票の電子化が促進されてきています。特に、2024年1月1日からは、電子帳簿保存法の改正により「電子取引データ保存の義務化」が適用されました。これにより、電子メールなどで授受した注文書、契約書、見積書、領収書などの取引情報(電子取引データ)は、定められた保存要件に従って電子データとして保存することが、全ての対象者に義務付けられています。電子データによる保存は「電子帳簿等保存」(電子的に作成した帳簿・書類を電子のまま保存)、「スキャナ保存」(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)、「電子取引データ保存」(電子的に授受した取引情報をデータで保存)の3つの区分に分類されています。
この義務化の要件には、真実性の確保(改ざん防止のための措置)と、可視性の確保(電子データの検索を可能にするための措置)を講じることが明確に定められています。
さらに、2024年4月からは建設業に時間外労働の上限規制が適用されるなど、働き方改革が進む中、生産性の向上は必須であり、電子取引の導入による移動時間の削減や図面・品質管理書類のデジタル化が推進されています。
書類電子化のメリット
書類電子化の推進は、建設業における業務の効率化、コスト削減、セキュリティ強化に大きく貢献します。検索性・共有性の向上
契約書や図面、仕様書などさまざまな書類を電子化し、クラウド型システムで管理すれば、パソコンやタブレット端末から管理・確認できるようになります。電子帳簿保存法の保存要件の一つである検索機能を満たせば、自身のPCやタブレットから、即座に情報を引き出すことができ、情報共有が容易になります。これにより、資料を探す際の人的コストを減らせることもメリットです。また、部署を横断する請求書なども一元管理でき、社内の情報共有がシンプルになります。
保管コストとスペースの削減
電子帳票を導入することで、紙ベースで必要だったコピー用紙やファイル代などの費用が不要となり、大幅なコスト削減が見込めます。さらに、工事請負契約書や工事注文請書を電子取引で行う場合は、契約金額に応じた印紙税がかからないため、印紙代などの経費削減が可能です。印紙代のみで年間数億円削減できたという事例もあり、経費削減効果は計り知れません。印紙代だけでなく、協力会社と現場、現場と支店などで毎月行われていた請求書の郵送費用や、その手間なども削減可能です。ペーパーレス化が進むことで、国税関係帳簿等の保存のために社内に書庫スペースを確保する必要もなくなります。
業務スピードの向上
電子化は、業務の効率化を可能にし、業務スピードの向上につながります。現場で入力した帳票は即データ化され、オフィスに戻ってからのデータ入力作業(後処理工数)を大幅に短縮できます。また、電子帳票システムを利用すれば、帳簿等の保管・管理にかかる時間を大幅に削減でき、取引先とのやりとりもシステム上で完結できるため、業務全体が効率よく進みます。従来の紙媒体の管理で発生していた、打ち間違いや送信ミスといったヒューマンエラーの軽減にもつながります。
リモート対応との相性
電子化を進めることで、現場での作業効率が向上し、働き方改革に寄与します。iPadなどのタブレット端末を活用すれば、外出先でも書類の確認がスムーズに行え、業務の効率化が可能です。特に図面は枚数が多く嵩張りますが、タブレット端末なら時間や場所を問わずアクセスでき、常に綺麗な状態で閲覧・書き込みができます。これにより、今まで事務所でないと出来なかった書類作成が現場で完了することが可能になってきており、移動時間の削減にもつながります。
エコ・環境負荷の軽減
ペーパーレス化は、印刷代や用紙代などのコスト削減に直結するだけでなく、エコな取り組みとしても重要です。特に図面など、枚数やサイズが大きく嵩張る資料が多い建設業界において、紙の消費を抑えるデジタル化は環境負荷の軽減に大きなメリットをもたらします。現場で進む電子化の具体例
建設業界では、取引書類から現場資料に至るまで、多岐にわたる書類の電子化が進んでいます。施工図・日報の電子化
写真台帳の簡単な作成や手書き入力にも対応し、タブレット端末を活用して報告書作成を現場で完結させることができる現場帳票システムが現場で有効活用されています。また、スマートフォンやタブレットを利用して現場で帳票作成ができ、事務所に戻ってからのデータ化の手間や作成ミスを大幅に軽減できるツールもあります。経営支援ソフト「要 〜KANAME〜」は、現場からの日報の入力情報を基に、材料費・労務費の計上が自動で連動できます。これにより、工事ごとの原価・利益をリアルタイムに把握できるようになり、経営に直結させることが可能です。
電子契約・電子請求書の普及
電子帳簿保存法の改正に伴い、請求書や見積書のやりとりは、電子メールやシステムを用いて行われることが一般的となっています。電子取引は印紙税がかからないというメリットがあり、経費削減に貢献します。請求書の受領と電子データ化(スキャン)を代行し、経理業務の省人化に活用できるクラウド請求書受領サービスも存在します。申請/承認・一覧表示・仕分け入力・会計ソフト連携などの機能もあり、部署を横断する社内の請求書を一元管理することも可能です。
タブレットを活用した現場管理
クラウド型システムを活用することで、契約書や図面、仕様書などさまざまな書類をパソコンはもちろん、施工現場でもタブレット端末から手軽に管理・確認できるようになります。タブレット端末は、図面を常に綺麗な状態で閲覧・書き込みができるため、現場管理を円滑にします。現場帳票システムでは、帳票作成だけでなく、図面や写真、PDFなど関連するすべてのドキュメントを作業指示と合わせて一つの端末で確認できるため、一元管理が可能です。建設・工事業に特化した書類管理システムのように、工事情報と関連付けることでスムーズなファイル検索を実現し、セキュリティ強化にもつながるシステムもあります。
写真や図面のクラウド共有
建設業で必要となる工事写真や施工体制台帳などの資料を電子化すれば、スムーズな検索と保管コストの削減を実現できます。デジカメからの写真転送が不要で、タブレットで撮影した写真をそのまま台帳に貼り付けられ、図面や写真への書き込みが可能なシステムもあります。これらのデータは、プロジェクトファイルへのフォルダ自動生成や、BOX、GoogleDriveなど各種クラウドストレージへの自動アップロードも可能で、情報共有のスピードを大幅に向上できます。
発注・検収プロセスのデジタル化
取引書類を電子化することにより、押印や郵送の手間を削減し、顧客とのスムーズな取引を実現できます。また、各担当者が作成した見積りや注文書を一覧で視える化することで、リアルタイムな見込み管理が可能となり、シンプルな経営判断に役立ちます。電子化に伴う課題
電子化は大きなメリットをもたらしますが、導入にあたってはいくつかの課題も存在します。システム導入コストと負担
電子帳票を利用するには、システムやソフトウェアの導入が必要です。導入にあたり、初期費用・運用費用などの継続的なコストが発生します。紙ベースでは発生しなかった費用が発生することがデメリットの一つです。使える機能が豊富なシステムほど高額になる傾向があるため、導入前に「どのような機能が重要か」を吟味し、導入コストと予算を検討することが重要です。操作教育と従業員の定着率
電子帳票の導入は、社内の運用ルールや作業内容の変更を伴うため、組織全体へのルール体系の浸透が課題となります。特に、高齢の作業員が多い建設現場ではデジタルツールの浸透が難しいという懸念もあります。しかし、現場ノウハウの詰まった紙帳票のレイアウトをそのまま電子帳票に移行できるシステムを利用すれば、現場への操作説明が不要で直感的に利用できるため、導入から浸透するまで円滑に進みます。導入企業が「なぜ導入において現場からの抵抗がなかったか」を解説する資料も用意されています。クラウド依存のセキュリティリスク
電子帳票は帳票の紛失リスクを軽減しますが、システム側のエラーやトラブル発生の可能性も考慮し、導入するシステムのセキュリティ対策を確認しておく必要があります。電子帳簿保存法では、真実性の確保のため、タイムスタンプの付与、訂正・削除の履歴が残るシステム等での保存、または事務処理規定を定めて守るなどの措置が定められています。また、物理的なセキュリティ対策として、書類管理システムを利用し、閲覧権限を工事担当者単位で設定することで、社外への情報漏えいを防ぎ、コンプライアンス・セキュリティの強化を図ることも可能です。
電子化しても利益管理は別問題
現場の書類電子化は業務効率化に役立ち、生産性を向上させますが、それだけでは経営分析や利益拡大という経営の目的を達成することはできません。電子化によって現場のデータが集約されても、それを工事台帳と結びつけ、リアルタイムで原価管理や収支把握を行わなければ、シンプルな経営判断を下すことは難しいままです。生産性を向上させ、利益を拡大するという目的を達成するには、国税関係帳簿等を含めた図面などの書類を一括管理できる専用システムの導入が推奨されます。
電子化と連動した原価管理の必要性(要 〜KANAME〜の有用性)
建設業において、生産性をさらに向上させ、利益拡大を目指すには、現場のデータを経営に直結させる仕組みが必要です。経営支援ソフト「要 〜KANAME〜」は、シンプルな経営判断、業務効率化のすべてを叶えることを支援するシステムです。
最大の特長は、工事台帳に情報を集約し一元管理できる点です。見積書、請求、注文書、日報、現場資料等すべてを台帳に紐づけることで、社内の情報共有がシンプルになります。工事台帳ごとにフォルダがつくられるため、工事にまつわる図面や資料をまとめて管理できます。
これにより、工事ごとの収支をリアルタイムに把握することが可能になり、原価管理・分析(工事台帳一覧、工事の収支、グラフ、売上集計)が行えます。特に労務費は、日報からの情報によって自動で人工計算され、現場の情報を経営に直結させることが可能です。
また、作成した見積りや注文書を一覧で視える化することで、リアルタイムな見込み管理が可能となり、経営分析や生産性向上、利益拡大という目的に貢献します。
「要 〜KANAME〜」の導入により、「現場の状況を視える化できて、獲得案件の判断材料が出来た」、「現場で抜けがちの施工費が視えるようになり、見積りの金額があがりました」、「会社の『今』を数字で見れるから経営課題に気づけた」、といった喜びの声が寄せられています。
現場における書類の電子化についてよくある質問
Q1. 建設業で電子帳簿保存法に対応するために、必ずシステムを導入する必要がありますか?
A1. 電子帳簿保存法の要件を満たすために、必ずしも専用のシステムを導入する必要はありません。電子取引データの真実性を確保するための要件(改ざん防止措置)には、タイムスタンプの付与、訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存、または事務処理規定を定めて守るなど、これらのいずれかの措置を行うことが求められています。しかし、建設業においては、建設工事の請負契約など金額が大きく契約期間が長期にわたる取引について、建設業法上の原本性の確保が特に重要とされています。原本性を確保するためには、「公開鍵暗号方式による電子署名や、電子的な証明書の添付」が必要な措置として掲げられています。電子帳簿保存法においては専用のシステムを導入せずとも要件を満たすことは可能ですが、建設工事の請負契約の電子取引は、こうした建設業法上の厳格な要件を満たすためにも、システムやサービスを利用することが望ましいとされています。
Q2. 電子化された見積書などの「一般書類」は、保存要件が緩和されたと聞きましたが、具体的にどう変わりましたか?
A2. 2024年の電子帳簿保存法の改正により、紙で受け渡しが行われた国税関係書類(スキャナ保存の対象)の保存要件が緩和されました。国税関係書類は、資金や物の流れに直結する「重要書類」(契約書、納品書、請求書、領収書など)と、それに直結しない「一般書類」(見積書、注文書、検収書など)に分類されます。改正以前は、スキャナ保存したすべての国税関係書類について、帳簿の記載事項と相互に関連性を確認できるようにする(相互関連性の確保)必要がありましたが、改正により、この要件は「重要書類」のみに限定されました。したがって、見積書や注文書などの一般書類については、帳簿との相互関連性の確保が不要になりました。また、スキャナ保存においては、解像度・階調・大きさに関する情報の保存や、入力者等情報の確認要件も不要となっています。
Q3. plusCADのソフトを利用すると、見積りに関する業務はどのように効率化されますか?
A3. 株式会社プラスバイプラスが提供するplusCADシリーズ(電気CAD、水道CAD、総合CADなど)は、図面作成と見積り作成を連動させることで業務効率化を実現します。例えば、plusCAD電気αやplusCAD総合αなどのソフトでは、「材料の拾い出し『0分』で図面を描けば見積書が自動で完成」するシステムです。これは、電気・空調・設備工事専用のCAD見積り連動システムであり、図面を描くだけで見積書も同時に完成するため、見積り作成時間を大幅に短縮できます。
さらに、積算見積りソフトの見積りプラスは、メーカーカタログ材料約20万点を搭載し、複合単価登録も可能であるため、見積り作業時間全体の大幅な短縮をサポートします。
Q4. 「要 〜KANAME〜」を導入すると、特にどのような業務が改善されますか?
A4. 「要 〜KANAME〜」は、工事台帳をベースにした利益管理システムであり、経営者層、経理担当者、現場管理者など、幅広い層の業務改善に寄与します。経営者にとっては、工事台帳を中心に必要な情報が紐づけられ、顧客ごと、担当者ごとの売上実績や粗利・粗利率、営業利益・営業利益率などが一発で集計できるため、経営分析やシンプルな経営判断を可能にします。
経理担当者にとっては、工事完了のタイミングでの請求書発行やキャッシュフロー管理・集計までを一元管理でき、事務作業が効率化されます。
現場管理者や担当者にとっては、日報からの労務費計算の自動化 や、作成した見積り・注文書などを一覧で視える化し、リアルタイムに見込み管理を行うことができます。また、現場で抜けがちだった施工費が視えるようになり、見積り金額の向上につながったという導入効果も報告されています。
Q5. 電子帳票システムを選ぶ際、セキュリティ面で確認すべきことは何ですか?
A5. 電子帳票システムを選ぶ際は、システムのセキュリティ対策が電子帳簿保存法における「真実性の確保」(改ざん防止)と「可視性の確保」(検索機能など)の要件を満たしているか確認することが重要です。具体的には、真実性の確保のため、タイムスタンプや訂正・削除履歴の保持が講じられているかを確認します。また、システムの利用者に対する権限管理が適切に行われているかを確認することが、情報漏洩を防ぐうえで重要です。書類管理システムにおいては、閲覧権限を工事担当者単位で設定できることで、社外への情報漏洩を防ぎ、セキュリティ強化を図ることができます。システムのセキュリティレベルやバックアップ体制を事前に確認しておくことで、トラブル発生時への備えとなります。