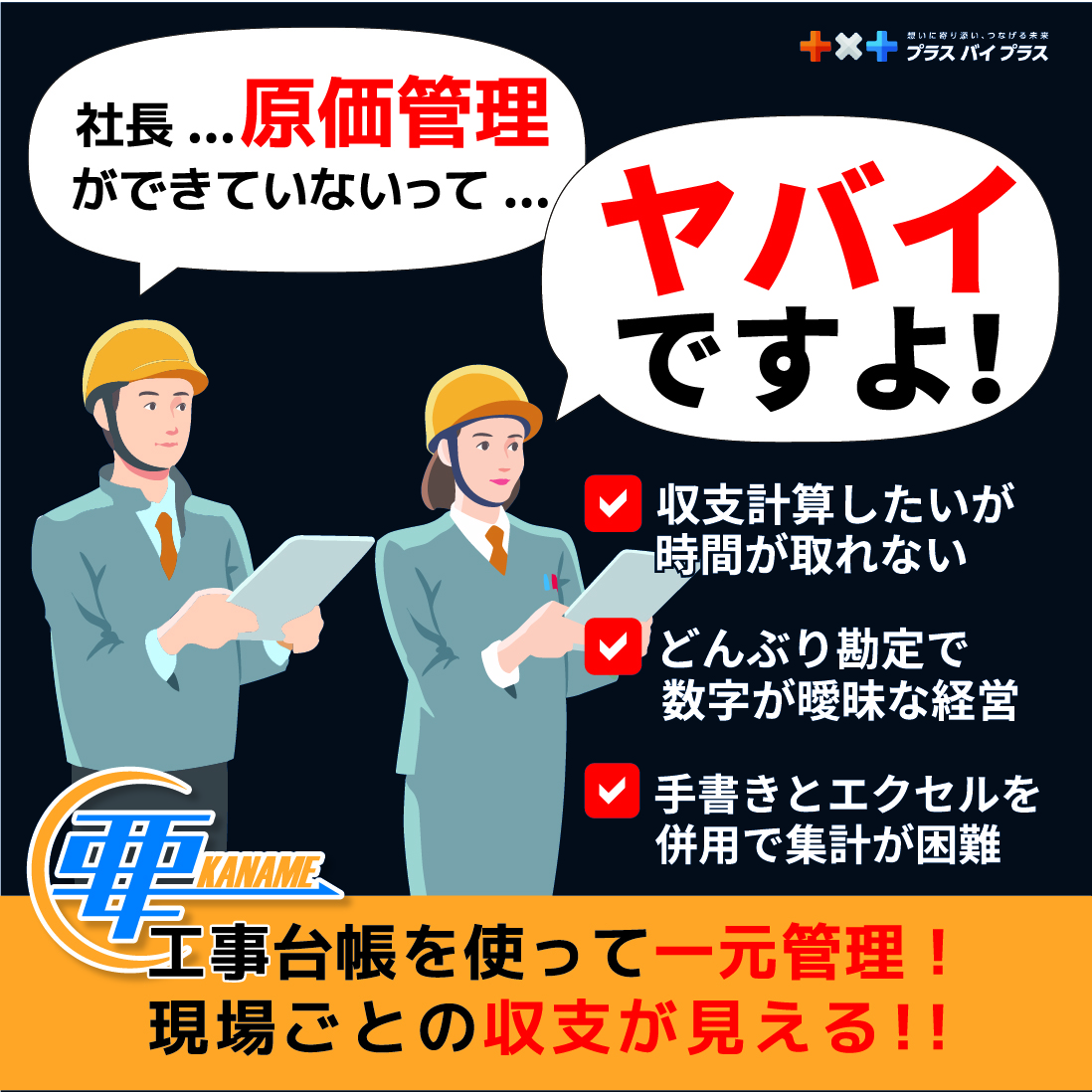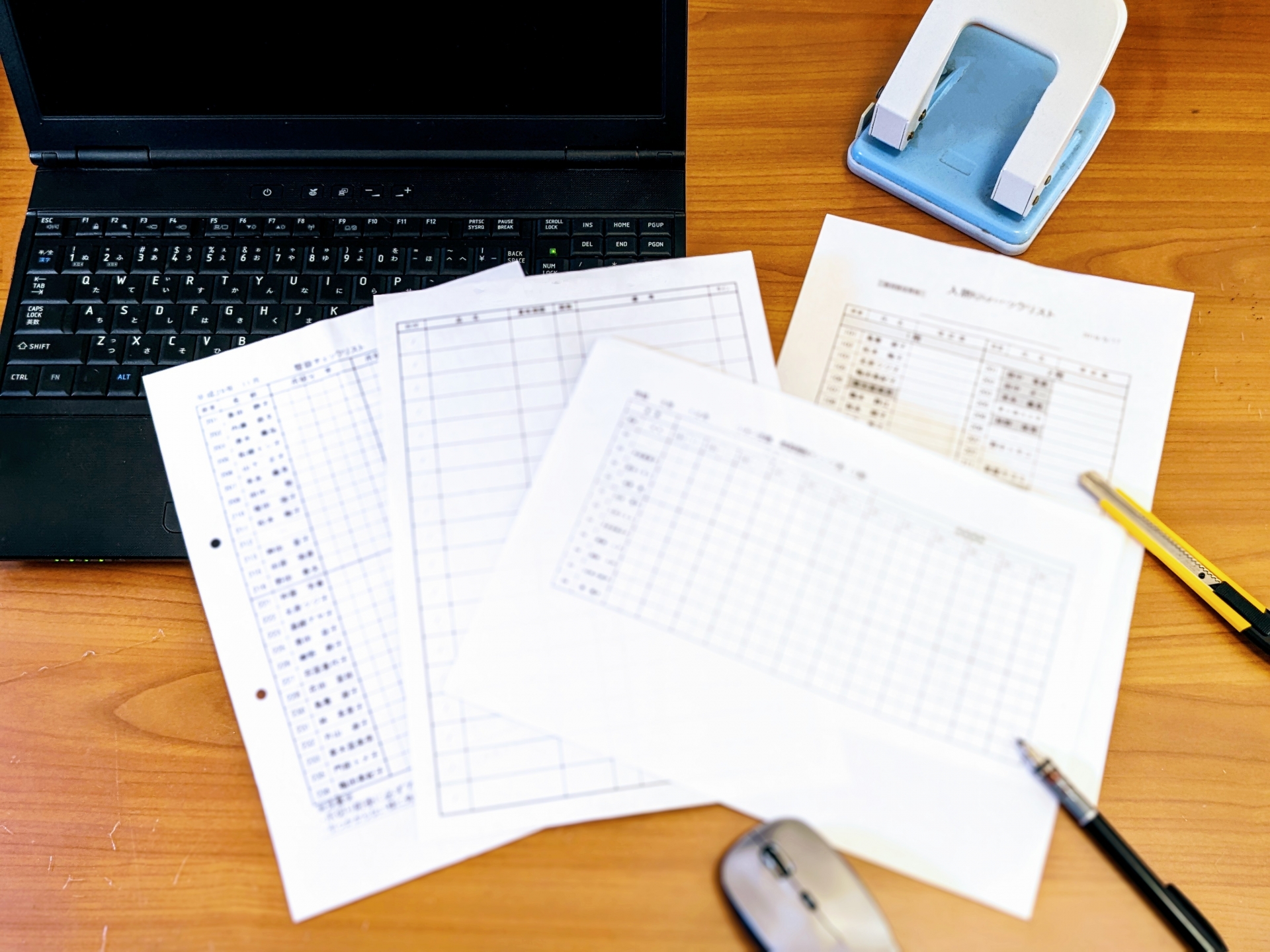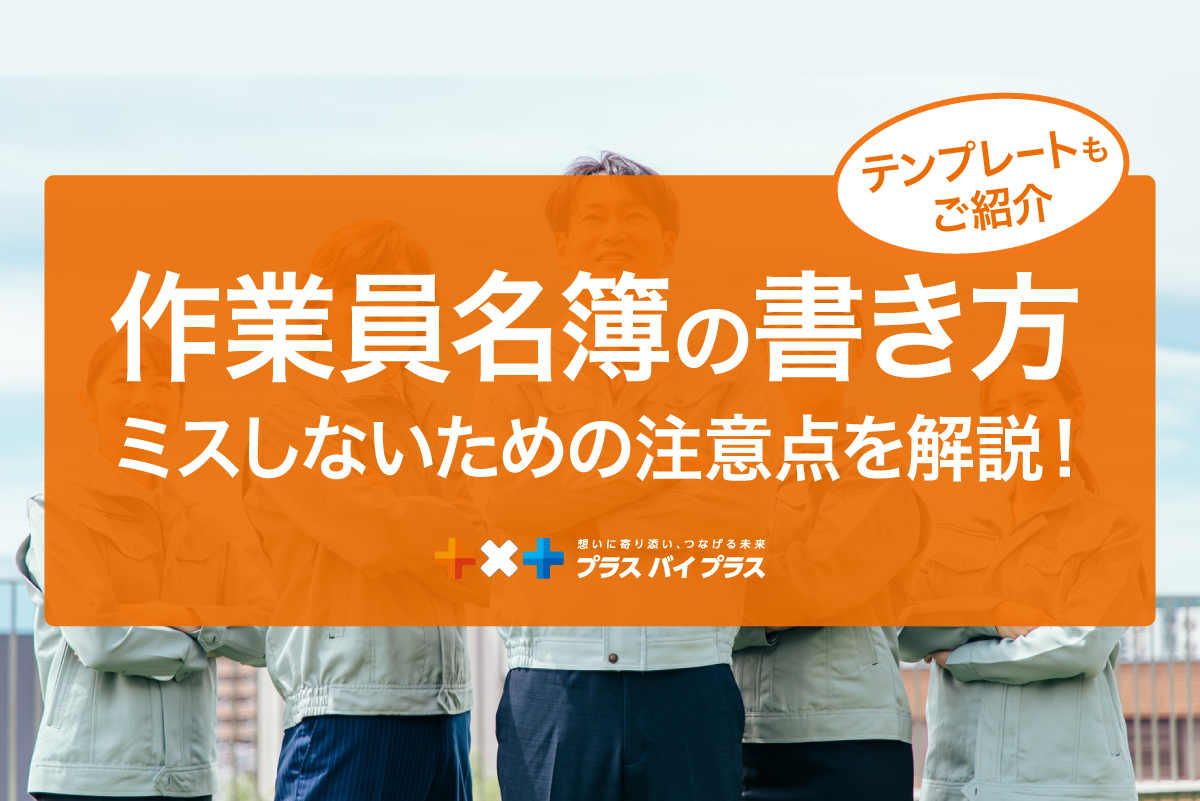- 2025年10月17日
工事現場におけるAI活用方法とは?安全管理・効率化・利益確保の実例

建設業界は今、深刻な人手不足と高齢化、長時間労働という課題に直面しており、生産性向上と安全確保の両立が喫緊の課題となっています。
こうした背景から、工事現場AI活用は建設DXを推進するための重要なテーマです。AI技術は、施工管理から事故予防、そしてコスト管理に至るまで、現場のあり方を劇的に変える可能性を秘めています。
この記事では、建設現場におけるAIの具体的な活用事例と期待できる効果、そしてAI導入の成果を最大化するために不可欠な要素について詳しく解説します。
コンテンツ
建設業界で注目されるAI活用の背景
建設業界で工事現場AI活用が急速に注目を集める背景として、主に以下の4点があげられます。現場の人手不足・高齢化
建設業界では、人口減少や少子高齢化に伴う人手不足が深刻化しています。国土交通省のデータによると、建設業就業者数は平成9年のピーク時、平均685万人と比べて、令和4年度平均では約30%減少し、479万人となっています。さらに、建設業就業者のうち55歳以上が35.9%を占める一方で、29歳以下は11.7%に留まっており、高齢化が進行していることが分かります。専門知識を持つ技術者が高齢化する中で、次世代への技術継承が滞っている点も大きな課題です。
また、2024年4月からは労働基準法の改正により、建設業でも時間外労働の上限規制(原則月45時間かつ年360時間)が適用されており、今後、働き手の不足がより表面化すると考えられています。このため、人材不足の解消や技術継承の困難さを補う手段として、AIの活用に期待が集まっています。
生産性向上と安全確保のニーズ
建設業では、長時間労働の問題も深刻です。国土交通省の調査では、建設業の令和3年度の年間総実労働時間は全産業平均と比較して90時間長いというデータが出ています。また、建設業者においては週休2日の確保率が他業種に比べて低いことにも課題があります。このような長時間労働の是正が求められるなかで、AIによる業務効率化や生産性の向上が急務とされています。また、建設現場は危険が伴う場所もあり、安全性の向上が長年の課題です。死亡災害は過去50年間で大幅に減少したものの、業種別に見ると建設業がトップであり、依然として安全性向上のニーズは高い状況です。事故の内訳としては、墜落や転落が最も多くを占めており、AIによるリスク検知や安全対策への活用が強く求められています。
海外で先行するAI導入
日本の建設業界ではDX化やIT技術の浸透が他の業界と比較して遅れているという実情がありますが、海外ではAI技術やデジタル技術を活用した建設DXが先行しています。海外の事例では、AI画像生成を用いて建築物デザインや構造データを分析し、イメージ図を作成することで、関係者からの承認を得やすくし、トラブルを防ぐなど、設計業務の効率化にAIを活用しています。
また、AIが資材調達パターンや工事フローを分析することで、最適な工事計画を策定し、現場のミスやスケジュールの遅延を減らしています。AIは、過去の事故データや現場状況を分析し、リスクが高まる場面を特定することで、安全管理に役立てられています。海外の事例が示すように、AIの導入は労働力不足や長時間労働の是正、安全性向上といった課題を解決する可能性を秘めており、日本でもその動向を参考に導入が進められています。
国土交通省が進めるDX政策
工事現場AI活用を後押ししているのが、国土交通省が推進するDX政策です。国土交通省は2017年から「第4期国土交通省技術基本計画」を発表し、人を主役とするIoT、AI、ビッグデータなどを積極的に活用していく方針を示しています。また、建設現場の生産性を向上させ、魅力ある現場を目指す取り組みとして「i-Construction」を推進しています。i-Constructionは「ICT(情報通信技術)の全面的な活用」を柱の一つとしており、官民が協力してICT導入を強化しています。
さらに、平成29年6月には「未来投資戦略2017」が閣議決定され、AIやロボットの活用により、あらゆる建設現場の生産性を2025年までに2割向上させるという具体的な目標が設定されています。これにより、「土日の休日をきちんと確保する」ことを目指しており、国全体としてAI導入による建設DXを強力に推進しています。
工事現場におけるAIの具体的な活用事例
実際に工事現場AI活用は多岐にわたり、現場の効率化と安全確保に直結する具体的なAI技術の活用事例を解説します。施工管理における AI画像解析
AI画像解析は、現場のカメラ映像や写真データをAIが解析することで、施工管理における進捗把握や品質チェックを自動化します。具体的な用途としては、現場の資機材をAIが認識し、その位置を現場の3Dモデル上に表示することで、資機材管理の作業時間を大幅に削減できます。また、コンクリートの品質管理では、生コン車から荷下ろしをする様子をカメラなどで撮影することで、AIがコンクリートのスランプを測定し続け、品質に問題がある場合は担当者に警告を出すシステムも活用されています。この技術は、進捗状況の自動把握や品質チェック、設計図との照合などにも応用されており、人的リソースを削減し、業務効率化に貢献しています。
重機・資材の最適配置
AIは、現場のレイアウトや作業動線を分析し、重機や資材の最適な配置計画を策定することで、移動ロスの削減や作業時間の短縮を実現します。建設機械の自律走行化も進んでおり、操作者が具体的な作業内容を設定するだけで、設定通りの施工を自動で行うブルドーザーなどの自律施工技術が開発されています。このような自律施工が実現すれば、現場の生産性を大幅に向上させることが可能です。
さらに、現場で使用された仮設足場材のパイプを、AIの画像認識技術を活用して種類や長さに応じて自動選別する装置も開発されています。これにより、足場の解体後の選別にかかる時間を大幅に効率化できます。
事故予防・リスク検知
AIは、作業員の危険行動や、重機接触リスクをリアルタイムで検知・警告することで、労働災害を未然に防ぐ安全管理に大きく貢献します。例えば、鉄骨上などで安全帯(墜落制止用器具)を使用していない人を画像認識技術で検知すると、管理者に通知がいくシステムが導入されています。また、重機に搭載された安全監視カメラAIシステムは、画像解析AIに骨格推定アルゴリズムを組み込み、作業員が重機を視認しているかを確認できます。
作業員が重機に接近した場合や視認していない場合には、警告アラートを出し、安全性の大幅な改善に成功しています。さらに、過去の膨大な事故事例の対策を搭載したAIシステムは、作業内容や現場状況から関連する事故リスクと対策を提示し、適切な注意喚起に役立ちます。
ドローンとAIを組み合わせた進捗確認
ドローンで撮影した広域の画像データをAIが分析し、工事の進捗率を自動で算出したり、土量測定を迅速に行ったりする活用法は、現場の作業効率化に有効です。また、高層建物の外壁調査において、ドローンで撮影した赤外線画像から、AIが建物の外壁タイルの浮きを自動判定し、熱分布データとして抽出するシステムが実用化されています。これにより、仮設足場の設置コストを削減でき、人の感覚によらない高精度・高品質な調査を実現できます。
さらに、コンクリート構造物の損傷箇所をAIが自動検知し、CAD図面化できるようにする画像解析システムも開発されており、従来の作業に比べて業務削減効果が見込まれています。
予測分析による工期短縮
AIは、過去のプロジェクトデータや現在の現場状況(天候、資材納入状況など)を学習し、潜在的な遅延リスクを予測することで、最適な人員配置や工程調整案を提示し、工期短縮に貢献します。例えば、シールド掘進管理において、学習させたAIモデルを用いて高頻度で高精度な方向予測を行うことで、シールド掘進の線形精度を向上させ、品質管理の効率化を実現する技術があります。また、経済予測AIを活用し、建設費指数の予測を参考に見積り金額に加味したり、個別品目の価格予測を発注時期の判断に役立てたりすることで、見積りコストと実際の購入金額との乖離リスク低減を目指す事例もあります。
さらに、過去の現地観測データを学習させたAIにより、建設現場向けのピンポイントの高精度気象予測サービスも開発されており、強風時のクレーン作業の中止判断や熱中症対策など、安全性向上に寄与することが期待されています。
AI活用で期待できる効果
工事現場 AI 活用によって、建設業者が具体的に享受できるメリットは大きく分けて四つの柱があります。工期短縮と品質向上
AIの導入は、作業の自動化や精度の高い予測、計画の最適化を通じて工期短縮に貢献します。設計業務では、過去のデータに基づき構造検討を支援するAIにより、設計の時間と労力が大幅に削減されます。また、画像生成AIを活用することで、発注者とのイメージのすり合わせが容易になり、設計段階での問題点に気づけるため、後の工程でのトラブルを防ぐことができます。さらに、ドローンとAIを組み合わせた調査は、仮設足場の設置コストを削減し、人の感覚によらない高精度・高品質な調査、調査期間の短縮を実現できます。AIは、工事の進捗や品質をリアルタイムでモニタリングし、問題や遅延が発生した場合に原因や対策を分析し、工程やスケジュールを自動的に修正することも可能です。これにより、工期遵守と品質向上に寄与します。
人的ミスや労働災害の削減
AIの活用は、ヒューマンエラーの低減と、リアルタイムのリスク検知による事故防止に有効です。AIは安全性向上のための手段として活用でき、より働きやすい環境を実現します。AIは過去の事故データや現場状況を分析し、リスクが高まる場面を特定できるため、事故防止のための対策ができ、安全管理に役立てられます。具体的には、画像認識技術を用いて、作業員の危険な行動(安全帯不使用者など)を検知し、管理者に通知するシステムが導入されています。また、AIが作業員の骨格を推定するアルゴリズムと組み合わされることで、作業員が重機を視認しているかを確認でき、重機への接近時などに警告アラートを出すことで、安全性が大幅に改善されます。さらに、膨大な事故事例の対策を搭載したAIシステムは、作業内容や現場状況から関連する事故リスクと対策を提示し、適切な注意喚起を促すことができます。
データに基づく意思決定
AIの導入により、経営者や現場責任者は、経験や勘に頼るのではなく、AIが分析した客観的なデータに基づき最適な判断を下せるようになります。AIは工事フローや資材調達のパターンを分析し、最適な工事計画を策定できるほか、稼働データから進捗や効率性を分析して計画を調整することも可能です。これにより、現場のミスやスケジュールの遅延を減らすことができます。利益率向上につながるコスト管理
AI活用は、資材の最適発注や無駄な手戻りの削減、工期遵守による間接費の削減など、コストコントロールの側面から利益向上に貢献します。例えば、AIによる物価変動予測を活用すれば、建設コストを適正に見積りし、実際の購入金額との乖離リスクを低減できます。また、宅地開発における区画割りや造成工事費の概算算出をAIが自動化・予測することで、時間とコストの削減につながる事例があります。さらに、過去データから工事見積りを算出するAIシステムは、見積り作成にかかる時間の大幅な削減や、属人性の低減に成功しています。AIによる効率化は、人手不足の解消や、現場以外の仕事増加につながり、雇用確保や労働環境改善にも寄与します。
AI導入の課題と注意点
工事現場 AI 活用は大きな可能性を秘めていますが、導入にあたってはいくつかの課題が存在します。それらを事前に理解し、対策を講じることが重要です。高額な初期投資
AIシステムの導入には、高額な初期投資が必要となる場合があります。AIソフトウェア自体の導入費用に加えて、それを運用するために付随するセンサーやカメラなどのハードウェア投資、そして既存の業務フローに合わせてシステムを構築・連携させるための費用が発生します。特に、AIを活用して現場の状況をリアルタイムで把握するためには、現場に固定カメラやドローン、エッジデバイスなど、新たなインフラを導入する必要があります。また、高精度なAIモデルを構築するためには、建設分野に特化した大量の学習データが必要となり、その収集・整備にもコストがかかります。
ただし、プラスバイプラスが取り扱うソフトの一部は、設備投資優遇税制の対象となる場合があります。初期投資に見合う効果を出すためにも、導入目的を明確化し、費用対効果を慎重に判断することが重要です。
現場従業員の教育・スキル習得
新しい技術に対する抵抗感や、AIツールを使いこなすための教育・スキル習得も大きな課題です。建設業は他の業界と比べてIT技術の浸透やDX化が遅れている実情があり、書類など紙を使ってのコミュニケーションが多いのが現状です。
そのため、AI技術やデジタルツールに対する現場従業員のデジタルリテラシーの向上が不可欠です。生成AIの活用に関するアンケートでも、建設業の企業からは、「生成AIで得た情報が正確なものであるか、信頼できるレベルにはない」といった不安を感じている回答があり、技術の信頼性に対する懸念も存在します。
AIのメリットを最大限に享受するためには、経営層がAIの性質やできることを正確に理解し、従業員がそのツールを使いこなせるよう、適切な教育とサポートが求められます。
AIだけでは解決できない原価把握
AI技術は現場の効率化やリスク低減には大きく貢献しますが、企業の経営の根幹である複雑な原価管理や利益確定といった部分は、AI単体では解決が難しい課題として残ります。AIは現場での作業効率や進捗の視える化を図れますが、現場で抜けがちな施工費の把握 や、実行予算と実績原価の比較分析、最終的な利益の確定といった経営判断に必要なデータ処理は、正確で迅速な原価管理システムによって補完される必要があります。
例えば、生成AIの応答が、土地の規模や形状、地域ごとの法令や条例など、現場でしか分からない情報に対応しきれないことも考えられます。現場の効率化(AI)と、経営の利益視える化(原価管理)の両輪が揃って初めて、真の生産性向上と利益確保が実現します。
AI活用効果を最大化するには「原価管理」が不可欠
工事現場 AI 活用によって現場の生産性が向上しても、それが最終的に企業の利益率向上に結びついていなければ意味がありません。現場の効率化効果を最大限に引き出し、利益を確実に確保するためには、「原価管理」が不可欠です。AI技術が現場の「効率」を高める一方、企業の利益の「要」となるのは、正確で迅速な原価把握です。建設業に特化したplusCADシリーズを提供する株式会社プラスバイプラスが提供する「要 〜KANAME〜」は、まさにこの原価管理の課題を解決するために、工事台帳をベースにした建設業向け利益管理ソフトとして誕生しました。
工事台帳に情報を集約し一元管理できるため、日報から材料費・労務費の計上が連動することで、工事ごとの原価・利益をリアルタイムに把握できます。これにより、赤字につながる要因を早期に特定し、迅速な対策を講じることが可能です。
AI導入による現場の改善効果と、「要 〜KANAME〜」による徹底した原価管理が組み合わさることで、真の利益率向上、すなわちAI活用の可能性を最大化することができるのです。
工事現場における AI活用について よくある質問
Q1. 建設業界がAI活用を急ぐ主な理由は何ですか?
A1. 建設業界がAI活用を急いでいる背景には、構造的な課題の深刻化があります。最も大きな理由は、深刻な労働力不足と高齢化です。建設業就業者はピーク時から約30%減少し、高齢化が進んでいます。これにより、技能継承の難しさも増しています。また、長時間労働の是正と安全確保のニーズも高まっています。2024年4月からの時間外労働の上限規制の適用もあり、「業務の効率化」と「生産性の向上」は建設業界にとって喫緊の課題です。
国もこの状況を後押ししており、国土交通省はi-Constructionや建設DXを推進し、「未来投資戦略2017」では2025年までに生産性を2割向上させるという具体的な目標を設定しています。AIは、設計業務の効率化、工程の最適化、リスクの提案、若手の育成など、多岐にわたる課題を解決する可能性を秘めています。
Q2. AIを導入することで、具体的にどのような業務が効率化されますか?
A2. AIは、これまで時間と手間がかかっていた多くの業務を効率化・自動化します。主な効率化事例は以下の通りです。- 施工管理・進捗確認の効率化:ドローンで撮影した現場の画像データをAIが解析し、資機材の位置を認識したり、工事の進捗率を自動で算出したりできます。これにより、職員による現場巡回や目視での確認作業を大幅に削減できます。
- 品質管理の自動化:コンクリートのスランプ測定をスマートフォンのカメラとAIで行い、品質不良をリアルタイムで検知・警告するシステムなどがあります。
- 安全管理の強化:AIカメラが、作業員の安全帯未着用などの危険行動や重機接触リスクをリアルタイムで検知・警告し、労働災害を未然に防ぎます。
- 設計業務の短縮:過去のデータに基づき、設計案や3Dモデルを生成するAIツールも登場しており、設計初期段階の検討業務の負担を軽減します。
- 事務作業の軽減:建設現場に特化した生成AIによる議事録作成サービスもあり、事務的な業務負担の軽減につながります。
Q3. AI技術の導入は、中小企業や小規模事業者でも可能ですか?
A3. AI技術の導入は、大手ゼネコンだけでなく、中小企業や専門工事業者でも進められています。AIの活用は、必ずしも大規模な自社開発システムに限定されません。例えば、既存の業務管理システムにAI機能が組み込まれて提供されるケースが増えています。小規模な現場でも、スマートフォンと連携するAIカメラシステム や、ドローンを用いた画像解析サービス など、比較的導入しやすいサービスが利用可能です。
また、plusCADシリーズのように、図面作成と見積り連動を自動化するCADソフトも普及しており、これらはDX化の第一歩として生産性向上に大きく貢献します。
Q4. AI導入を成功させるために、導入前に何を準備すべきですか?
A4. AI導入を成功させるためには、技術導入以前に、自社の業務プロセスとデータ環境を整備することが重要です。- 課題の明確化とゴールの設定:人手不足や安全性の問題など、最も解決したい現場の課題を明確にし、AIによってどの程度の効果(生産性向上、コスト削減など)を目指すのか、具体的なゴールを設定します。
- データ基盤の整備:AIはデータに基づいて学習し機能するため、過去の施工データ、事故データ、見積り実績データなど、AIに学習させるためのデータの整理・収集が必要です。
- 原価管理体制の強化:現場でAIが効率化を実現しても、最終的な利益確保のためには、正確な原価管理が不可欠です。「要 〜KANAME〜」を活用し、原価管理を視える化できる体制を整えることが、AIの効率化効果を最大限に生かす土台となります。
- 従業員の理解と教育:新しい技術に対する抵抗感を減らすため、導入の目的を従業員と共有し、AIツールを使いこなすための教育プログラムを実施することが重要です。
Q5. AIが進化しても、人間の仕事(施工管理や職人)は残りますか?
A5. AIが急速に進化しても、施工管理や職人の仕事が完全にAIに奪われる可能性は極めて低いといえるでしょう。AIは、膨大なデータを分析し、パターン認識や予測を行う作業、または危険な環境下での単純な繰り返し作業 を得意とします。しかし、AIには、我々人間が得意とする「創造力」が求められる作業など、苦手な分野が存在します。
例えば、現場で突発的に発生する予期せぬ状況への対応、地域特有の法令や現場の微妙な状況を考慮した判断など、現場でしか分からない情報に基づく柔軟な意思決定は、依然として人間の役割です。
これからの施工管理は、AIが代替できないような思考や創造性が必要な業務を人が行い、AIはデータ収集、リスク検知、単純作業の自動化を担うという役割分担が進むと想定されます。AI技術をうまく活用し、人間はより付加価値の高い業務に集中することで、建設業界の未来はより明るくなるといえるでしょう。