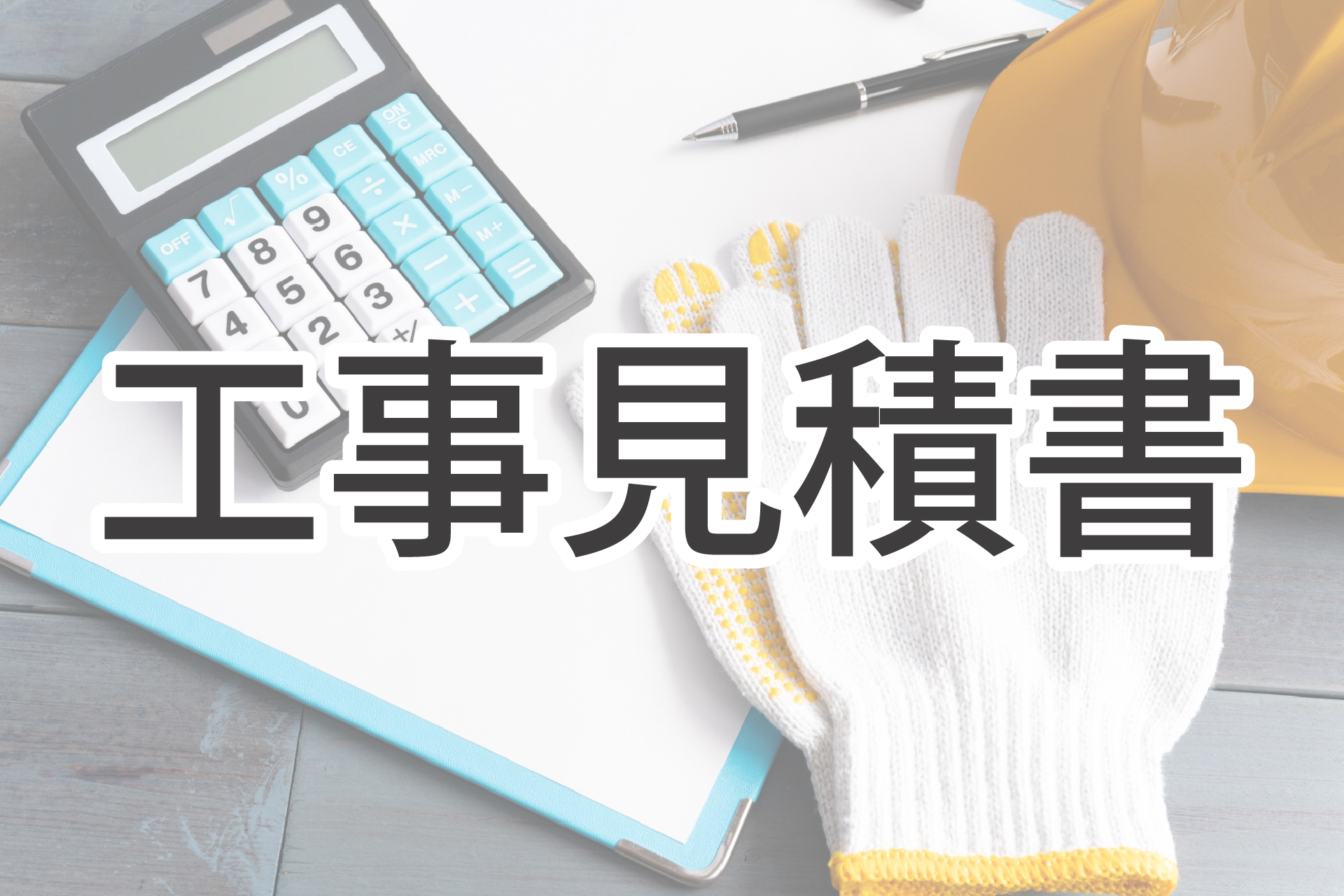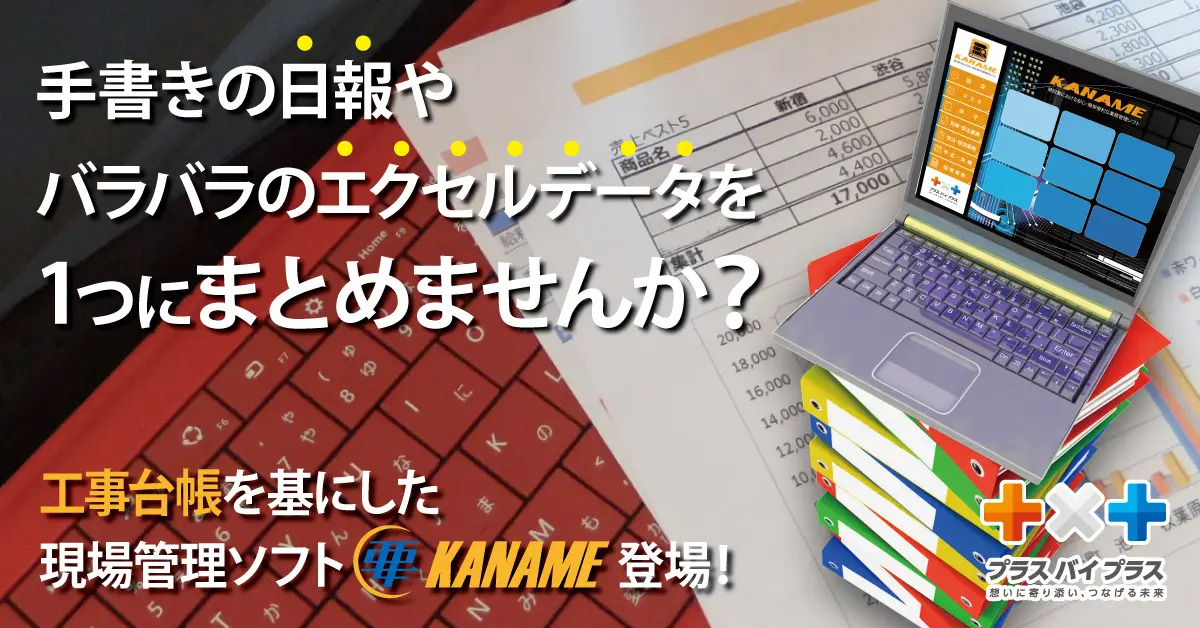- 2025年12月10日
建設業における見積りの掛け率とは?相場や計算方法、歩掛との違いなどを解説
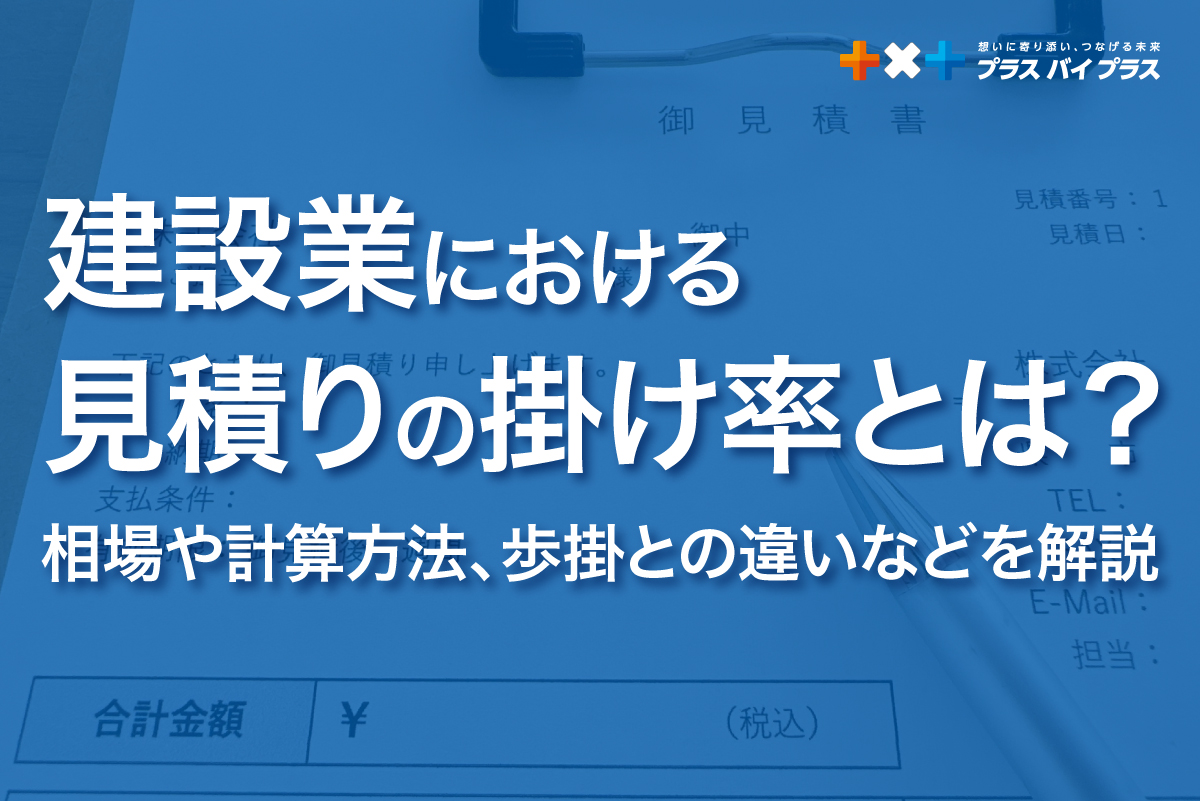
建設業における見積り作成において、「掛け率」は非常に重要な要素です。適切な掛け率を設定することで、利益を確保しつつ競争力のある価格を提示できます。
本記事では、建設業の見積り担当者や経営者に向けて、掛け率の意味や計算方法、さらには歩掛との違い、そして掛け率を適切に管理するメリット・デメリットについて詳しく解説します。見積り業務の精度向上と利益確保のために、ぜひ参考にしてください。
コンテンツ
見積書全体の構造や作り方から知りたい方は、先にこちらの記事をご覧ください。
工事見積書とは?記入項目、内訳や諸経費、作成方法など解説
建設業における見積りの基本
建設業において、見積りは工事を受注するために不可欠なプロセスです。適切な見積りを作成することで、工事の費用を正確に算出し、発注者に対して提示します。見積りには材料費や人件費、その他の経費が含まれ、これらの要素を正確に把握することが重要となります。
見積りの目的と重要性
建設業における見積りの最も重要な目的は、工事にかかる費用の概算を発注者に伝え、契約の判断材料を提供することです。また、見積りを通して工事内容や条件について発注者との認識を一致させる役割も担っています。適切な見積りは、その後の工事を円滑に進めるために不可欠であり、精度の高い見積りを作成することは受注者と発注者の間の信頼関係構築にも繋がります。さらに、見積り作成の過程でコストを詳細に把握することは、工事の実行予算管理や利益確保の上でも非常に重要です。
建設業特有の見積りの特徴
建設業の見積りは、他の業種と比較していくつかの特有の特徴を持っています。
まず、工事やプロジェクトは一つとして同じものがなく、常にオーダーメイドであるため、定価というものが存在しません。このため、過去の類似事例や標準単価を参考にしつつも、個別の工事の条件に合わせて詳細な見積りを作成する必要があります。
また、工事期間が長期にわたることも多く、その間の物価変動や予期せぬ事態によるコスト増減のリスクを考慮する必要がある点も特徴です。さらに、下請け業者への発注も多く発生するため、資材の仕入れ価格だけでなく、各工程の外注費なども見積りに正確に反映させる必要があります。
掛け率とは
建設業の見積りにおいて重要な概念の一つに「掛け率」があります。これは見積金額や原価に対して、特定の割合を示す数値として使用されます。掛け率を理解し適切に扱うことは、適正な利益を確保し、価格競争力を維持するために不可欠です。
掛け率の定義と役割
建設業における掛け率は、主に二つの意味合いで使用されます。
一つは、資材の定価やメーカー希望価格に対して、実際の仕入れ価格が占める割合を示す場合です。例えば、「7掛け」であれば、定価の70%で仕入れができることを意味します。この場合の掛け率は、仕入れ価格を計算する際に用いられる割合、数として機能します。
もう一つは、原価に対して利益や経費を上乗せして見積金額を算出する際に使用される割合、数です。この掛け率を調整することで、工事全体の利益率をコントロールし、競争力のある見積金額を設定する役割を果たします。
掛け率の重要性
掛け率の適切な設定は、建設業の経営において極めて重要です。特に、原価に対する掛け率を適切に定めることは、工事ごとの利益率を確保する上で直接的な影響を持ちます。
掛け率が高すぎると他社との価格競争で不利になる可能性があり、低すぎると十分な利益が得られず経営を圧迫する恐れがあります。市場の相場や自社の経営状況、工事内容などを総合的に考慮し、最適な掛け率を設定することで、安定した利益率を維持し、企業の持続的な成長に繋げることが可能となります。
掛け率の計算方法
建設業において掛け率を正確に計算することは、適切な見積金額を算出し、利益を確保するために不可欠です。掛け率の計算方法を理解することで、資材の仕入れ価格の算出や、原価に基づいた見積金額の設定を適切に行うことができます。
掛け率の算出方法
掛け率の算出方法は、その使用目的によって異なります。
資材の仕入れ価格における掛け率を計算する場合、一般的には「実際の仕入れ価格÷定価」という数式で求められます。例えば、定価10,000円の資材を7,000円で仕入れた場合、掛け率は7,000÷10,000=0.7(7掛け)となります。
一方、原価から見積金額を算出する際の掛け率は、「見積金額÷原価」で計算されます。例えば、原価が100万円の工事で見積金額を120万円とする場合、掛け率は120万円÷100万円=1.2となります。この場合の掛け率は、原価に対して1.2を乗じることで見積金額が算出されることを意味します。
掛け率を計算する際の注意点
掛け率を計算する際にはいくつかの注意点があります。
まず、掛け率は取引先や取引量、さらには市場の状況によって変動する可能性があるため、常に最新の情報を把握しておくことが重要です。
また、掛け率には消費税が含まれているか別途計算するのかなど、取引条件によって解釈が異なる場合があるため、事前に明確な確認が必要です。
さらに、原価に基づいて見積金額を算出する際の掛け率を設定する際には、材料費や労務費といった直接的な原価だけでなく、現場管理費や一般管理費などの間接的な経費、そして見込みたい利益を含めて考慮する必要があります。
これらの要素を正確に反映させることで、実行可能な見積金額を算出するための適切な掛け率という数を設定することができます。
掛け率と関連する要素
建設業の見積りにおいて、掛け率は他のいくつかの重要な経営指標と関連しています。これらの指標との関係性を理解することは、より戦略的な価格設定や利益管理に繋がります。
利益率や原価率との違い
掛け率と混同しやすい言葉に利益率や原価率があります。
利益率は、売上高に対して利益が占める割合を示す指標であり、「利益÷売上高」で計算されます。
一方、原価率は売上高に対する原価の割合を示し、「原価÷売上高」で計算されます。掛け率が原価に上乗せする割合や仕入れ価格の割合を示すのに対し、利益率と原価率は売上高を基準とした収益性を示す指標です。
掛け率を適切に設定することは、結果として目標とする利益率を達成するために不可欠な要素となります。原価率が高いと、同じ売上でも利益が少なくなるため、掛け率を調整することで原価を抑えたり、適切な見積金額を設定して利益率を向上させたりすることが可能になります。
歩掛との関連性
建設業の見積りにおいて、掛け率と関連性の深いもう一つの要素に「歩掛」があります。
歩掛とは、ある一定の作業量や工事を行うために必要とされる標準的な手間、つまり作業員数や作業時間を数値化したものです。例えば、ある作業における歩掛が「1人工」であれば、それは作業員1人が1日で完了できる作業量を示します。この歩掛に、作業員の賃金である労務単価を乗じることで、その作業にかかる人件費(労務費)を算出できます。
見積金額は材料費と人件費、その他の経費に利益を加えて算出されますが、材料費の計算に掛け率が用いられる場合がある一方で、人件費の算出には歩掛という数が基礎となります。
このように、掛け率が主に材料費の価格設定に関連するのに対し、歩掛は労務費の算出に直接的に関わる点で異なりますが、どちらも正確な原価計算と見積金額の算出に不可欠な要素と言えます。
建設業における掛け率を押さえるメリットとデメリット
建設業において掛け率を適切に設定し管理することは、多くのメリットをもたらしますが、一方で考慮すべきデメリットも存在します。これらの点を理解することで、より効果的な見積り戦略を立てることが可能です。
掛け率を押さえるメリット
掛け率を適切に設定する最大のメリットは、自社の利益率を確保できる点です。原価に対して適切な掛け率を乗じることで、工事に必要な費用だけでなく、会社の運営にかかる経費や見込みたい利益を確実に計上できます。
また、仕入れにおける掛け率交渉を適切に行うことで、材料費を抑え、結果として工事全体の原価低減に繋がり、利益率の向上に貢献します。
さらに、明確な掛け率の基準を持つことは、見積り担当者による金額のばらつきを抑え、統一性のある見積書を作成することにも役立ち、顧客からの信頼を得やすくなるでしょう。相見積りが行われる状況でも、自社の利益を確保しつつ競争力のある価格を提示するために、掛け率の理解と適切な設定は不可欠です。
掛け率を押さえるデメリット
掛け率に過度に依存することにはデメリットも存在します。市場の相場や競合他社の掛け率を無視して自社の基準のみで掛け率を設定すると、提示価格が市場から大きく乖離し、受注機会を損失する可能性があります。
また、掛け率だけで見積金額を決定しようとすると、個別の工事における難易度や特殊性、現場の状況などを十分に考慮できない場合があります。その結果、見積金額が実情に合わず、工事中に予期せぬ追加費用が発生したり、実行予算が狂ったりするリスクが高まります。
さらに、発注者によっては掛け率の根拠について説明を求められる場合もあり、明確な根拠に基づかない掛け率は不信感に繋がる可能性も否定できません。
見積り作成の効率化
建設業における見積り作成は、多岐にわたる項目や複雑な計算が必要となるため、多くの時間と労力を要する業務です。この見積り作成プロセスを効率化することは、業務全体の生産性向上に繋がります。
見積り作成を効率化するためには、いくつかの方法があります。まず、過去の見積りデータをテンプレートとして活用することが有効です。類似の工事であれば、過去のデータを基に必要な調整を加えることで、ゼロから作成するよりも大幅に時間を短縮できます。
また、材料費や労務費の単価リストを整備し、これをシステム的に管理することで、単価の確認や計算の手間を省くことができます。さらに、現在では建設業向けの見積り作成ソフトやその他サービスが多数提供されており、これらのツールを導入することで、自動計算機能や過去データの引用、内訳の階層化などが容易になり、計算ミスを防ぎつつ迅速に見積りを作成することが可能です。
これらのツールを活用することで、見積り担当者は計算作業に追われることなく、より戦略的な価格設定や顧客とのコミュニケーションに時間を充てられるようになります。
まとめ
建設業における見積りにおいて、掛け率は材料費の算出や原価に基づいた見積金額の設定に用いられる重要な割合を示す数です。掛け率を適切に理解し活用することで、適正な利益率を確保し、価格競争力を高めることができます。
また、掛け率は利益率や原価率、そして歩掛といった他の経営指標とも関連しており、これらの要素を総合的に考慮した上で掛け率を設定することが重要です。掛け率を適切に管理することは多くのメリットをもたらしますが、市場動向や個別の工事特性を考慮しない場合はデメリットにも繋がり得ます。
建設業の見積り業務を効率化するためには、見積りソフトの活用なども有効な手段となります。正確な見積りと適切な掛け率の設定は、工事の成功と企業の持続的な成長に不可欠と言えるでしょう。
利益漏れを防ぐためには「根拠のある見積り」を作ること
見積りの精度が低いと、値切り交渉で妥協せざるを得なくなり、結果として利益が圧迫されてしまいます。単に「業界では○○掛けが相場」といった平均的な数値に頼った見積りでは、発注者に納得してもらえず、価格競争で不利に立たされることもあります。
とはいえ、毎回詳細な原価計算や根拠資料を手作業で準備するには、現場も忙しく時間が足りないのが実情です。だからこそ、根拠のある見積りを効率的に作成するためのツールとして、見積りソフトや原価管理ソフトの導入が有効です。
CAD・見積り連動ソフト「plusCAD」や原価管理ソフト「要 〜KANAME〜」なら、過去の単価や歩掛データを活かして短時間で説得力のある見積書を作成できるだけでなく、材料費・労務費などの項目も自動計算され、利益を見逃さない価格設定が可能になります。
<電気設備CAD・見積り連動ソフト「plusCAD電気α」を詳しく見る>
<機械設備CAD・見積り連動ソフト「plusCAD機械α」を詳しく見る>
<建設業向け原価管理ソフト「要 〜KANAME〜」を詳しく見る>
よくある質問
Q1. 掛け率は業種や工種ごとに違いますか?
A: はい、異なります。例えば土木と内装、電気工事では原価構造が異なるため、適正な掛け率も変わります。業種別の慣習や相場に応じた設定が必要です。
Q2. 元請から提示された掛け率が妥当か判断するには?
A: 業界の相場を把握し、自社の原価と利益を基に「最低限必要な掛け率」を計算することが大切です。過去の類似案件や同業者との比較も参考になります。
Q3. 見積りにどの程度の利益を乗せるべきですか?
A: 利益率の目安は原価に対して業界平均で20%前後ですが、14%〜34%程度と幅があり、案件の難易度やリスクによって変わります。利益を過小にすると後で赤字になることがあるので注意が必要です。
Q4. 掛け率と利益率はどう違うのですか?
A: 掛け率は「原価に乗じて見積額を出すための数値」で、利益率は「売上に対してどれだけ利益が出たか」を示します。混同しないようにしましょう。
Q5. 掛け率は毎回同じにすべきですか?
A: 一律ではなく、案件の内容や工期、リスク、発注者の信用度などを踏まえて柔軟に調整するべきです。固定してしまうと機会損失や赤字の原因になります。
Q6. 見積りの妥当性を発注者に説明するには?
A: 材料費や労務費、管理費の内訳を明示し、掛け率の根拠や相場との整合性を資料で提示すると信頼を得やすくなります。過去実績や業界標準を示すのも効果的です。
Q7. 見積りソフトは導入した方がいいですか?
A: 作業効率を大きく改善できます。特に見積書の整合性・精度向上、過去案件の活用、掛け率の一元管理などが可能になり、属人化も防げます。