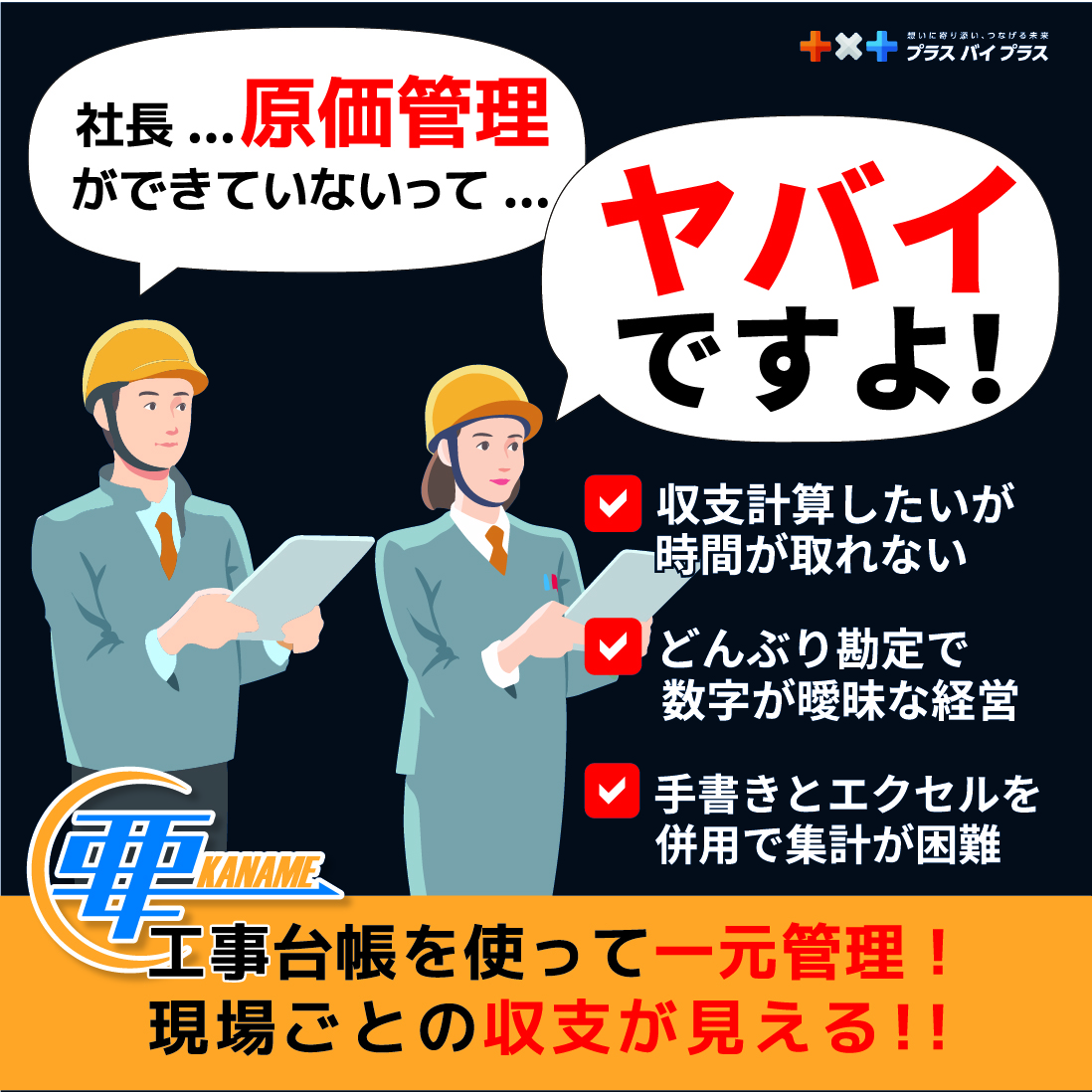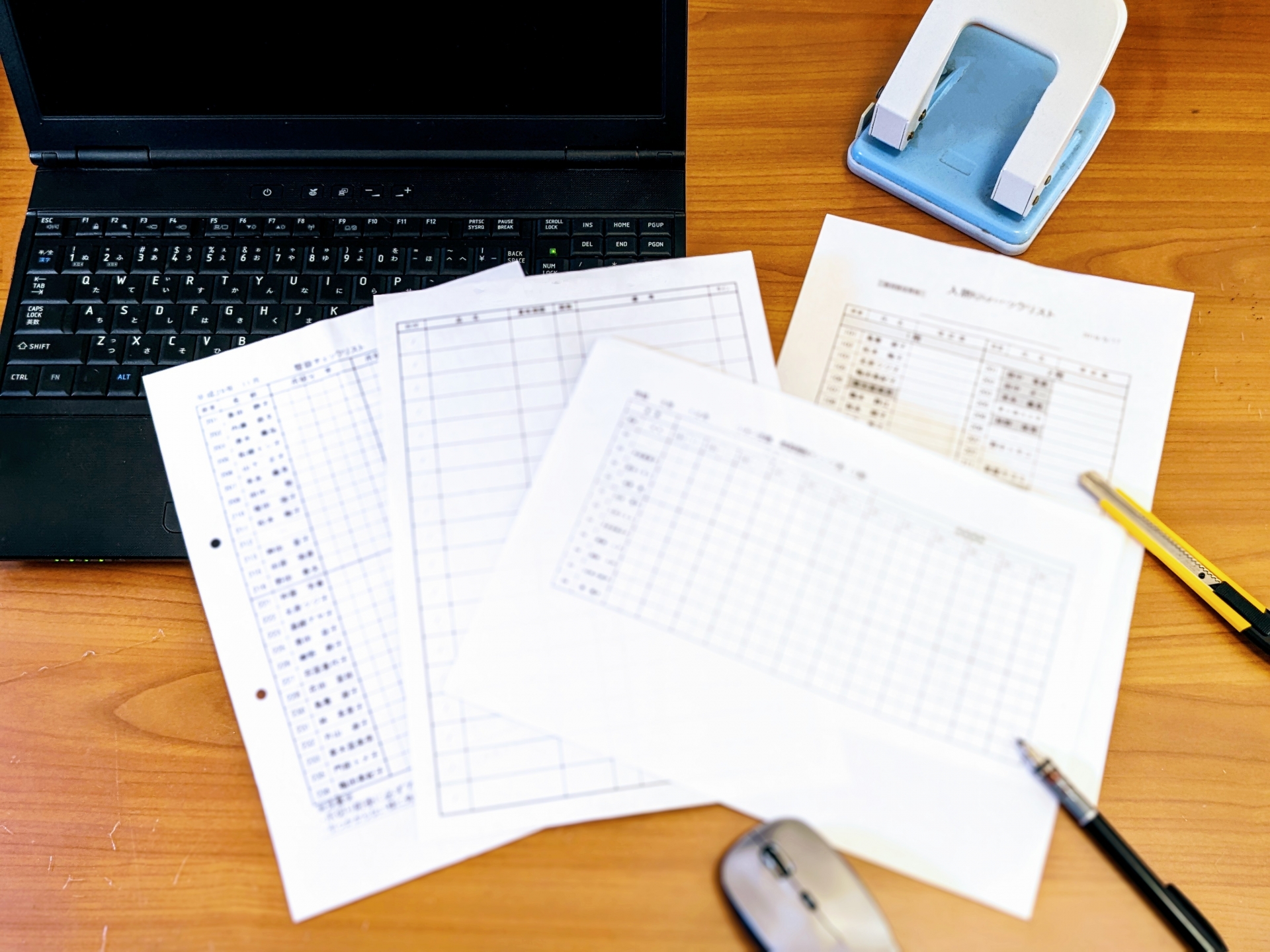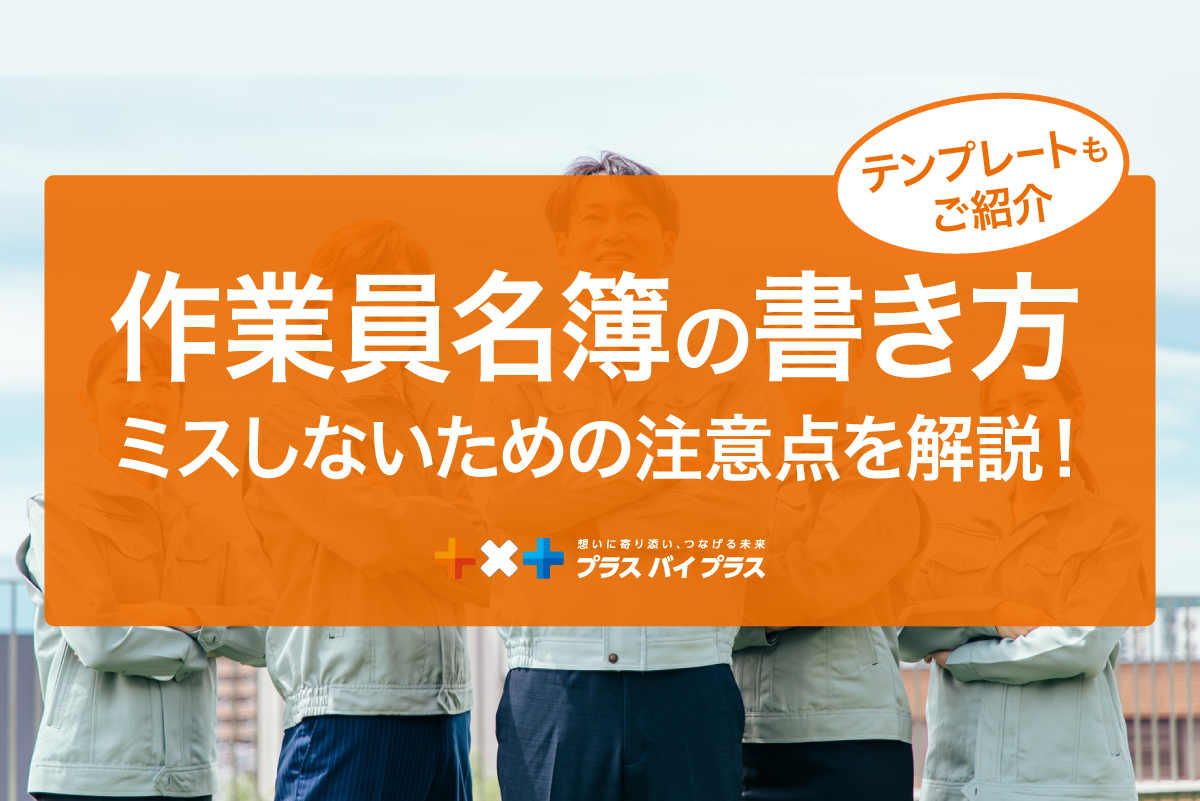- 2025年10月16日
建設業のRPA自動化|定型業務を削減して利益を守る方法

近年、建設業界では、老朽化対策や災害対策を含む大規模な建築プロジェクトが進んでおり、業界の需要は引き続き高いと見込まれています。
しかし、労働市場の変化に伴い、人手不足や高齢化の進行、離職率の増加といった深刻な構造的課題に直面しています。これにより、従業員一人ひとりへの負荷が増し、長時間労働が常態化している状況です。また、依然として紙ベースでの情報共有やアナログな処理が残るなど、業界全体のDX化の遅れも指摘されています。
こうした状況下で、建設業におけるRPAの自動化は、作業手順の決まっている定型業務をソフトウェアロボットに任せることで、業務効率化と人的ミスの削減に大きく貢献する解決策として注目を浴びています。RPAの導入は、作業負荷の軽減や人為的なミスの防止に加え、現場とバックオフィスの情報連携もスムーズにし、業務全体の効率化と安定化が図れます。
この記事では、建設業界がRPAを導入する具体的なメリットや活用事例、そしてより高い利益改善を目指すための方法について詳しく解説します。
コンテンツ
建設業におけるRPA導入の必要性
建設業界は、厳しい品質基準、コスト管理の要求に加え、労働時間規制の強化が進むなか、多くの構造的課題を抱えています。従来の体制では生産性を維持することが困難であり、ルーティンワークを自動化するRPAの導入は、生産性を維持・向上させるために不可欠な手段となっています。
人手不足で増える事務負担
日本全体の人口減少に加え、建設業界特有の高齢化の進行や離職率の増加は深刻な人手不足を引き起こしており、若手人材が少なくなっています。このため、残された従業員一人一人に過度な負荷がかかり、残業や休日出勤の常態化を引き起こしています。現場管理からバックオフィス業務まで、一部の社員に負担が集中することで、離職リスクの増加やミスの発生につながる実態があります。RPAは24時間365日稼働できるため、限られた人員でも処理量を維持することが可能となります。RPAを導入すれば、人員配置に柔軟性が生まれ、事務作業の負荷を軽減することで、離職率の低下にもつながるでしょう。
また、属人化しやすい事務作業をRPAに任せることで、業務の標準化と引き継ぎのしやすさが実現します。既存の労働力で生産性を向上させることは、人手不足に悩む企業にとって非常に有効な手段です。
複雑化する契約・請求業務
建設業界では、協力会社からの見積書や請求書の確認やシステムへの入力、国への申請書類や請書の入力など、多くの定型業務が日常的に発生しています。特に、契約関連資料や各種申請書類、経理業務などでは、手入力によるミスが許されないため、作成・入力・チェックに膨大な時間と注意力が求められます。RPAは、受領した請求書のPDFデータやスキャン画像を読み取り、必要な情報を社内の基幹システムや台帳などの特定のフォーマットに自動入力します。これにより、転記ミスを防ぎ、チェック作業の負担を軽減します。
また、国や自治体などから届く工事注文書が紙で発行されるケースでも、内容を読み取り、発注番号や工事名、金額などの情報をRPAで社内システムに自動入力できます。複雑な帳票処理を自動化することで、作業負荷が軽減され、事務作業にかかる時間とリソースを大幅に削減できます。
残業時間の増加とコスト圧迫
長時間労働が慢性化している建設業界では、従業員の負担増大は残業時間の増加を招き、人件費の膨張、ひいてはコスト圧迫につながります。さらに2024年4月からは働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が適用され、従来の労働時間を延ばすことで生産性を担保する手法が使えなくなりました。RPAを活用すれば、見積り作成や発注処理、請求書の管理など、繰り返し行われる業務プロセスを自動化でき、これらの作業にかかる時間的コストを大幅に削減できます。
また、ヒューマンエラーを防げるため、修正による作業時間も減らせます。作業時間の短縮は長期的な人件費の削減につながり、資材の高騰や円安による外部要因の影響を受けやすい建設業界にとって、内部のコスト削減ができることは大きなメリットとなります。
法令遵守・コンプライアンス対応
国や自治体への申請書類、請書、契約関連資料など、建設業界では法令遵守のために正確な書類作成・入力・チェックが求められます。これらの業務は手入力によるミスが重大な問題を引き起こす可能性があるため、RPAによる自動化が有効です。RPAは、必要な情報をシステムから抽出して特定のフォーマットに入力・転記したり、画像を添付したりといった、手間のかかる申請書や請書の作成を自動で処理します。また、複数の協力会社の許可番号を手入力で確認・管理する作業は煩雑ですが、RPAが確認サイトから情報を自動で取得し、所定のフォーマットやシステムに転記・照合することも可能です。
RPAによる自動化と正確性の担保は、コンプライアンス対応における書類作成や確認にかかる時間を大幅に短縮し、ミスの防止に役立ち、企業の信頼性を高めることにもつながります。
RPAが得意とする業務領域
RPAは、作業手順が決められている定型業務を忠実に再現し、自動化する技術であり、繰り返し発生するデータ入力や転記といった業務の効率化に効果を発揮します。特に、データ入力、転記、集計といった繰り返し発生するバックオフィス業務や、複雑な事務処理を伴う現場管理業務において高い効果を発揮します。見積書や請求書の自動処理
見積書や請求書に関する業務は、RPAが建設業界で特に得意とする領域です。RPAは、基幹システム内の顧客情報や工事内容、金額などの情報をもとに、見積書や請求書を自動で作成し、PDF化、さらにはメール送信まで対応可能です。これにより、人的ミスや送付漏れを防ぐことができます。また、協力会社から受領した請求書のPDFデータやスキャン画像を読み取り、必要な情報を基幹システムや台帳などの特定のフォーマットへ自動入力する業務も自動化できます。この自動化により、転記ミスを防ぎ、チェック作業の負担も軽減されます。RPAは、見積り作成や請求書の管理といった繰り返し行われる業務プロセスを自動化することで、作業にかかる時間的コストを大幅に削減します。
勤怠・労務管理の自動化
勤怠管理は、建設業界で日常的に発生する定型業務の一つであり、RPAの活用シーンとして挙げられています。従業員の勤怠確認・管理を自動化することで、業務効率化が図れます。具体的には、勤怠システムからデータをダウンロードし、超過残業時間や勤務時間の集計、給与計算システムへの反映までの作業を自動化することが可能です。さらに、現場で手書きされた紙の勤怠表についても、出勤日数や労働時間などの情報をRPAが勤怠管理システムや給与ソフトに自動で入力します。これにより、手入力によるミスや集計の手間を減らすことができます。RPAでこれらの業務を自動化することは、単調で注意力を要する作業から従業員を解放し、精神的負担を軽減することにもつながります。
発注・支払処理の効率化
資材発注や支払処理も、RPAで効率化できる重要な領域です。RPAは、社内の資材や備品の申請情報をもとに発注書を自動作成し、メール送信まで自動化します。これにより、発注ミスの防止や作成・送付作業の時短に貢献します。在庫管理および資材発注業務をRPAで自動化することで、タイムリーに在庫状況を把握できるようになり、納期の遅延などが減り、営業生産性や顧客満足度が向上した事例もあります。
また、経費精算においては、Excelや経費精算システムから提出された交通費や立替金などの経費明細をRPAが自動で確認し、仕訳や金額を給与・会計システムへ転記できます。申請内容に不備や差異がある場合は、経理担当者へ自動で通知することも可能です。
帳票類の転記・入力作業削減
建設業界には、施工日報、安全書類、工程表、各種申請書類など、転記や入力作業が求められる膨大な量の帳票が存在します。RPAは、これらの定型的な入力・集計・転記といった作業から従業員を解放します。例えば、各現場から提出される施工日報が紙やPDFで届く場合、AI-OCRで内容を読み取り、社内システムや台帳へRPAが転記します。Excelで提出された場合も、RPAがそのまま迅速に転記処理を行うため、記録ミスや作業の遅れを防ぎます。
さらに、新規プロジェクトごとに作成される工事情報や工程表を指定のフォーマットに転記したり、新規受注案件のファイルを雛形から複製し、自動で特定のフォルダにリネームして保存することも可能です。月間で3000件ほどのExcelやGoogleスプレッドシートの情報を電子申請サイトに登録する業務をRPAで自動化し、およそ250時間分のコスト削減に成功した事例もあります。
定型メール・報告書作成
定型的なメール業務の処理や、進捗状況の報告書作成もRPAで自動化が可能です。例えば、資材や備品の発注書作成後のメール送信 や、得意先からの受注メールを処理する業務の自動化事例もあります。また、工程表や作業員名簿、施工体制台帳作成の補助も可能です。作業工程や担当者、工期などの情報をもとに、テンプレートへ自動入力することで、作業ごとの転記や確認の手間を削減します。さらに、複数の協力会社や作業員情報を取り込んで、作業員名簿や施工体制台帳の作成を補助することもできます。
重機や運搬車両の使用予定管理においては、現場ごとの使用予定を申請内容や工程に基づいて一覧表やスケジュール表に自動で反映できます。これにより、手作業での確認や入力の手間が減り、使用日程の重複や漏れを防ぎながら、効率的な運用が可能になります。
RPA導入のメリット
建設業界がRPAを導入することで得られるメリットは多岐にわたります。定型作業の正確性を高め、コスト削減と生産性向上を実現するとともに、従業員が本来注力すべき業務に時間を充てられるようになり、業界全体が抱える構造的課題の解決に大きく貢献します。人為的ミスの削減
建設プロジェクトにおいて、膨大なデータ入力や複雑な計算は手作業ではミスが発生しやすくなります。RPAは、決められた手順通りに作業を正確に繰り返すため、ヒューマンエラーを防ぐことが可能です。特に、定型的な入力作業や数値計算において間違いが起きにくくなるため、全体的な品質向上を期待できます。建設業界では一度のミスが大きな損失や安全面への影響に直結するため、RPAによる高い正確性の継続的な担保は、検証や修正に費やす時間・コストの削減につながります。計画書や報告書の作成、資料の整理など、各種ドキュメントに関するヒューマンエラーを防げるようになる点もメリットです。
作業スピードの向上
RPAを導入することで、繰り返し業務の作業負荷が軽減され、事務作業にかかる時間とリソースを大幅に削減できます。ロボットは24時間365日稼働できるため、作業待ちのタイムラグを最小化し、業務スピードを格段に高めることができます。ある建設業界の事例では、メールやFAXなどで受理した補修サービスの紙面データを社内システムに登録する業務を自動化した結果、年間で5,000万円相当の人的コストの削減に成功しています。
また、得意先からの受注メール処理業務を自動化することで、年間5,000時間以上のコスト削減に成功した事例もあります。迅速かつ正確な業務処理は、企業の競争力向上に直結します。
人材を付加価値業務にシフト
入力・集計・転記といった定型作業から解放されることで、従業員は、本来注力すべきコア業務により多くの時間を充てることができます。RPAが担うのは、あくまで定型化されたルーティンワークであり、人は、現場管理や工程調整、品質管理、顧客対応など、人の判断が求められる業務 や、企画立案、問題解決といった付加価値の高い仕事に専念できるようになります。人材をコア業務に集中させることはコストパフォーマンスを高め、業務全体の質を改善する動きにつながります。これは、人手不足が深刻化する建設業界において、既存の人材を最大限に活かすための重要な戦略です。働き方改革への貢献
労働時間の上限規制が強化されるなか、RPAの導入は働き方改革への貢献として非常に重要です。大量の帳票処理や定期的な集計作業、申請書類の作成など、単調で注意力を要する作業は従業員の精神的負担となりますが、RPAによる自動化でこれらの負荷が大きく軽減されます。
業務負荷の分散が実現されることで、従業員の残業削減やストレス軽減につながり、労働環境の改善と人材定着率の向上に寄与します。労働環境が改善され、業界のイメージアップがされれば、若い人材へのアピールもしやすくなります。
コスト削減と利益率改善
RPAの導入は、作業負荷の軽減による事務作業にかかる時間とリソースの削減、そしてヒューマンエラーによる修正作業時間の削減を通じて、結果的に人的コストを削減します。ロボットが稼働することで、従業員の残業代や外注費なども抑えられ、トータルの運用コストが削減できる可能性があります。
例えば、発注先企業の工事内容と許可番号の照合業務を自動化することで、高額なコストをかけてデータ販売業者に依頼していた費用を年間1,200万円ほど削減できた事例があります。コスト削減は企業の収益に貢献し、建設業界全体の競争力を底上げする重要な要素となります。
RPA導入の落とし穴
RPAは建設業界の業務効率化に大きな効果をもたらしますが、導入にあたってはいくつかの「落とし穴」も存在します。RPAが万能ではないこと、特に複雑な判断を伴う業務への適用は難しい点を理解し、適切な導入計画を立てることが成功の鍵となります。複雑業務は自動化できない
RPAは作業手順が決まっている定型業務の自動化に特化しています。しかし、複雑な判断を必要とする業務や、イレギュラー対応が多い業務に対しては、RPAの効果が限定的となります。建設業界においては、現場独自の判断を要するケースが多々あるため、すべての業務をロボットに任せることは現実的ではありません。RPAで実現できるのは、あくまで定型業務の自動化であり、プロセスの数やデータ量が膨大であっても、非定型な業務は人の手で対応する必要があります。適用範囲の制約があるため、RPA導入の際は、まずは成果を出しやすい定型業務から段階的に取り組むのが望ましいといえます。
運用・メンテナンスコスト
RPAを導入しても、運用が滞ると想定していた費用対効果が得られないケースがあります。RPAツールのライセンス費用だけでなく、導入前の業務整理やプロセス設計に時間と初期コストをかける必要があります。特に、現場担当者のヒアリングや各部署との調整は欠かせません。また、運用開始後も、ツールのメンテナンスや更新、不具合への対応が必要となるため、運用サポート体制の構築が不可欠です。社内に専任担当者を置く場合は、その要員の育成コストや研修プログラムの整備も必要となります。導入後に起こるツールの不具合やバージョンアップへの対応が滞ると、せっかくのメリットが半減してしまうため、継続的な運用サポート体制の構築は必須です。
短期的効果にとどまるケースも
RPAは、まず小規模な業務から試験的に導入し、短期間で成功事例をつくることが推奨されますが、その効果が短期的で終わってしまうリスクもあります。これは、RPAの活用が一部の部門に留まり、属人化してしまい、全社的な業務改善につながらない場合に起こり得ます。RPAの導入成功には、小さく始めて段階的に拡大していく戦略が重要です。もし、導入後の効果検証や改善が進まない場合、初期に削減できたコストも、運用・メンテナンス費用に相殺され、長期的な利益率改善には至らない可能性があります。RPAは、継続的な改善サイクルを回すためのきっかけとして機能すべきです。
業務全体の最適化が進まないリスク
RPAは業務を効率化しますが、既存の非効率な業務プロセスをそのまま自動化しても、業務全体の最適化は進みません。建設業界ではDX化の遅れが長期的な成長を阻害する要因となっており、労働時間規制への対応のためにも包括的な業務改革が求められています。RPAの導入は、反復的業務を自動化してデジタル化の恩恵を実感し、企業全体のDX化を進めるための「第一歩」と位置づけることが重要です。RPAを活用して業務フローそのものを見直す機会とし、継続的な改善サイクルを回すことで、初めて業務全体の最適化に貢献します。
RPAと相性の良い「原価管理システム」
RPAは、データ入力や転記といった定型作業を正確かつ迅速に自動化し、原価管理に必要な実績データの正確な基盤を整備します。このRPAによる自動化効果と極めて相性が良いのが、工事台帳をベースとした建設業向け利益管理ソフト「要 〜KANAME〜」です。特に重要なのは、日報から材料費・労務費の計上が自動で連動する仕組みです。これにより、工事ごとの原価と利益をリアルタイムに把握することが可能となります。さらに、各担当者が作成した見積や注文書を一覧で視える化し、リアルタイムな見込み管理を可能にします。
RPAが正確な実績データを「要 〜KANAME〜」に転記・集約することで、利益の視える化が実現し、コスト超過リスクの早期発見や、経営層や現場責任者による迅速な意思決定を強力に支援します。これは、単なる事務作業の効率化を超えて、企業の収益改善に直結する重要な要素となります。