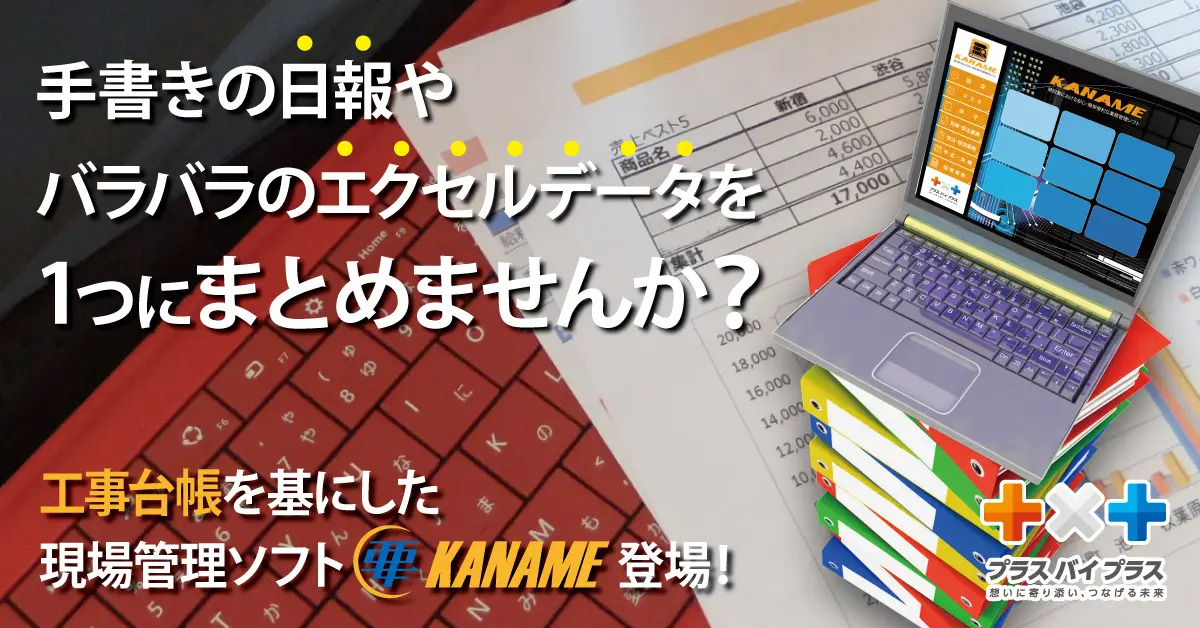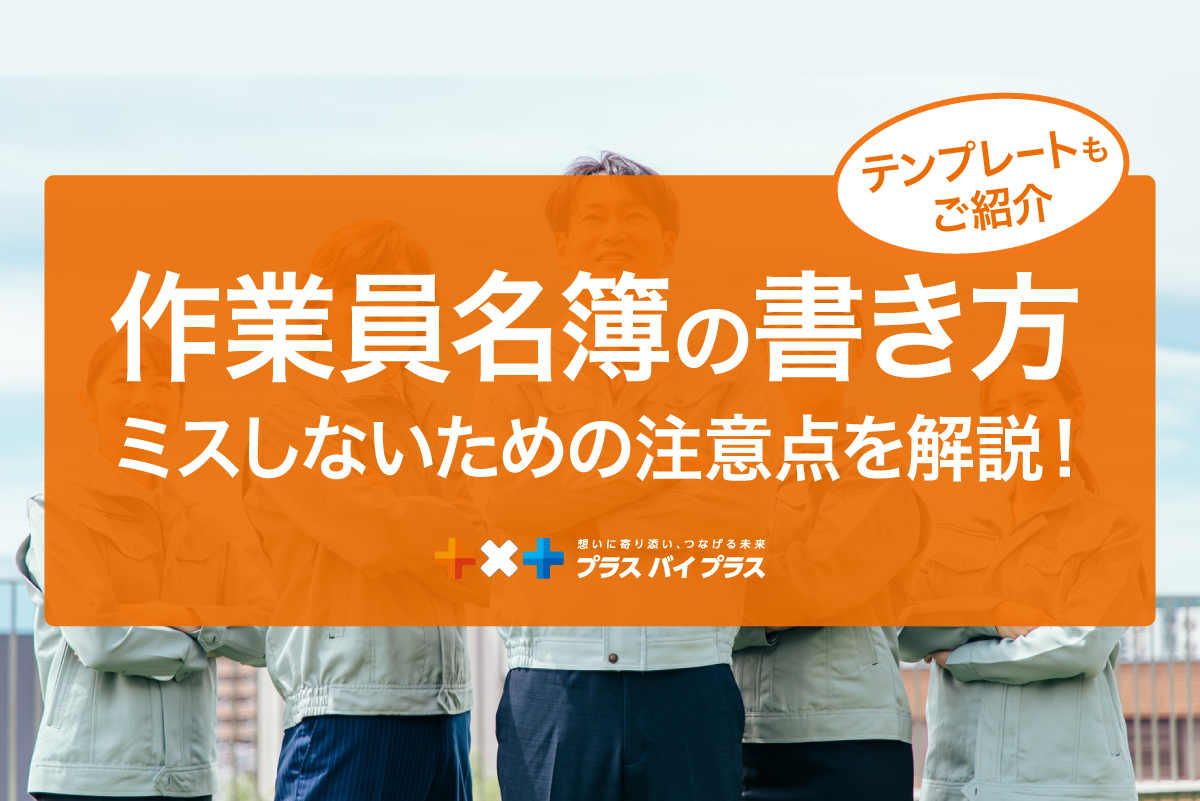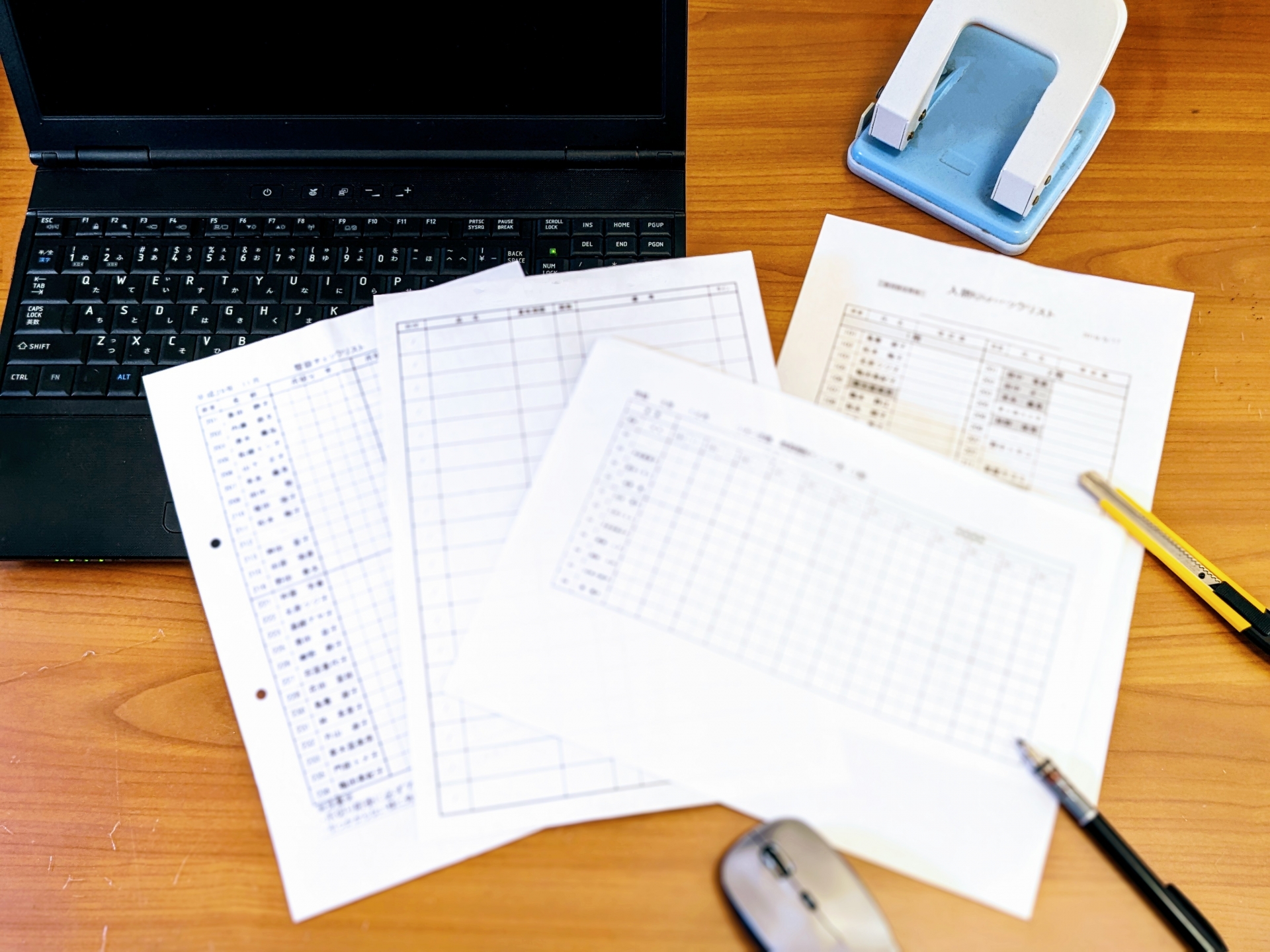- 2025年11月07日
建設業のペーパーレス化が進む理由とは?メリットやツール導入のコツを解説
建設業に関する知識

建設業界において業務のペーパーレス化が急速に進んでいます。
ピラミッド構造の工事発注により、見積書や契約、請求などの書類のやり取りが必然的に多いため「脱・紙文化」が非常に重要です。
この記事では、建設業におけるペーパーレス化の背景やメリット、課題を解説したうえで、最終的に原価管理を担うソリューションもご紹介します。
コンテンツ
建設業界でペーパーレス化が求められる背景
建設業でペーパーレス化が求められる裏には以下のような背景があります。紙書類の多さによる業務の非効率
建設業界の工事発注はピラミッド構造(多重下請構造)と呼ばれ、業者間で契約や見積り、請求といった書類のやり取りが多く発生します。現場では、膨大な図面や工程管理表、作業指示書などの紙資料が必要に。
工事数が増えるほど、これらの持ち運びの負担が大きくなる可能性があります。
さらに、バックオフィス業務においても、まだ多くの企業が請求書を手作業で転記しており、紙文化が根強く残っていることが浮き彫りになっています。
情報共有の遅れとトラブル
紙資料中心の運用では、情報の検索や参照に手間がかかります。図面は版が変わることが多いにもかかわらず、紙で管理していると資料の先祖帰りによる情報の混乱や手戻りを招くリスクがあります。
また、現場では、資料を探すために事務所に戻るといったムダな移動時間が発生することもあるでしょう。
電子化により、検索性が向上したり、他部署や取引先と情報を共有しやすくなったりするメリットが期待できます。
脱炭素・環境意識の高まり
ペーパーレス化のメリットとして、建設業従事者から最も多く挙げられているのは「紙代・印刷代の削減」です。紙での運用では、インク代、紙の費用、保管場所の確保、輸送コスト、コピー機やシュレッダーのメンテナンス費用、書類の廃棄費用など、物理的・間接的なコストが発生します。
これらの費用を削減し、ファイリングや資料検索にかかる人件費も減らすことで、経営効率の向上を促進できます。
行政・元請けからの DX要請
国はペーパーレス化を推奨しており、建設業界においてもその流れは顕著です。建設業法が改正され、取引相手の承諾を得ることを条件に、工事請負契約書を電子契約で締結することが可能になりました。
さらに、電子文書法が施行され、会社法などで保管義務づけられている書類を、見読性、完全性、機密性、検索性といった要件を満たせば、電子データ化して保存することが認められました。
国土交通省も、工事写真や図面などの完成書類を電子成果品として提出する「電子納品」を推奨しており、行政側からの積極的にデジタル化を推進しています。
建設業におけるペーパーレス化のメリット
建設業が抱える書類に依存した課題に対し、ペーパーレス化は業務効率化、コスト削減、セキュリティ強化など、多くのメリットをもたらします。情報共有のスピード向上
書類を電子データで保存することで「書類の検索・参照が容易になる」というメリットがあります。電子化によって閲覧や検索がスムーズになり、図面に修正が入った場合でも、現場ですぐに確認できるため、情報の混乱を防ぎやすくなるのです。
また、従業員間や部署間での連携が円滑化し、会社全体の生産性向上に繋がります。
紛失・誤送信リスクの軽減
紙資料の持ち運びや保管中の紛失による情報漏洩のリスクを防げる点も、ペーパーレス化の重要なメリットです。電子データ化することで、重要なデータにパスワードや閲覧権限を設定でき、セキュリティを強化できます。
コスト削減と管理効率向上
「紙代・印刷代の削減」もペーパーレス化のメリットです。印刷費や郵送費、資料を探す手間、ファイリングやコピーにかかる人件費など、紙に関わる物理的・人的コストを大幅にカットできます。
さらに、コピー機のメンテナンス費用や書類の廃棄費用なども不要に。
資料が電子化されれば、書類に関するチェックがスムーズになり、法律に基づく社内監査の円滑化にも繋がり、コンプライアンスの強化に役立ちます。
現場・事務間の連携強化
ICTツールの活用により、業務プロセス全体の効率化が図れます。例えば、施工管理アプリを利用すれば、帳簿や図面、写真など、工事に関わる情報を一括管理でき、事務と現場が同じ情報をリアルタイムで共有しやすくなります。
これにより、業務の効率化・業務時間の削減に繋がり、働き方の効率向上に寄与します。
建設現場で進むペーパーレス化の具体例
建設業界では、取引書類の電子化から現場での情報共有まで、さまざまな領域でデジタルツールの導入が進んでいます。電子契約書・電子請求書
建設業界では、受発注システムを利用した取引書類の電子化が一般的です。インターネット上で見積り回答や契約締結を行えるシステムが開発されており、押印や郵送など時間や手間のかかる作業を削減し、取引をスムーズにすることが可能です。
例えば、毎月4,000社以上の取引先に支払通知書を郵送していた企業が電子化したことで、年間500万円のコスト削減を実現した事例もあります。
施工図・日報のデジタル化
建設業界に欠かせない施工図面などの大量の紙資料をデータ化して管理・共有することで効率化が図れます。また、現場で作成されていた紙の日報を電子化すれば、出先で作成・提出することができ、現場から会社に一旦戻って作成・提出するといったムダな移動を省くことが可能に。
電子帳票システムを導入することで、帳票の作成や送信、管理を自動化し、業務効率の向上に繋がります。
スマホ・タブレットによる現場入力
ペーパーレス化を進めるうえで、スマートフォンやタブレットの導入は有効な手段です。クラウドサービスで管理されている図面や資料をいつでも現場で確認できるようになります。
また、タブレットはノートのような感覚で取り出せて、電子ペンを使えばPDFに書き込みもできるため便利です。
これにより、端末一つで資料を確認でき、大量の資料を現場に持ち込む負担も軽減されます。
検査・安全書類の電子化
工事写真、完成図などの品質管理書類は特に電子化が優先されており、「完全に電子化」の割合が他のカテゴリより高くなっています。一方で、勤怠管理表、新規入場者記録などの労務・安全衛生書類は「全く電子化されていない」という割合が高く、運用改善が求められる領域です。
作業打ち合わせ記録や危険予知活動記録などの現場帳票をペーパーレス化することで、関係者の受領・サイン・捺印の手間や物理的コストの削減に成功した事例もあります。
ペーパーレス化の課題と注意点
ペーパーレス化はメリットが多い一方、従業員のデジタルリテラシーや既存の業務フローとの兼ね合いなど、導入・運用にあたっての課題も存在します。操作定着の難しさ
ペーパーレス化の推進における最大の障壁は、「高齢化・リテラシー不足で社内に浸透しない」ことです。従業員全体のデジタルスキルが不十分な場合、ペーパーレス化の運用が難しくなり、特に現場レベルでは教育やトレーニングが欠かせません。
データ管理とバックアップの重要性
書類を電子データとして保存する場合、電子文書法に基づき、改ざんを防ぐ「完全性」や、必要なデータをすぐに活用できる「検索性」といった要件を満たす必要があります。また、電子化によりセキュリティが強化される一方で、データの閲覧権限の設定や不正アクセスの対策(機密性)が重要になります。
システムトラブルや万が一の破損に備え、クラウドサービスを利用するなど、適切なデータ管理とバックアップ体制の構築が不可欠です。
電子化だけでは利益管理が難しい
ペーパーレス化は「コスト削減」や「業務効率化」といった効果を生みますが、単に書類を電子化するだけでは、真の経営目標である「利益最大化」には繋がりません。紙の資料では、データの比較や推移の確認、課題の抽出に手間がかかり、分析結果の視える化にも時間を要します。
ペーパーレス化で得られたデータを活用し、原価を正確に把握する仕組みがなければ、競争力の向上は難しいでしょう。
ペーパーレス化を成功させるポイント
ペーパーレス化を社内に定着させ、最大限の効果を得るためには以下のポイントを押さえて導入を進めましょう。現場主導で小さく始める
ペーパーレス化をスムーズに進めるには、リスクを軽減するためにも、段階的に導入することが重要です。すべての書類を一気に電子化しようとするのではなく、まずは社内で完結する書類や、よく使う契約書、図面など、効果が出やすい領域から優先順位をつけて始めることをおすすめします。
また、導入したいITツールやシステムを決めたら、トライアル期間を活用して使い心地を確かめ、現場の声を反映させながら進めることが成功に繋がります。
運用を定着させる教育体制も同時に整備する
建設現場では、オフィスだけでなく現場でもICTツールを使用する機会が多くあります。そのため、ペーパーレス化を始める際には、事前にツールの使い方について社内で共有する時間を設ける必要があります。
特に、高齢化やリテラシー不足が障壁となるため、説明会の開催やマニュアル作成を行うなど、現場で混乱が起こらないよう準備を整えることが大切です。
導入後も効果測定を行い、継続的な評価と改善を行うことで、社内に浸透しやすくなります。
他システムとの連携を考慮する
電子化に必要なITツールやシステムを選定する際は、単体の機能だけでなく、他システムとの連携性も考慮することが重要です。例えば、見積り回答や契約締結が同じツール内で完結できるか、あるいは基幹システムと連携できるかなど、既存の業務フローやシステムとの兼ね合いを見直す必要があります。
特に、大量の帳票を配信する必要がある場合、取引先のデータ形式にも柔軟に対応できる連携の豊富さを持つツールを選ぶと、導入後の利便性が高まります。
ペーパーレス化と原価管理の連携で利益を最大化!
ペーパーレス化は、書類作成の手間やコストを削減し、現場の業務効率を大きく向上させます。しかし、次の段階として、デジタル化した情報を経営判断や利益管理に活かす仕組みづくりが求められます。
そのためには、図面・見積書・請求書・外注費といった各種データを一元化し、工事ごとの原価や利益を正確に把握できる体制が必要です。
建設業向け原価管理システム「要 〜KANAME〜」なら、工事台帳をベースにデータを一元管理でき、工事ごとの利益をリアルタイムで見える化できます。
<3分でわかる!「要 〜KANAME〜」を動画で見る>
建設業のペーパーレス化についてよくある質問
Q1. 建設業界でペーパーレス化が遅れている主な要因は何ですか?
A. 最も多く挙げられる要因は、「高齢化・リテラシー不足で社内に浸透しない」ことです。現場レベルでの教育不足や、従業員全体のデジタルスキルが不十分であることが運用を難しくしています。
また「建設業界特有の多重下請構造(ピラミッド構造)により書類のやり取りが多いこと」や「電子化が難しい書類が多い」ことも障壁となっています。
Q2. ペーパーレス化によって、具体的にどのようなコストが削減できますか?
A. 最も直接的な効果は「紙代・印刷代の削減」です。これに加え、大量の資料を運ぶ輸送コスト、書類の検索やファイリングにかかる人件費、コピー機のメンテナンス費用、さらには書類の廃棄費用など、物理的・間接的なコストも削減できます。
Q3. 建設業の書類のなかで、電子化が進んでいるものと遅れているものはありますか?
A. 品質管理書類(工事写真、完成図など)は、現場効率化のため電子化が優先されています。工程関係書類も比較的進展が見られます。一方で、労務・安全衛生書類(勤怠管理表など)は電子化が遅れ気味です。
また、契約関係書類(請負契約書、見積書など)も法的な慣習から紙の依存度が高い状況です。
Q4. 中小企業がペーパーレス化を導入する際のポイントは何ですか?
A. 中小企業規模ではコストや人的リソースの不足が課題となり、ペーパーレス化が進んでいないケースが多いです。成功のためには、はじめから全てをペーパーレス化しようとせず、段階的に導入することが重要です。
まずは社内で完結する書類や、利用頻度の高い図面などから着手し、現場での負担を減らすために、デジタルペンで書き込みができるタブレットを同時に活用することをおすすめします。
Q5. 建設工事の契約書を電子化することはできますか?
A. はい、可能です。建設業法改正により、取引相手の承諾を得れば、工事請負契約書を電子契約で締結することが認められました。インターネット上で見積り回答や契約締結を行えるシステムを導入することで、押印や郵送の手間を削減し、スムーズな取引が可能になります。