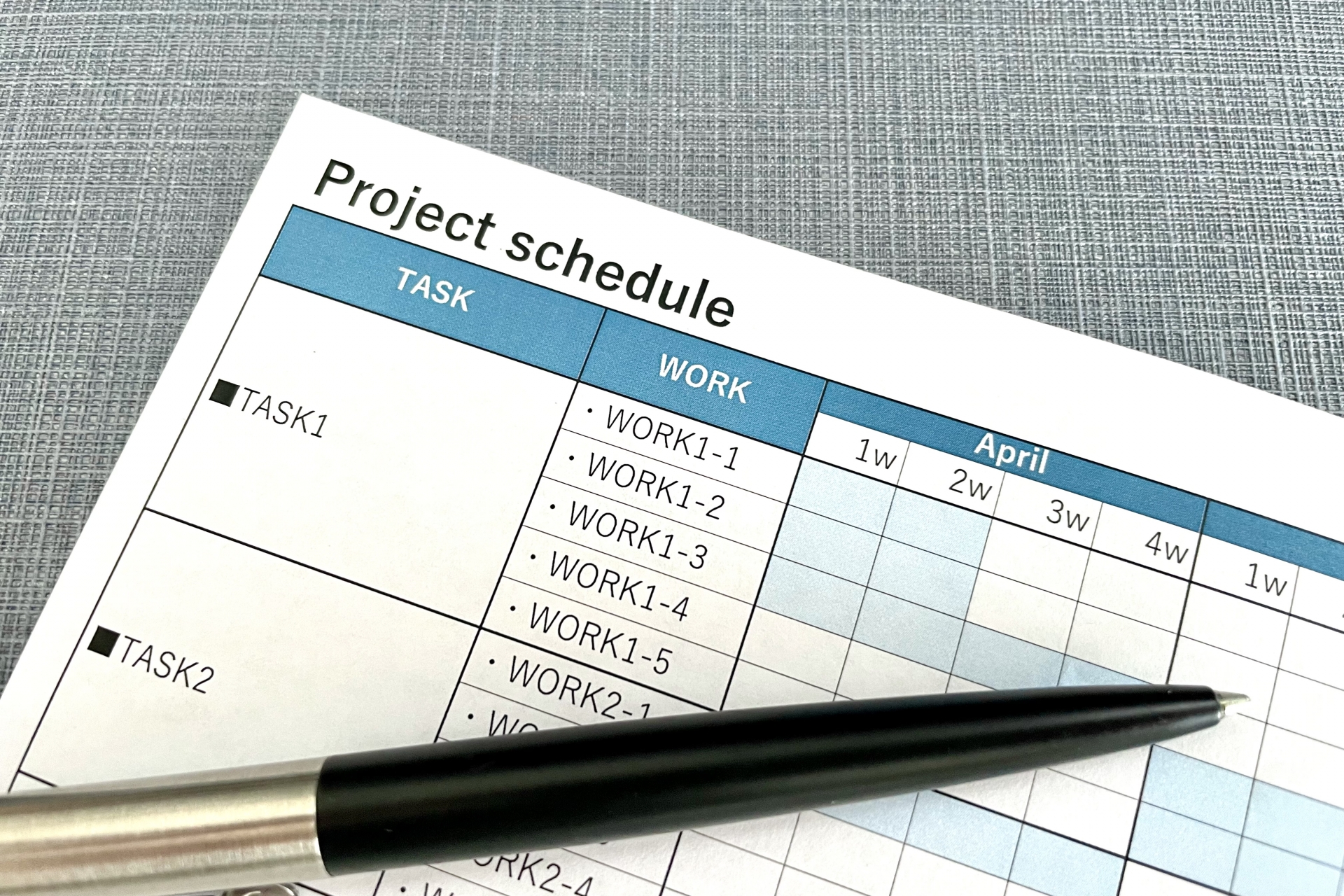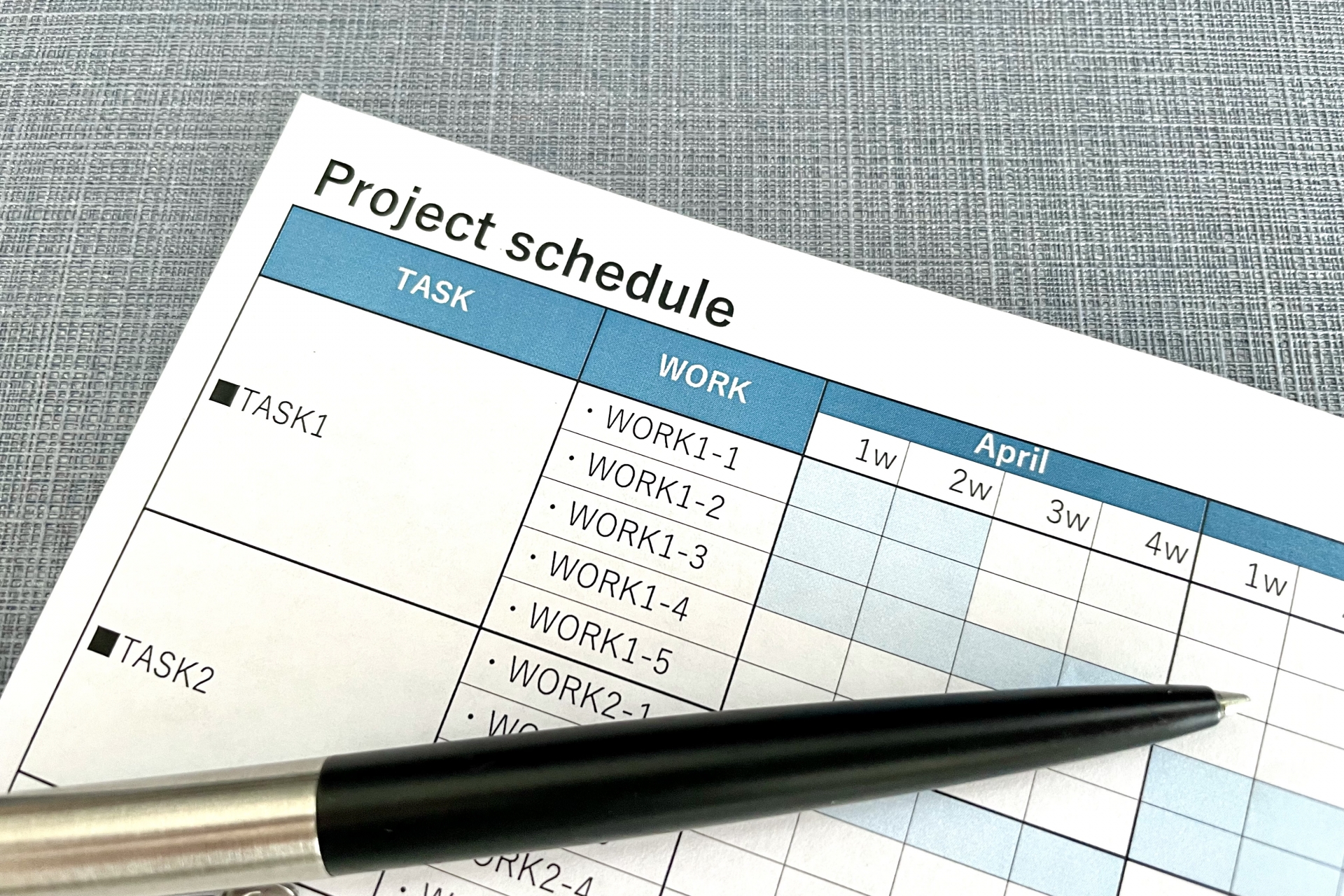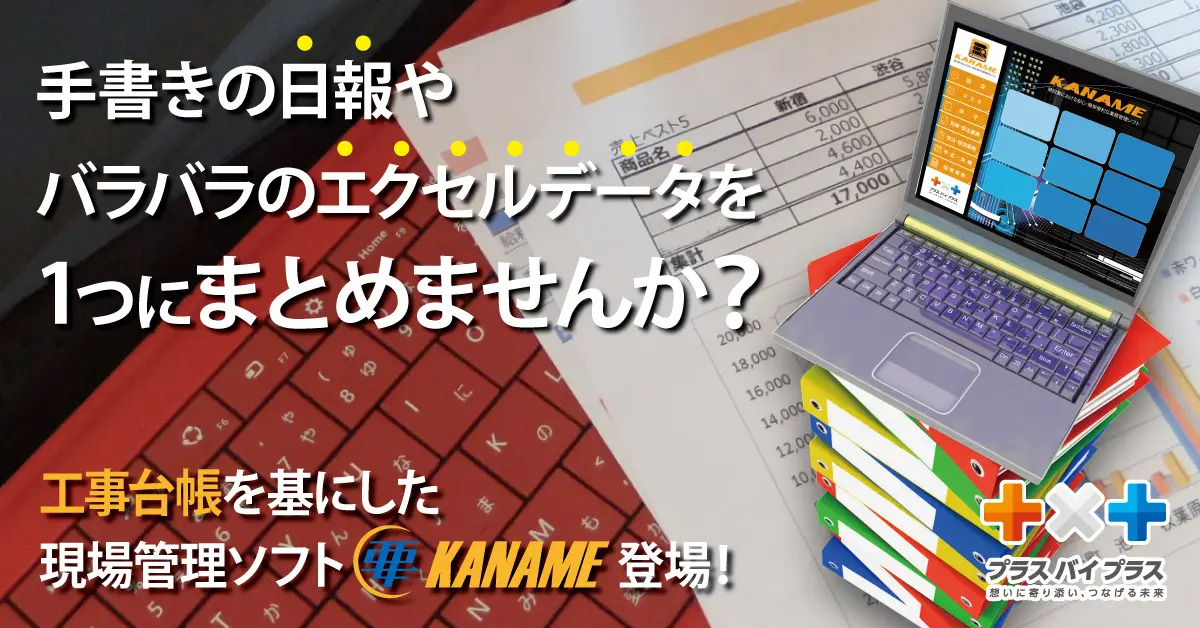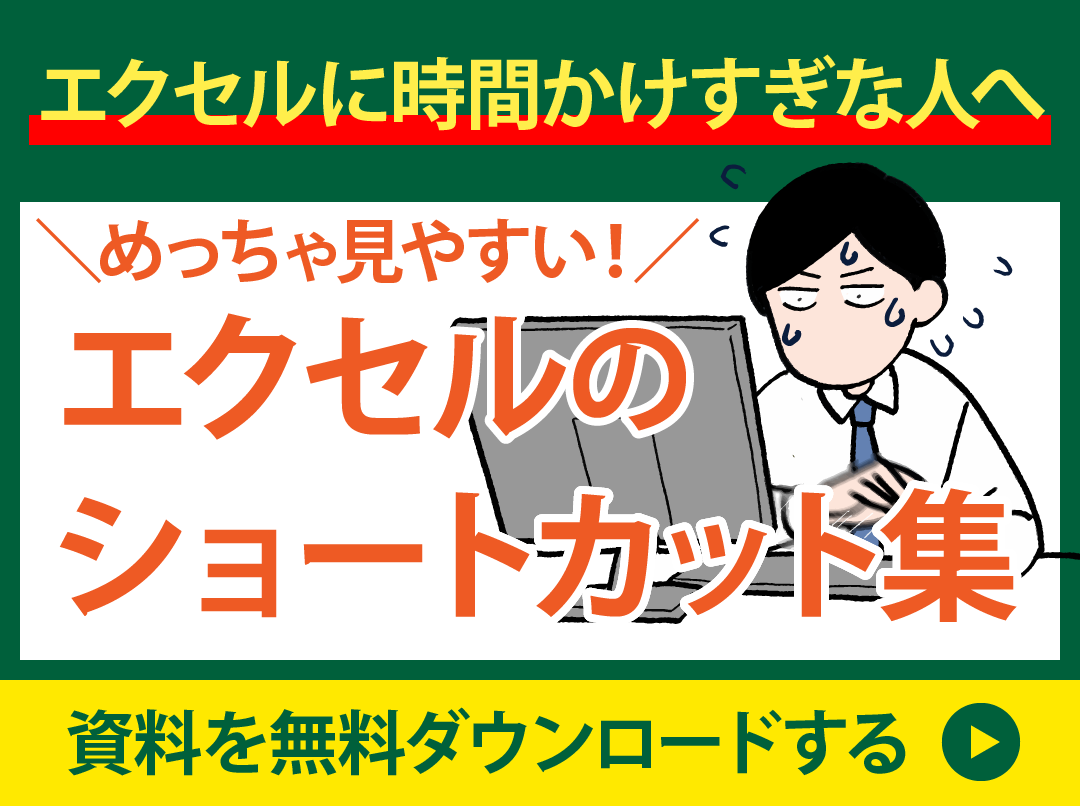- 2025年10月28日
作業員名簿の書き方とは?ミスしないための注意点を解説(テンプレートもご紹介)
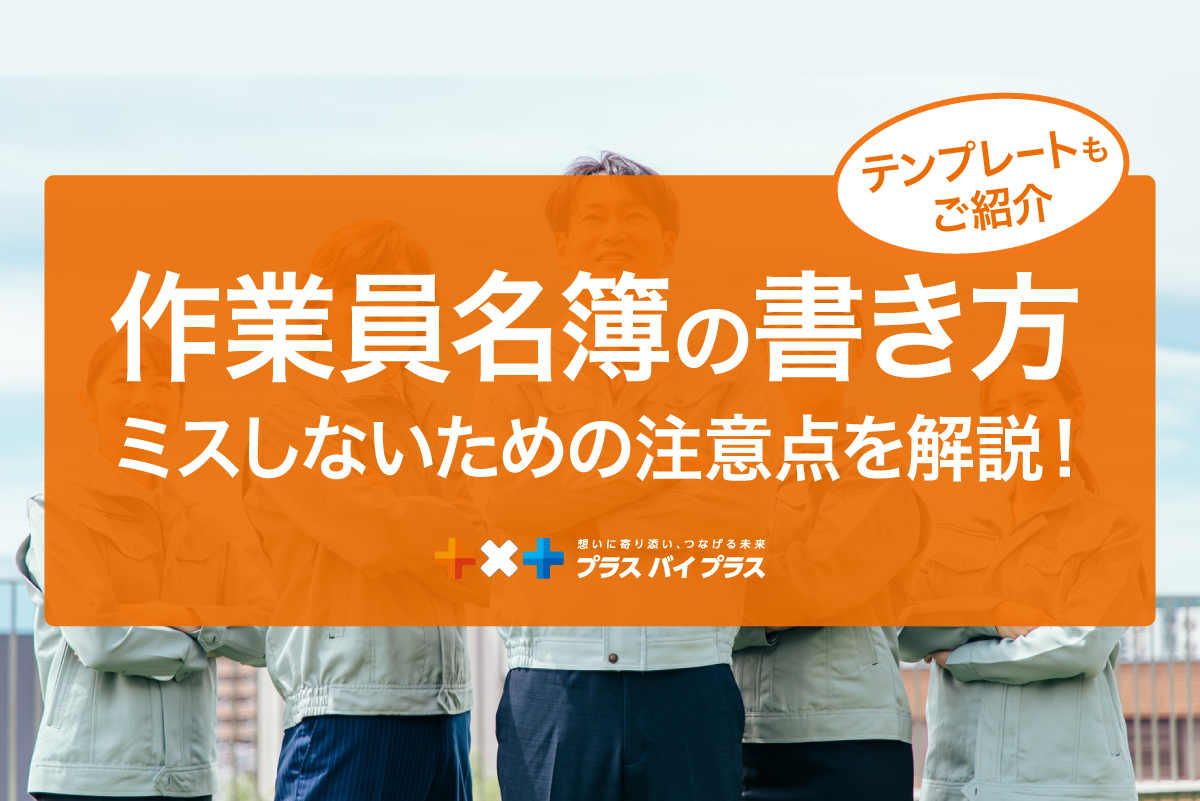
建設業において、作業員名簿の作成は法令で義務付けられています。この名簿は、現場で働く作業員の情報を正確に把握し、安全管理や緊急時の対応に不可欠な書類です。
ここでは、作業員名簿の書き方について、必要な項目や記載時の注意点、さらには一人親方の場合の書き方まで、テンプレートを交えながら網羅的に解説します。
コンテンツ
作業員名簿とは?目的と必要性
建設業における作業員名簿は、建設現場に従事する全ての作業員の氏名や資格、緊急連絡先などを一覧にした書類です。これは、どの現場に誰が入場しているかを明確にすることで、安全衛生管理や労災発生時の対応に役立てる目的があります。
建設業法改正により、「建設工事従事者に関する事項」が施工体制台帳に追加され、作業員名簿の作成が実質的に義務化されました。この法令に基づく義務付けは、建設業界で働く人々の適切な管理や待遇改善、安全な労働環境の確保を目指す国土交通省の方針によるものです。したがって、作業員名簿は単なる書類ではなく、現場の安全と適正な施工体制を確保するための重要な役割を担っています。
作業員名簿のテンプレートの利用
作業員名簿の作成にあたっては、一般的に広く使用されているテンプレートを活用するのが効率的です。
テンプレートを利用することで、必要な項目があらかじめ決まっているため、スムーズに作成を進めることが可能です。ただし、提出先である元請業者によっては、独自の書式やフォーマットを指定する場合もあるため、事前に確認することが重要です。テンプレートはあくまで作成を補助するツールとして捉え、提出先の指示に従って必要な情報を正確に記載する役割を理解しておきましょう。
国交省が公開しているテンプレートはこちらからダウンロードができます。
作業員名簿の作成に必要な項目
作業員名簿には、現場で働く作業員の情報を網羅的に記載する必要があります。これは、労働安全衛生法や建設業法施行規則で定められた事項を網羅し、現場の安全管理体制を明確にするためです。基本的な項目に加え、それぞれの作業員が持つ資格や社会保険の加入状況など、多岐にわたる情報が記載事項となります。
これらの必要事項を正確に記載することで、万が一の事故や災害発生時に迅速な対応が可能となり、また適切な施工体制が構築されていることを証明できます。一般的には、全建統一様式第5号が広く用いられており、この様式には作業員の詳細な情報や、事業者に関する情報などを記入する欄が設けられています。
記入例で確認する基本項目
作業員名簿の基本項目と記載のポイントは下記のようなことが挙げられます。
| 項目 | 記入のポイント |
|---|---|
| 氏名 | 正確に記入し、ふりがなも忘れずに記入します。 |
| 生年月日 | 和暦・西暦どちらでも構いませんが、提出先の指定があればそれに従いましょう。 |
| 年齢 | 作成日時点の年齢を記載します。 |
| 職種 | 現場での具体的な役割がわかるように記入します。 |
| 経験年数 | 会社での勤続年数ではなく、その職種での実務経験年数を記載します。 |
| 現住所・連絡先 | 緊急時に確実に連絡が取れるように正確に記入することが求められます。 |
| 家族連絡先 | 緊急時に備えて正確に記載します。 |
| 健康診断に関する情報 | 必要事項を正確に記載します。提出先によって様式が異なる場合もあります。 |
| 社会保険の加入状況 | 加入の有無などを明確に記載します。 |
| 保有資格 | 所持している資格を漏れなく記載します。 |
会社名や社名の書き方
作業員名簿における会社名の記載は、名簿を作成する自社の正式名称を記入します。
元請業者が作成する場合は元請業者の会社名を、一次下請業者が作成する場合は一次下請業者の会社名を記載します。
二次以降の下請業者が作成する場合も同様に自社の会社名を記入し、自身が元請から数えて何次下請であるかを明記することが求められます。会社名の代わりに自社の現場代理人の氏名を記載することも可能ですが、元請業者への確認が必要です。
建設キャリアアップシステムに登録している場合は、併せて事業者IDも記載します。複数の会社が関わる現場では、各社がそれぞれの作業員名簿を作成し、上位の会社に提出するのが一般的です。
作成日・提出日の記載方法
作業員名簿には、名簿を作成した日付である作成日と、元請業者などの提出先に提出した日付である提出日を記載します。
作成日は、名簿を完成させた時点の日付を記入します。
提出日が確定している場合は、提出日欄にその日付を記入しますが、確定していない場合は提出直前に記入するか、空欄で提出し元請業者が追記することもあります。
いつからいつまでの期間の作業員が記載されているかを明確にするためにも、これらの日付は正確に記載することが重要です。
職種の記入例と一覧
作業員名簿における職種の記入は、作業員が現場で実際に担当する具体的な業務内容がわかるように記載します。例えば、「型枠大工」「オペレーター」「電気工事士」「とび工」「配管工」「鉄筋工」「土工」など、専門性の高い職種や一般的な作業内容を示す言葉が用いられます。施工管理技士や作業主任者のような資格に基づいた職務も記載されます。
アルバイトとして従事している場合でも、現場での具体的な作業内容に応じた職種を記入することが適切です。会社内で使用している呼称と現場で一般的に使用される職種名が異なる場合は、後者に合わせて記載することで、元請業者をはじめとする関係者が容易に理解できるようになります。
経験年数の書き方
経験年数の項目には、現在担当している職種における実務経験の年数を記入します。これは、単に現在の会社に所属している期間ではなく、該当する職種で業務に携わってきた通算の年数を示すものです。
複数の会社での経験や、一時的にブランクがあった場合も、その職種での経験を合計して記載します。
正確な経験年数を記載することで、作業員の技能レベルを把握し、適切な人員配置や作業分担の判断材料となります。経験年数が不明確な場合は、本人に確認するなどして正確な情報を把握し記載することが重要です。
生年月日・年齢の正しい記入
作業員名簿には、作業員の生年月日と作成日時点での年齢を正確に記載します。
生年月日は、和暦または西暦で記入し、元請業者からの指定があればそれに従います。
年齢は、名簿を作成した日付時点での満年齢を記載します。特に18歳未満の作業員を現場に入れる場合は、労働基準法によって就業制限があるため、年齢を証明する書類(住民票記載事項証明書など)の提出を求められることがあります。
正確な生年月日と年齢の記載は、労働法令遵守の観点からも重要です。
現住所・連絡先の記入のポイント
現住所と連絡先の項目には、作業員本人と確実に連絡が取れる情報を記入します。
現住所は、住民票に登録されている住所を正確に記載します。
連絡先としては、日中連絡がつきやすい携帯電話番号などを記入することが一般的です。
これらの情報は、現場での緊急時や、作業に関する重要な連絡を行う際に不可欠です。引っ越しなどで住所や連絡先が変更になった場合は、速やかに名簿の情報を更新する必要があります。
家族連絡先の書き方と注意点
家族連絡先(緊急連絡先)の項目には、作業員本人に万が一の事態が発生した場合に連絡が取れる親族などの連絡先を記入します。これは、労災事故や急病など、緊急時に迅速な対応を行うために非常に重要な情報です。一般的には、配偶者、親、兄弟姉妹などの連絡先を記載することが多いです。
この情報は個人情報の中でも特に慎重な取り扱いが必要であり、個人情報保護法の観点から、必ず本人の同意を得て記載する必要があります。記載された情報は、緊急時の連絡以外の目的で使用しないよう厳重に管理することが求められます。
健康診断に関する記載項目
作業員名簿には、労働安全衛生法に基づき実施された健康診断に関する情報を記載する項目があります。具体的には、直近の健康診断の受診年月日を記入します。
労働者は年に一度の定期健康診断の受診が義務付けられており、ここに記載する日付は最新のものである必要があります。また、特定の有害業務に従事する作業員は、別途特殊健康診断の受診が義務付けられている場合があり、該当する場合はその受診日と健康診断の種類を記載する項目もあります。
血圧・血液型など健康情報欄
健康情報に関する項目として、血圧や血液型を記載する欄が設けられている場合があります。
血圧については、最高血圧と最低血圧の両方を記入します。血液型も緊急時の医療措置に役立つ情報として記載されることがあります。
これらの健康に関する情報は、個人のプライバシーに関わる重要な個人情報であるため、取り扱いには十分な注意が必要です。記入にあたっては、必ず作業員本人の同意を得て、目的外の利用や漏洩がないように厳重に管理する必要があります。
雇用保険・年金保険などの保険番号記入
作業員名簿には、雇用保険、健康保険、厚生年金保険などの社会保険の加入状況を記載する項目があります。これらの項目には、各保険の被保険者番号などを記入します。
健康保険については、協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険など、加入している保険の種類を記載し、被保険者番号を記入します。
年金保険についても、厚生年金や国民年金など種類を記載し、基礎年金番号などを記入します。
雇用保険についても同様に加入状況と被保険者番号を記載します。
これらの保険情報は、作業員の社会保障を確認する上で重要な情報となります。ただし、個人情報保護の観点から、これらの情報を記載する際には本人の同意を得ることが求められます。
特殊健康診断や特別教育の記入例
特殊健康診断や特別教育に関する項目には、該当する健康診断の受診日や特別教育の実施年月日、教育内容などを記入します。
特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する作業員に義務付けられている健康診断であり、じん肺検診や有機溶剤健康診断など、その種類と最新の受診年月日を記載します。
特別教育は、特定の危険・有害な業務に就く作業員に対して義務付けられている教育であり、フォークリフト運転技能講習や高所作業車運転特別教育など、受講した特別教育の名称と実施年月日を記入します。
これらの情報は、作業員が担当する業務に必要な資格や教育を受けていることを証明するものです。
免許・資格欄の書き方
免許・資格欄には、作業員が業務に関連して保有している各種免許や資格を記載します。
建設工事に関連する国家資格(例:1級・2級建築施工管理技士)や、技能講習の修了証、運転免許証など、現場での作業に必要なものや、作業員の技能レベルを示すものを記入します。記載する際は、正式名称や取得年月日なども併記するとより詳細な情報となります。
多くの場合、記載した免許や資格を証明するために、免許証や資格証の写しを作業員名簿に添付することが求められます。これにより、記載内容の正確性を担保し、作業員の適正な配置に役立てられます。
技能講習・受入教育実施年月日の記入
技能講習の項目には、各都道府県の労働局に登録された教育機関で受講した技能講習の名称と修了年月日を記入します。これに対し、受入教育実施年月日の項目には、新規入場者に対して現場のルールや安全注意事項などを教育した年月日を記入します。
一般的に、入場年月日と同じ日付になることが多い項目です。これらの教育や講習の実施記録は、作業員の安全意識向上や事故防止のために重要であり、適切に記入・管理する必要があります。
退職金共済制度の必要事項
退職金共済制度に関する項目には、作業員が加入している退職金共済制度の種類を記載します。
建設業界で一般的に利用されているのは、建設業退職金共済制度(建退共)や中小企業退職金共済制度(中退共)です。該当する制度に加入している場合は、「建」や「中」といった記号や、加入している旨を記載します。
これにより、作業員の退職金制度への加入状況を把握することができます。
全建統一様式第5号の欄外記入例
全建統一様式第5号の欄外には、工事に関する基本的な情報や、名簿の作成者に関する情報を記入する項目があります。具体的には、事業所の名称(工事名や現場名)、所長名(元請業者の現場代理人の氏名)、作成日、一次会社名(名簿を作成する一次請負業者の会社名、または現場代理人名)、そして名簿を作成する自社の会社名と、その会社が元請から数えて何次下請にあたるか(例:「二次」)などを記載します。
これらの欄外情報は、その作業員名簿がどの工事の、どの会社の、いつ作成されたものかを示すものです。建設キャリアアップシステムに登録している場合は、事業所の名称欄に現場IDを、会社名欄に事業者IDを併記することもあります。
作業員名簿の提出と保管
作成した作業員名簿は、定められた提出先に期日までに提出し、また一定期間適切に保管することが義務付けられています。これは、建設業法に基づくものであり、施工体制台帳の一部として取り扱われます。
作業員名簿の提出と保管は、現場の安全管理体制を確保し、関係者が必要な情報をいつでも確認できるようにするために不可欠です。提出義務があるケースや、提出時の注意点、そして定められた保存期間と保管方法について理解しておくことが重要です。
提出義務があるケース
作業員名簿の提出義務は、建設業法改正により実質的に全ての建設工事において発生します。具体的には、元請業者が特定建設業の許可を受けているか否かに関わらず、また下請契約の金額にかかわらず、施工体制台帳の作成とその中に作業員名簿を含めることが義務付けられています。したがって、現場に作業員を送り出す全ての建設業者は、自社が雇用する作業員に関する名簿を作成し、上位の請負業者を通じて元請業者に提出する必要があります。
再下請負が発生する場合も、それぞれの会社が自社の作業員名簿を作成し、上位の会社に提出します。元請業者は、これらの名簿を取りまとめて施工体制台帳に添付し、発注者や関係機関に提出することが求められます。
提出時の注意点
作業員名簿を提出する際は、いくつかの注意点があります。
まず、記載内容に漏れや誤りがないか、提出前に必ず確認することが重要です。特に氏名や生年月日、社会保険の加入状況など、基本的な情報が正確に記載されているかを入念にチェックしましょう。
また、資格や免許、健康診断結果など、記載内容を証明するための書類の写しを添付する必要がある場合が多いです。これらの添付書類が不足していると、書類不備として差し戻される可能性があります。誰に、いつまでに提出する必要があるかなど、提出先の元請業者からの指示を事前に確認し、不明な点があれば質問することが大切です。
現場に新たな作業員が追加される場合は、名簿全体を作り直すのではなく、既存の名簿に追記して提出することで対応できることが一般的です。
保存期間と保管方法
作業員名簿は、建設業法により、工事完成後の引き渡し日から5年間の保存が義務付けられています。これは、労働基準法で定められている労働者名簿の保存期間である5年間(以前は3年間)と同様の期間です。
保管方法は、紙媒体でも電子媒体でも可能ですが、個人情報を含む重要な書類であるため、適切な管理が必要です。紙媒体で保管する場合は、水濡れや汚損、紛失を防ぐため、ファイリングして施錠可能な書庫などに保管することが望ましいです。
電子媒体で保管する場合は、データの漏洩や改ざんを防ぐために、アクセス制限やバックアップなどのセキュリティ対策を講じる必要があります。
一人親方や現場に応じた作業員名簿
作業員名簿の作成は、企業に雇用されている作業員だけでなく、一人親方や、元請、下請といった立場によっても書き方や提出方法が異なります。それぞれの立場や現場の状況に応じた適切な方法で作業員名簿を作成することが重要です。
ここでは、一人親方の場合の書き方や、元請・下請それぞれの立場で作業員名簿を作成する際のポイントについて解説します。
一人親方の場合の書き方
一人親方の場合も、基本的に作業員名簿の作成・提出が必要です。法人が作成する場合と大きく異なる点はありませんが、いくつかの項目で一人親方特有の記載が必要となります。
一次会社情報には、直接契約している一次下請業者の会社名を記載します。自社の情報欄には、自身が何次下請にあたるかを記入し、会社名の欄には屋号があれば屋号を、なければ個人名を記入します。
社会保険の項目では、健康保険は国民健康保険、年金保険は国民年金となるため、それぞれ「国民健康保険」「国民年金」と記載し、保険番号の下4桁などを記入します。雇用保険は一人親方は加入できないため、「適用除外」などと記載します。
元請の場合の書き方
元請業者は、自社が直接雇用する作業員の作業員名簿を作成するだけでなく、下請業者から提出された作業員名簿を取りまとめる役割を担います。元請として作業員名簿を作成する際は、欄外の事業所名称や所長名には、工事全体の名称や元請の現場代理人の氏名を正確に記載します。
また、下請業者から提出された名簿についても、記載漏れや添付書類の不足がないかを確認し、必要に応じて修正や追記を指示します。元請業者は、全ての作業員の名簿を網羅的に把握し、施工体制台帳の一部として適切に管理する責任があります。
下請・二次の場合の書き方
下請業者(一次、二次以降)は、自社が雇用する作業員に関する作業員名簿を作成し、直接の請負元である上位の会社に提出します。作成にあたっては、欄外の会社名欄に自社の正式名称を記入し、自身が元請から数えて何次下請であるかを明確に記載します。
欄内の各項目には、自社の作業員一人ひとりの情報を正確に記載します。二次下請以降の場合は、一次下請の会社名も欄外に記載することが一般的です。
記載内容に不明な点がある場合は、上位の会社に確認しながら作成を進めることが重要です。提出時には、記載内容を証明する書類の添付も忘れずに行います。
個人情報や記載時の注意事項
作業員名簿には、氏名、生年月日、住所、連絡先、社会保険情報など、多くの個人情報が含まれます。これらの情報の取り扱いには、個人情報保護法の観点から細心の注意が必要です。適切な管理方法を理解し、情報漏洩や不適切な利用を防ぐための対策を講じることが求められます。
また、名簿作成時には、記載内容の正確性を期すために、証明書類の添付が必要となる項目があります。さらに、現時点で不明な項目がある場合の対応についてもあらかじめ把握しておくことが重要です。
個人情報の管理方法
作業員名簿に含まれる個人情報は、その性質上、厳重な管理が必要です。個人情報保護法を遵守し、情報漏洩や目的外利用を防ぐための対策を講じなければなりません。具体的には、名簿の保管場所を限定し、関係者以外のアクセスを制限する、電子データで管理する場合はパスワード設定や暗号化を行うといった物理的・技術的な対策が有効です。
また、作業員に対して、どのような目的で個人情報を収集し、どのように管理するのかを明確に説明し、同意を得ることも重要です。建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用することで、一部の個人情報をシステム上で一元管理し、情報の安全性を高めることも可能です。
証明書類や免許証の添付
作業員名簿に記載された資格や免許、健康診断の結果などの情報の正確性を証明するために、関連書類の写し(コピー)を作業員名簿に添付することが一般的です。具体的には、運転免許証、技能講習修了証、国家資格の合格証明書、健康診断結果通知書、特殊健康診断個人票、建設業退職金共済手帳の写しなどが挙げられます。
これらの添付書類は、記載内容の裏付けとして提出先に確認されるため、漏れがないように準備する必要があります。原本ではなく写しを提出することが一般的です。
現時点で不明な項目への対応
作業員名簿を作成する時点で、一部の項目について情報が不明な場合があります。例えば、新規入場者の受入教育実施年月日など、着工前に作成する場合は確定していないことがあります。このような場合は、該当する項目を空欄にして提出し、情報が確定次第速やかに追記するという対応が可能です。
ただし、提出先の元請業者によっては対応が異なる場合もあるため、事前に確認することが重要です。不明な項目をそのままにせず、いつまでにどのように追記するかを明確にしておくことが、書類不備を防ぐ上で大切です。
作業員名簿の最新様式・法令対応
作業員名簿の様式や記載事項は、法令改正などにより変更されることがあります。特に建設業においては、働き方改革の推進や建設キャリアアップシステムの導入など、様々な動きがあり、それに伴って関係書類の様式が見直されることがあります。最新の様式や法令の要求事項を常に把握し、適切に対応することが重要です。
ここでは、統一様式や最新版のポイント、関連する安全書類である施工体制台帳の概要、そして書類作成・管理の効率化について解説します。
統一様式・最新版のポイント
作業員名簿には、一般的に「全建統一様式第5号」が広く普及していますが、これはあくまで標準的な様式であり、法令で定められた特定の様式があるわけではありません。ただし、建設業法の改正に伴い、2021年3月には国土交通省から新たな様式が提示されており、全建統一様式と比較して記載項目が一部変更されています。
最新版のポイントとしては、建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携を考慮した項目が追加されたり、一部の個人情報に関する記載が任意になったりする傾向があります。現場や元請業者によって使用する様式が異なる場合があるため、作成前にどの様式を使用するか確認することが重要です。
安全書類や施工体制台帳の概要
作業員名簿は、建設現場における安全管理に必要な一連の書類、いわゆる「安全書類」(グリーンファイルとも呼ばれます)の一部です。これらの安全書類の中心となるのが「施工体制台帳」です。
施工体制台帳は、元請業者が作成し、工事に関わる全ての会社の情報や施工分担、技術者などを記載することで、工事全体の施工体制を明確にするものです。建設業法施行規則により、施工体制台帳の記載事項として作業員名簿が含まれることになっており、作業員名簿は施工体制台帳に添付する書類として位置づけられています。
施工体制台帳や安全書類を適切に作成・管理することは、法令遵守はもちろん、現場の安全確保や円滑な工事の進行に不可欠です。
統一と台帳管理のコツ
作業員名簿を含む施工体制台帳の管理を効率的に行うためには、様式を統一し、情報を一元管理することが有効です。現場ごとに異なる様式を使用すると、作成の手間が増えたり、情報の管理が煩雑になったりする可能性があります。可能な限り、自社または元請業者指定の統一様式を使用することで、書類作成の標準化を図ることができます。
また、紙媒体での管理だけでなく、電子データとして管理することも効率化につながります。専用のソフトウェアやクラウドサービスを活用することで、作業員情報の入力、更新、検索、提出などがスムーズに行えるようになります。これにより、書類作成にかかる時間を削減し、人的ミスの軽減にも繋がります。
よくあるミスとその対策について
作業員名簿の作成においては、記載漏れや誤記、添付書類の不足など、様々なミスが発生する可能性があります。これらのミスは、書類不備として差し戻されるだけでなく、現場の安全管理体制に影響を与える可能性も否定できません。ミスを防ぐためには、作成段階での確認作業が非常に重要です。具体的には、チェックリストの活用や、複数人でのクロスチェックなどが有効な対策となります。
また、不明な項目をそのままにせず、必ず提出先に確認することも重要です。提出先の元請業者によっては、独自のチェック体制を設けている場合もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
まとめ
作業員名簿は、建設業において法令(建設業法施行規則)に基づき作成が義務付けられている重要な書類です。現場で働く全ての作業員の情報を正確に記載することで、安全衛生管理や緊急時の対応、適切な施工体制の確保に不可欠な役割を果たします。
作業員名簿の書き方には、氏名や職種、経験年数といった基本的な項目に加え、社会保険情報や保有資格、健康診断の結果など、多岐にわたる情報が含まれます。特に個人情報の取り扱いには、個人情報保護法を遵守し、細心の注意が必要です。一人親方の場合も作成義務があり、それぞれの立場に応じた記載方法があります。
作成した名簿は、元請業者に提出し、工事完成後5年間保存する必要があります。最新の様式や法令改正に対応し、記載漏れや誤りがないように正確に作成することが重要です。
登録済みのデータから作業員名簿を自動作成できる原価管理ソフト「要 〜KANAME〜」
作業員名簿の作成や管理は、多くの項目があり、記載漏れやミスが発生しやすい作業です。また、現場ごとに異なる様式や提出方法に対応する必要があり、担当者にとって大きな負担となることがあります。このような書類作成の手間を削減し、ミスをなくすためには、原価管理ソフトや安全書類作成・管理サービスの活用が非常に有効です。
原価管理ソフト「要 〜KANAME〜」なら登録済みのデータから、国交省の様式・CCUSの様式・社会保険なしパターンなど様々な様式のエクセルデータを自動作成できます。
年齢などのデータも自動で計算されるので、手間なくデータを作成し提出することが可能です。
よくある質問
作業員名簿はエクセルでも良いですか?
はい、エクセル形式でも問題ありません。ただし、提出先の指定様式がある場合は、そのフォーマットに従う必要があります。作業員名簿に求められる基本項目(氏名・年齢・職種・資格情報など)を網羅していれば、エクセルでの管理・提出が可能です。
一人親方も名簿の提出が必要ですか?
原則として必要です。一人親方であっても、現場に入場する作業員の一人として見なされるため、作業員名簿への記載が求められることがあります。元請や現場のルールによって対応が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
作業員名簿の保存期間はどれくらい?
工事完成後の引渡日から5年間データを残す義務があります。これは建設業法で元請けの義務として定められていますが、下請けとして自社で作成した名簿も同じように保管しておくと安心です。