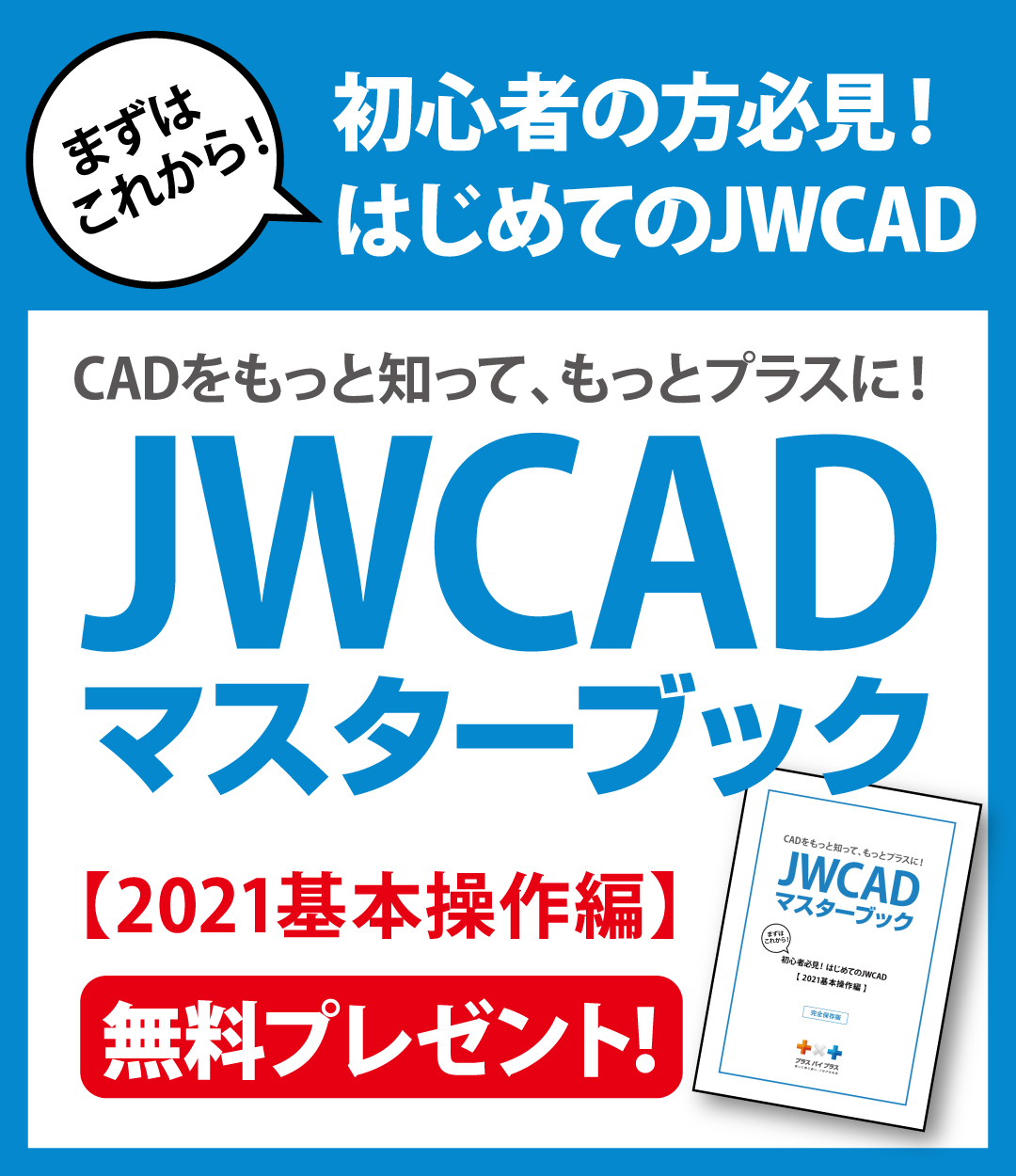- 2024年12月26日
電気配線図とは?読み方・作成方法・便利なツールを徹底解説
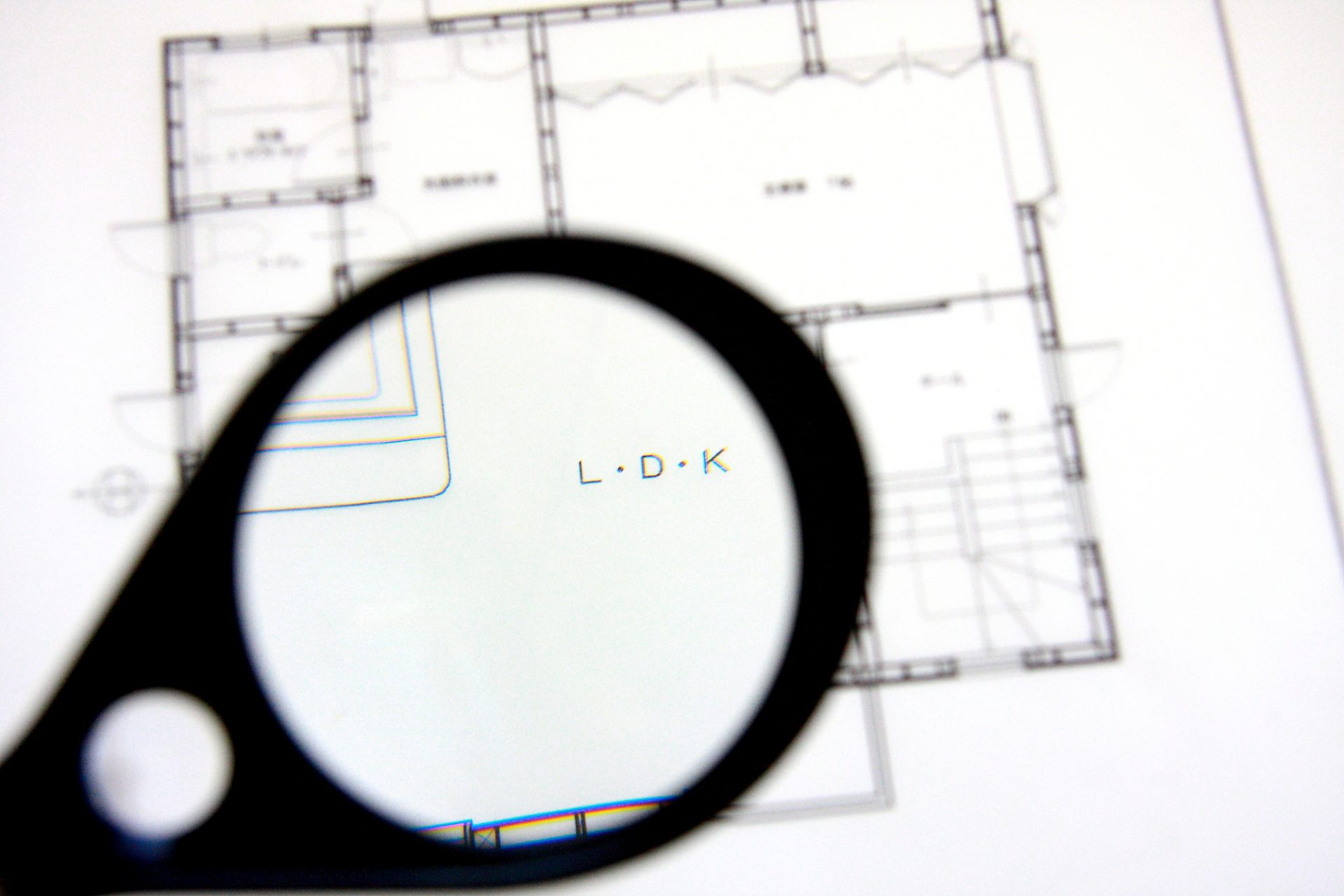
電気配線図は、建物の電気が流れる系統を具体化し、配線や設備・部品の設置場所をわかりやすく記した図面です。電気工事に欠かせない図面の1つで、一般的には記号を用いて複雑な現場での配線や設備配置をわかりやすくまとめる必要があります。
本記事では、電気配線図を作成するメリットや種類、図面の読み方や使用する記号などについて解説します。電気配線図の作成方法についても紹介しますので、効率的な電気配線図の作成にお役立てください。
コンテンツ
電気配線図とは?
電気配線図とは、電気工事における配線や設備、部品などの配置をわかりやすくまとめた図面です。住宅やビルなど建物内の電気の接続方法を、記号を使って図面に落とし込んでいます。電気配線図を見ることで、電気接続を構成する要素や配線はもちろん、現場における電気回路やシステムの相互関係を理解できます。また、図面通りに施工することで、設計時の電気計画から外れてしまい、トラブルになるような事態を避けられます。
電気配線図を作成する目的
電気配線図は、電気工事の現場だけでなく、電気回路の製造や電子機器などさまざまなシーンで作成されます。ここでは、電気配線図を作成する主な目的について解説します。電気設備の設計のガイドラインとして
電気工事は、コンセントやスイッチ、分電盤、変圧器、ブレーカーなどさまざまな設備や部品を配線で接続する複雑な工事です。それぞれの部品や機器の位置と数を、記号を用いて詳細に記した図面が、電気配線図です。電気工事を行う上で、図面が詳細に正しく記載されていないと、事故やトラブルにつながる可能性があります。そのため、電気配線図の内容は、電気設備の設計のガイドラインとしての役割も担っています。
法的要件や安全基準の遵守
電気配線図は、電気設備技術基準や建築基準法などの関連法規に基づいて設計されます。そのため、設計の段階で、施工に適した材料や配置が決定され、配線経路や保護装置の配置を確認できます。また、必要な回路保護装置や接地方法などを正確に示すことで、火災や漏電などのリスクを未然に防ぎ、安全性の確保につながります。加えて、検査機関や許認可申請時に必要な設計内容を提示することで、承認プロセスを円滑に進めることが可能です。
保守・点検の基礎資料として
電気配線図は、 電気設備の保守やメンテナンスでも使われる重要な図面です。電気配線図を基にして、問題箇所を特定し、部品の修理や交換をスムーズに行うことが可能です。もし図面がない、もしくは正しい情報が図面から読み取れないとなると、電気設備の配置や容量、配線の接続などの詳細がわからず、修理を円滑に行うことは難しいでしょう。また、現地調査などの追加コストや手間がかかる可能性も高まります。
コミュニケーションの円滑化
電気配線図は、工事に関与する関係者とのコミュニケーションを円滑にします。設計者と作業者、検査担当者といった立場の異なる人同士がスムーズに情報を共有でき、設計者の意図や仕様を正確に伝えることが可能になります。また、配線経路や接続方法を、テキストではなく図やイラストとして視覚的に示すことで、誤解やミスの防止にも寄与します。さらに、顧客へのプレゼン資料としても活用でき、プロジェクト全体の理解を深め、信頼関係の構築にもつながるでしょう。
建築プロジェクト全体の調整
プロジェクト全体における電気設備の相互関係を把握し、必要な調整を行うために電気配線図が必要です。建物や施設では、電気以外にも給排水や空調、通信設備など多くの設備を設置します。これらの設備との干渉を防ぐために、電気の接続や配線の経路を明確に図示することが重要です。電気経路が視覚的にわかりやすい電気配線図を作成することで、全体における空間的な調整を容易にします。また、建築設計図や施工計画と統合すれば、プロジェクト全体の工程管理やリソース配分の最適化にもつながるでしょう。さらには、建築プロジェクト全体の効率向上や、コスト削減にも寄与します。
電気配線図の種類
電気配線図は、特徴や用途に応じてさまざまな種類に分けられます。ここでは、代表的な以下6つの図面を取り上げます。- 単線接続図
- 複線接続図
- 展開接続図
- 裏面接続図
- 電気設備図
- 系統図
各図面はどのような目的で使われるのか、詳しく解説します。
単線接続図
単線接続図とは、電気接続に関する概要を示す図面です。通常の電気配線は、往路と復路の2本の電線が使用されますが、単線接続図では、設置される設備の配線を1本の線で概念的に記しています。シンプルな図面のため、設備と配線の関係性を直感的に理解しやすい点が特徴です。また、遮断器や変圧器などの容量、開閉器や分電盤の接続など、全体的な電気の流れがまとまっていて、電気の設計や保守などでもよく利用されています。
同じ単線接続図でも、オフィスなど現場によってはさらに詳細に図示されることがあり、情報量が多いものもあります。単線接続図だけで配線することも可能ですが、実際の配線がわかりにくいため、施工作業ではより詳しく情報が書かれた「複線接続図」を用います。
複線接続図
複線接続図は、機器や設備を含む電気接続や配線の経路について、実際に使う電線の本数で記した図面です。単線接続図をより詳細にし、実際に現場で施工する配線本数を正しく図面に反映しています。複線接続図では、図記号や文字記号、器具番号を使用し、各機器の端子番号も含めて実際の結線通りに表記します。具体的な接続方法が理解できるため、電気回路の全体像を把握するというよりも、現場での施工や電気設備の設計・保守、製作といった用途で使われます。
ただし、複線接続図も簡易的な表現であって、照明器具やスイッチ、ジョイントボックスなどの周辺機器の場所について、正確な情報は記載されないケースが多いでしょう。
展開接続図
展開接続図とは、機械やシステムの動作順序が理解できるように視覚化した図です。シーケンス図や主回路とも呼ばれています。すべての電気設備の動作手順を確認した上で、電気経路や配線の種類、設備の設置位置などに関する指示が記されます。一般的には、縦書きの場合は左から右、横書きの場合は上から下へ、という流れに従って記載される点が特徴です。また、設備機器の制御や開閉器、コイルといった各部品から配線の情報を網羅しています。
展開接続図は、制御回路の設計や制御装置の製作・試験、メンテナンス、トラブルシューティングなどで用いられています。単線接続図や複線接続図と同様に、図記号や文字記号を使って表現されますが、特殊性が高く、作成には専門知識が求められます。
裏面接続図
裏面接続図とは、機器の配置や相互接続について、実際の位置や結線通りに詳細に描いた図面です。内部接続図や配線図とも呼ばれています。単線接続図のような概念的な図面に対して、裏面接続図は具体的な機器の内部を図示している点が異なります。配電盤や分電盤、制御盤の内部における配線や接続、各器具の端子まで網羅しています。特に配電盤の内部は接続や位置関係が複雑になりやすく、正確な情報を把握するためにも裏面接続図が欠かせません。また、厨房の大型冷蔵庫やモーターの配線で使われることもあります。
電気配線は、一箇所でもミスがあれば設備や機器が正常に動作しない上、ショートや火災などの事故を引き起こすリスクがあるため、内部接続図も重要な役割を担っています。
電気設備図
電気設備図は、屋内に設置される各種電気設備に関する図面です。屋内配線図とも呼ばれます。「電源設備」「負荷設備」「通信設備」という3つの種別ごとに、細分化された図面を作成します。代表的な図面には、以下があります。電源供給
- 電力引込設備図
- 受変電設備図
- 自家発電設備図
- 蓄電池設備図
- UPS設備図
- 幹線設備図 など
負荷設備
- 電灯設備図
- 温泉設備図
- 動力設備図
- 舞台照明・音響設備図 など
通信・情報設備
- 電話設備図
- 構内交換設備図
- インターホン設備図
- 拡声設備図
- ページング設備図
- テレビ共同受信設備図 など
各図面には、照明器具やスイッチ、コンセントなどの配置、空調設備の配線などが記載されます。また、キッチンや浴室、トイレなど細かな配線図が必要な場合は、区画ごとに電気設備図を作成する場合もあります。
工場などでは、機械ごとに電圧が異なる場合があり、安全に施工するためにも各機械の配線図を作成することが望ましいでしょう。電気設備図は、各業者との打ち合わせで用いられることの多い重要な図面です。
系統図
系統図とは、電気設備や装置などを含む系統を示した図面です。配線ルートがわかりやすいよう、多くの機器が複合された全体像を図として記載します。単線接続図と同じように、電気工事やプロジェクト全体の概要を押さえるための図面と言えます。施工が難しい場所など、平面図だけでは詳細がわかりにくい場合は、平面図だけでなく断面図を作成するケースもあります。
電気配線図の読み方
電気配線図は、多くの記号や線種が用いられるため、意味を知らないと情報を正しく読み取ることができません。また、電気の流れを理解するために、電気工事における図面のルールも押さえておく必要があります。ここでは、電気配線図の基本的な読み方について解説します。電気配線図を読むうえでの基礎知識
まず、電気の流れを正しく把握する必要があります。電気は、発電機から照明器具やコンセントを通り、元の場所に戻ってきます。電流を発電機から送るときに通る電線と、元の場所に戻ってくる電線は異なり、2本の電線が使われます。電気図面を書く際のルールとして、一般的には電流や信号は「左から右」へ流れるよう記載します。電気配線図を読む際にルールを理解しておけば、どんな複雑な図面でも左から右、上から下へと見ていくだけで、必要な情報を読み取れるでしょう。
電池や電源を示す場合は、電気図面の右側に表記します。そして、電気配線図でもう1つ重要なのが「記号」です。記号について、次から詳しく解説します。
主な記号
電気配線図では、配線と機器、設備などそれぞれの要素に記号が用いられます。多くの電気工事では、スイッチやコンセント、ジョイントボックス、分電盤、空調などの設備機器など多彩な機器が設置されます。また、配線の種類も多岐にわたり、図面に記載すべき情報が多くなるため、複雑化しがちです。そこで、現場の作業者が施工に必要な情報を簡単に読み取るために、専用の記号を用います。企業や案件によって独自の記号を用いるケースもありますが、共通するものも多いため、基本的な記号だけでも覚えておくと便利です。
図面記号の種類は膨大ですが、代表例として「配線」「スイッチ」「コンセント」「照明」「設備機器」などが挙げられます。似たような電線や設備を混同しないよう、視覚的にもわかりやすく工夫されており、以下に主な記号例を示します。
- スイッチ:黒の塗りつぶし円、R(リモコンスイッチ)、P(プルスイッチ)、3(3路スイッチ)など
- 照明器具:円、三角形、四角形、CL(シーリングライト)、DL(ダウンライト)
- コンセント:円の中に縦線2本
- モータ(電動機):M
- 配線:線または破線、T字
- コンデンサ:b
記号や図形とテキストの組み合わせにより、より具体的に電気機器や配線の情報を示すことが可能です。
電気配線図の作成方法
電気配線図の作成方法は、従来までは手書きが主流でしたが、現在はCADなどのソフトを用いるのが一般的になっています。ここでは、手書きとツールを利用した作図方法について、特徴やメリット・デメリットについて解説します。手書きで作成する方法
手書きでの作図は、簡単な表現に向いており、コストがかからない点さが特徴です。直感的で創造力が発揮されやすいとも言われており、スケッチ感覚で使えばアイデアの共有やコミュニケーションの活性化を促します。また、作業内容がわかりにくい場合に、手書きで説明する方が言葉よりも伝わりやすいケースが少なくありません。現場で緊急の問題が発生した際に、手書きで修正図を作成して解決を図る、といった使い方も可能です。
ただし、まっすぐな直線を書く、数値を正しく記載する、といった正確性を重視する場合には不向きです。また、一度作成した後は修正が難しく、保存や管理に手間やコストがかかる点もデメリットです。
紙の図面を万が一紛失してしまった場合、情報漏えいのリスクも高まります。こうした課題を解消するために、昨今は、紙の図面をスキャンして、データ化する手法も用いられています。
ツールを使用して作成する方法
CADなどのツールは、正確性やスピード、柔軟な対応に優れています。直線や円形などの図形、寸法数値も正確に表現でき、スピーディな作図が可能です。また、パソコンだけでなく、タブレットやスマホでも閲覧が可能なソフトなら、現場や移動中に図面を確認できます。リアルタイムで図面データが更新されるため、いつでも最新版を確認できる点も便利です。迅速なデータ共有と、高い保存性・検索性により図面作業の効率化を促します。電気図面に特化したCADソフトなら、各設備や配線の記号も簡単に入力できるため、作業時間の大幅な短縮が見込めます。
ただし、最初にCADの作図操作を覚える時間が必要になるため、社内研修やオンライン講座などで利用者をサポートする必要があります。加えて、JWCADのように無料のCADソフトもありますが、電気工事専用のソフトなど特殊な機能を利用したい場合、有料ソフトの方が望ましく、導入コストが発生する点も見逃せません。
plusCAD電気αなら電気配線図をラクラク作成、同時に見積もり作成も可能!
電気配線図は、現場での作業内容を正確に示すだけでなく、法的な要件や安全基準の遵守、プロジェクト全体の把握などさまざまな役割を果たします。また、施工後の保守やメンテナンスにも欠かせない図面です。さまざまな図面に細分化されますが、一般的には図や記号を用いるため、よく使われる記号だけでも覚えておくことを推奨します。また、電気配線図の作成にはCADなどのツールを活用し、データ化する方が情報共有や保存性、セキュリティ面でも有利です。
電気工事に特化したCADソフト「plusCAD電気α」は、マウス操作だけで簡単に図面を作成できます。電気シンボルをデフォルトとして多数収録しており、作業の効率化が可能です。また、図面の作成と連動して見積書も自動で作成できるため、事務作業の負担軽減にもつながります。この機会にぜひ導入をご検討ください。
plusCAD電気α
電気配線図についてよくある質問
電気配線図の主な種類は?
電気配線図を細分化すると、以下のような図面に分類されます。- 単線接続図
- 複線接続図
- 展開接続図
- 裏面接続図
- 電気設備図
- 系統図
単線接続図や系統図は、電気接続や設備の相互関係、現場全体の概要を押さえるために便利な図面です。複線接続図は、実際の配線通りに記述されており、工事作業でも用いられます。
展開接続図は、機器や部品の動作順序の把握に、裏面接続図は、機器の内部を理解するために役立ちます。電気設備図は、区画ごとにさらに細かく分けられます。上記の図面を使い分けることが、電気工事の現場では求められます。
電気設備図(屋内配線図)にはどのような図面がある?
電気設備とは、屋内に設置される電気設備を具体的に記すための図面とです。電気設備図は、以下のような図面に分けられます。【電源供給図面】
- 電力引込設備図
- 受変電設備図
- 自家発電設備図
- 蓄電池設備図
- UPS設備図
- 幹線設備図 など
【負荷設備図面】
- 電灯設備図
- 温泉設備図
- 動力設備図
- 舞台照明・音響設備図 など
【通信・情報図面】
- 電話設備図
- 構内交換設備図
- インターホン設備図
- 拡声設備図
- ページング設備図
- テレビ共同受信設備図 など
用途やシーンごとに図面を作成すれば、施工内容を1つの図面にわかりやすくまとめることが可能です。
電気配線図と概要図の違いは?
電気配線図は、「概略図」と比較されることがあります。配線図は、電気の接続における設備の配置や配線経路を表した図面です。 さまざまな記号を用いて、電気回路全体の情報を正確に示します。ピクトリアルと呼ばれる写真で構成される特殊な図面も、配線図の1種と言えます。概略図とは、名称の通りイメージで電気の流れを表現する図面です。配線や電気機器などの概要のみを表し、電気回路を構成するすべての要素と接続関係を理解しやすいようまとめています。
配線図が、電気接続の物理的な構成要素を示すものであるのに対し、概略図は電気回路の形や機能を図にしたものです。また、配線図は主に電気回路図の設計などに用いられ、概略図は、電気システムのメンテナンスや修理にも採用されます。
電気工事の施工図と設計図はどう違う?
電気配線図の中には、施工で使われる施工図としての役割を持つものもあります。電気工事の施工図とは、工事スケジュールや施工方法を示した図面のことです。実際の現場では、施工図に基づいて作業を進めます。一方、設計図は、電気接続や配線情報を記号で表した図面で、設備の要件や配線について書かれています。ただし、具体的な施工方法は記載されないケースがほとんどです。
電気配線図を作成する主なメリットは?
電気配線図は、プロジェクト全体における電気接続を把握するために不可欠な図面です。電気配線図にミスがあれば、配線をしても設備機器は動作しない可能性があります。また、工事の途中でショートなどのトラブルが発生するリスクもあるため、正確な電気配線図が必要です。加えて、法的要件の遵守や関係者との適切なコミュニケーションにおいても、電気配線図の内容が重要になります。さらに、保守や検査の際にも使われるため、適切に保存する必要があります。