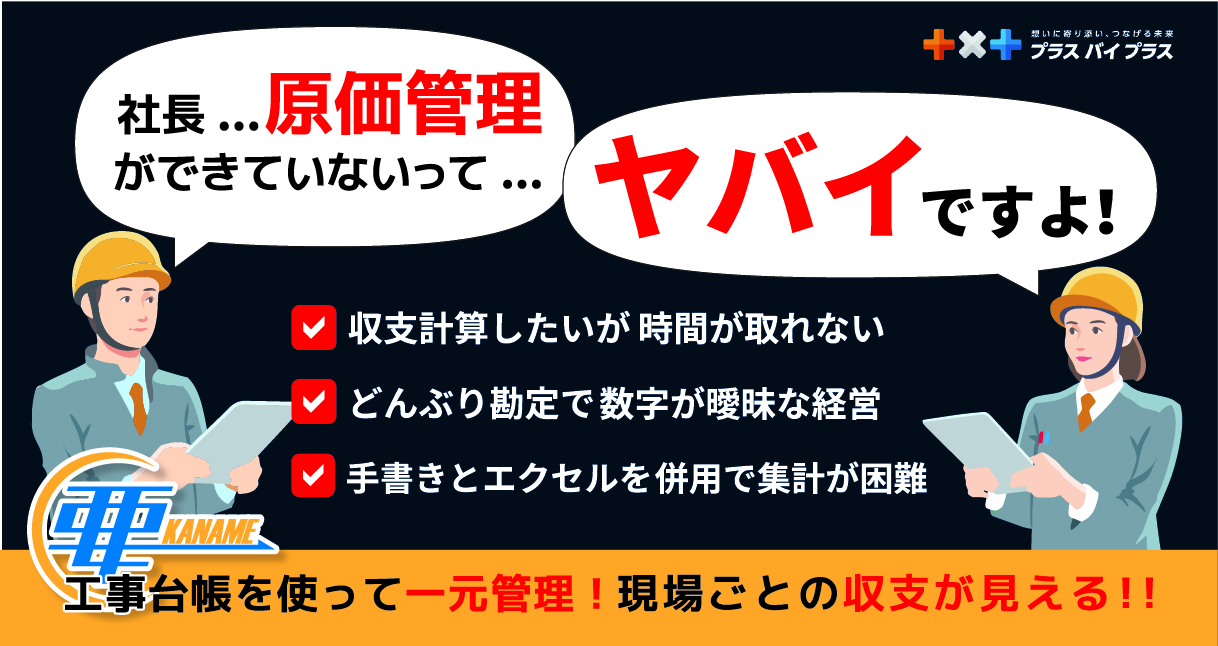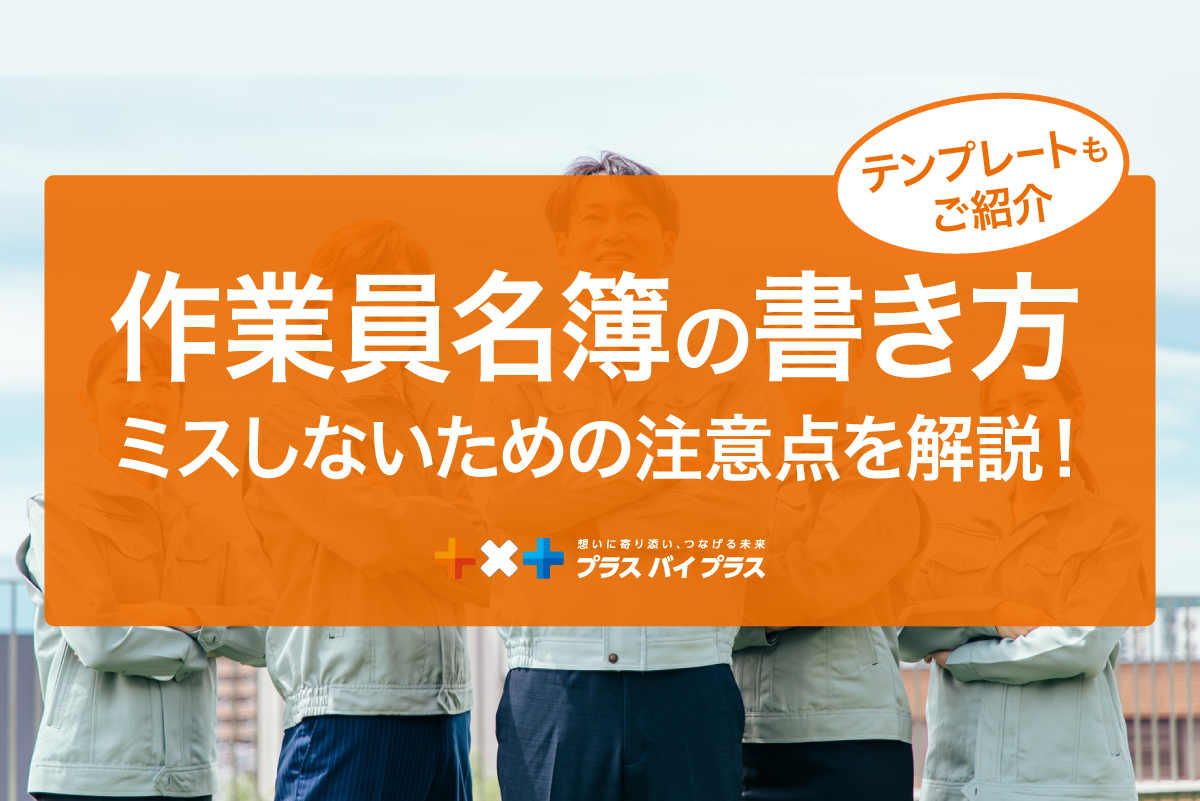- 2025年11月07日
建設業の人材不足を解決する5つのアプローチとは?生産性向上・業務効率化のポイントを解説
建設業に関する知識

労働人口の減少が叫ばれる昨今、多くの業界でIT化や省人化、採用手段の見直しが進められていますが、社会のインフラを支える建設業界では、特に人手不足への対策が急務となっています。
この記事では、建設業界が直面する人材不足の現状とその原因を解説したうえで、解決策として不可欠な業務効率化および利益管理の中心となる原価管理ツールを紹介します。
コンテンツ
建設業における人材不足の現状
建設業界では、複数の構造的な問題が絡み合い、深刻な人員不足という課題に直面しています。高齢化と若手の定着率低下
建設業における高齢化は他業界に比べて特に顕著であり、人手不足の大きな要因の一つです。国土交通省の調査結果でも、建設業の就業者のうち55歳以上が全体の約3分の1に達しています。
一方、29歳以下の若年層の割合は低く、高齢化の進行が明確に示されています。
高齢化が進む背景には、建設現場の危険性や体力を使う作業、長時間労働といったネガティブな印象が若者にあるため、新しい人材の雇用が進んでいないことが挙げられます。
また、新規高卒者の建設業における離職率は高く、人材の定着も大きな課題です。
現場の属人化と技能継承問題
人手不足が加速するなかで、熟練技能者が持つノウハウや技術が個人に依存する「属人化」が技能継承の課題を深刻化させています。建設業界には「技術は現場で学べ」という伝統的な考え方があり、明確な教育プログラムを持たない企業も多いです。
このままでは、属人化されたノウハウを次世代に体系的に伝えることが困難になるでしょう。
この問題に対処するためには、OFF-JT(職場外研修)などの実践的な手法教育の推進に加え、知識や経験値をデータ化し、誰もがアクセスできるように視える化する仕組みづくりが重要です。
また、技能者のキャリアや就業履歴を登録・蓄積し視える化する取り組みも、この継承問題を解決する手段の一つです。
長時間労働と低利益構造
建設業界では、他の産業に比べて長時間労働が常態化しています。長時間労働には、高齢化と建設需要の拡大に対して人材供給が追いついていないことが背景にあり、労働者の疲労蓄積や健康面、モチベーションの低下を招きます。
さらに、日給制の企業が多い建設業では、天候や欠勤によって給与が変動するため、給与が不安定になりやすいという問題も。
労働環境の改善と人材確保のためには、労働基準法改正への対応だけでなく、給料水準を上げるために受注単価や利益管理を見直すことが必要になるでしょう。
人材不足が引き起こす業務課題
人材不足は、単なる人手不足にとどまらず、現場の運営や企業の成長性全体に悪影響を及ぼします。工期遅延や品質低下
人材が不足し、残された社員の負担が増加すると、現場での業務の進行が滞り、工期遅延や品質低下のリスクが高まります。短い工期設定は労働者に過酷な勤務を強いるため、離職率を高める要因に。
適切な工期設定ができていない状況では、慢性的な疲労から作業ミスが発生しやすくなり、結果として品質の低下を招きます。
また、情報共有が非効率であることも工期遅延の原因です。
例えば、紙の書類管理や承認作業が残っていると、情報の流れが滞り、迅速な意思決定ができなくなります。
この課題を解決するためには、ICTツールを用いた効率的な情報共有と進捗管理が不可欠です。
社員の負担増加
人手不足が続くと、既存の社員一人あたりが担う業務量と責任が増大し、負担が増加します。特に、専門的な知識や技術を必要とする作業では有資格者への負担が集中しやすく、これがさらなる疲労やモチベーション低下、ひいては離職につながる悪循環を生み出すのです。
人材確保が難しい場合、企業は現場移動時間の削減や工期等のデータの視える化といった方法により、人的工数を減らすための効率化を最優先する必要があります。
また、複数の作業に対応できる多能工の育成も、特定の社員への負担集中を防ぐ手段となります。
採用コストの上昇
人材不足の深刻化に伴い、企業は優秀な人材を確保するために、多大な採用コストを費やさざるを得なくなっています。若年層へのアプローチとしてSNSの活用は欠かせませんが、採用活動の強化はコスト増につながります。
さらに、仮に採用に成功したとしても、長時間労働、少ない休日、低賃金といった課題が解決されなければ、すぐに退職・転職されてしまい、抜本的な改善には至りません。
外国人労働者の確保は解決策の一つですが、円安の影響で日本の賃金メリットが薄れており、外国人材の採用も難易度が上がっています。
建設業の人材不足を補う5つの解決策
変わりゆく建設業界の環境を意識しながら、人手不足に対応していくためには、以下の5つの解決策が有効です。業務のデジタル化・自動化
ICTやAIの活用による業務効率化は、職人不足の解消に期待される対策の一つです。ロボットやAIによる作業の自動化は、少ない人手で高品質な仕事を可能にします。
具体的には、クラウドを利用することで図面や工程画像を容易に管理し、場所や時間を問わず情報を共有できるため、進捗管理がスムーズになります。
AI技術は、構造設計の単純作業や施工現場の画像認識などに応用され、作業品質の向上と時間の短縮に有効です。
また、見積り作成や勤怠管理などの基幹業務にシステムを導入したりすることで、貴重な人的工数を削減できます。
多能工育成とキャリア支援
人手不足解消のため、複数の専門的な工事作業をこなせる多能工の育成が注目されています。多能工は幅広いスキルを持つため、現場での生産性向上に大きく貢献するのです。
多くの建設企業が多能工訓練施設を設置し、従業員の技能習得を支援しています。
また、人材の定着と育成を促進するため、キャリア支援の充実も不可欠です。
技能者のレベルに合わせた適切な給与水準への見直しや昇給制度の明確化が求められます。
協力会社との連携強化
インボイス制度により「適格請求書発行事業者」から仕入れないと「仕入税額控除」が使えなくなったため、取引の多くが1000万円以下である建設業界では、発注元企業の税負担が大きく変わりました。「適格請求書発行事業者」に登録しない一人親方は、仕入先として選んでもらえないリスクを負うことになったのです。
円滑な業務遂行のためには、協力会社との連携をこれまで以上に強化し、インボイス制度への対応状況を含めた取引の明確化が必要です。
また、工事情報共有システムを活用し、図面や工程表、写真などのデータを効率よく共有することで、協力会社との連携をスムーズにし、現場運営の効率化を図ることができます。
リモート現場管理
現場への移動時間削減は、人的工数を減らすための重要な効率化策の一つです。遠隔臨場の活用は、ウェアラブルカメラなどを用いて現場に足を運ばずに遠隔で確認作業を行う技術であり、移動時間や労働時間の短縮という大きなメリットがあります。
遠隔臨場は、建設業界における新しい働き方のスタンダードとして注目されています。
さらに、現場間の工期や進捗状況をデータで視える化し、効率化を測ることも、リモート管理の有効な手段です。
打ち合わせをオンライン化することも、費用を抑えつつ移動時間を削減し、録画による記録・見直しを可能にするなど、業務効率化に役立ちます。
働き方改革による離職防止
人材の採用・確保だけでなく、退職を防ぐためには、労働環境の抜本的な改善が不可欠です。労働時間の上限規制適用は、長時間労働の是正に大きく寄与します。
長時間労働を防ぐためには、適切な工期設定が重要であり、工期に関する基準を作成し、かかる日数を細分化して見積りることが求められるようになりました。
また、休日確保も急務であり、国土交通省は国が直接管轄する工事等において週休2日制を原則としています。
処遇改善の面では、日給制から固定月給制への移行は、職人に安心感を与え、定年まで勤めたいという意欲を高める可能性があります。
DX・RPAによる業務効率化の可能性
生産性の向上は、労働人口の減少という課題への最も重要な解決策であり、DXやRPAの推進が鍵となります。定型業務の自動化で人手を省力化
人手不足を解決するためには、新工法の採用やロボットの導入により、人的工数を削減する省人化が重要です。人の手を使う必要がない定型業務は、機械やツールに任せることで人手を省力化できます。
RPAツールは、繰り返し発生する事務作業の自動化に有効であり、また、給与計算ソフト、勤怠管理システム、見積管理システムなどの基幹システムを導入することで、バックオフィス業務の効率化が図れます。
現場においても、大手ゼネコン各社が現場巡視ロボットや自動清掃ロボット、自動運搬ロボットの導入を進めており、将来的な省力化が期待されています。
AI・データ活用による生産性向上
AI技術やデータの活用は、建設業界の生産性を大きく向上させる可能性を秘めています。AIを導入することで、ルーチンワークの自動化やヒューマンエラー対策が可能になり、設計や画像認識の分野での活用も広がっています。
国土交通省も、AIなどのテクノロジーの積極的な導入と活用を推奨しています。
現場の効率化を図るためには、現場間の工期などをデータで視える化して効率化を計ることも重要です。
さらに、日報や報告書、スケジュール、工程進捗などの情報を一元管理し視える化することで、社内業務のプロセス自体を改善することができます。
属人化を防ぐ仕組みづくり
ノウハウの属人化を防ぎ、効率的かつ均質な業務遂行を実現するためには、情報共有と知識の体系化が求められます。ナレッジ共有アプリの活用は、経験やノウハウを一元管理し、若手を含めた誰でもアクセスできる状態を作るうえで有効です。
また、クラウドを利用した工事情報共有システムは、図面や工程画像を共有し、特定の個人に依存しない進捗管理を可能にします。
さらに、技能者のキャリアや就業履歴を登録しデータとして蓄積することは、経験値を客観的な記録として残し、属人化を防ぎつつ、体系的な技術継承を支える仕組みとなります。
人材育成を支える情報共有・視える化
技術継承と人材育成は、高齢化が進む建設業界の未来にとって最も重要な課題です。これを実現するには、情報の共有と「視える化」による教育の高度化が欠かせません。
ナレッジ共有アプリの活用
技術継承の課題を克服し、効率的に若手を育成するには、ナレッジ共有アプリの活用が有効です。これにより、熟練職人の持つ知識や現場のノウハウをデジタルデータとして蓄積し、必要に応じて従業員全体で共有することが可能になります。
また、工事情報共有システムを導入すれば、図面や工程表、写真などの膨大なデータを効率よく共有でき、経験が浅い職人でも、現場の全体像や過去の事例を容易に把握し、学習を進めることができます。
現場データを活かした教育
現場から得られるデータを活用することは、経験や勘だけでなく、具体的な事実に基づいた効率的な教育を可能にします。たとえば、現場間の工期や進捗をデータで視える化し、非効率な部分を特定することで、改善点を教育プログラムに組み込むことができます。
また、ドローンやICT端末から得られた高精度のデータは、現場の状況を詳細に分析するのに役立ち、より実践的で効果的な教育を支えます。
経験値をデータ化して継承
技能者の経験値をデータ化し、キャリアを視える化することは、処遇改善だけでなく、技術継承を確実にする手段となります。CCUS(建設キャリアアップシステム)は、技能者の資格や就業履歴を登録・蓄積し、キャリアを可視化します。
これにより、熟練技能者の知識やスキル習得の過程が客観的な記録として残り、引退後もその経験を次世代の職人育成に役立てることができます。
データに基づいたレベル設定は、若手職人にとって明確な目標となり、モチベーション向上と体系的な成長を促進します。
「要 〜KANAME〜」による業務効率化で人材不足を補おう!
建設業界が直面する法改正や環境の大きな変化、そして深刻な人材不足に対応するためには、業務効率化と利益管理の徹底が欠かせません。しかし、現場ごとに異なるエクセルや紙ベースでの管理では、集計や確認作業に時間がかかり、担当者の負担が増える一方です。
建設業向け原価管理システム 「要 〜KANAME〜」 は、見積り・受注・発注・原価管理といった情報をクラウドで一元化。
これまで手作業で行っていた集計や利益計算を自動化し、現場・経理・経営の連携をスムーズにします。
これにより、
- 担当者一人あたりの作業時間を大幅に短縮
- 属人化していた原価管理を標準化
- 利益の“見える化”によって経営判断を迅速化
限られた人員でも正確な利益管理とスピーディーな業務運営を実現することで、
人材不足を「仕組み」で補う体制づくりが可能になります。
<3分でわかる!原価管理システム「要 〜KANAME〜」を動画で見る>
建設業の人材不足についてよくある質問
Q1. 建設業で「2024年問題」が引き起こす影響とは何ですか?
A. 建設業における「2024年問題」とは、2024年4月から適用され、時間外労働の上限規制によって生じた労働力不足問題のことです。この規制により、時間外労働の上限は原則「月45時間・年間360時間」に制限され、最低でも毎週1日の休日確保が原則となりました。
建設業は他産業に比べて年間実労働時間が長く、長時間労働が常態化しているため、この規制によって従来の労働環境を変化させる必要に迫られます。
Q2. 建設業における人材不足対策に、外国人労働者の雇用はどのように貢献していますか?
A. 外国人労働者の雇用は、現状の建設就労者数を支える重要な要素となっており、建設業界の外国人就労者数は急ピッチで増加しています。特に「特定技能」制度は、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを可能にしました。
Q3. 技能実習制度と特定技能制度の違いは何ですか?
A. 技能実習制度は、母国で学ぶことができない技能を日本で習得し、母国の経済発展に生かしてもらう技能移転を目的とした人材育成制度です。一方、特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。
Q4. 建設業の職人不足対策にもなる「省工数化工法」とは、具体的にどのようなものですか?
A. 「省工数化工法」とは、人件費の削減と作業効率の向上を目指し、人手不足が深刻な建設業界で注目されている工法です。主な事例には、現場での型枠解体作業を省き工期短縮を可能にするプレキャストコンクリート工法、工場で鉄筋部材を組み立ててから現場へ搬入し組み立ての手間を大幅に削減する鉄筋ジャバラユニット工法、そして足場の組み立て・解体にかかる時間とコストを大幅削減できる移動式吊り足場があります。
これらの工法は、建設現場での作業効率を向上させ、人手不足の解消やコスト削減につながります。
Q5. 建設業における給与水準の現状と処遇改善のポイントは何ですか?
A. 建設業は、製造業などの他業種が50〜54歳まで給与が上がり続けるのに対し、45〜49歳で賃金のピークを迎える傾向があります。また、日給制を採用している企業が多く、天候不順や欠勤によって給与が不安定になるという課題を抱えています。
若手職人の処遇改善は急務であり、給与面では、日給制から固定月給制への移行が推奨されています。
固定月給制は、職人たちがより安心して働ける環境を提供し、定年まで勤めたいと希望する職人を増やす可能性もあります。
さらに、福利厚生の拡充(週休二日制の導入や各種社会保険の整備)や、技能者のレベルに合わせた適切な昇給制度の見直しも必要です。
社会保険の加入は、企業に経費負担が発生しますが、労働者の処遇改善のためには徹底すべき取り組みとされています。