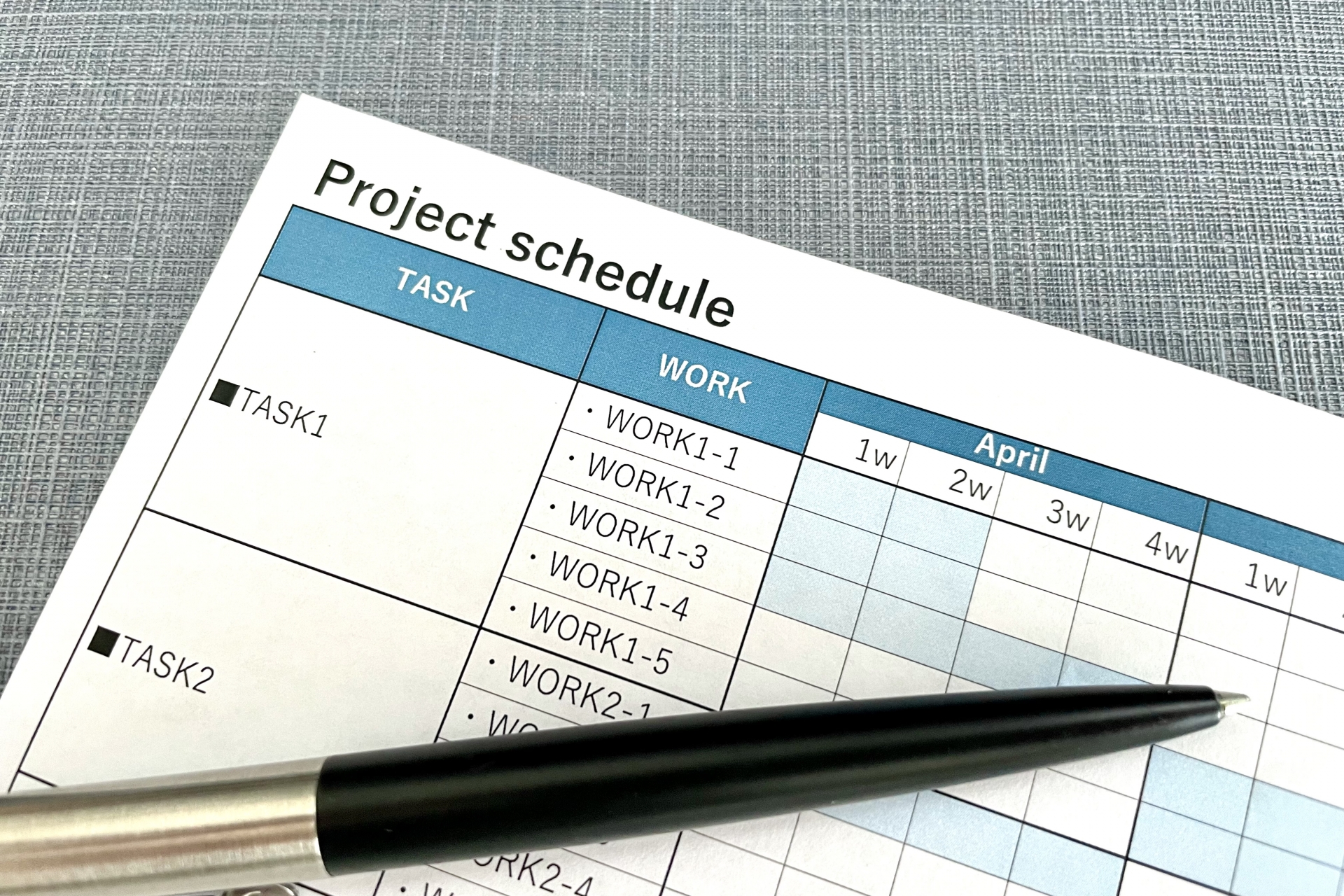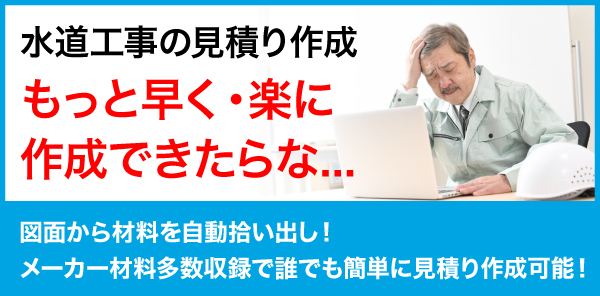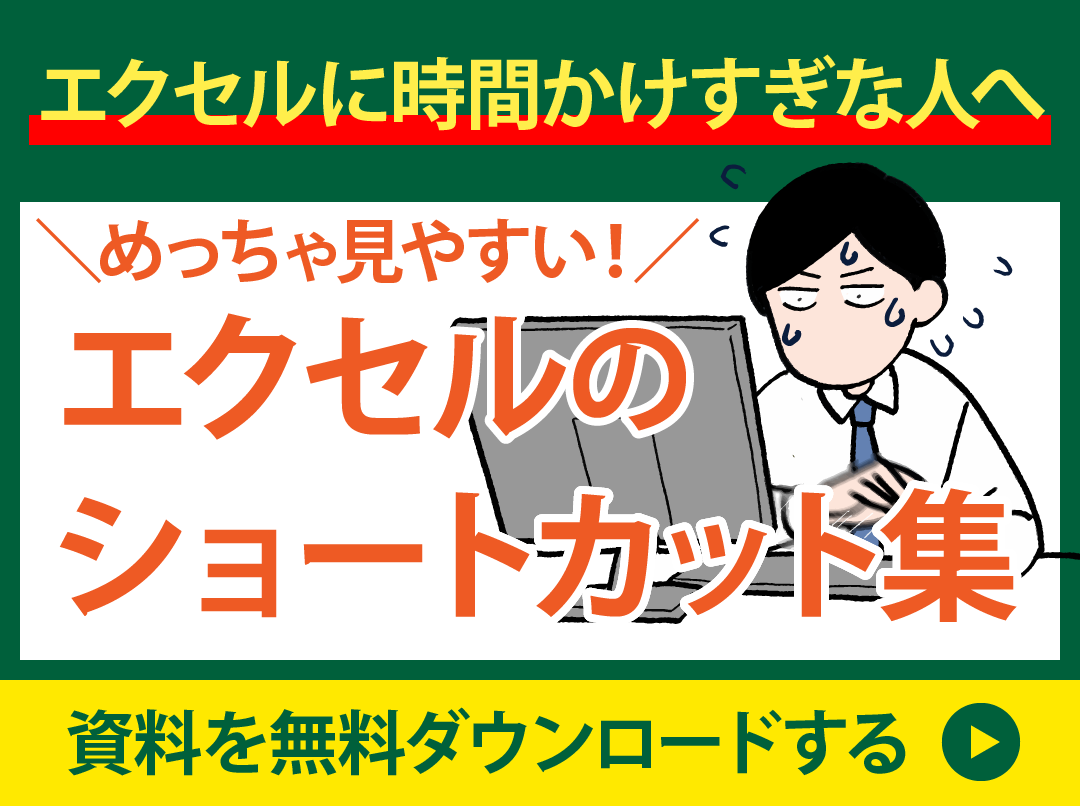- 2025年11月20日
【初心者向け】積算とは?仕事内容や見積りとの違い、失敗しないためのポイントを解説
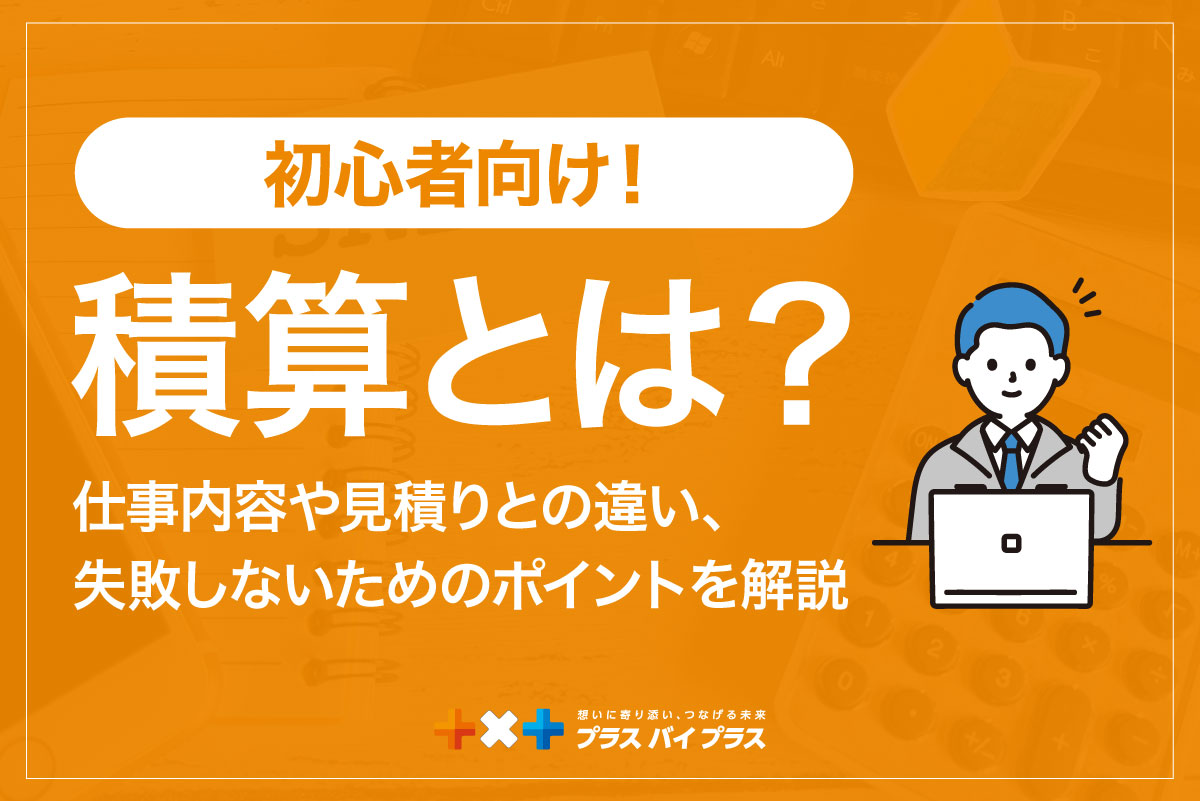
積算とは、初心者にもわかりやすく言うと、建設工事に必要な費用を細かく算出する専門的な業務です。設計図や仕様書をもとに、必要となる材料の数量や人件費、機械費などを積み重ねて計算し、工事全体のコストを正確に把握します。
積算は工事ごとに条件や施工環境が異なるため、仕事内容も案件ごとに多様で柔軟な判断が求められます。積算と見積は混同しがちですが、積算が純粋な工事原価の算出を指すのに対し、見積は積算したコストに利益や経費などを加えて提示する金額を指します。積算の精度が高いほど見積の妥当性が高まり、受注や施工における信頼性の向上や、収益確保にも直結します。
失敗しない積算のコツとしては、仕様書や図面をしっかりと読み込み、数量の根拠を明確にし、見落としや計算ミスを防ぐ丁寧な作業が欠かせません。
積算の仕事は、現場の円滑な進行や企業の利益確保の要となる重要な職務であり、着実なスキルアップも期待できます。
コンテンツ
積算の基礎知識
積算とは、工事に必要な材料費や人件費などのコストを事前にまとめて計算する作業です。あらかじめ費用を整理しておくことで、工事の無駄を減らし、スムーズな準備やお金の管理がしやすくなります。
これから積算を学ぶ方にとって大切なのは、現場によって条件や工事の内容が違うため、その都度やり方を見直す必要があるということです。
積算では、材料費だけでなく、人件費や経費などさまざまな費用を計算します。作業にかかる時間や手間を「歩掛(ぶがかり)」という基準で見積もることもあり、専門的な視点が求められます。
積算の基本をしっかり学んでおけば、工事費の全体像がつかめ、無駄な出費や赤字を防ぎやすくなります。また、正確な積算ができることで、発注者からの信頼も得られ、会社の信頼や競争力のアップにもつながります。
関連記事:
積算とは?意味や費用の考え方、業務全体の流れをわかりやすく解説【建設業ガイド】
積算とは何か
積算とは、建築や土木工事を行う前に、かかる費用をできるだけ正確に計算する作業のことです。材料費や人件費を足し算するだけではなく、設計図や仕様書をもとに、「何がどれだけ必要か」「どれくらい時間がかかるか」を読み取り、それを金額に直していくのが特徴です。
積算の目的は、工事の総費用を明確にして、発注者に適正な価格を示すこと。そして、工事を請け負う側としても、しっかり利益が出るように資金計画を立てることにあります。
たとえば建築工事の積算では、材料費や人件費だけでなく、足場の設置などの仮設費や現場の管理にかかる費用など、すべてを含めて計算します。
積算を正確に行うことで、赤字のリスクを減らし、安定した経営につなげることができます。だからこそ、積算は建設業にとってとても大切な業務です。
積算の意味と必要性
積算は、工事やプロジェクトにかかる費用を細かく計算する作業です。単なる「見積り」とは違い、「なぜその金額になるのか」を根拠を持って説明できるのが積算の特徴です。
材料費、人件費、機械を使う費用など、すべての費用を一つずつ整理し、合計金額を出していくのが積算のやり方です。わかりやすく言えば、「どの作業にいくらかかるか」を細かく書き出していく作業です。
積算が重要とされる理由は、費用の見通しが立てば、無理な価格で受注したり赤字になるリスクを減らせるからです。積算がしっかりできていれば、会社にとっても、ムリなく利益を確保できる大きな武器になります。
また、発注者側も、積算を通じて正確な予算がつかめるため、安心して発注ができるというメリットがあります。逆に積算が曖昧だと、途中で予算オーバーになったり、トラブルの原因にもなりかねません。
このように、積算の意味と必要性をきちんと理解し、目的を意識して取り組むことが、工事や経営の成功につながっていきます。
見積りや施工管理との違い
積算は、設計図や仕様書をもとに、工事にかかる費用を細かく計算して総額を出す作業です。これに対して「見積り」は、積算で出した原価に会社の利益や経費を加えて、発注者に提示する金額(売値)を決める工程になります。見積りは、受注を取るための価格調整も含まれるのが特徴です。
一方で施工管理は、実際の工事現場で工程の進み具合や品質、安全面をチェックしながら、工事をスムーズに進めるための仕事です。
このように、積算・見積り・施工管理はそれぞれ役割が違います。
積算:設計段階での費用計算
見積り:受注のための価格設定
施工管理:現場での工事管理・品質や安全の確保
それぞれの役割をしっかり理解することで、工事全体の流れを把握しやすくなります。
積算と見積りの違い
積算とは、工事に必要な材料費や人件費などの原価を一つひとつ積み上げて計算する作業です。ここには、仮設費や現場管理費などの間接費も含まれます。
この積算で出た原価に、会社の利益や間接的な経費(事務所運営費など)を加えたものが「見積り」です。つまり、見積りは発注者に提示する最終的な工事価格になります。
簡単に言えば、
積算=工事に本当にかかるコスト(仕入れ原価)
見積り=お客様に出す販売価格(利益込み)
正確な積算ができていれば、無理のない見積りが作れ、赤字工事を避けることができます。
積算と施工管理の違い
積算は、工事が始まる前に、設計図や仕様書をもとに工事全体の費用を計算する仕事です。材料費や人件費などのコストを見積もるのが中心です。
それに対して施工管理は、工事が始まってから現場で行う業務です。具体的には、工程の進み具合や作業の品質、安全管理などを現場で見守りながら、計画通りに工事を進める役割を担います。
つまり、
積算=工事前の計画・費用の計算
施工管理=工事中の現場運営・品質・安全の管理
どちらも工事の成功に欠かせない重要な仕事ですが、関わるタイミングや内容が大きく異なります。
積算と算出の違い
「積算」と「算出」は似ている言葉ですが、意味は少し違います。
積算は、建設工事に必要な費用をすべて積み上げて計算する専門的な作業です。材料費、労務費、機械費など、項目ごとに細かく費用を出し、それを合計して全体の金額を出します。ここには専門的な知識と経験が必要です。
一方、「算出」はもっと広い意味を持ちます。たとえば、数量、作業時間、材料の必要量など、数字やデータを使って結果を出すこと全般を指します。
つまり、
積算=費用を出すための専門的な「算出方法」
算出=幅広く数字を計算して結果を出す行為
積算は「算出」の一部ですが、より高度で専門的な内容を含んでいます。
積算業務の基本的な流れ
積算を行うときは、いきなり数字を出すのではなく、計画的に手順を踏んで進めることが大切です。
まずは、設計図や仕様書をよく見て、工事の内容を正確に把握します。次に、使う材料や必要な作業員の一覧を作り、チェックリストとして確認します。これにより、抜けや漏れを防げます。
その後、材料費・人件費などを一つずつ金額にして積み上げていきます。この積み上げによって、工事費全体がどのように構成されているかが見えてきます。
最後に、出した費用の内訳を「内訳明細書」や「積算書」としてまとめ、関係者に共有・承認してもらうのが一般的な流れです。
こうした流れをきちんと守ることで、無駄がなく、正確な積算ができるようになります。
STEP1:図面・仕様書を読み取り、工事内容を把握する
積算の最初の作業は、設計図や仕様書を読み解くことです。
たとえば住宅のリフォーム工事なら、どの部屋をどう改修するのか、使用する建材や施工範囲はどこまでかを図面と書類から確認します。
電気や水道工事なら、どの場所に機器や配線が設置されるのか、平面図や展開図をもとに詳細を読み取ります。
この段階で工事の全体像を把握しておくと、後の材料拾い出しや費用計算がスムーズに進みます。逆に読み違いがあると、積算のズレにつながるため、経験が浅い場合は図面担当や設計士と一緒に確認するのも効果的です。
STEP2:必要な材料・作業員をリストアップする
工事内容が把握できたら、必要な資材や職種を具体的に洗い出します。
たとえば「エアコンの取替工事」であれば、エアコン本体・配管部材・電線・ドレンホースなどの部材をリストアップし、同時に電工1名で何時間作業が必要かも検討します。
この工程では、漏れが積算ミスの原因になるため、「資材拾い出し表」や「施工内容ごとのチェックリスト」を作っておくと安心です。
過去の現場写真や実績表も参照しながら「この作業では他に何が必要だったか?」と振り返ることで、実務に即した積算がしやすくなります。
STEP3:材料費・労務費などを積み上げて計算する
リストアップした内容をもとに、実際の単価を調べながら費用を計算していきます。
たとえば、電線100m、エアコン本体1台、冷媒管20mなど、それぞれの数量に対して仕入れ単価を掛けて材料費を出します。
労務費も、「作業員1人×4時間」のように人工(にんく)単位で積算します。
工事の内容によっては、足場や車両の手配費用、残材処分費なども加える必要があります。
この段階では、「何にいくらかかるか」が見えるように、項目別に内訳を整理しておくと、見積作成や社内説明もスムーズになります。
STEP4:歩掛(ぶがかり)を使って労務費を算出する
歩掛とは、「ある作業にどれだけの人と時間がかかるか」を数値で示したものです。
たとえば「配管20m=0.5人工」や「コンセント取付10箇所=1人工」など、作業量に対する標準的な時間をもとに人件費を算出できます。
歩掛の数字は、公共工事の基準(国交省の資料など)をもとにする場合もありますが、自社の過去実績や熟練者の経験値を参考にしても構いません。
ただし、あまりに楽観的な設定にすると、実際の現場で人件費が不足するリスクがあるため、少し余裕を持って見ておくのが現実的です。
STEP5:積算結果を「内訳明細書」としてまとめる
すべての金額を積み上げたら、内訳明細書や積算書として整理します。表形式で「項目/数量/単位/単価/金額」が並ぶようにまとめると、後で見積書に転記しやすくなります。
この資料は、見積価格の根拠にもなるため、「なぜこの金額になったのか」を説明できるようにしておくと、発注者とのやりとりもスムーズです。
Excelや積算ソフトを使って、自社用のテンプレートを持っておくと、次回以降も流用できて業務効率が上がります。
注意点・積算のポイント
チェックリストを必ず使う
過去の現場や標準工事の内容をもとにしたチェックリストがあると、資材や作業の抜け漏れを防げます。
単価は必ず“今の相場”で見積もる
部材や労務費は時期によって変動します。仕入先や専門誌、ネットで最新価格を確認するようにしましょう。
現場の実情を反映させる
「狭い」「搬入が難しい」「近隣対策が必要」など、現場特有の事情も費用に加味するのを忘れずに。
積算の精度が、経営の土台になる
積算が甘いと、いくら工事を頑張っても利益が出ません。粗利の確保には、正確な積算が欠かせません。
積算業務の仕事内容
積算は、工事に必要なすべての費用を事前に計算する仕事です。
図面や仕様書を見て、どんな資材がどれだけ必要か、どのくらいの人数と作業時間がかかるかを把握します。
そのうえで、材料費や人件費(労務費)、機械使用料、その他の経費を一つずつ見積もり、全体の工事費を積み上げていきます。
単に金額を出すだけでなく、「なぜこの金額になるのか?」をきちんと説明できるように、根拠や内訳も明確にしておく必要があります。発注者や社内と信頼関係を築くためにも、この説明力はとても大切です。
積算には、工事に関する知識、数字の正確さ、丁寧なチェックが求められます。金額のミスが利益に直結するため、責任の重い業務でもあります。
積算を行う人の仕事
積算を担当する人は、工事の計画段階で非常に重要な役割を担います。
まず、設計図や仕様書を読み解き、必要な材料の種類や数量、工事にかかる時間を見積もります。
次に、資材の単価や職種ごとの人件費を調べて、費用を具体的に計算します。このとき、管理費や経費などの「間接費」も含めて、総合的な工事費を出すのが積算担当者の役割です。
さらに、積算結果を見積書や明細書にまとめ、社内や発注者にわかりやすく説明することも仕事の一つです。
積算には、最新の単価情報や施工基準を反映させる必要があるため、常に情報をアップデートしておくことが大切です。施工計画や予算の成否を左右するため、プロジェクト全体に影響を与える責任のある仕事です。
工事に必要な資料と書類作成
積算を始めるには、まず設計図、仕様書、工事計画書などの資料をそろえます。これらの資料をもとに、使う材料の種類と量、工事条件を一つひとつ拾い出していきます(いわゆる「拾い」作業)。
拾った内容は、数量・単価ごとに整理し、材料費や人件費などの見積りに使われます。その結果を「内訳明細書」や「見積書」にまとめるのが、積算業務の大事な流れです。
書類の作成時にはテンプレートやチェックリストを使うことで、漏れやミスを防げます。過去の内訳明細書を参考にすれば、精度の高い資料が作りやすくなります。
正確な書類は、金額の根拠を示す「証拠」にもなります。発注者との信頼関係を築くためにも、ていねいに、わかりやすくまとめることが大切です。
直接工事費や材料費の計算
「直接工事費」とは、現場で直接かかる費用のこと。主に、材料費・人件費・機械経費が含まれます。
たとえば、電線や給排水管のような材料費は、実際に必要な長さや数量を出し、それに最新の仕入れ価格を掛けて計算します。
人件費は、作業にかかる時間と人数を「歩掛(ぶがかり)」を使って計算します。機械経費も、重機の使用時間や台数によって費用を見積もります。
これらに加えて、工事に直接は関わらないけど必要な「共通仮設費」や「管理費」などの間接費も一緒に考えることで、全体の費用バランスが取れるようになります。
金額のミスは赤字につながるため、信頼できる単価データを使い、落ち着いて丁寧に計算することが大切です。
工事の原価管理
原価管理とは、計画した費用(積算)と、実際に使った費用を比較しながら、ムダや赤字を防ぐための管理です。
工事が始まると、思わぬ設計変更や追加作業が発生することがあります。そういった場合でも、どれだけ予算を使ったか、どこにムダがあるかを常に確認しておくことで、必要以上の出費を防ぐことができます。
現場では、急な調整が必要になることもあるため、リアルタイムでお金の動きを追いながら柔軟に対応する力が求められます。
きちんと原価管理ができていれば、赤字リスクを減らし、利益を守りながら工事を完了させることができます。それが結果的に、お客様の満足や会社の信頼につながっていきます。
積算に必要な能力と資格
積算の仕事をきちんとこなすには、建設の専門知識と注意深い作業力が欠かせません。
まず、設計図や仕様書を正確に読み取れる力が必要です。「どの材料を使うか」「どれだけの人手が必要か」などをしっかり把握する力が求められます。
それに加えて、材料や人件費の単価、工事にかかる時間の目安(歩掛:ぶがかり)など、費用に関する知識も必要です。それらをもとにして「実際にいくらかかるか?」を現実的に計算するのが積算の役割です。
また、計算ミスを防ぐための丁寧さ、関係者とやり取りするコミュニケーション力も大切です。資格としては「建築積算士」などを持っていると、専門性の証明になるため、信頼性が高まり仕事の幅も広がります。
積算に必要な知識とスキル
積算では、ただ数字を出すだけではなく、建築の知識や道具の使い方も重要になります。
たとえば、設計図から「床面積」「壁の面積」などを正しく拾えること。さらに、その工事に必要な材料や職人の手間がどれくらいかかるかを見積もれることが必要です。
そのとき使うのが、歩掛(ぶがかり)や単価表といった基準資料です。これらを使いこなして、材料の数量や労務費を正確に出すスキルが求められます。最近では、積算ソフトやExcelも必須ツールになってきており、最低限のパソコン操作ができると仕事がぐっとラクになります。
また、建設に関する税金や法律の知識も持っていると、より現場に合った積算ができます。「現場の条件が急に変わった!」といったときでも、柔軟に考えて対応できる力も必要です。
積算業務に役立つ資格
積算の仕事を深く理解し、信頼される立場になるには、関連資格の取得もおすすめです。
とくに以下の資格は、積算に直接役立ちます:
建設業経理士
工事の費用管理や帳簿のつけ方が学べるので、原価管理と相性抜群です。
施工管理技士(1級・2級)
現場全体を管理する知識があるため、積算の際も「現場で本当に起こること」を考えながら費用を見積もれます。
一級建築士・二級建築士
図面の構造や材料の意味を深く理解できるため、設計意図をくみ取った精度の高い積算が可能になります。
測量士補
図面を正しく読み、面積や距離を正確に把握できるスキルが身につきます。
こうした資格があると、積算だけでなく、設計や現場管理などにも関わるチャンスが増え、キャリアの幅も広がります。
セミナーや通信講座を活用して、無理なくステップアップを目指すこともできます。
建築士の資格が活きる理由
積算の現場でも、「一級建築士」や「二級建築士」の資格は非常に役立ちます。
これらの資格を持っていると、設計図の細かい内容や建物の構造、使われている材料などを深く理解できます。
たとえば「この設計ではどんな工法が使われているか」「その工法にはどんな費用がかかるか」といった判断ができるため、積算の精度がぐっと高まります。
また、建築士資格があると、設計・監理・積算といった幅広い業務に対応できるようになり、将来的には現場の責任者やマネジメントにも関わることができます。
資格は難しいと感じるかもしれませんが、持っていて損はない大きな武器になります。
積算で失敗しないためのポイント
正確な積算のカギは「段取りと確認」
積算で失敗を防ぐには、事前の準備とこまめな確認が何より大切です。
まずは、設計図や仕様書をしっかり読み取り、工事の内容や範囲を正しく理解しましょう。図面の見落としがあると、必要な材料や工程を積算から抜かしてしまい、大きなミスにつながります。
そのため、積算の際はチェックリストを活用して、「材料に漏れはないか」「工程に抜けはないか」などを一つずつ確認するクセをつけるのがポイントです。
また、費用の計算では、最新の材料単価や歩掛(作業の標準時間)を使うことが重要です。単価の古いデータを使うと、工事が始まってから「想定より高かった」と焦ることになりかねません。
積算業務で意識すべきポイント
積算の質を高めるには、まず「正確な数量出し」が基本です。たとえば、壁の面積や配線の長さなどを図面から読み取るときに、うっかり見逃したり、ざっくりで済ませてしまうと、あとで金額に大きなズレが出ます。
材料単価も、仕入れ先や市場相場をこまめに確認して、今の価格で積算することを心がけましょう。とくに銅線・鋼材・合板など、価格が変わりやすい材料は要注意です。
歩掛の設定や間接費(仮設費や管理費など)の計算も、しっかり根拠を持って行う必要があります。「前回と同じでいいだろう」と思っていると、現場条件に合っていなかったというケースも多いです。
また、判断に迷う部分は、一人で抱え込まずに相談するのが鉄則です。設計担当や過去の担当者、仕入れ業者など、頼れる相手がいれば、早めに確認しておきましょう。
ミスを防ぐための流れ
積算業務は、次のような流れで進めるとミスが起きにくくなります。
STEP1:図面と仕様書の読み取り
まずは工事の内容をきちんと理解。施工条件(搬入ルートや作業場所の制限など)にも目を通します。
STEP2:必要資材と人員のリストアップ
施工内容をもとに、必要な材料や作業人数を一覧化します。ここでチェックリストを使うと、漏れを防げます。
STEP3:単価と数量の確認
材料や人件費の単価を最新の情報で確認。数量と掛け合わせて、項目ごとの費用を算出します。
STEP4:積算書の作成とダブルチェック
出した金額を「内訳明細書」や「積算書」にまとめます。そのあと、社内でダブルチェックを行い、数字の誤りや見落としがないか確認します。
このように、「段階を追って」「チェックしながら」進めることが、積算の失敗を防ぐ最大のポイントです。
自分の作業だけで完結させず、「誰かに見てもらう」「チェックリストで見直す」という“ひと手間”が、赤字工事を防ぐ安心材料になります。
手作業からシステム化へ、積算はもっとラクになる
最近では、積算作業の負担を減らすために「積算専用ソフト」を導入する会社が増えています。
これまでのようにExcelや電卓を使って1つひとつ手計算していた方法に比べ、クラウド対応の積算アプリやソフトを使えば、作業がグッと早く、正確にできるようになります。
たとえば、最新の単価データが自動で反映されたり、内訳明細書を自動で作ってくれたりと、ミスが減って確認もラクになります。
また、クラウド型であれば、会社にいなくてもスマホやパソコンからデータを確認できるので、現場との連携もスムーズになります。
無料から使えるソフトもあるので、「まずは試してみたい」という会社にとっても始めやすいのが大きなポイントです。
積算ソフトとExcelの違い
積算ソフトは、建設業向けに特化されたツールで、材料費や人件費などの単価が最初からデータベースとして搭載されています。面倒な計算も、金額や歩掛を入力すれば自動で集計してくれるため、専門的な知識がなくても一定の精度で積算が可能です。
また最近は、Web上で使えるクラウド型のソフトも増えており、現場担当者や事務所のスタッフとリアルタイムで情報を共有できる仕組みが整っています。
・入力ミスを防ぐ「チェック機能」
・作業ごとに分かれた「テンプレート」
・単価の自動更新
といった便利な機能があり、手作業で行っていた頃と比べて業務のスピードと正確さが大幅にアップします。
ただし、すべて手入力のため、計算ミスや数式のズレに気づきにくいというデメリットもあります。
特に、複数案件を同時に扱ったり、過去の見積と比較したりするには時間と手間がかかるため、案件数が増えるとExcelでは非効率になりやすいのが現実です。
最近の積算ソフトには、セミナーや使い方のサポートもついていることが多く、ITが苦手な人でも導入しやすくなっています。
積算ソフトの活用事例:積算ソフトで“残業見積り”からの脱却に成功
積算ソフトの導入で「見積りにかかる時間を減らしたい」という思いから、「plusCAD電気α」を導入したある企業の声をご紹介します。
以前はExcelで見積書を作成しており、小さな案件でも30分、大きな案件では1週間かかることも。にもかかわらず、受注率は3割程度。「数を打つしかない」と、現場から戻ってきた夜に慌てて見積りを作成する日々が続いていたそうです。
最初は他社ソフトを導入していたものの、サポートが不十分で使いこなせず断念。そんなとき、電材屋の紹介で出会ったのがplusCADでした。「ちゃんとサポートする」という営業担当の一言に背中を押され、即日導入を決定。
導入後は、材料拾い・見積り作業の時間が半分以下に短縮。女性社員が拾い出しを行っても、ソフトが一括で集計してくれるため、「作業がラクになった」と高評価。また、PDF図面を読み込んで編集できる機能や、DXF・JWW変換などにも対応しており、「お客様への返答も早くなり、信頼度が上がった実感がある」とのこと。
短縮できた時間は、利益を出すための戦略立案や、自分の時間の確保に活用。「夜中まで見積りをしていた頃と比べると、ストレスも減って前向きに仕事に向き合えるようになった」と喜んでいただけました。
▼▼下記からplusCADシリーズの詳細をご覧いただけます▼▼
<電気設備CAD・見積り連動ソフト「plusCAD電気α」の詳細を見る>
<水道設備CAD・見積り連動ソフト「plusCAD機械α」の詳細を見る>
<給排水工事申請専門CAD「plusCAD水道V」の詳細を見る>
【初心者向け 積算のよくある質問】
Q1. 積算と見積りの違いは何ですか?
積算は工事に必要な材料費・人件費・機械費などの原価を一つずつ積み上げて計算する作業です。見積りは、その積算結果に利益や経費を加えて発注者に提示する最終的な金額です。積算が正確であれば、無理のない見積りが作成でき、赤字工事を防げます。
Q2. 積算で失敗しないためのポイントはありますか?
事前の段取りと確認が重要です。設計図や仕様書を正しく読み取り、材料や工程の漏れがないかチェックリストで確認します。また、最新の材料単価や歩掛を使い、現場条件(搬入経路や作業制限など)も加味することで、見落としや誤差を防げます。
Q3. 積算ソフトを導入するメリットは何ですか?
材料単価の自動更新や内訳明細書の自動作成などにより、作業時間の短縮と精度向上が可能です。クラウド型なら現場と事務所で情報共有もしやすくなり、手作業に比べて計算ミスも減らせます。ITが苦手でも、サポート付きのソフトなら導入しやすいのが特徴です。