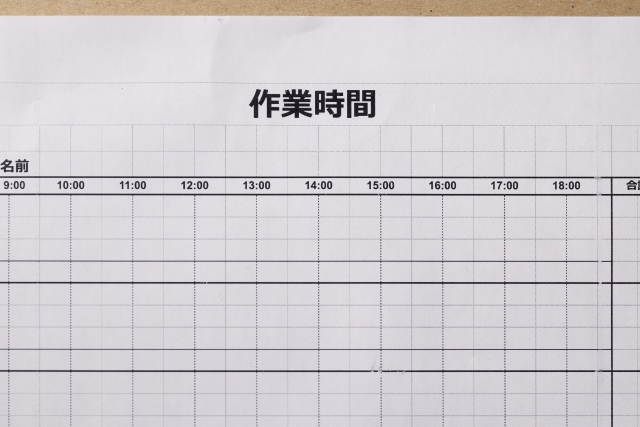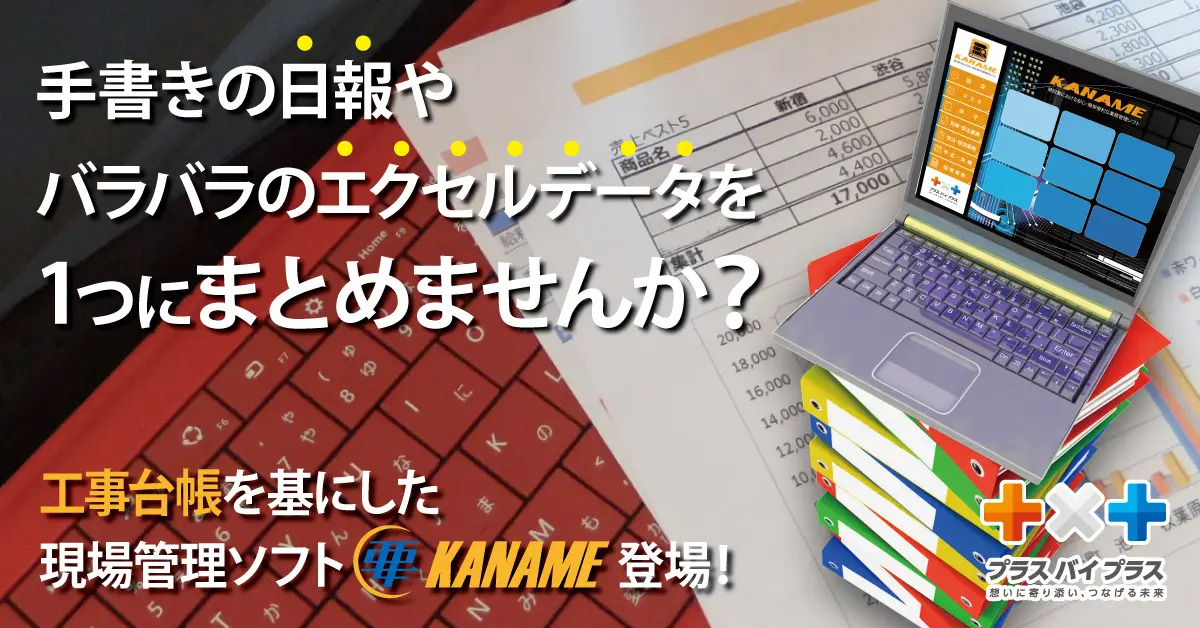- 2025年10月28日
建設業のDXとは?導入のメリットと成功のポイントを徹底解説
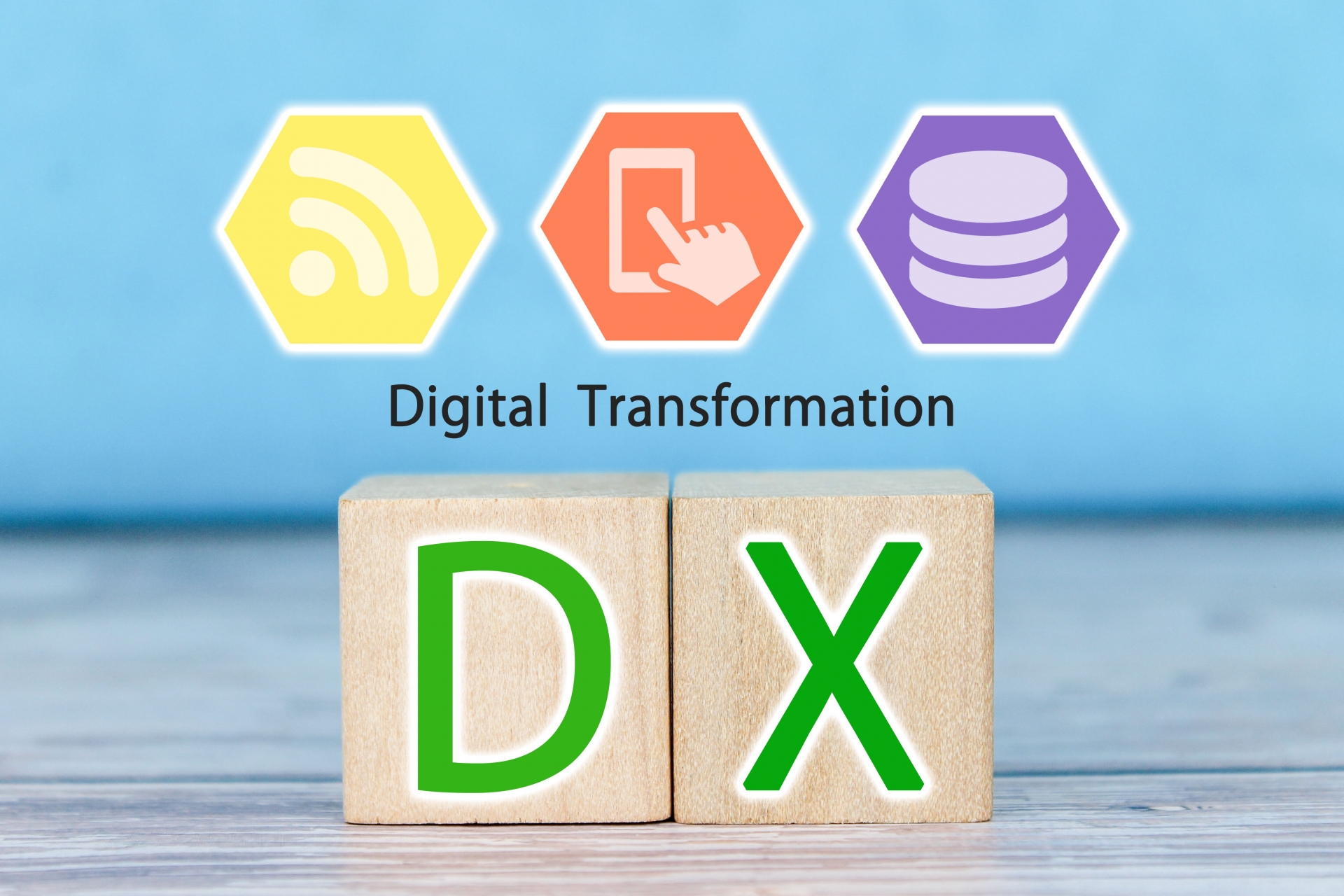
現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は業界を問わず重要な経営課題となっています。特に、伝統的な手法が根強く残る建設業界においても、DXへの取り組みは避けて通れない道であり、企業の持続的成長と競争力強化の鍵を握っています。
建設業におけるDXとは、単にITツールを導入することだけではなく、デジタル技術を活用して業務プロセス、組織文化、ビジネスモデルを変革し、生産性向上や新たな価値創造を目指す包括的な取り組みです。しかし、「何から始めればいいかわからない」「効果が見えない」といった理由で、DXへの一歩を踏み出せない企業も少なくありません。
本記事では、建設業におけるDXの基礎知識から、導入メリット、成功への具体的なステップまでを徹底解説します。
コンテンツ
建設業界におけるDXの現状と課題
まず、建設業界におけるDXの状況と、その推進を阻む課題について理解を深めましょう。DXとは何か、そしてなぜ今この業界で強く求められているのか、その背景を解説します。
建設業のDXとは?定義と背景
建設業におけるDXとは、IoT、AI、クラウド、BIM/CIMといったデジタル技術を活用し、従来の建設業のプロセスや働き方、ビジネスモデル自体を変革する取り組みです。部分的なデジタル化を超え、デジタルを前提とした新しい価値創造や競争優位性の確立を目指す、より戦略的な概念と言えます。
具体例としては、BIM/CIMによる設計情報の3次元統合管理、ドローン測量や建機自動制御による現場の省人化、ウェアラブルデバイスによる安全管理、クラウドを活用した迅速な情報共有などが挙げられます。これらは個々の業務効率化だけでなく、関係者間の連携強化を通じてプロジェクト全体の生産性向上に貢献します。
この動きは、経済産業省が指摘する「2025年の崖」(既存システムの老朽化リスク)への対応、国土交通省が推進する「i-Construction」(ICT技術の全面活用による生産性向上)、そして新型コロナウイルスによるリモートワーク需要の高まりなどを背景に、近年急速に加速しています。建設業のDXは、外部環境の変化と内部課題の解決の両面から、重要な経営戦略として位置づけられているのです。
なぜ今、建設業にDXが求められているのか
建設業でDX推進が急務とされる最大の要因は後述する「人手不足」です。少子高齢化による労働力減少と熟練技術者の引退が進むなか、限られた人員で高い生産性を維持するには、デジタル技術による省人化・効率化が不可欠です。
次に、「働き方改革」への対応も大きな理由です。長時間労働が課題の建設業界にとって、時間外労働の上限規制への対応は必須です。DXによる業務効率化は、労働時間短縮や休日確保を促進し、より良い労働環境整備による人材確保・定着にも繋がります。
また、AI、IoTなどの「技術革新」の進展とともに、他業界でのDX成功事例は、建設業界にも変革への期待とモチベーションをもたらしています。
さらに、品質向上、工期短縮、コスト削減に加え、安全性向上や環境負荷低減といった「社会からの要求水準の高まり」に応えるためにも、DXによる精緻な管理やリスク可視化が求められています。これらの要因から、建設業のDXは単なるトレンドではなく、業界が持続的に発展するための必須条件となっています。
建設業界が抱える代表的な課題
建設業がDXを推進せざるを得ない背景には、業界特有の根深い課題があります。ここでは特に深刻な「人手不足」「業務の属人化」「非効率な管理」という3つの課題について解説します。
人手不足
建設業の人手不足は、他の産業と比較しても際立って深刻です。建設技能労働者数はピーク時から大幅に減少し、特に若年層の入職が低迷しています。一方で就業者の高齢化は進行し、熟練技術者の大量退職による技術・技能継承の危機と労働力供給の減少が目前に迫っています。
この背景には、「3K」イメージによる若年層の敬遠、長時間労働や休日取得の難しさといった労働環境の問題、他産業と比較して必ずしも高くない賃金水準などがあります。
人手不足は、受注機会損失、工期遅延、労務費高騰による利益率低下、安全管理体制の脆弱化といった経営リスクに直結します。この状況を打開し、持続可能な産業構造を維持するためには、生産性の抜本的な向上が急務であり、DXによる省人化・効率化がその鍵を握っています。
業務の属人化
建設業では、熟練技術者の経験や勘が品質を支える一方で、特定の担当者しか業務内容を把握していない「業務の属人化」が進みやすい傾向があります。設計、積算、施工管理、原価管理など、多くの業務で個人の知識やノウハウへの依存が見られます。
属人化は、担当者不在時の業務停滞リスク、技術・ノウハウ継承の阻害による若手育成の遅れ、業務のブラックボックス化による不正やミスの温床化といった問題を引き起こします。貴重な個人の経験や勘も、共有・標準化されなければ組織全体の力にはなりません。
この課題に対し、DXは有効な解決策です。業務プロセスの標準化、情報共有プラットフォームの導入、BIM/CIMによる情報統合などを通じて、知識やノウハウを組織全体で共有・活用できる体制を構築し、業務の継続性確保、技術継承促進、組織全体の生産性向上を目指すことが求められています。
非効率な管理
建設業界では、依然として紙ベースの書類管理やアナログなコミュニケーションが多く、非効率な管理体制が課題となっています。膨大な量の図面、仕様書、報告書などの作成、保管、検索、共有には多大な時間と労力、コストがかかっています。
特に協力会社が多いプロジェクトでは、情報伝達の遅れや齟齬が生じやすく、手戻りや工期遅延、コスト増のリスクを高めます。最新情報が末端まで正確に伝わらない、現場の問題がリアルタイムで共有されないといった問題も頻発します。
原価管理や勤怠管理も、Excelや手作業に依存している場合が多く、データの入力ミスや集計漏れ、リアルタイムでの状況把握の困難さといった課題を抱えています。
このような非効率な管理は、生産性低下だけでなく、従業員の負担増、ミスやコンプライアンス違反のリスクを高めます。DXにより、クラウドツール、施工管理アプリ、原価管理システム、電子契約などを導入し、ペーパーレス化、リアルタイム情報共有、作業自動化を進めることで、管理業務の効率を大幅に向上させることが可能です。
建設業DXの導入メリットとは
建設業界がDXを導入することで、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、業務効率化、原価管理の可視化、情報共有の強化、人材育成への貢献という4つの代表的なメリットを解説します。
業務の効率化と作業時間の短縮
DX導入による最大のメリットは、業務の効率化と作業時間の大幅な短縮です。手作業や紙ベースの業務をデジタル化・自動化することで、従業員の負担を軽減し、生産性を向上させます。
施工管理ソフトを使えば、日報作成、写真管理、工程管理などを現場からスマホやタブレットで完結でき、事務所に戻る手間や事務作業時間を削減できます。クラウドでのリアルタイム情報共有は、関係者間のコミュニケーションを円滑にし、確認作業などの時間を短縮します。
BIM/CIMは、設計段階での干渉チェックやシミュレーションにより、施工の手戻りを削減。3次元モデルによる情報一元管理で、図面整合確認や数量拾いも効率化します。ドローン測量・点検は、従来手法より短時間・少人数での作業を可能にします。
原価管理ソフトや勤怠管理ツールは、データ入力・集計作業を自動化し、事務負担を軽減します。これらの効率化はコスト削減だけでなく、長時間労働の是正やワークライフバランス向上にも貢献し、創出された時間をより付加価値の高い業務に充てることで、企業の競争力強化に繋がります。
原価管理・利益管理の可視化
正確な原価管理と利益管理は、建設業のプロジェクト成功に不可欠ですが、従来の方法ではリアルタイムでの把握が困難でした。DXは、この課題を解決し、経営判断の質を高めるうえで大きなメリットをもたらします。
原価管理ソフトやERPを導入することで、実行予算から実績原価までを一元管理できます。現場の原価情報をリアルタイムでシステムに反映させることで、プロジェクトごとの原価進捗や利益率をいつでも正確に把握可能になります。
これにより、予算と実績の差異を早期に発見し、原因分析と適切な対策を迅速に行えます。過去の原価データを蓄積・分析すれば、将来の見積もり精度も向上し、赤字リスクを低減できます。
経営層は、全社的な視点で各プロジェクトの採算性をリアルタイムで把握し、経営資源の最適配分や事業戦略立案に役立てられます。データに基づいた客観的な経営判断が可能となり、個々のプロジェクトの採算性改善だけでなく、企業全体の収益力向上と経営基盤強化に直結します。
ペーパーレス化・情報共有の強化
建設業の現場では大量の紙書類が使われ、その管理・共有に多くの時間とコストがかかっています。DXによるペーパーレス化は、この非効率を解消し、情報共有のスピードと質を向上させます。
クラウドストレージや文書管理システムを導入すれば、図面や書類をデジタルデータで一元管理し、どこからでもアクセス可能になります。常に最新情報が共有されるためミスを防ぎ、書類を探す時間も大幅に短縮。印刷コストや保管スペースも削減できます。
施工管理アプリやビジネスチャットツールは、現場と事務所、協力会社間の情報共有を迅速かつスムーズにします。写真、日報、指示などをリアルタイムで共有でき、認識の齟齬を防ぎ、迅速な意思決定を支援します。記録が残るためトラブル回避にも繋がります。
電子契約システムは、契約業務をオンラインで完結させ、時間、手間、コストを大幅に削減し、コンプライアンスも強化します。
DXによるペーパーレス化と情報共有強化は、業務プロセス全体のスピードアップ、コミュニケーション円滑化、ミス削減、コスト削減、柔軟な働き方の実現に貢献し、企業全体の生産性と競争力を高める基盤となります。
人材育成・属人化の解消への貢献
深刻な「人手不足」と「業務の属人化」に対し、DXは有効な解決策を提供し、人材育成の効率化と特定個人に依存しない組織体制構築を支援します。
DXツールを活用すれば、熟練技術者の知識やノウハウを動画マニュアルやデータベースとして蓄積・形式知化できます。これにより、若手はいつでも必要な知識を学べ、OJTだけに頼らない効率的な人材育成が可能となり、早期戦力化を促進します。
BIM/CIMは、3次元モデルで複雑な情報を直感的に理解しやすくするため、経験の浅い技術者の学習効率を高め、教育コスト削減にも繋がります。
業務プロセスをデジタル化し情報を一元管理することで、属人化を解消できます。施工管理ソフトや原価管理ソフトにデータが集約されれば、担当者不在時でも他の従業員が状況を把握し、業務を引き継ぎやすくなり、組織の継続性と回復力が向上します。
また、DXによる単純作業の自動化・効率化は、従業員がより高度な業務に集中できる環境を作り、スキルアップやモチベーション向上、ひいては人材定着にも貢献します。DXは、人材育成、技術継承、属人化リスク低減を通じて、建設業界の持続的発展を支える重要な役割を担います。
建設業DXでよく導入されるITツール
建設業のDXを具体的に進めるためには、様々なITツールの活用が鍵となります。ここでは、業界で広く導入され、業務改善に貢献している代表的なツールを紹介します。
施工管理ソフト
施工管理ソフトは、現場管理業務を効率化するクラウド型ツール群です。スマホやタブレットから手軽に利用でき、現場監督や作業員の負担軽減、情報共有の円滑化に貢献します。
主な機能には、工程計画の作成・共有・進捗管理を行う「工程管理」、現場写真を工種別に自動整理し報告書作成を効率化する「写真管理」、最新図面をクラウドで一元管理・共有する「図面管理」、日報などの報告書作成を簡略化する「日報・報告書作成」などがあります。関係者間の「チャット」や「安全管理チェックリスト」機能なども備わり、現場管理の主要業務をデジタル化し、移動時間や事務作業の削減、情報共有の迅速化、ミスの防止に繋がります。
自社の業務や規模に合ったツール選定が重要です。
原価管理ソフト
正確な原価管理は建設業の利益確保に不可欠です。
原価管理ソフトは、実行予算作成から実績原価(材料費、労務費、外注費、経費)の収集・集計・分析までを一元管理し、プロジェクトの採算性をリアルタイムで可視化します。「実行予算作成」機能で計画を立て、「実績原価入力」機能で日々のデータを蓄積。最も重要な「原価集計・分析」機能では、予算との差異分析、工事別損益計算などをリアルタイムで行い、ダッシュボードで視覚的に表示します。
これにより、赤字工事の早期発見・対策、将来の見積もり精度向上、経営判断の支援が可能になります。経理や現場担当者の事務負担も大幅に軽減され、企業の収益力向上に直結するDXの重要ツールです。
勤怠・労務管理ツール
働き方改革やコンプライアンス遵守のため、正確な勤怠・労務管理の重要性が高まっています。
勤怠・労務管理ツールは、出退勤記録、労働時間集計、休暇管理、給与計算連携などを効率化し、適正な労務管理を支援します。クラウド型ツールなら、スマホ、ICカード、生体認証などでどこでも打刻でき、直行直帰にも対応可能です。データは自動集計され、残業時間などをリアルタイムで把握。労働基準法違反リスクをアラートで通知する機能もあります。有給休暇管理や申請・承認フローも電子化できます。給与計算ソフトとの連携で、計算業務も効率化・正確化します。管理部門の負担軽減だけでなく、従業員の労働時間意識向上にも繋がり、働き方改革を支える基盤となります。
BIM・CIMなどの設計支援ツール
BIM(Building Information Modeling)/CIM(Construction Information Modeling/Management)は、建物や構造物の情報を3次元モデルに統合し、設計から施工、維持管理までの全プロセスで活用するDXの中核技術です。単なる3D CADではなく、属性情報(材料、コスト等)を含むデータベースを構築します。
設計段階では、干渉チェックや各種シミュレーションにより手戻りを削減し、品質を向上させます。3次元モデルは関係者間の合意形成も円滑にします。施工段階では、正確な数量算出による積算効率化、4Dシミュレーションによる工程・安全計画支援、ICT施工との連携などが可能です。維持管理段階では、点検・修繕履歴を付加し効率的なファシリティマネジメントを実現します。導入には課題もありますが、国土交通省も推進しており、今後の業界標準となる可能性が高い重要技術です。
モバイル・クラウド連携ツール
建設業の業務は現場や移動中など多岐にわたるため、場所や時間に縛られない情報アクセス・コミュニケーション環境が不可欠です。
モバイルデバイスとクラウドサービスを連携させたツールがその基盤となります。クラウドストレージで図面や書類をどこからでも共有。施工管理アプリやビジネスチャットで現場と事務所間のリアルタイムな情報共有・指示伝達を実現。Web会議システムで遠隔地との打ち合わせを効率化し、移動時間・コストを削減します。これらのツールは、他の業務システムと連携することでさらに効果を発揮します。
モバイル・クラウド活用は、情報のサイロ化を防ぎ、業務のリアルタイム性と柔軟な働き方を実現する建設業 DXの土台です。
DX導入のステップと失敗しない進め方
建設業 DXを成功させるには、計画的なアプローチが必要です。やみくもなツール導入は失敗のもと。ここでは、DX導入を成功に導く基本的なステップと注意点を解説します。
自社の課題を明確化する
DX導入の出発点は、自社が抱える課題を正確に把握し、「DXで何を解決したいか」「どんな目標を達成したいか」を明確にすることです。DXは目的ではなく手段。目的が曖昧だと、ツール導入自体が目的化し失敗に繋がります。経営層から現場まで、ヒアリングやワークショップを通じて現状の問題点を具体的に洗い出します。
次に、DXで解決可能な課題、特に経営インパクトや緊急性の高い課題に優先順位をつけます。そして、「現場の残業時間〇〇削減」「粗利率〇〇%改善」のように、DX導入の目的を具体的かつ測定可能な形で設定します。これがツール選定や効果測定の指針となります。
業務フローを洗い出し、改善箇所を可視化する
DXの目的と課題が明確になったら、次に関連業務の現状フローを詳細に洗い出し、非効率や問題点を具体的に可視化します。これにより、DXツールを導入すべき箇所や、効果を最大化するための業務プロセス見直しポイントが明らかになります。対象業務の開始から終了までのステップ、担当者、使用帳票、情報フロー、所要時間などを書き出し、フローチャート化すると効果的です。この作業は、現場担当者を巻き込んで行うことが重要です。洗い出したフローを分析し、「無駄・重複作業はないか」「効率化できるステップは?」「情報が滞る箇所は?」「手作業・紙ベースで時間がかかる箇所は?」といった観点から問題点を特定します。例えば、「現場メモを事務所でExcel転記」なら「現場アプリ入力」へ、「複数システムへの重複入力」なら「システム連携」へ、といった具体的な改善策が見えてきます。現状把握と改善箇所の特定が、的確なツール選定とDX効果最大化の鍵です。
小さく始めて徐々に拡大(スモールスタートが重要)
建設業 DXは企業全体の大きな変革であり、最初から大規模に行うと現場の抵抗や混乱を招き失敗しやすいです。成功のためには「スモールスタート」が重要。特定の部門、業務、プロジェクトなど範囲を限定して小さく始め、効果検証や課題抽出を行いながら徐々に拡大するアプローチが有効です。まず、明確化した課題の中から、効果が見えやすく影響範囲をコントロールしやすいテーマを選びます(例:特定現場でのアプリ試行、経理部での原価管理ソフト一部利用開始)。試行導入期間中に、使い勝手、効率変化、現場の反応、問題点などを記録・分析し、フィードバックを収集します。結果を評価し、効果が確認できれば、成功事例やノウハウを基に他部門へ段階的に拡大。効果が見られない場合は計画を見直します。スモールスタートは、初期投資リスク低減、現場の混乱抑制、成功体験による全社展開の円滑化といったメリットがあります。焦らず着実に進めることがDX成功の秘訣です。
現場の声を反映させた運用体制の構築
DXの成否は、最終的に現場で「使われる」かどうかにかかっています。高機能ツールも現場が使いこなせなければ意味がありません。ツール選定から導入後の運用まで、常に現場の声を聞き、それを反映した運用体制を築くことが極めて重要です。ツール選定では「使いやすさ」を優先し、ITに不慣れな従業員でも直感的に操作できるものを選びます。可能なら現場での試用と比較検討が理想です。導入時には丁寧な説明会・研修で、操作方法だけでなく導入目的・メリットを伝え、従業員の納得感を得ることが大切です。導入後も、質問・要望・改善提案を吸い上げる仕組みを設け、継続的に運用を見直します。現場のDX推進リーダー任命も効果的です。業務プロセス変更時は、新ルールやマニュアルで現場の混乱を防ぎます。現場の意見や知恵を尊重し、DX推進に主体的に関わってもらうことが、DXを定着させ真の効果を発揮させる鍵です。
建設業の原価管理に強いDXツール「要 〜KANAME〜」
建設業向けDXツールのなかでも、特に経営の根幹である「原価管理」強化を目指す企業におすすめなのが、原価管理システム「要 〜KANAME〜」です。専門工事業や中小建設会社が抱える原価管理の課題解決に特化しており、建設業 DXを力強く推進します。
要 〜KANAME〜は、複雑な原価計算や利益管理をシンプルかつ効率的に行う機能が豊富です。最大の強みは、実行予算作成からリアルタイムでの工事原価把握、発注・支払管理、請求・入金管理まで、原価管理業務を一気通貫でデジタル化できる点。これにより、Excelや手作業による煩雑な管理から解放され、大幅な業務効率化を実現します。
精度の高い「実行予算作成」、日々の実績データを反映させる「リアルタイム原価実績把握」機能に加え、工事別・担当者別など多角的な「原価分析機能」が充実。経営状況を詳細に分析し、データに基づいた改善策立案を支援します。赤字工事の早期発見や利益率の高い工事の傾向把握も可能です。「発注・支払管理」「請求・入金管理」機能も連携し、業務フロー全体を効率化します。
要 〜KANAME〜の導入は、業務効率化に留まらず、原価と利益の「見える化」を通じてどんぶり勘定からの脱却を支援し、全社的なコスト意識向上を促進。データに基づいた客観的な経営判断を可能にし、企業の収益力強化と持続的成長をバックアップします。分かりやすいインターフェースで、ITに不慣れな方でも導入・運用しやすい点も魅力です。
「儲かる体質」への変革を目指す建設業にとって、「要 〜KANAME〜」は検討すべき実効性の高いDXソリューションと言えるでしょう。
▼原価管理システム「要 〜KANAME〜」の詳細はこちら▼
https://www.pluscad.jp/products/kaname/
まとめ:DXで変わる建設業の未来、今こそはじめるとき
本記事では、建設業におけるDXの重要性、課題、メリット、ツール、成功のポイントを解説しました。人手不足、属人化、非効率な管理といった業界課題の解決にはDXが不可欠です。DXは単なるツール導入ではなく、業務プロセスや組織文化を変革する経営戦略です。
導入メリットは、業務効率化、原価管理精度向上による利益改善、ペーパーレス化によるコスト削減・情報共有強化、人材育成促進・属人化解消など多岐にわたります。施工管理ソフト、原価管理ソフト「要 〜KANAME〜」、勤怠管理ツール、BIM/CIMなどがその実現を支援します。
成功の鍵は、自社課題の明確化、業務フロー可視化、スモールスタート、そして現場の声を反映した運用体制構築です。DXはもはや一部企業のものではなく、企業の規模に関わらず取り組むべきテーマです。業務効率化による競争力強化だけでなく、働きがいのある環境創出にも繋がります。
変化を恐れず、まずは身近な業務改善から一歩を踏み出し、DXツールを活用してデータに基づいた経営へ移行すること。今こそ、建設業の明るい未来を切り拓くために、DXへの取り組みを始める時です。
建設業DXについてよくある質問
Q1. 中小建設会社でもDXは可能ですか?費用は?
A1. はい、可能です。中小企業向けのクラウド型サービスが多く、初期費用を抑え月額料金で利用できるツールが多数あります。特定の業務課題解決ツールからスモールスタートするのがおすすめです。費用はツールや規模によりますが、月額数千円から始められるサービスもあります。
Q2. ITに詳しくない従業員が多いのですが、大丈夫でしょうか?
A2. 多くの建設業向けツールは、IT初心者でも直感的に使えるよう設計されています。「使いやすさ」を重視し、導入前に現場で試用するのが理想です。導入時の研修や導入後のサポート体制が充実したベンダーを選び、社内でのフォロー体制も整えましょう。焦らず徐々に慣れていくことが大切です。
Q3. DXの効果が出るまでどれくらいかかりますか?
A3. ツールや目的、取り組み方で異なります。勤怠管理や施工管理アプリによる効率化は比較的短期間(数週間〜数ヶ月)で実感しやすいですが、原価管理改善やBIM/CIMによるプロセス改革は、データ蓄積や習熟に時間が必要で、効果が明確になるまで半年〜1年以上かかることもあります。中長期的な視点で効果測定と改善を継続することが重要です。
Q4. 建設業DXで最も重要なことは何ですか?
A4. 「経営層の強いコミットメント」と「現場の巻き込み」です。経営トップがDXの重要性を理解し、ビジョンを示し推進するリーダーシップが不可欠です。同時に、実際にツールを使う現場の意見を尊重し、課題明確化から運用改善まで主体的に関われるようにすることが、DXを定着させ成功させる鍵です。
Q5. DX導入のセキュリティ対策はどうすればよいですか?
A5. クラウドやモバイル利用では対策が不可欠です。信頼できるセキュリティ基準を満たしたツール・サービスを選び、ベンダーの対策内容を確認しましょう。社内セキュリティルール(パスワード管理、不審メール注意、デバイス紛失時対応など)を策定し、従業員教育を徹底することも重要です。適切なアクセス権限設定も有効です。信頼できるベンダー選定と社内ルールの整備・遵守で、安全にDXを進められます。