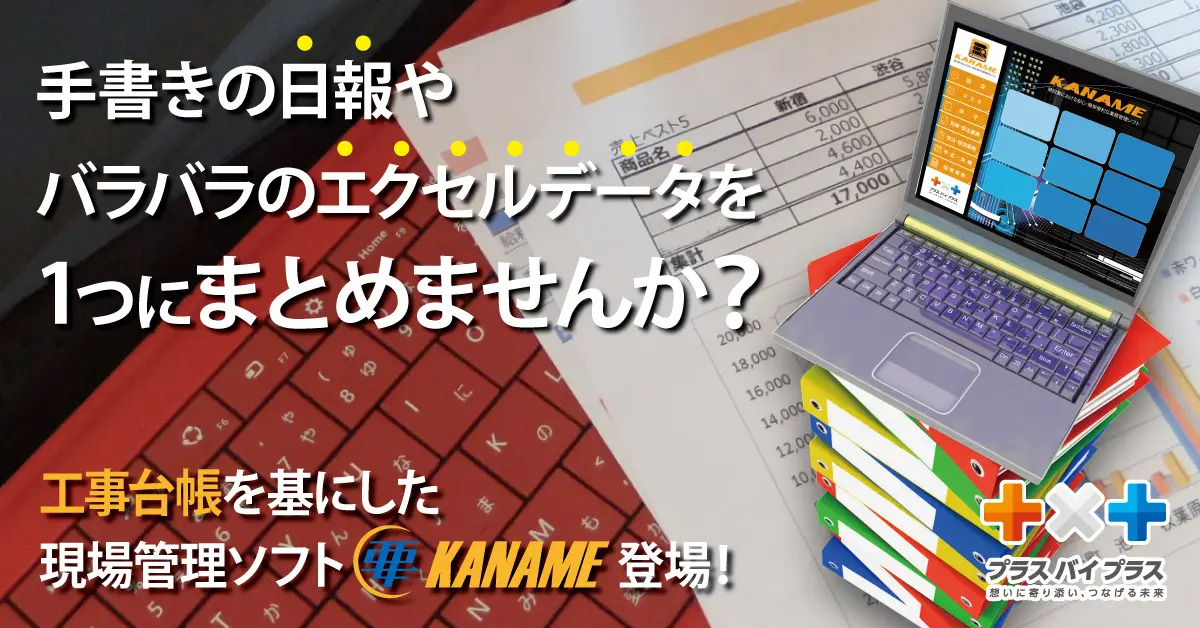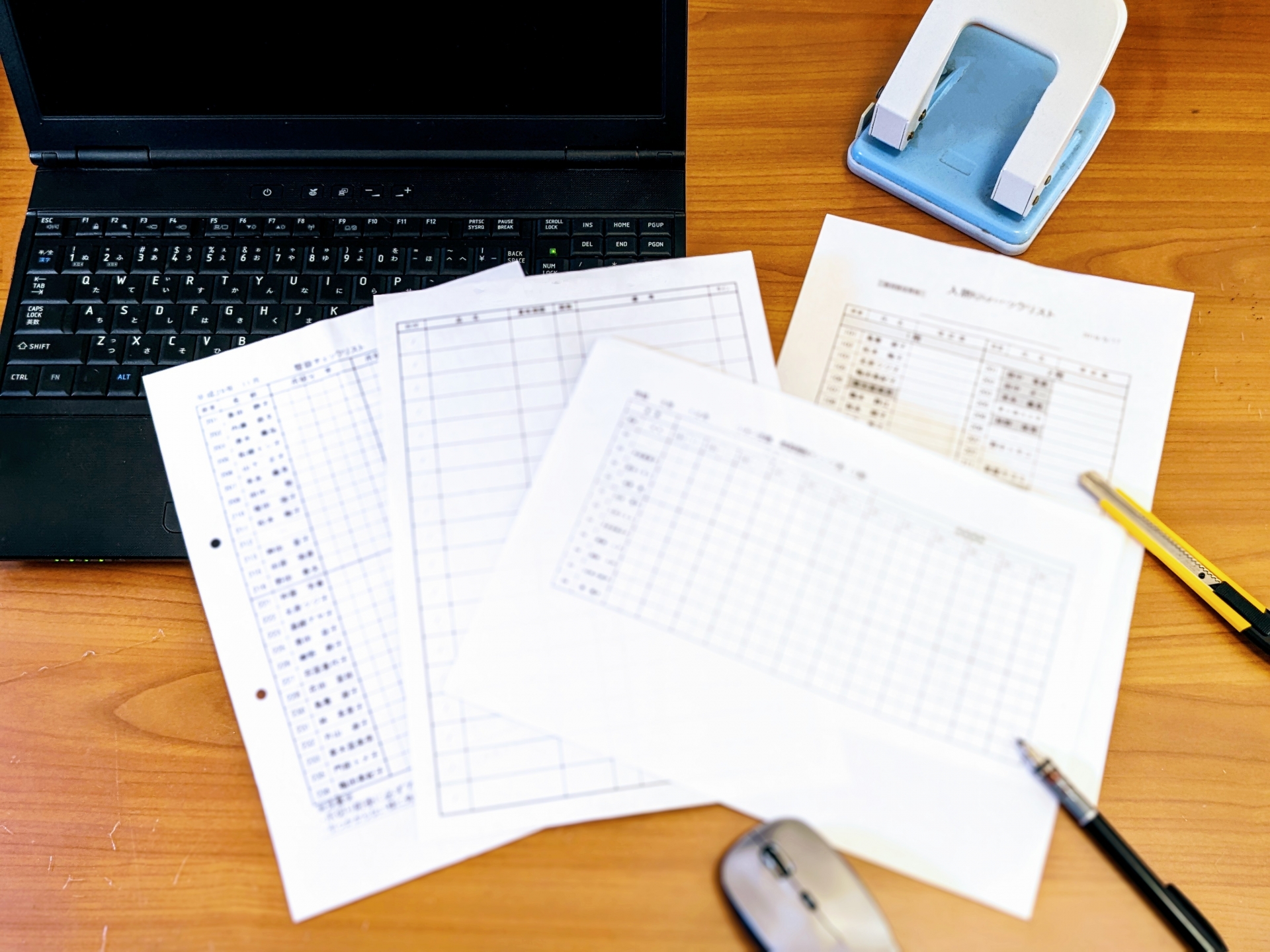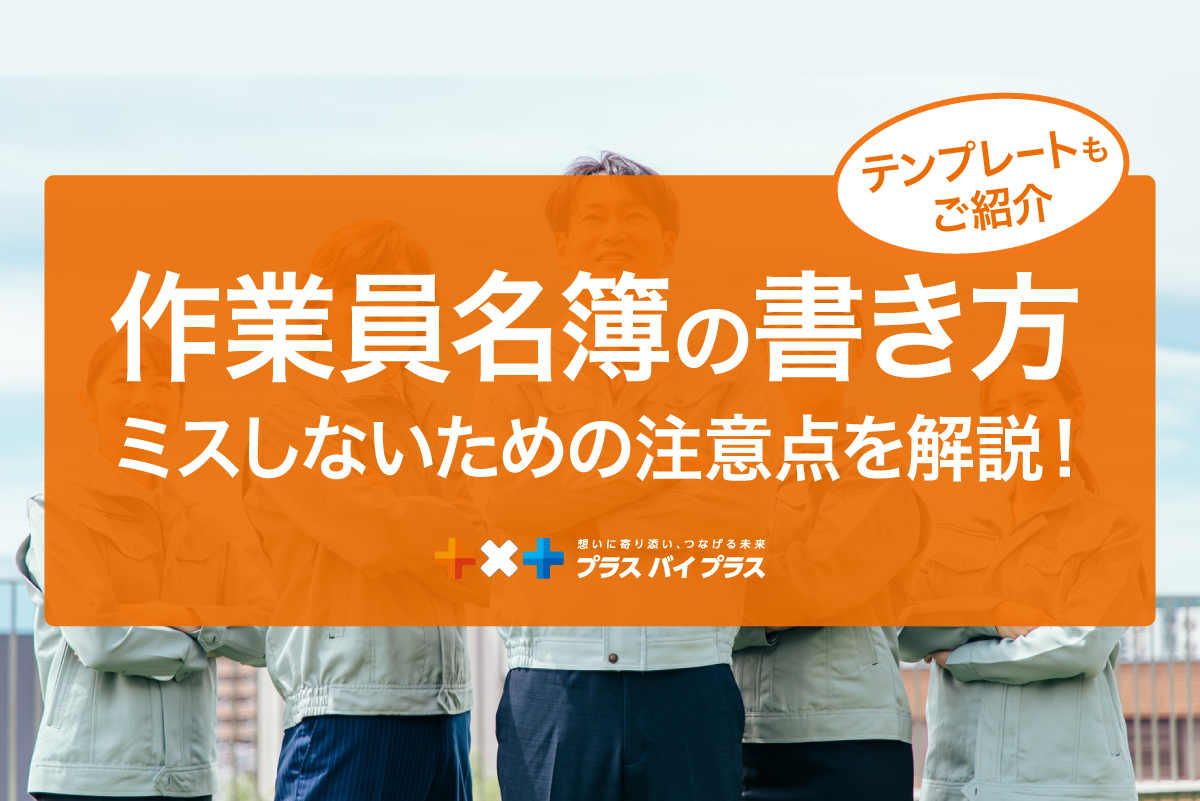- 2025年11月07日
建設現場を効率化するアプリ活用術を徹底解説!現場管理デジタル化のポイントとは
建設業に関する知識

建設業界では、長時間労働や人材不足といった複数の労働課題が長年問題視されてきました。
しかし近年、DXの推進に伴い、現場管理のデジタル化が加速しており、その中核を担っているのが施工管理アプリです。
施工管理アプリは、工程、写真、図面、原価などをデータで共有・管理することを可能にし、業務効率の向上やコスト削減、品質管理の精度向上につながります。
この記事では、現場作業を効率化できるおすすめの現場効率化アプリや導入のポイントについて解説します。
コンテンツ
建設業で現場効率化が重要視される理由
建設現場で現場効率化アプリの導入が進む背景には、建設業界特有の構造的な課題と、社会的な法規制の変化があります。人手不足と長時間労働
建設業界は、長時間労働や人材不足という複数の労働課題を抱えています。特に2024年4月からは、建設業においても時間外労働の上限規制が適用されたため、労働時間を正確に把握し、業務のムリ・ムダを省く必要性が高まりました。
従来の施工管理では、現場監督は遠方でも施工状況を確認するために現場に足を運ぶ必要があったり、現場外での写真整理や報告書作成のために事務所に戻る必要があったりと、アナログな手法が一般的でした。
現場業務を効率化することで、余計な残業を減らし、本来の施工業務に集中できる体制を作ることが求められています。
複数現場の同時管理の難しさ
建築や土木の現場では、職人が工程ごとに参加したり離脱したりと流動的であり、複数の現場を同時並行で管理することが難しいという課題があります。現場は不具合や打ち合わせによる変更が多い「生き物」と言われるほどであり、変更資料の共有が遅れるだけで作業工程の遅れが生じ、問題点となっていました。
工事を滞りなく進めるには、施工現場の状況を常に共有・管理する必要があります。
現場効率化アプリを活用することで、担当者不在で必要な情報が得られないといったトラブルを防ぎ、複数案件の状況を横断的に把握して、人員配置や工事スケジュールの調整を容易にすることができます。
デジタル化の遅れによる非効率
建設業界の業務は、紙の図面やFAXなどのアナログな手法が多く残っており、非効率な状態にあります。施工管理における課題として、現場外の写真整理や報告書作成などの事務業務が大変であること、また、工程表作成や修正に時間がかかり、個々の職人への情報共有(電話、メール、FAXなど)が面倒であることなどが挙げられます。
これらのアナログな管理は、無駄な人件費や工期の遅延につながりがちです。
現場効率化アプリは、これらのアナログな煩わしさを解消し、必要な情報や関係者との連絡履歴を一つのアプリにまとめることができます。
現場効率化アプリの主な種類
現場効率化アプリ、すなわち施工管理アプリは、多岐にわたる現場業務をデジタルでサポートするさまざまな機能を搭載しています。ここでは、代表的なアプリの主な種類をご紹介します。
日報・報告アプリ
日報・報告アプリを利用すれば、現場にいながらスマホやタブレットで日報を作成できるため、わざわざ事務所に戻ってPCなどで日報を作成する手間や時間が省けます。アプリによっては、現場担当者の作業内容や作業量の把握も可能になるため、各現場への適切な人員配置に役立ちます。
また、日報作成が容易になることで、社員間の情報共有が促進され、管理職にとっても日報確認の負担が大きく軽減されます。
勤怠・シフト管理アプリ
勤怠・シフト管理機能を有するアプリでは、労働時間を簡単に記録可能であり、記入漏れや集計ミスを防ぐことができます。現場や個人の予定をアプリに登録することで、施工プロジェクト期間内の予定などを関係者間で容易に共有・可視化でき「予定を確認するためだけに帰社する」といった煩わしさが解消されます。
正確な労働時間を把握することは、建設業の時間外労働の上限規制への対応にもつながります。
進捗・タスク管理アプリ
進捗・タスク管理アプリを利用すると、これまでExcelや紙で作成していた工程表をアプリ上で作成・管理し、クラウドで関係者間で共有できます。常に最新の工程表をメンバーに共有できるため、作業スケジュールの確認はもちろん、工事内容の変更時もスムーズに対応できます。
現場で施工を進めるなかで状況が変わった場合でも、現場でアプリを開いて連絡事項を入力しておけば、関係者に一斉に連絡が飛び、ほかの担当者が資機材手配などを進めることも可能になります。
写真・図面共有アプリ
写真・図面共有アプリを活用することでスマホやタブレットで撮影した現場写真や図面データをクラウド上で一元管理・共有可能です。データの一元管理により検索性が高まるため、膨大な資料から該当する資料を探したり、渡したりする手間も軽減されます。
写真や図面に直接書き込める機能が搭載されているアプリもあり、指示内容の共有が容易に。
また、写真撮影と同時に情報を付与できるアプリを使用すれば、工事写真台帳の作成など、写真を起点とした業務の効率化が実現できます。
現場効率化アプリ導入のメリット
現場効率化アプリを導入することで、単に現場業務がデジタル化されるだけでなく、経営や品質管理にも大きな効果をもたらします。現場間の情報共有スピード UP
施工管理アプリは、インターネット上で情報を管理しているため、常に最新の情報をネットにつなげるだけで確認できます。工事現場では、変更点や伝えたいことを各地の作業員に連絡するコミュニケーションストレスが大きいものです。
アプリを導入することで、工事関係者に一斉に情報共有でき、コミュニケーション面でのストレス軽減に役立ちます。
リアルタイムでの情報共有が可能になることで、変更資料の共有遅れによる作業工程の遅延を防げます。
報告・承認作業の簡略化
施工管理アプリを導入することで、報告や承認の際に書類を作成する手間がかからなくなり、現場業務を効率化できます。現場監督が事務所に戻って行っていた写真整理や工事報告書の作成などのデスクワークを、アプリ上で現場にいながら完結できるようになります。
データ蓄積による再利用性向上
施工管理アプリを活用することで過去・現在の案件情報をデータとして蓄積・一元管理できます。案件ごとに情報が整理され、検索性も高いため、担当者が変わっても経緯や事情が把握しやすくなることもメリット。
また、過去の案件情報を営業管理に活かすことも可能になり、優秀な営業マンのノウハウや活動内容がデータとして残るため、再現性を高め、新人営業マンの育成にも役立ちます。
属人化の防止
従来の現場管理では、個々の職人への情報共有がアナログだったため、情報が個人に紐づきやすく、属人化しやすい傾向がありました。施工管理アプリを使用することで工程表や工事写真、図面、チャットのやり取りに至るまで、工事に関わる情報を一元管理できるため、「誰が何を言ったか」というやり取りの記録も残り、進捗や経緯を把握しやすくなります。
これにより、知識やノウハウを社内で共有しやすくなり、特定の担当者に依存することなく業務を進められるため、属人化の防止につながります。
アプリ導入のデメリット・課題
多くのメリットを持つ現場効率化アプリですが、導入時にはいくつかのデメリットや課題に直面することがあります。現場での操作定着が難しい
建設業界は平均年齢が高く、年配の方も多いことからITツールに慣れていないユーザーが多いです。そのため、現場での操作定着が難しいという課題があります。
多機能な施工管理アプリは、現場監督には適しているかもしれませんが、使わない機能が増えると操作が複雑化し、現場への浸透を妨げる要因となるケースが少なくありません。
導入コストをかけたにもかかわらず、一部の機能しか使われず、結局現場で使われなくなってしまうという失敗例もあります。
通信環境の影響
施工管理アプリの多くはインターネット接続を前提として情報を管理・共有します。現場の通信環境が不安定な場合、リアルタイムの情報共有が滞ったり、容量の大きな写真や図面データのアップロード・閲覧に時間がかかったりする影響が出る可能性があります。
通信環境が確保できない現場では、アプリの利便性が損なわれる場合があります。
教育体制
現場効率化アプリを導入しても、操作方法を理解し、現場の運用に組み込むための教育体制が整っていないと、業務に支障をきたし、定着しないリスクがあります。自社だけで運用ルールや社内浸透を進めようとすると、導入担当者にかなりの負担がかかってしまうことがあります。
アプリ間の連携不足
施工管理アプリは、工事写真に特化したシンプル型から、原価管理や受発注、顧客管理などの基幹業務までカバーする多機能型まで、さまざまな種類があります。複数の現場管理機能を別々のアプリで賄おうとすると、アプリ間の連携不足により情報の転記や重複入力が発生し、かえって非効率になる可能性があります。
施工管理アプリを選ぶ際は、自社のカバーしたい業務範囲を明確にし、オールインワンで必要な機能が連携されている製品を選ぶことが望ましいでしょう。
効率化アプリを活かすための運用ポイント
導入の失敗を避け、現場効率化アプリを最大限に活用するためには、選定時と運用開始後にいくつかの重要なポイントがあります。目的を明確にする
アプリ導入の最大の失敗原因の一つは、機能が多すぎて使いこなせないことです。導入の際は、「自社にとって必要な機能は何か?」と目的を明確にすることが大切です。
守備範囲の広い多機能な製品を選びがちですが、使わない機能が増えることで操作が複雑化し、結果として導入コストが割高に感じられることがあります。
自社の課題と、その課題を解決するために本当に必要な機能を整理し、「本当に現場の課題を解決できる製品」を選定することが重要です。
現場担当者の声を反映
施工管理アプリは、現場監督だけでなく職人や関係者全員の利用を目的にしているツールです。ITツールに慣れていない方が多い建設業界において、現場への浸透率を高めるには操作性の高さが極めて重要です。
そのため、直感的な操作ができるか、シンプルで使いやすいか、見やすい工夫がされているか、年配者でも使いやすいか、という3つの点に注意しながら選択しましょう。
導入後の運用サポートを重視
施工管理アプリを使用していくうえで、サポート体制の整っているメーカーを選択することが大切です。アプリ利用時にトラブルが起きたとき、サポート体制が整っていないと業務に支障をきたすためです。
業務時間に電話やメール相談を受け付けているメーカーを選択すると、いざというときでも迅速な対応ができます。
「要 〜KANAME〜」で原価管理の視える化を実現しよう!
現場効率化アプリは、情報共有や事務作業の削減に大いに役立ちますが、最終的に現場全体の利益を最大化するには、正確な原価管理が必要です。アプリ導入の利点と限界を理解したうえで、原価管理の重要性に気づくことが、現場全体の利益管理には不可欠です。
原価管理とは、業務フローに沿って情報を入力していくだけで、売上・粗利・原価を正確に計算できる機能です。
Excelや紙を使った管理では、転記ミスや関数の間違いなどのリスクが伴いますが、施工管理業務に特化したアプリを利用することで、ミスを低減し、属人化を防ぐことができます。
現場全体の利益管理に欠かせない、原価管理ツールとして「要 〜KANAME〜」が挙げられます。
正確な原価管理は、建設業における業務効率化と利益向上の目標を達成するうえで非常に有効な現場効率化アプリです。
<3分でわかる!「要 〜KANAME〜」を動画で見る>
現場管理アプリについてよくある質問
Q1. 施工管理アプリを導入する最大のメリットは何ですか?
A. 施工管理アプリを導入する最大のメリットは、作業の効率化とリアルタイムでの情報共有により、工事品質の向上と工期の順守に繋がる点です。スマートフォンやタブレットで図面や写真といった現場情報を一元管理することで、現場と事務所の往復や紙ベースでの煩雑な事務作業が大幅に削減されます。
これにより、浮いた時間を改善事項の検討やマネジメント業務に充てることが可能となります。
Q2. 施工管理アプリの料金相場はどれくらいですか?
A. 施工管理アプリの料金相場は、サービスによって大きく異なりますが、大体1人あたり月額1,000円〜数千円程度が多いです。多くは利用人数に応じて金額が高くなるID課金型が一般的です。
Q3. 完全無料で使える施工管理アプリはありますか?
A. はい、あります。ただし、無料アプリは、有料版と比べて機能やサポート体制が限定的である場合があるため、導入前に自社の目的に合っているか確認が必要です。
Q4. 施工管理アプリ導入で失敗しやすい例は何ですか?
A. アプリ選びで失敗する原因は、主に以下の3点です。1. 多機能すぎて使いこなせない:
多くの機能を備えたアプリを選んだ結果、現場で覚えることが増え、一部の機能しか使われず、高い費用が無駄になってしまう。
2. 操作が複雑すぎて現場に浸透しない:
特にITに不慣れな年配の作業員や職人が操作に戸惑い、利用を諦めてしまい、結果的にアプリが使われなくなる。
3. 無料版や低価格版でサポートが不足する:
サポート体制が十分でない場合、運用ルールや社内浸透を自社だけで進めることになり、導入担当者に負担がかかり、定着が進まない。
Q5. アプリを選ぶ際に失敗しないための最大のポイントは何ですか?
A. 最も重要なポイントは、自社の課題を明確にし、その解決に必要な機能が過不足なく搭載されているかを確認することです。導入時に多機能すぎるアプリを選んでしまうと、操作が複雑化して現場に定着しなかったり、使われない機能の分のコストが割高になったりするリスクがあります。
また、ITツールが苦手な人でも使いやすい操作性の高さや、導入後のサポート体制を重視して選定し、無料トライアルで現場での試用を行うことが、失敗を避けるために有効です。