一人親方として順調に事業を続けていると、必ず頭をよぎるのが「法人化」です。
「法人化した方が税金が安くなるって聞くけど、実際どうなんだろう?」
「取引先から法人化を勧められたけど、本当に必要なの?」
「将来の年金や社会保険が不安…法人化したらどう変わる?」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、一人親方が法人化を考えるきっかけから、メリット・デメリット、そして具体的な年収別の判断基準まで、わかりやすく解説します。
一人親方が法人化を考えるきっかけとは?
まずは、どのようなタイミングで法人化を検討し始めるのか、具体的な例を見ていきましょう。
税金が高くなったとき
事業が拡大して所得が増えると、所得税や住民税の負担が重くなります。個人事業主は累進課税のため、所得が増えるほど税率が上がり、税負担の悩みを抱える一人親方は多いです。
取引先から法人化を求められるケース
大手企業や官公庁を取引先とする場合、コンプライアンスや信用力の観点から、法人との取引を基本としているケースがあります。安定した取引を続けるために、法人化を検討するきっかけになります。
将来の年金・社会保険への不安
個人事業主は国民年金や国民健康保険に加入しますが、将来の年金や万一の保障に不安を感じる人も少なくありません。法人化することで、厚生年金や健康保険に加入できるようになり、保障が手厚くなります。
融資や信用力を高めたいとき
事業拡大のために融資を受けたい場合、個人事業主よりも法人の方が社会的信用力が高く、審査に通りやすくなる傾向があります。
法人化のメリット
法人化には、主に以下のようなメリットがあります。
節税効果(役員報酬・経費計上の幅が広がる)
法人化すると、自分自身に「役員報酬」として給与を支払う形になります。この役員報酬は給与所得控除の対象となるため、所得税の負担を軽減できます。また、生命保険料や退職金など、経費にできる範囲が広がるため、より多くの節税対策が可能になります。
社会保険に加入できる(老後の年金・医療保障が安定)
法人の代表になると、厚生年金や健康保険への加入が義務付けられます。国民年金よりも将来の年金受給額が増える可能性があり、病気や怪我をした際の傷病手当金なども保障されます。
信用力アップで仕事が取りやすい
法人として登記することで、社会的信用力が向上します。これにより、新規の取引先や金融機関からの信頼を得やすくなり、事業を拡大する上で有利になります。
家族に給与を出して所得分散できる
家族を役員や従業員として迎え入れることで、役員報酬や給与を支払い、所得を分散させることができます。所得が分散されると、世帯全体での税負担を軽減する効果が期待できます。
法人化のデメリット
一方で、法人化には注意すべきデメリットも存在します。
設立費用がかかる
株式会社を設立する場合、登録免許税や定款認証費用などで約20万円〜25万円の費用がかかります。合同会社であれば、設立費用は約6万円〜10万円と抑えられますが、いずれにしても個人事業主にはない初期費用が発生します。
毎月の社会保険料負担が増える
厚生年金や健康保険に加入すると、保険料の半分を会社が負担することになります。つまり、個人事業主時代よりも事業全体で見た社会保険料の負担額は増えます。
経理・決算が複雑になる(税理士費用が発生)
法人の経理は、個人事業主の確定申告よりも複雑です。専門的な知識が必要なため、多くの場合は税理士に依頼することになり、その費用が発生します。
赤字でも法人住民税がかかる
個人事業主は赤字であれば税金はかかりませんが、法人の場合、事業が赤字でも「法人住民税の均等割」として、年額自治体によりますが最低7万円前後の税金が発生します。
一人親方は年収いくらから法人化すべき?
法人化によるメリットが大きくなるのは、ある程度の事業所得がある場合です。一般的に、年収の目安は以下の通りです。
| 年収 | 法人化の判断 | 理由 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 個人事業主のままでOK | 節税メリットが少なく、かえって社会保険料や税理士費用などの負担が重くなる可能性があるため。 |
| 700万円〜1000万円 | 法人化を検討するタイミング | 所得税の税率が上がり始め、法人化による節税メリットが大きくなるため。 |
| 1000万円超 | 法人化による節税メリットが大きい | 個人事業主の所得税率が大幅に上昇するため、法人化による節税効果が顕著に現れます。 |
【法人化シミュレーション例】
| 項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 年収700万円 | 所得税・住民税:約65万円 | 所得税・住民税(給与):約25万円 |
| 事業税・消費税:約20万円 | 法人税・法人住民税:約25万円 | |
| 合計:約85万円 | 合計:約50万円 |
※あくまで概算であり、経費や家族構成によって変動します。
法人化の手続きと流れ
法人化の手続きは、自分で行うこともできますが、専門家に依頼するのが一般的です。
自分で設立する方法(法務局)
自分で手続きを行うと費用は抑えられますが、書類作成や手続きに時間と手間がかかります。
司法書士や税理士に依頼する方法
司法書士は設立登記の手続きを代行し、税理士は設立後の税務関係をサポートします。専門家に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
設立後に必要な手続き(社会保険・税務署・年金事務所)
法人設立後は、年金事務所で厚生年金・健康保険の加入手続き、税務署で法人設立届出書の提出など、様々な手続きが必要です。
一人親方が法人化する前に考えるべきこと
法人化は事業の大きな転換点です。手続きを進める前に、以下の点をじっくりと検討しましょう。
本当に節税になるのか?(数字で確認)
節税効果だけでなく、社会保険料や税理士費用、設立費用などのコストをすべて含めて、トータルでメリットがあるのかをシミュレーションすることが重要です。
将来の事業拡大や雇用の予定はあるか?
法人化は社会的信用力が高まるため、将来的に従業員を雇い入れたり、事業規模を拡大したりする計画がある場合は、法人化のメリットを最大限に活かせます。
家族構成やライフプランとの相性
家族を従業員にする予定があるか、将来の年金や医療保障をどう考えているかなど、ご自身のライフプランと照らし合わせて検討しましょう。
税理士に相談してシミュレーションする重要性
ご自身の状況に合わせた最適な判断をするためには、専門家である税理士に相談するのが最も確実です。節税効果や税金・社会保険料のシミュレーションをしてもらうことで、具体的な数字で比較検討できます。
まとめ
一人親方の法人化は、事業規模が拡大し、年収が一定のラインを超えたタイミングで大きなメリットをもたらします。
法人化によって「節税・信用力アップ」という大きなメリットがある一方で、「社会保険料負担・手間」も増えることを忘れてはいけません。
法人化すべきかどうかの判断基準は、「年収・将来の計画・家族のライフプラン」によって異なります。
もし迷っているなら、まずは具体的な数字でシミュレーションを行い、信頼できる税理士に相談することをお勧めします。それが、あなたにとって最良の選択をするための第一歩となるでしょう。
独立って何から始めればいい?経営者になるための教科書公開中
「とりあえず独立したけど、営業や経営は初めてで手探り状態…」
そんな独立1〜3年目の水道工事業の社長に向けて、仕事を安定させる前段階から役立つ情報をまとめたページをご用意しました。
このページでは、
- まず何を準備すればいいか
- お客様をどう見つけ、どう信頼を得るか
- 少しずつ仕事を増やしていく方法
など、職人から経営者へとステップアップするための具体的なヒントを解説しています。
独立したてで「これからどう動けばいいか」に悩んでいる方はぜひご覧ください。
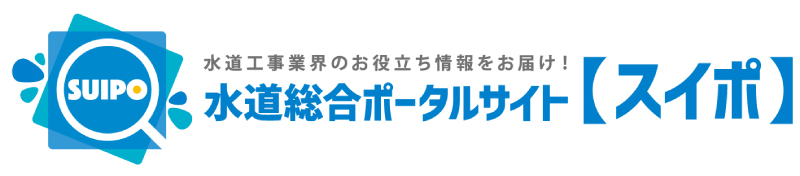



\【スイポ】サイトへのご意見募集してます/ 「こんなこと知りたい」、「ここが使いにくい」などの貴重なご意見を募集しております。