会社員として長年経験を積んできたあなた。「そろそろ独立して自分の腕で稼ぎたい」「もっと自由に働きたい」と考えているのではないでしょうか?
ですが、いざ独立を考え始めると、「一人親方と個人事業主って何が違うの?」「独立したら税金や保険はどうなるんだろう?」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるかもしれませんね。特に建設業界など、専門性の高い分野で長くキャリアを築いてきた方ほど、「会社を辞めて一人親方になる」という具体的な道筋が見えつつも、その実態が掴みにくいと感じるでしょう。
この記事では、そんなあなたの疑問や不安を解消するために、「一人親方」と「個人事業主」の違いを徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたがどの働き方を選ぶべきか、そして独立のために何から始めればいいのかが明確になります。
まずはここから!「一人親方」と「個人事業主」の基本を理解しよう
まずは、それぞれの言葉が何を意味するのか、基本的な定義から見ていきましょう。
「個人事業主」とは?
個人事業主とは、法人を設立せずに、個人で事業を営む人全般を指す言葉です。
簡単に言えば、会社に属さず、自分の名前でビジネスをしている人なら、誰でも個人事業主になることができます。業種に制限はなく、従業員を雇うことも可能です。例えば、フリーランスのWebデザイナーやコンサルタント、カフェの経営者なども個人事業主にあたります。
「一人親方」とは?
では、一人親方とは何でしょう? 実は、一人親方は「個人事業主」の一種です。
もう少し詳しく言うと、「労働者を雇わずに(またはごく短期間のみ)、特定の事業を行うことを常態とする個人事業主」のことを指します。
「一人親方」という言葉は、特に建設業や運送業、林業といった労災リスクの高い業種で使われることが多いのが特徴です。これは、後述する労災保険の特別加入制度と深く関係しています。
つまり、個人事業主という大きな枠組みの中に、特定の条件を満たす「一人親方」が存在する、と考えると分かりやすいでしょう。
ココが重要!一人親方と個人事業主の「7つの違い」を徹底比較
ここでは、一人親方と個人事業主の具体的な違いを7つのポイントに絞って解説します。
1. 法的根拠と定義
個人事業主:
税法上の区分であり、事業を営む個人のことです。
一人親方:
労災保険法における特別加入の対象者として定義されることが多いです。
2. 労働者を雇えるか
個人事業主:
従業員を雇用できます。事業を拡大し、人を雇うことも自由です。
一人親方:
原則として労働者を使用しません。ただし、年間100日未満の範囲で一時的に補助的な労働者を使うことは例外的に認められます。
3. 加入できる保険
独立後の生活で特に気になるのが保険です。ここが会社員時代と大きく変わる部分であり、一人親方と個人事業主で明確な違いが出るところです。
労災保険:
個人事業主:
原則として労災保険の対象外です。なぜなら、労災保険は「労働者の保護」を目的としているためです。
一人親方:
ここが最大の違いであり、一人親方の大きなメリットです。建設業などの特定業種の一人親方は、「労災保険の特別加入制度」を利用することで、労働者と同じように労災保険に加入できます。万が一の事故や病気で働けなくなった場合に、給付金を受け取れる安心感は大きいでしょう。
雇用保険:
どちらも加入できません。
社会保険(健康保険・年金):
どちらも基本的に国民健康保険と国民年金に加入します。会社員の時に加入していた健康保険や厚生年金からは脱退することになります。
4. 税務上の扱い
所得税や消費税など、基本的な税務上の扱いはどちらも同じ「個人事業主」として扱われます。
所得税・住民税・個人事業税・消費税:
事業で得た所得に応じてこれらの税金がかかります。
節税のポイント:
どちらの形態でも、青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けられるなど、大きな節税メリットがあります。また、小規模企業共済への加入も、節税と退職金準備を兼ねられるためおすすめです。
5. 契約形態
どちらも事業主として、顧客と「請負契約」や「業務委託契約」を結びます。会社員のように雇用契約ではありません。
6. 業界特性
個人事業主:
業種に縛りはありません。
一人親方:
主に建設業、運送業、林業、漁業など、身体を使って作業を行う業種で使われることが多く、これらの業界特有の労災リスクに対応した制度が存在します。
7. 屋号の有無と事業規模
どちらも屋号(例:〇〇工務店、〇〇デザイン事務所など)を付けて事業を営むことが可能です。
事業規模についても、個人事業主は従業員を雇って事業を拡大していくことが一般的ですが、一人親方はあくまでも「一人」での事業を前提としています。
【比較表】一人親方 vs 個人事業主:一目でわかる!あなたの疑問を解決
| 項目 | 個人事業主 | 一人親方 |
| 定義 | 個人で事業を営む人の総称 | 個人事業主の一種、特定の業種 |
| 雇用 | 従業員を雇用できる | 原則雇用しない(例外あり) |
| 労災保険 | 原則加入できない | 特別加入制度で加入可能 |
| 業種制限 | なし | 特定の7業種に限定 |
| 税務 | 同一(所得税・住民税など) | 同一(所得税・住民税など) |
| 社会保険 | 国民健康保険・国民年金 | 国民健康保険・国民年金 |
| 主な例 | Webデザイナー、飲食店経営 | 建設業の大工、運送業のドライバー |
独立するなら知っておきたい!必要な手続きと独立後の落とし穴
「よし、独立しよう!」と決めたら、次は具体的な手続きと、事前に知っておくべきリスクについて確認しましょう。
独立の第一歩!開業届の提出
個人事業主として事業を始めるなら、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を提出します。これは、事業を開始したことを税務署に知らせるための書類です。
提出のタイミング:事業を開始した日から1ヶ月以内
提出場所:所轄の税務署
開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」も提出することを強くおすすめします。これを提出することで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるなど、大きな節税メリットがあります。
一人親方として働くなら必須!労災保険の特別加入手続き
建設業など、労災リスクが高い業種で一人親方として働くなら、労災保険の特別加入は必須と言えるでしょう。
加入方法:
厚生労働大臣から承認を受けた一人親方団体を通じて加入します。
メリット:
万が一の業務中の事故や通勤災害時に、治療費や休業補償が受けられます。会社員時代と同じレベルの保障が得られるため、安心して仕事に取り組めます。
税金対策の基本
独立後は自分で税金を計算し、納税する義務があります。
経費計上:
事業に関わる費用は「経費」として計上できます。交通費、消耗品費、通信費、工具代、打ち合わせの飲食代などが該当します。何が経費になるかを理解し、領収書を保管しておくことが重要です。
確定申告:
毎年3月15日までに、前年1月1日から12月31日までの所得を計算し、確定申告を行います。
社会保険の切り替え
会社員を辞めたら、社会保険の切り替えが必要です。
会社員時代の健康保険・厚生年金から、国民健康保険と国民年金に切り替えます。市区町村役場での手続きが必要です。
【要注意!】「偽装一人親方」問題とは?
特に建設業界で問題になりやすいのが「偽装一人親方」です。これは、実態は労働者であるにもかかわらず、形式上だけ一人親方として契約を結ばされている状態を指します。
リスク:
労働者としての保護(労災保険、最低賃金、残業代など)が受けられない、元請け企業も労働関係法令違反に問われる可能性があるなど、双方にとって大きなリスクがあります。
判断基準:
契約内容だけでなく、仕事の指示命令権がどこにあるか、時間的な拘束があるか、他の仕事を受けられないかなど、実態に基づいて判断されます。
対策:
不安な場合は、厚生労働省が策定した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」などを参照し、自分の働き方が適正か確認しましょう。
2024年問題も知っておこう(建設業の方へ)
2024年4月1日以降、建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、これまでの働き方が大きく変わる可能性があります。一人親方として独立する場合も、元請けとの関係でこの問題が影響するケースも出てくるかもしれません。常に最新情報をチェックし、柔軟に対応できるよう準備しておきましょう。
あなたはどっち?最適な働き方を見つけるための判断ポイント
一人親方と個人事業主、どちらの道を選ぶべきか悩んだら、以下のポイントで考えてみましょう。
業種で決める
建設業や運送業など、労災リスクの高い現場で働く場合:一人親方として労災保険特別加入を検討すべきです。万が一の怪我や病気で仕事ができなくなった時の安心感が全く違います。
Webデザイナーやコンサルタントなど、労災リスクが低い業種の場合は、個人事業主として特に問題ありません。
将来の事業規模で決める
将来的に従業員を増やし、事業を拡大したい明確なビジョンがある場合:最初から個人事業主として、法人化も視野に入れておくのがおすすめです。
あくまで「自分のペースで一人で稼ぎたい」という場合は、一人親方でも問題ありません。
リスク許容度で決める:
労災リスクに対して手厚い保障を求めるなら、労災保険に特別加入できる一人親方が安心です。
税金・社会保険の知識レベルで決める
複雑な手続きや税金計算に不安があるなら、専門家(税理士、社会保険労務士など)への相談も視野に入れましょう。
困った時はココに相談!役立つ情報源と相談窓口
独立後の不安を解消するためには、信頼できる情報源と相談先を知っておくことが大切です。
公的機関のウェブサイト
厚生労働省:
労災保険の特別加入制度や、フリーランスに関するガイドラインの最新情報が得られます。
国税庁:
開業届の提出方法や確定申告に関する情報、各種税金の詳しい解説が確認できます。
中小企業庁:フリーランスを含む中小企業・小規模事業者向けの支援策やガイドラインが掲載されています。
専門家への相談
税理士:
税金計算、確定申告、節税対策の相談。
社会保険労務士:
労災保険、社会保険の手続きや労務に関する相談。
行政書士:
開業届など各種許認可手続きの相談。
一人親方団体や業界団体:
特定の業種に特化した一人親方団体は、労災保険の加入手続き代行や、同業者同士の情報交換の場を提供しています。
まとめ:あなたの独立を応援!最適な一歩を踏み出そう
「一人親方」も「個人事業主」も、会社に縛られず自分の力で仕事をする素晴らしい働き方です。
一人親方は、特に労災リスクの高い業種で働く個人事業主が、労災保険に特別加入できるという大きなメリットを持つ形態です。
個人事業主は、より幅広い業種で、将来的に事業を拡大し、従業員を雇うことも可能な自由度の高い形態と言えます。
どちらの道を選ぶにしても、この記事で解説した「違い」を理解し、必要な手続きやリスク対策をしっかり行うことが、安心して独立し、事業を成功させるための鍵となります。
あなたの豊富な経験と技術を活かし、最適な働き方を見つけて、独立への一歩を踏み出してください。この記事が、あなたの未来を切り開く一助となれば幸いです。
独立って何から始めればいい?経営者になるための教科書公開中
「とりあえず独立したけど、営業や経営は初めてで手探り状態…」
そんな独立1〜3年目の水道工事業の社長に向けて、仕事を安定させる前段階から役立つ情報をまとめたページをご用意しました。
このページでは、
- まず何を準備すればいいか
- お客様をどう見つけ、どう信頼を得るか
- 少しずつ仕事を増やしていく方法
など、職人から経営者へとステップアップするための具体的なヒントを解説しています。
独立したてで「これからどう動けばいいか」に悩んでいる方はぜひご覧ください。
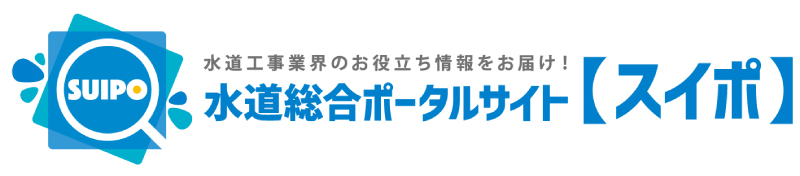
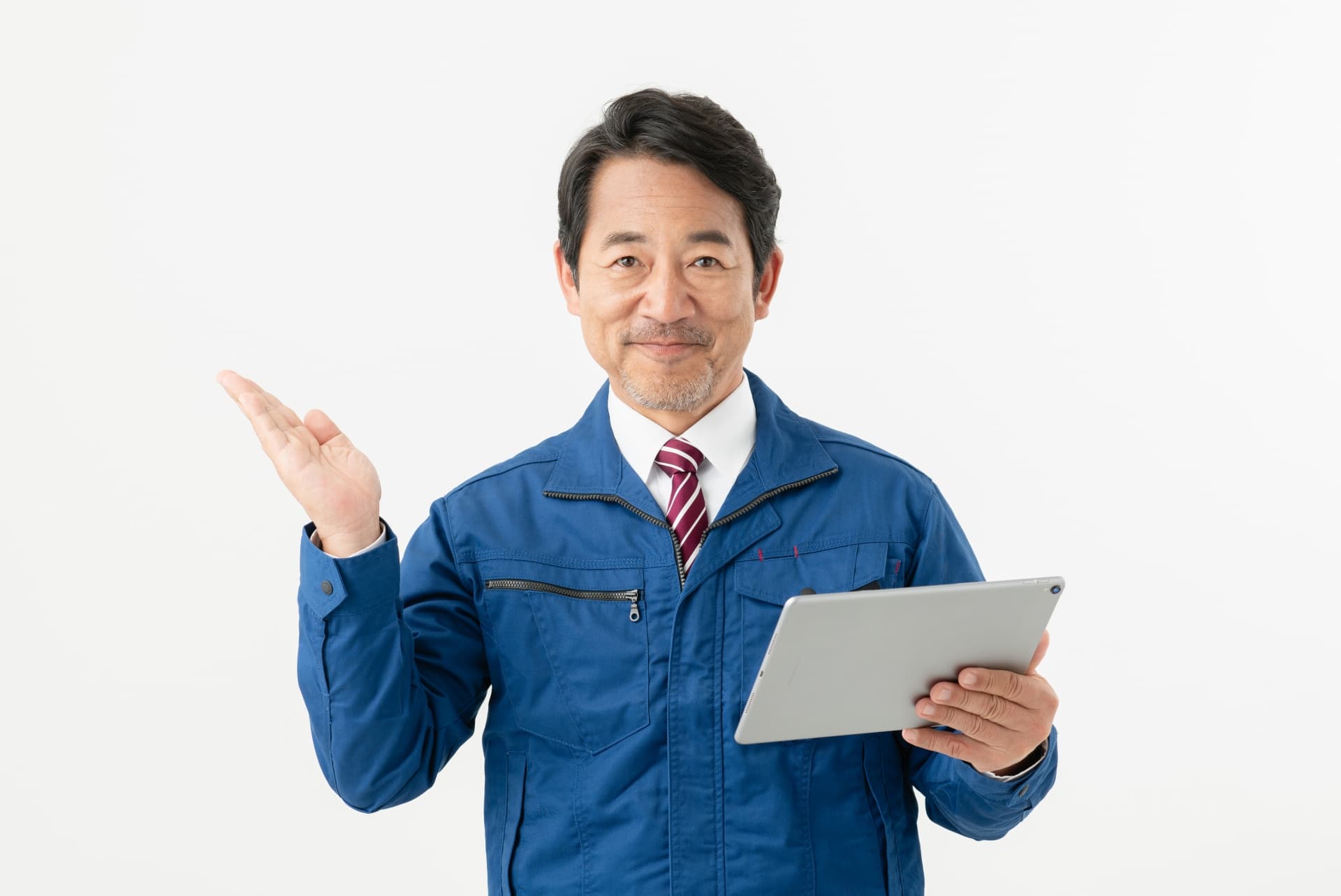


\【スイポ】サイトへのご意見募集してます/ 「こんなこと知りたい」、「ここが使いにくい」などの貴重なご意見を募集しております。