「建設業許可」と聞くと、手続きが複雑で難しそう、自分にはまだ関係ない、と感じる方もいるかもしれません。しかし、事業を拡大し、より大きな仕事に挑戦していくためには、この許可が非常に重要になります。
この記事では、独立したての建設業経営者の方に向けて、建設業許可の基本から、なぜ必要なのか、どうすれば取得できるのかをわかりやすく解説します。これを読めば、あなたの事業を次のステージに進めるための具体的な道筋が見えてくるはずです。
建設業許可の「なぜ?」を解消!その目的と、許可なしでもできること
まず、「そもそも建設業許可って何?」という疑問から解消していきましょう。
建設業許可は、建設業法に基づいて、国や都道府県から与えられる許可のことです。簡単に言うと、「一定規模以上の建設工事を請け負うために必要な“お墨付き”」と考えてください。
この許可制度があるのは、大規模な建設工事をきちんと管理し、皆さんが安心して工事を依頼できるような、健全な業界を育てるためです。
すべての工事に許可が必要かというと、そうではありません。実は、「軽微な建設工事」と呼ばれるものについては、許可がなくても請け負うことができます。
具体的には、以下の工事が「軽微な建設工事」に該当します。
- 1件の請負金額が消費税込みで500万円未満の工事
- 建築一式工事(※1)の場合は、請負金額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
※1 建築一式工事とは、複数の専門工事を組み合わせて総合的に実施する大規模な建築工事のことです。
あなたがもし、現時点で上記のような小規模な工事を中心に請け負っているのであれば、すぐに許可が必要というわけではありません。
しかし、材料費なども含めて500万円を超える工事や、さらに大きな工事を請け負いたい場合は、建設業許可が必須となります。事業の成長を考えるなら、いずれは取得を検討するタイミングが来るでしょう。
【水道工事店の皆さんへ】 水道工事において、個人宅のちょっとした水漏れ修理や蛇口交換など、金額の小さい工事は「軽微な建設工事」に該当し、許可がなくても請け負えます。しかし、アパートや店舗の給排水設備工事、公共施設の配管工事など、規模が大きくなればなるほど500万円を超えるケースは増えてきます。例えば、一棟まるごとの給排水設備工事では、あっという間に500万円を超えてしまうことも少なくありません。大きな仕事を受注していくためには、建設業許可が不可欠だと考えておきましょう。
建設業許可の有効期限って?更新を忘れるとどうなる?
一度許可を取れば終わり、ではありません。建設業許可には有効期限があり、許可日から5年間と定められています。
例えば、令和4年4月1日に許可を取得した場合、有効期限は令和9年3月31日までです。この期限が切れる前に、更新手続きを行う必要があります。うっかり更新を忘れてしまうと、せっかく取得した許可が失効してしまい、再び大規模な工事を請け負えなくなる可能性があります。
更新申請は、有効期間が満了する日の3ヶ月前から30日前までに行うのが一般的です。早めに準備を始めることが大切です。(※自治体によって異なる場合があります)
どんな許可を取ればいい?「知事許可」と「大臣許可」の違い、29種類の工事区分
建設業許可には、いくつかの種類があります。あなたの事業内容や規模に合わせて、どの許可を取るべきかを見極める必要があります。
1. 営業所の所在地による区分:都道府県知事許可 vs 国土交通大臣許可
これは、あなたの会社の営業所がどこにあるかで決まります。
- 都道府県知事許可: 営業所が1つの都道府県内にのみある場合。例えば、大阪府内にしか営業所がない場合は、大阪府知事許可を取得します。
- 国土交通大臣許可: 営業所が2つ以上の都道府県にわたってある場合。例えば、大阪府と兵庫県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可が必要です。
独立したばかりの頃は、まず都道府県知事許可からスタートすることが多いでしょう。
2. 工事内容による区分:29の業種
建設業の工事は、その内容によって29の業種に細かく分類されています。あなたが請け負いたい工事がどの業種に当たるのかを確認し、その業種の許可を取得する必要があります。
例えば、建物の内装工事を請け負うなら「内装仕上工事」、電気設備工事なら「電気工事」の許可が必要です。1つの許可で何でもできるわけではないので注意しましょう。
すべての業種を覚える必要はありませんが、代表的なものには以下のようなものがあります。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工工事
- 電気工事
- 管工事
- 内装仕上工事
- 解体工事
もし「複数の種類の工事を請け負いたい」という場合は、それぞれの工事に応じた許可を追加で取得していくことになります。
【水道工事店の皆さんへ】 あなたの事業の核となる給排水設備工事や配管工事は、ほとんどの場合「管工事」に該当します。また、場合によっては「水道施設工事」の許可も必要になることがあります。どの業種が必要か迷ったら、まず「管工事」の取得を目指すのが一般的です。
3. 元請けでの下請け発注額による区分:一般建設業許可 vs 特定建設業許可
これは、あなたが元請けとして工事を請け負った際に、下請け業者に発注する金額によって変わってきます。
- 一般建設業許可: 元請けとして請け負った工事で、下請けへの発注総額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)の場合に必要です。下請けとしてのみ仕事をする場合も、この一般建設業許可で問題ありません。
- 特定建設業許可: 元請けとして請け負った工事で、下請けへの発注総額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となる場合に必要です。
独立したばかりの段階では、まず「一般建設業許可」の取得を目指すのが一般的です。事業が大きくなり、大規模な工事で多くの下請けを使うようになったら、「特定建設業許可」へのステップアップを検討することになります。
建設業許可を取るための「5つの壁」を乗り越えよう!
建設業許可を取得するには、建設業法で定められたいくつかの要件をすべて満たす必要があります。これらは、あなたがきちんと建設業を運営できる能力と信頼性があるかを判断するための基準です。
1. 適切な経営体制があること(「経営業務管理責任者」の設置)
あなたの会社に、建設業の経営を適切に管理できる人がいることが求められます。具体的には、「経営業務管理責任者」と呼ばれる人が常勤している必要があります。
この人は、建設業に関して5年以上の経営経験があるなど、特定の要件を満たす必要があります。個人事業主であれば、あなた自身がその要件を満たす場合もありますし、法人であれば役員の中から選任することになります。
2. 各営業所に技術者がいること(「専任技術者」の設置)
それぞれの営業所には、その営業所で行う建設工事に関する知識や経験を持った「専任技術者」を常勤させる必要があります。
この技術者は、工事の契約や施工に関する技術的な指導・監督を行う役割を担います。保有する資格や実務経験によって、担当できる工事の種類や規模が変わってきます。
3. 真面目に仕事に取り組むこと(「誠実性」の確認)
過去に建設業法などの法律に違反したり、許可を取り消されたりといった不誠実な行為がないかが審査されます。法令を遵守し、健全な事業運営を行う意志があるかが問われます。
4. お金に困らないこと(「財産的基礎」の確認)
工事を途中で投げ出したり、未完成になったりしないよう、十分な資金力があるかもチェックされます。具体的には、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金を調達できる能力があることなどが求められます。
【独立したての水道工事店の皆さんへ】 「自己資本500万円以上」という要件は、独立したばかりの経営者にとっては大きな壁かもしれません。しかし、これは「今すぐに現金が500万円手元にないとダメ」というわけではありません。会社の貸借対照表の純資産の部が500万円以上であれば良いので、設立時の資本金や、その後の利益の蓄積でこの要件を満たすことも可能です。もし不足している場合は、金融機関からの融資(借入金)で一時的に資金を調達し、自己資本に計上することで要件を満たす方法もあります。この際、事業計画書をしっかり作成し、融資担当者に熱意と具体的な計画を伝えることが重要です。
5. 許可が出ない「欠格要件」に注意!
上記の要件を満たしていても、特定のケースに当てはまる場合は建設業許可を取得できません。
例えば、申請書類に嘘の記載があったり、会社の役員や個人事業主本人が過去に重い刑罰を受けてから5年が経っていない場合などが含まれます。
これらの要件は、すべて満たす必要があります。独立したばかりの経営者にとっては、特に「経営業務管理責任者」や「専任技術者」、そして「財産的基礎」の要件がハードルに感じられるかもしれません。しかし、これらをクリアすることで、信頼できる事業者としての証明になります。
建設業許可取得までの道のり:申請手続きと費用
実際に建設業許可を取得するには、いくつかのステップを踏んで申請手続きを進める必要があります。
1. 申請先を確認しよう
あなたの会社の営業所の所在地によって、申請先が異なります。
- 都道府県知事許可: 営業所のある都道府県庁(担当部署は都道府県によって異なります。例えば東京都なら都市整備局、千葉県なら土木事務所など)
- 国土交通大臣許可: 国土交通省の各地方整備局
事前にホームページなどで確認し、不明な場合は問い合わせてみましょう。
2. 必要書類を準備しよう
建設業許可の申請には、非常に多くの書類が必要です。主なものとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 許可申請書
- 工事経歴書
- 会社の財務諸表(損益計算書、貸借対照表など)
- 定款(法人の場合)
- 役員の情報に関する書類
- 専任技術者の資格や経験を証明する書類
- 営業所の場所を示す書類
これらの書類は、申請区分(法人か個人か、知事許可か大臣許可かなど)によって異なる場合があります。また、正本1部と、あなたの控え用として副本1部が必要になることが多いです。
書類の準備は時間と手間がかかる作業です。不備があると申請が受け付けられず、何度も足を運ぶことになりかねません。
3. 申請費用を知っておこう
建設業許可の申請には手数料が必要です。
- 新規で知事許可を取得する場合:9万円
- 新規で国土交通大臣許可を取得する場合:15万円
これは収入印紙などで納める費用です。この他に、各種証明書(登記事項証明書、納税証明書など)の取得費用も必要になります。
もし、ご自身での書類作成や手続きに不安がある場合は、行政書士などの専門家に依頼することも検討してみてください。依頼費用はかかりますが、スムーズな手続きで許可取得までの時間を短縮できるというメリットがあります。
【独立したての水道工事店の皆さんへ】 申請手続きは複雑で、慣れない書類作成に多くの時間を費やしてしまう可能性があります。本業に集中するためにも、行政書士への依頼は有効な選択肢です。また、自治体の商工会議所や中小企業診断士の窓口でも、許可取得に関する相談や、資金調達に関するアドバイスを受けられる場合があります。積極的に活用して、時間と労力を節約しましょう。
許可を取ると、あなたの事業はこんなに変わる!
建設業許可の取得は、手間も費用もかかりますが、それ以上の大きなメリットがあなたの事業にもたらされます。
1. 大規模工事の受注が可能に!売上アップのチャンス
これが最大のメリットです。許可がなければ請け負えなかった500万円以上の高額な工事を受注できるようになります。これにより、売上や利益が大きく伸びる可能性が広がります。
2. 社会的な信用度が格段に向上!仕事が増える
建設業許可を持っているということは、あなたの会社が厳しい要件をクリアしていることの証明になります。これにより、対外的な信用度が大幅にアップします。
- 元請け業者からの信頼が高まり、受注機会が増える
- 金融機関からの融資を受けやすくなる
- 取引先との契約がスムーズになる
など、ビジネスのあらゆる面で有利に働くでしょう。
3. 公共工事にもチャレンジできる!経営の安定化
公共工事の入札に参加するためには、建設業許可が必須です。公共工事は安定した受注が見込めるため、事業の安定化に大きく貢献します。許可を取得することで、新たなビジネスチャンスが生まれます。ƒ
【独立したての水道工事店の皆さんへ】 建設業許可を取得した後、公共工事を受注するためには、さらに経営事項審査(経審)という審査を受ける必要があります。経審の結果は点数化され、その点数に応じて入札に参加できる工事の規模が決まります。そして、実際に公共工事に入札するためには、各自治体の入札参加資格も取得しなければなりません。少し先のステップですが、許可取得はそのための最初の大きな一歩となります。
4. 法令遵守で安心!人材確保にも有利に
許可を取得することで、あなたが法律をきちんと守って事業を営んでいることを明確に示せます。これにより、無許可営業による罰則や業務停止といったリスクを回避できます。
また、特定の制度(例:技能実習生の雇用など)を利用できるようになるため、人材確保の面でも有利になることがあります。
許可取得は、あなたの「志」を実現するための第一歩
独立したばかりの建設業経営者にとって、建設業許可の取得は、今後の事業展開を大きく左右する重要なステップです。
「いつかは大きな仕事をしたい」「もっと社会に貢献できる事業にしたい」と考えているのであれば、ぜひ前向きに取得を検討してみてください。
最初はハードルが高く感じるかもしれませんが、一つひとつの要件を理解し、準備を進めていけば、必ず取得できます。この許可が、あなたの事業の可能性を広げ、夢を実現するための強力な武器となるはずです。
建設業許可に関するFAQ
Q1: 独立したばかりで、まだ小さな工事しか受注していません。建設業許可は必要ですか?
A1: 現時点で、1件の請負金額が消費税込みで500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)のみを請け負っているのであれば、いますぐ建設業許可は必要ありません。 これらは「軽微な建設工事」と呼ばれ、許可なしで合法的に行えます。
しかし、もし将来的に500万円以上の工事を受注したい、事業を拡大したいとお考えであれば、建設業許可は必須となります。早めに情報収集を始め、準備を進めることをおすすめします。
Q2: 建設業許可は、一度取得すればずっと有効なのでしょうか?
A2: いいえ、建設業許可には有効期限があります。許可日から5年間です。例えば、令和4年4月1日に許可を取得した場合、有効期限は令和9年3月31日までとなります。
許可が切れる前に更新手続きが必要です。一般的には、有効期限の3ヶ月前から30日前までの間に更新申請を行います。更新を忘れてしまうと許可が失効し、再び500万円以上の工事を請け負えなくなってしまうので、期限管理には十分注意しましょう。
Q3: 水道工事店を経営していますが、どの種類の建設業許可を取得すれば良いですか?
A3: あなたの事業の核となる給排水設備工事や配管工事は、ほとんどの場合「管工事」の建設業許可に該当します。まずはこの「管工事」の許可取得を目指すのが一般的です。
また、営業所が1つの都道府県内にのみある場合は「都道府県知事許可」を、2つ以上の都道府県にわたる場合は「国土交通大臣許可」を取得することになります。独立したばかりであれば、「都道府県知事許可」からスタートすることがほとんどでしょう。
元請けとして請け負う工事で、下請けに発注する金額が4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)であれば、「一般建設業許可」が必要です。大規模な下請け発注がない限りは、まず「一般建設業許可」の取得を目指してください。
Q4: 建設業許可を取得するために、自己資金が500万円ないとダメですか?
A4: 「自己資本の額が500万円以上」という要件はありますが、必ずしも現金で500万円を保有している必要はありません。 会社の貸借対照表における「純資産の部」が500万円以上であればこの要件を満たします。
もし自己資本が不足している場合は、設立時の資本金を増やす、または金融機関からの融資(借入金)で資金を調達し、自己資本に計上することで要件を満たせる場合があります。融資を受ける際は、しっかりとした事業計画書を作成し、金融機関にあなたの事業の成長性をアピールすることが重要です。
Q5: 建設業許可の申請手続きは複雑そうですが、一人でもできますか?
A5: 建設業許可の申請手続きは、必要書類が多く、専門的な知識も求められるため、非常に複雑で時間と手間がかかります。 ご自身で申請することも可能ですが、書類の不備があると再提出を求められ、許可取得までに時間がかかってしまう可能性があります。
ご自身の本業に集中するためにも、行政書士などの専門家に依頼することを検討してみても良いでしょう。費用はかかりますが、スムーズな手続きで早期の許可取得が期待できます。また、自治体の商工会議所や中小企業診断士の窓口でも、許可に関する相談やアドバイスを受けることができますので、活用してみるのも手です。
独立って何から始めればいい?経営者になるための教科書公開中
「とりあえず独立したけど、営業や経営は初めてで手探り状態…」
そんな独立1〜3年目の水道工事業の社長に向けて、仕事を安定させる前段階から役立つ情報をまとめたページをご用意しました。
このページでは、
- まず何を準備すればいいか
- お客様をどう見つけ、どう信頼を得るか
- 少しずつ仕事を増やしていく方法
など、職人から経営者へとステップアップするための具体的なヒントを解説しています。
独立したてで「これからどう動けばいいか」に悩んでいる方はぜひご覧ください。
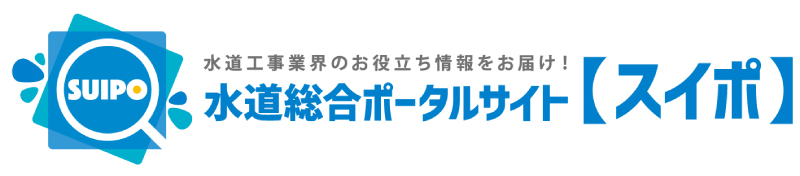



\【スイポ】サイトへのご意見募集してます/ 「こんなこと知りたい」、「ここが使いにくい」などの貴重なご意見を募集しております。