独立して会社を経営されている方のなかには、業務量の増加にともない「従業員を雇うタイミングはいつか」と悩まれている方もいるのではないでしょうか。
事業が軌道に乗り売上が上がっても、一人でこなせる業務には限界があるため、どこかのタイミングで人を雇うことを検討し始めるはずです。
そこで本記事では、独立した経営者が知るべき、人を雇うタイミングについて徹底的に解説していきます。
人を雇うべきタイミングはこの4つのサインで判断できる
会社経営において、人を雇うことは事業拡大の重要なステップですが、そのタイミングは慎重に見極める必要があります。
自身の業務負担や会社の状況を客観的に判断し、最適な時期に人材を確保することが、事業をさらに成長させるカギとなります。
具体的には、自身の業務量が限界を超えている、安定した売上が確保できているなど、人を雇うべきサインがいくつか存在します。
サイン1:業務量が限界を超えている
事業が軌道に乗り始めた独立経営者の皆様は、日々の業務量に圧倒され、夜遅くまで作業を続けている方も多いのではないでしょうか。
例えば、契約書作成や資料作成といった間接業務から、顧客対応やサービス提供といった直接業務まで、あらゆるタスクを一人でこなす状況が続いているかもしれません。
その結果、睡眠時間が削られ、疲れが蓄積し、集中力の低下から普段ならしないようなミスが増えていませんか。
日本政策金融公庫の2023年度の調査によると、起業家(事業に週35時間以上充てる者)の約半数(50.3%)が週50時間以上労働しているというデータがあります。また、1週間当たりの労働時間が5年前(2013年)の平均51.1時間から減少傾向にあるものの、長時間労働が依然として課題であると考えられます。このような状況は、事業の成長を阻害するだけでなく、経営者自身の健康にも悪影響を及しかねません。
また、従業員を雇用せず、一人で全てを抱え込んでいると、新しい顧客の獲得やサービスの改善など、本来注力すべき戦略的な業務に時間を割くことが難しくなります。
業務が多すぎて、目の前のタスクをこなすことで精一杯になり、将来を見据えた経営判断が鈍る可能性も出てきます。
このような状況に陥っている場合は、業務量が限界に達しているサインであり、従業員を雇うタイミングが来ていると判断できます。
サイン2:売上・利益が安定し、固定費が支払える見通しがある
人を雇う上で最も重要な判断基準の一つは、会社の売上と利益が安定し、人件費を含む固定費を継続的に支払う見通しが立つことです。
例えば、月に新規顧客が安定して5件以上獲得できており、その売上から従業員の給与や社会保険料などの固定費を支払っても、会社の利益が確保できる状態が目安となります。
人件費を売上総利益に対してどのくらいの割合に抑えるかは、業種や会社規模によって異なりますが、一般的には50%以下が適正値とされています。
もし、現時点で売上が不安定な場合や、毎月の変動が大きい場合は、人を雇うことが経営を圧迫するリスクを高める可能性があります。
まずは、売上予測を立て、最低でも6ヶ月から1年程度の固定費を賄えるだけのキャッシュフローがあるかを確認することが重要です。
さらに、季節変動などによって売上が増減する場合も考慮に入れ、余裕を持った資金計画を立てる必要があります。
固定費を支払える見通しが立つことで、従業員を安心して雇用でき、事業を継続的に成長させていく基盤を築くことができます。
サイン3:案件を断り始め、機会損失が発生している
事業が順調に成長し、業務量が増加していく中で、新たな顧客からの依頼やプロジェクトの相談が増えることは喜ばしいことです。
しかし、一人で対応できる業務量には限りがあり、結果としてせっかくの依頼を断らざるを得ない状況に直面していませんか。
例えば、既存の顧客対応で手一杯になり、新規の大型案件や魅力的な提携話であっても「人手が足りない」という理由で断念してしまうケースなどが考えられます。
このような状況は、単に目の前の案件を失うだけでなく、将来的な事業拡大のチャンスを逃す「機会損失」に直結します。
特に、一度断ってしまった顧客が、再度依頼してくれる保証はありません。
これは、売上向上や事業成長の大きな足かせとなるだけでなく、企業のブランドイメージにも影響を与えかねません。
例えば、専門性の高い案件や緊急性の高い依頼に対応できない場合、顧客からの信頼を損なう可能性もあります。
このような状況に陥っている場合は、明確な「人を雇うべきサイン」と捉えることができます。
新たな人材を確保することで、断っていた案件に対応できるようになり、売上拡大はもちろんのこと、企業としての信頼性も向上させることが期待できます。
サイン4:経営者自身が“作業員化”して戦略時間が消えている
事業が軌道に乗り、日々の業務に追われている経営者の方の中には、本来の経営戦略を練る時間が取れないと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
例えば、顧客への連絡、資料作成、経理処理といった定型的な「作業」に忙殺され、新規事業の立案や市場分析、競合他社の動向調査といった、将来に向けた重要な「戦略」を考える時間がほとんどなくなってしまうケースです。これは、経営者自身が「作業員」化してしまっている状態であり、事業の成長を停滞させる大きな要因となります。
本来、経営者は会社の羅針盤となり、中長期的な視点から事業全体を俯瞰し、戦略的な意思決定を下すことが役割です。しかし、目の前の業務に追われていると、どうしても短期的な視点に陥りがちになり、重要な経営判断が後回しになったり、機会を逃したりするリスクが高まります。実際に、中小企業の経営者を対象とした調査では、約7割の経営者が労働時間管理に課題を感じているという結果が出ています。
このような状況は、事業の拡大を阻害するだけでなく、経営者自身のモチベーション低下にも繋がりかねません。経営者自身が作業から解放され、戦略的な業務に集中できる時間を確保するためにも、人材の採用は不可欠なステップと言えるでしょう。
人を雇うことで得られるメリット
人を雇うことで得られるメリットは多岐にわたりますが、大きく3つ紹介します。
最も大きな点は「時間」が増えることです。これにより、経営者本来の仕事である、事業の将来を見据えた戦略立案や新規事業の開拓といった、より重要度の高い業務に集中できるようになります。
また、人材が増えることで、会社の売上を最大化し、顧客満足度を向上させることも可能です。
一人では対応しきれなかった多くの案件に対応できるようになり、結果として売上アップに繋がります。
そして、人を雇うことは経営者の生活の質を改善し、より健全な会社成長を促します。
業務量が分散されることで、経営者は長時間労働から解放され、プライベートな時間や休息を確保できるようになります。
時間が増え、経営者本来の仕事に集中できる
最も大きな点は「時間」が増えることです。
これにより、経営者本来の仕事である、事業の将来を見据えた戦略立案や新規事業の開拓といった、より重要度の高い業務に集中できるようになります。
例えば、これまで一人でこなしていた顧客対応や経理業務などを従業員に任せることで、経営者は市場調査や競合分析、新たなサービスの開発といった、会社の成長に直結する業務に時間を投入できるようになります。
売上の最大化・顧客満足度の向上
人材が増えることで、会社の売上を最大化し、顧客満足度を向上させることも可能です。
一人では対応しきれなかった多くの案件に対応できるようになり、結果として売上アップに繋がります。
さらに、従業員が加わることで、顧客へのサービス提供体制が強化され、きめ細やかなサポートが可能になるため、顧客満足度の向上にも貢献します。
例えば、これまで対応できなかった緊急の依頼や、専門性の高い案件にも対応できるようになり、顧客からの信頼を獲得しやすくなります。
経営者の生活の質が改善し、より健全な成長ができる
そして、人を雇うことは経営者の生活の質を改善し、より健全な会社成長を促します。
業務量が分散されることで、経営者は長時間労働から解放され、プライベートな時間や休息を確保できるようになります。
これにより、心身ともにリフレッシュでき、ストレスが軽減され、より良い状態で経営判断を下せるようになります。
健康な経営者が健全な会社を育むという好循環を生み出し、持続的な事業成長を実現できるでしょう。
雇う前に必ず決めておきたいこと
人を雇うことは、事業拡大において非常に有効な手段ですが、同時に責任も伴います。
後々のトラブルを防ぎ、円滑な組織運営を行うためには、雇用前に明確にしておくべき重要な点がいくつかあります。
任せる業務の明確化
新たに雇用する従業員に「何を任せるのか」を具体的に明確化することが不可欠です。
漠然とした業務ではなく、例えば「顧客リストの作成とアポイント獲得」「ウェブサイトの更新とSNS運用」「経理データの入力と請求書発行」といったように、具体的な業務内容と範囲を言語化しておく必要があります。
これにより、従業員も自分の役割を理解しやすくなり、業務のミスマッチを防ぐことができます。
成果基準・評価方法の設定
任せた業務に対する「成果基準と評価方法」を事前に設定しておくことが重要です。
例えば、「月に新規アポイントを10件獲得」「週にブログ記事を3本公開」「毎月の経費精算を期日までに完了」といった具体的な目標値を設定し、その達成度合いをどのように評価するのかを明確にしておくことで、従業員は目標に向かって意欲的に業務に取り組めます。
また、公平な評価制度は従業員のモチベーション維持にも繋がります。
教育・引き継ぎの流れを整えておく
そして、最も重要なことの一つが、「教育・引き継ぎの流れ」を事前に整えておくことです。
新しい従業員がスムーズに業務を開始できるよう、マニュアルの作成やOJT(オンザジョブトレーニング)の計画を立てておくことが求められます。
例えば、既存の業務フローや使用するツール、社内ルールなどをまとめた資料を用意したり、最初の数週間は経営者自身がつきっきりで指導する期間を設けるなど、具体的な引き継ぎ計画を立てましょう。
この準備を怠ると、従業員が業務に慣れるまでに時間がかかりすぎたり、経営者自身が通常業務に加えて教育に多くの時間を割くことになり、かえって負担が増える可能性があります。
初めて人を雇うときに実際にかかる費用と必要な手続き
初めて会社で人を雇う際には、給与以外にも様々な費用が発生することや、見落としがちなコストがあることを理解しておく必要があります。
給与以外にかかる「会社負担の費用」
まず、給与以外に会社が負担する費用として最も大きいのが社会保険料です。
具体的には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料があり、これらは従業員の給与から天引きされる分と会社が負担する分に分かれています。
例えば、健康保険料と厚生年金保険料は労使折半が基本であり、従業員の給与額に応じて会社も同額を負担することになります。
この社会保険料は、従業員の給与の約15%程度を会社が負担する計算になるため、月給20万円の従業員を雇う場合、会社は約3万円の社会保険料を別途負担することになります。
採用時に発生しやすい見落としコスト
次に、採用時に発生しやすい見落としコストとして、求人広告費や採用活動にかかる人件費が挙げられます。
例えば、採用媒体に求人広告を掲載する場合、数万円から数十万円の費用がかかることが一般的です。
また、面接や書類選考といった採用活動にも、経営者自身の時間や労力がかかります。
さらに、入社後の研修費用や、備品購入費(デスク、PC、文房具など)も考慮に入れる必要があります。特にPCはスペックによって数万円から数十万円かかるため、事前に必要なものをリストアップし、予算を組んでおくことが重要です。
雇った後に必要な手続きと準備
最後に、従業員を雇った後に必要な手続きと準備についてです。
まず、労働基準監督署への届出や、ハローワークでの雇用保険の加入手続き、年金事務所での健康保険・厚生年金保険の加入手続きが必要になります。
これらの手続きは期限が定められているものもあるため、速やかに対応することが求められます。
また、就業規則の作成や労働条件通知書の交付も法的に義務付けられています。
特に就業規則は、従業員が10人以上になる会社で作成・届出の義務があります。
これらの準備を怠ると、後々トラブルの原因となる可能性もあるため、専門家(社会保険労務士など)に相談しながら進めることをおすすめします。
まとめ
独立した経営者にとって、人を雇うことは事業を成長させる上で非常に重要な判断ですが、そのタイミングを見極めるのは難しいものです。
業務過多、売上・利益の安定、機会損失の発生、経営者の作業員化といったサインが見られたら、雇用を検討する良い機会と言えます。
人を雇うことで、時間が増え経営者本来の仕事に集中できる、売上の最大化や顧客満足度の向上に繋がる、経営者の生活の質が改善されるといったメリットがあります。
ただし、雇用前には任せる業務の明確化、成果基準や評価方法の設定、教育・引き継ぎの流れを整えておくことが不可欠です。
また、初めて個人で人を雇う際には、給与以外に社会保険料などの会社負担の費用や、求人広告費などの見落としコストが発生します。
さらに、労働基準監督署やハローワーク、年金事務所への届出といった必要書類を伴う手続きも多岐にわたります。
これらを把握し、計画的に進めることが、スムーズな人材採用と事業の持続的な成長に繋がります。
Q1. どれくらい忙しくなったら、人を雇うタイミングだと判断すべきですか?
A. 一つの目安は「本来の経営判断に使う時間がなくなっているかどうか」です。
夜遅くまで作業が続く、ミスが増える、案件の問い合わせを断り始めた──こうした状態は典型的な“雇うべきサイン”です。業務量が限界を超えていると、売上の伸びよりも失う機会の方が大きくなります。
Q2. 売上がどれくらい安定していれば、雇っても大丈夫ですか?
A. 6〜12ヶ月分の人件費と固定費をカバーできる見通しが持てる状態が目安です。
月単位の売上が極端に上下している場合はリスクがありますが、「毎月ある程度の売上が継続している」「案件を断ってしまうことが増えてきた」なら、雇用が成長のブレーキを外すきっかけになります。
Q3. 初めての採用で、まず何を任せればいいですか?
A. 経営者自身の時間を奪っている“作業的な仕事”から切り出すのが正解です。
例:
・見積書・請求書の作成
・顧客対応の一部
・SNS更新、資料作成、データ入力
これらを手放すだけで、経営者は戦略や案件獲得に時間を割けるようになります。
Q4. 給与以外にどんな費用がかかるか、イメージがつきません…
A. 社会保険料(会社負担分)が最も大きく、給与の約15%が目安です。
さらに、PC・デスクなどの備品費、求人広告費、研修期間の時間コストも発生します。
ただし、これらは「案件を断る機会損失」と比較すると、多くの場合“投資”として回収できます。
Q5. 正社員を雇うのが不安です。もっとリスクを抑えた始め方はありますか?
A. あります。業務委託、パート、時短社員などからスタートする方法です。
最初からフルタイムを採用せず、
・まず小さく任せてみる
・相性や業務量を見ながら徐々に拡大
といった“段階的な採用”なら、経営リスクを大幅に下げられます。
独立って何から始めればいい?経営者になるための教科書公開中
「とりあえず独立したけど、営業や経営は初めてで手探り状態…」
そんな独立1〜3年目の水道工事業の社長に向けて、仕事を安定させる前段階から役立つ情報をまとめたページをご用意しました。
このページでは、
- まず何を準備すればいいか
- お客様をどう見つけ、どう信頼を得るか
- 少しずつ仕事を増やしていく方法
など、職人から経営者へとステップアップするための具体的なヒントを解説しています。
独立したてで「これからどう動けばいいか」に悩んでいる方はぜひご覧ください。
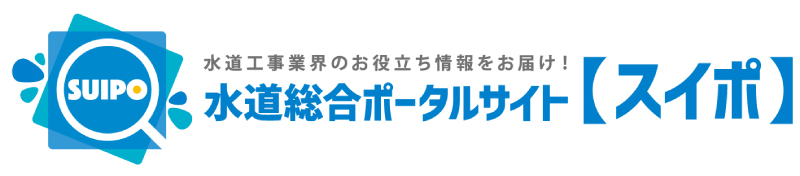



\【スイポ】サイトへのご意見募集してます/ 「こんなこと知りたい」、「ここが使いにくい」などの貴重なご意見を募集しております。