はじめに~ 職人から社長へ、数字の壁にぶつかっていませんか?
独立して1〜3年目の水道工事業の社長さん、こんな悩みはありませんか?
- 「現場は順調だけど、なぜかお金が残らない…」
- 「見積りと実際の支出が合わない…」
- 「税理士に任せきりで、数字のことがよくわからない…」
これは、原価管理ができていないことが原因かもしれません。
職人時代は、与えられた仕事をこなすことで評価されましたが、社長になると「お金を残す」ことが評価軸に変わります。そのためには、工事ごとの収支をしっかりと把握する「原価管理」の知識と実践が不可欠です。
原価管理とは?:現場ごとの「お金の流れ」を見える化すること
原価管理とは、工事ごとの収支を把握し、利益を確保するための管理手法です。簡単に言えば、「いくらかかって、いくら残ったか」を現場ごとにきちんと見えるようにすることです。
原価の主な内訳
- 直接費:材料費、労務費、外注費など、現場ごとに直接発生する費用
- 間接費:現場管理費、共通仮設費、一般管理費など、複数現場にまたがる費用
例えば、材料費はその現場だけの費用なので「直接費」、会社の事務所の家賃や事務員の人件費は「間接費」にあたります。
「粗利=売上-原価」の仕組みを知る
この原価管理ができていないと、利益がどこで消えているのかがわかりません。見積りでは利益が出ると思っていたのに、終わってみたら赤字だったということも起こりえます。
だからこそ、粗利(売上-原価)を正確に把握することが重要なのです。
原価管理の重要性:なぜ現場別に管理する必要があるのか?
建設業の特性として、工事ごとに収支構造が違うという点があります。たとえ同じ配管工事でも、現場条件や資材の価格、作業員の経験によってコストは変わります。
なぜ「全体の数字」ではダメなのか?
毎月の売上や利益を会社全体でざっくり把握していても、実際には、どの現場で稼ぎ、どの現場で損しているのかが見えなければ、経営判断ができません。数字を見ても「どこを改善すれば良いのか」が分からないのです。
原価管理によるメリット
- 赤字工事の早期発見:赤字になりそうな工事を途中で把握し、対応が可能に
- 見積り精度の向上:過去の実績を参考に、より正確な見積りが作成できる
- 利益率の改善:無駄な支出を削減し、効率的に利益を出す体質へ
- 経営判断のスピード化:数字に基づいた素早い意思決定が可能になる
原価管理のステップ:実践的な始め方
ステップ1:実行予算の作成
工事が始まる前に、実行予算を作成しましょう。
これは、工事にかかる予定の費用を見積もって、収支計画を立てることです。例えば、
- 材料費:◯◯万円
- 人件費:◯◯万円(何人工×単価)
- 外注費:◯◯万円
- 経費:◯◯万円
などを見積もっておき、最終的に「この工事でいくら利益を出すか」を明確にします。
ステップ2:工事台帳の作成と記録
工事が進む中で、**実際にかかった費用を記録するための「工事台帳」**を作ります。
これは、日々の支出(材料購入・外注費・交通費など)を現場ごとに記録していく台帳です。
この情報を記録しておくことで、後から「予算とどれだけズレがあったか」が比較できるようになります。
ステップ3:月次での原価集計と分析
月に1回は、各現場の予算と実績を比較し、差異があればその原因を分析します。
- 材料が予定より多く必要になったのか?
- 作業が遅れて人工が増えたのか?
- 外注に出す範囲が広がったのか?
こうした差異の原因を見つけて対策を打つことで、次回の工事での改善につながります。
原価管理の実践例:ある水道工事業者の取り組み
たとえば、神奈川県で個人事業として始めた水道工事店「たかはし設備」さんでは、創業2年目に原価管理を導入しました。
それまで、「勘」と「経験」に頼って現場を回していたため、収支はなんとなくの把握にとどまり、年度末に税理士から「思ったほど利益が出ていないですね」と言われて初めて気づく状況でした。
そこで、
- エクセルで簡単な工事台帳を作成
- 毎現場ごとに予算を立て、工事完了後に実績を入力
- 月に1回、工事ごとの粗利をチェック
という仕組みを社内で運用したところ、1年後には赤字工事が半減し、見積もりの精度も大きく改善しました。
「感覚」ではなく「数字」で判断することで、会社全体の安定感が増したといいます。
原価管理を支援するツールの活用
原価管理を効率よく、正確に行うには、ITツールの活用が非常に有効です。
専門システムの特徴
たとえば「要 〜KANAME〜」や「KAKUSA」などの建設業向け原価管理ソフトは、
- 工事ごとの実行予算の作成
- 支出の記録(材料・外注・労務など)
- 月次集計と利益分析
などの機能を備え、事務作業の効率化と数字の精度アップを実現します。
また、帳簿記入の手間が減り、他の業務に時間を使えるようになるのも大きなメリットです。
小規模事業者でも導入可能
「うちは小さいから…」と感じるかもしれませんが、最近では月額数千円から使えるクラウド型のツールも登場しています。
帳票作成、自動集計、グラフ表示など、日々の数字の管理が簡単になり、初めての人でも扱いやすい設計です。
まとめ:原価管理で利益を最大化しよう
原価管理は、建設業において「利益を出すための最も重要な仕組み」の一つです。
現場ごとの収支を把握し、赤字の芽を早期に潰すことで、経営の安定と成長が見えてきます。
まずは、簡単なエクセル管理からでも良いので、「現場ごとに収支を管理する」習慣をつけましょう。
そして、事業の成長に合わせて、専用の原価管理ソフトの導入を検討し、より精度の高い経営管理を目指していきましょう。
よくある質問
Q1. なぜ水道工事業では現場ごとに原価管理をする必要があるのですか?
A. 水道工事は現場ごとに条件やコスト構造が異なるため、会社全体の数字だけを見ても、どの現場が利益を出しているのか、どこで赤字になっているのかが分かりません。現場別に原価を管理することで、赤字工事を早期に発見したり、見積りの精度を高めたりすることができます。
Q2. 原価管理を始めるにはどんなステップがありますか?
A. まず工事ごとに実行予算を作成し、次に工事台帳を使って実際の支出を記録します。そのうえで、月に一度は予算と実績を比較し、差があれば原因を分析します。このサイクルを繰り返すことで、次の工事に活かせる改善点が見えてきます。
Q3. 小規模な事業でも原価管理システムを導入するメリットはありますか?
A. はい、あります。最近は月額数千円程度で使えるクラウド型の原価管理ツールもあり、エクセルより簡単に数字の見える化ができます。手間を減らしながら正確な管理ができるため、小規模事業者でも十分な効果を得られます。
独立って何から始めればいい?経営者になるための教科書公開中
「とりあえず独立したけど、営業や経営は初めてで手探り状態…」
そんな独立1〜3年目の水道工事業の社長に向けて、仕事を安定させる前段階から役立つ情報をまとめたページをご用意しました。
このページでは、
- まず何を準備すればいいか
- お客様をどう見つけ、どう信頼を得るか
- 少しずつ仕事を増やしていく方法
など、職人から経営者へとステップアップするための具体的なヒントを解説しています。
独立したてで「これからどう動けばいいか」に悩んでいる方はぜひご覧ください。
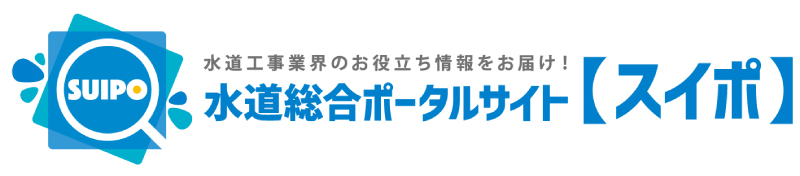


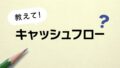
\【スイポ】サイトへのご意見募集してます/ 「こんなこと知りたい」、「ここが使いにくい」などの貴重なご意見を募集しております。