会社の書類や求人募集で、ホームページの記入欄を見て「そういえば自社にはホームページがないな」と感じた建設業の経営者の方は多いのではないでしょうか。
会社の看板としてホームページはあった方が良さそうだと感じつつも、ホームページ制作にかかる費用や維持の労力を考えると、なかなか踏み出せないのが実情かもしれません。
本記事では、建設業におけるホームページの必要性について、さまざまな目的別にメリットとデメリットを徹底解説し、本当に必要かどうかを判断するための一助となる情報をお届けします。
結論、ホームページが必要かどうかは目的によって変わる
ホームページは、現代ビジネスにおいて必須のツールだと認識されがちですが、実際には「あくまでも目標達成のための手段の一つ」に過ぎません。
ホームページを持つこと自体が目的になってしまうと、運用が形骸化したり、費用対効果が見合わなかったりする可能性があります。
そのため、ホームページが必要かどうかは、どのような目標を達成したいのか、具体的に何をしたいのかという「目的」によって大きく変わるのです。
例えば、新しい人材の採用を強化したいのか、特定エリアの個人顧客からの問い合わせを増やしたいのか、あるいは企業間の取引を拡大したいのかなど、業種や目指すゴールによってホームページに求める役割は異なります。
建設業においても同様で、例えばBtoBの取引が中心で既存顧客との関係性が強固であれば、緊急でホームページが必要となるケースは少ないかもしれません。
しかし、採用活動を強化したい場合や、元請けからの信頼性を高めたい場合には、会社の顔となるホームページが非常に重要な役割を果たすことがあります。
だからこそ、ホームページを制作する前に、まず「ホームページを使って何を叶えたいのか」という目的を明確にすることが最も重要です。
この目的が曖昧なままホームページ制作を進めても、期待する効果は得られにくいでしょう。
自社の現状と課題を深く掘り下げ、ホームページを通じて解決したい具体的な目標を設定することが、その必要性を判断する上での第一歩となります。
目的別に見るホームページの必要性
目的を明確にすることでホームページの必要性が判断できると理解できたものの、具体的な目的が定まった際に、それでもホームページが本当に必要なのかと疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。
建設業ではホームページの運用方法が他業種と異なることも多く、その必要性をイメージしにくいかもしれません。
そこで、ここでは目的別にホームページの必要性について詳しく解説していきます。
一般家庭(個人客)の新規案件獲得が目的の場合
一般家庭を対象とした新規案件獲得を目指す場合、ホームページは必須のツールと言えます。
住宅のリフォームや修繕など、家に何らかの問題が発生した際、多くの方がまずインターネットで情報を検索するためです。
もしホームページが存在しなければ、顧客はあなたの会社を見つけることができず、実質的に「存在しない」のと同じになってしまいます。
競合他社がホームページで情報発信している中で、自社が情報を持たないことは、機会損失に直結するでしょう。
ホームページは24時間稼働するため、会社の営業時間外でも顧客からの問い合わせを受け付けることが可能です。
ホームページを通じて、施工事例やお客様の声、料金体系などを明確に提示することで、潜在顧客の信頼獲得と問い合わせへの導線を構築できます。
一般企業の新規案件獲得が目的の場合
一般企業が取引先の場合でも、ホームページは作成した方が良いでしょう。
これは、一般家庭を取引先とする場合と似ており、情報がない会社は存在しないのと同じだと見なされやすいからです。
特に、既存の取引先や紹介以外の新規案件を獲得したいのであれば、自社の情報を積極的に発信することが重要です。
ただし、一般企業からの集客は、担当者と決済者が異なるケースが多いため、ホームページからの直接的な問い合わせに繋がりにくい側面があります。
そのため、会社情報を発信する程度に留め、費用を抑えたホームページでも十分な効果が期待できる場合があります。
採用が目的の場合
採用活動が目的であれば、ホームページは必須のツールです。
最近はワークライフバランスを重視する求職者が多く、仕事内容はもちろんのこと、安心して働ける会社なのかという点を特に注視しています。
そのため、ハローワークや求人サイトに掲載できる情報だけでは不十分で、なかなか応募に繋がりません。
SNSを活用して自社情報や社風を発信するのも効果的ですが、新卒採用や第二新卒を狙う場合は、親御さんや学校の就職担当者が検索する可能性が高いため、信頼性という観点からもホームページの有無が非常に重要になります。
自社情報の認知・拡大が目的の場合
自社の認知度向上や事業拡大を目指す場合、ホームページは非常に便利なツールです。
InstagramやX(旧Twitter)などのSNSでも情報発信は可能ですが、ホームページは会社の公式情報として最も信頼性の高い情報源となります。
特に、建設業の経営者様が社名で検索された際に、自社の情報が全く表示されないと、潜在的な顧客や取引先からの信頼を損なう可能性があります。
また、自社名で検索した際に、誤った情報が掲載された見慣れないページが表示されたり、同じ会社名の別会社がGoogleマップで「閉業」と表示されたりするケースも稀にあります。
このような状況は、企業の信用を著しく低下させることにつながりかねません。
ホームページは企業の信頼性を高め、会社の顔として正確な情報を発信する重要な役割を担っています。
おすすめのホームページを作る方法
それでは実際にホームページを作成するとなった際、どのような方法があるのかご紹介します。
ホームページを制作する方法は、大きく分けて4つあります。
- 無料サービスを使う(Googleサイト・ペライチなど)
- 自作する(WordPressなど)
- 有料の簡易ホームページサービスを使う(Jimdo・Wixなど)
- 制作会社に依頼する
それぞれにメリットとデメリットがあるため、ご自身の目的や予算、スキルレベルに合わせて最適な方法を選ぶことが重要です。
無料サービスを使う(Googleサイト・Jimdo・Wixなど)
先ほどご紹介したような、自社の社名で検索した際に別会社の情報が表示されたり、誤った情報が掲載されていたりするなどの状況の場合は、費用をかけずにホームページを作成できる無料サービスを活用することがおすすめです。
具体的なサービスとしては、Googleサイト、Jimdo(ジンドゥー)、Wix(ウィックス)などが挙げられます。
これらのサービスの最大のメリットは、無料で手軽にホームページを作成できる点にあります。
また、無料で利用できるテンプレートが豊富に用意されているため、専門知識がない方でもプロが作成したような品質の高いホームページを比較的簡単に作成できるでしょう。
一方でデメリットとしては、自分でホームページを作成する必要がある点が挙げられます。
これらのサービスは、プログラミングコードを直接編集するような専門知識がなくても、直感的な操作で作成できるように設計されていますが、初めて利用する場合は慣れるまでに時間がかかる可能性があります。
特に、レイアウトの調整やコンテンツの配置など、細部にこだわると多くの時間を要することもあります。
そのため、時間と手間をかけずにすぐにでもホームページを公開したいという場合には、不向きな選択肢となるかもしれません。
あくまで、とりあえず会社の情報を発信したい、という初期段階での活用に適していると言えるでしょう。
自作する(WordPressなど)
ある程度のWeb知識をお持ちの場合で、時間に余裕があり、ホームページの内容を細部までこだわりたい、Webサイトの運用スキルを身につけたいという意欲がある方には、WordPress(ワードプレス)などのCMS(コンテンツ管理システム)を利用して、ご自身でホームページを自作するのがおすすめです。
最近では、多くのレンタルサーバーでWordPressの自動インストール機能が提供されており、専門的な知識がなくても比較的簡単に導入できます。
例えば、さくらインターネットやエックスサーバーなどの主要なレンタルサーバーでは、管理画面から数クリックでWordPressの設置が完了し、すぐにホームページを作ることが可能になっています。
この方法の大きなメリットは、制作会社に依頼するよりも大幅に費用を抑えられる点です。
レンタルサーバー代とドメイン代(年間数千円~1万円程度)のみでホームページを運用できるため、初期投資を抑えたい場合に最適です。
また、デザインや機能にこだわりたい場合も、WordPressには豊富な無料・有料テーマが存在するため、比較的自由にカスタマイズできる柔軟性も魅力です。
ただし、サーバーやWordPressの管理、セキュリティ対策、問題発生時のトラブルシューティングなどはすべてご自身で行う必要があります。
特に、Webサイトの知識が全くない状態で始める場合は、学習コストがかかり、時間と労力がかかる可能性があります。
有料の簡易ホームページサービスを使う(ペライチなど)
簡単にホームページを作成したいけれど、操作に自信がなく、費用もできるだけ抑えたいと考える建設業の経営者の方には、有料の簡易ホームページサービスが大変おすすめです。
代表的なサービスとして「ペライチ」などがあり、これらはGoogleサイトやJimdo、Wixといった無料サービスと同様に、直感的な操作でホームページを制作できるのが大きな特長です。
例えば、ペライチではテンプレートを選んでテキストや画像を挿入するだけで、プロフェッショナルな見た目のページを簡単に作成できます。
さらに、困ったときには電話やメールでのサポートを受けられるため、初めてホームページを作成する方でも安心して進められる点がメリットです。
無料サービスでは自分で解決しなければならない問題も、有料サービスならサポート体制が整っているため、時間の節約にもつながります。
ペライチには無料プランと有料プランが存在します。無料プランには累計1万PV(のべ1万人の閲覧)の制限がありますが、有料プランを1ヶ月間無料で試せる「お試しビジネスプラン」も提供されています。
ただし、すべての有料簡易ホームページサービスに共通するものではないため、各サービスの提供内容を確認することをおすすめします。この期間中に、操作性や提供される機能、サポート体制などをじっくり評価し、納得した上で本格的に導入を検討できるため、失敗のリスクを低減できます。
例えば、ペライチの無料プランや「お試しビジネスプラン」を利用して、会社の紹介ページや問い合わせフォームを作成し、どの程度の労力で実現できるか試してみるのも良いでしょう。
制作会社に依頼する
ある程度の費用をかけてでも、ホームページ制作の目的を達成したい場合は、専門の制作会社に依頼するのがおすすめです。
制作会社はホームページをきれいに作るだけでなく、検索エンジンで上位表示させるためのSEO対策など、集客に繋がる施策も提供しています。
ただし、制作会社によって得意分野や料金体系が異なるため、自社の目的を明確にして選ぶことが大切です。
例えば、建設業界に特化した制作会社であれば、業界特有の専門用語やニーズを理解しているため、打ち合わせもスムーズに進み、より効果的なホームページを制作できるでしょう。
制作会社に依頼する最大のメリットは、プロの知識と技術によって高品質なホームページが期待できる点です。
デザイン性はもちろんのこと、採用活動を目的とするなら求職者に響くコンテンツ、新規案件獲得が目的なら集客に強いサイトなど、目的に合わせた最適な提案を受けられます。
また、ホームページ公開後の運用サポートやSEO対策、Web広告運用など、多岐にわたるサービスを提供している会社も多く、継続的な効果改善が見込めます。
一方でデメリットとしては、費用が高額になる傾向がある点です。ホームページ制作の費用は数万円から100万円以上と幅広く、依頼する内容やページ数、機能によって大きく変動します。
特に、オリジナルデザインや複雑なシステムを構築する場合は高額になりがちです。
しかし、費用対効果を重視し、目的を達成するための投資と捉えれば、長期的に見てもメリットは大きいと言えるでしょう。
制作会社を選ぶ際には、建設業での実績が豊富か、サポート体制が充実しているか、費用内訳が明確かといった点を比較検討することが重要です。
制作会社にホームページ作成を依頼する際の注意点
ホームページ制作を制作会社に依頼する際、特に注意すべきは、担当者が退職してログイン情報が不明になったり、依頼した制作会社が倒産したりするケースです。
実際に、高額な費用を投じて制作したにもかかわらず、その後の更新や管理ができなくなるという事態は少なくありません。
WEB業界は技術力さえあれば個人でも参入しやすく、設立から数年で会社がなくなってしまうケースも散見されます。
このようなリスクを避けるためにも、制作会社を選ぶ際には慎重な見極めが不可欠です。
具体的には、下記の2点に注目することが重要です。
- 自社の目的を達成できるホームページを制作してくれる会社であるか
- 長期的に安定して経営していける会社であるか
会社の安定性を判断する一つの目安として、例えば創業からの年数や、建設業界での実績、公開されている取引先実績などを確認してみるのも良いでしょう。
また、契約時にはホームページの管理情報や、更新・修正に関する取り決め、万が一の際のデータ引き渡しなどについて、明確に書面で取り交わしておくことが肝心です。
そうすることで、将来的に問題が発生した場合でもスムーズに対応でき、せっかく制作したホームページが無駄になることを防げます。
単に「良いデザイン」や「安い費用」だけで選ぶのではなく、長期的な視点を持って信頼できるパートナーを見つけることが、成功への鍵となります。
まとめ
建設業においてホームページが必要かどうかは、目的によって大きく変わります。
一般家庭からの新規案件獲得、採用活動、自社情報の認知拡大を目指す場合は、ホームページが必須のツールです。
特に採用においては、求職者が企業の信頼性や働きがいを重視するため、ハローワークや求人サイトだけでは伝えきれない情報を発信できるホームページが重要となります。
一方で、既存の企業間取引が中心で、新たな顧客獲得を目的としない場合は、必要性が低いこともあります。
ホームページ作成方法は、無料サービス、自作、有料簡易サービス、制作会社への依頼と多岐にわたり、予算やスキルに応じて選択することが可能です。
目的を明確にし、自社に最適な方法でホームページを制作・運用することが成功への鍵です。
建設業のホームページに関するよくある質問
建設業でもホームページは作るべきですか?
A. 目的によって異なります。
既存の元請け・下請けとの取引が中心なら、今すぐ困るケースは少ないです。
ただし、採用・信用性・個人客からの問い合わせなどを強化したい場合は、ホームページが大きな役割を果たすため、作成をおすすめします。
BtoBでもホームページは役に立ちますか?
A. 直接問い合わせは少ないものの、信用確認の場面では必須です。
企業の担当者は社名検索を行うため、情報が出てこないと「実態が分からない会社」と見なされ、取引に不利になる可能性があります。
採用目的ならホームページは必要ですか?
A. 必須です。
求職者・親御さん・学校の担当者は必ずネット検索をします。
会社の雰囲気・仕事内容・社員の様子など、求人票だけでは伝えられない情報を補えるため、応募率が大きく変わります。
Q4. 個人客(一般家庭)向けの工事は、ホームページがないと不利ですか?
A. はい。ほぼ必須です。
個人のお客様は、まず「ネット検索」が基本のため、ホームページがないと候補に入りにくくなります。
施工事例や料金目安を載せることで問い合わせにつながりやすくなります。
Q5. ホームページを作るとしたら、どの方法がおすすめですか?
A. 目的と予算で選ぶのがおすすめです。
・信用目的だけ:無料サービス(Googleサイトなど)
・費用を抑えて自作:WordPress
・簡単・早く作りたい:ペライチなどの簡易サービス
・採用・集客を本格化したい:制作会社へ依頼
自社の目的に合った方法を選ぶことで、ムダな費用や手間を避けられます。
独立って何から始めればいい?経営者になるための教科書公開中
「とりあえず独立したけど、営業や経営は初めてで手探り状態…」
そんな独立1〜3年目の水道工事業の社長に向けて、仕事を安定させる前段階から役立つ情報をまとめたページをご用意しました。
このページでは、
- まず何を準備すればいいか
- お客様をどう見つけ、どう信頼を得るか
- 少しずつ仕事を増やしていく方法
など、職人から経営者へとステップアップするための具体的なヒントを解説しています。
独立したてで「これからどう動けばいいか」に悩んでいる方はぜひご覧ください。
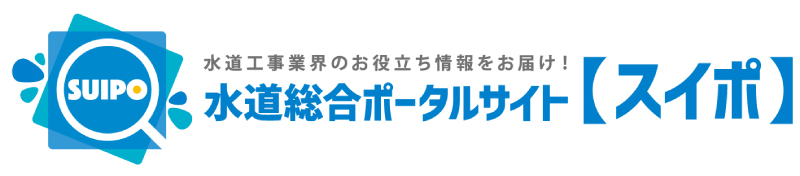



\【スイポ】サイトへのご意見募集してます/ 「こんなこと知りたい」、「ここが使いにくい」などの貴重なご意見を募集しております。