はじめに~ 忙しいのにお金が残らない…その原因、粗利率かもしれません
「毎日現場に出て頑張ってるのに、月末になるとお金が残らない。なんでだろう?」
独立して1〜3年目の水道工事業の社長さんから、よくこんな声を聞きます。
実はその原因、受けている仕事の「粗利率」にあるかもしれません。
粗利率とは、売上から直接かかった原価(材料費や外注費など)を引いた「粗利」が、売上に対してどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。
この粗利率を意識せずに仕事を受けていると、いくら忙しくても手元にお金が残らない状況に陥りがちです。
この記事では、粗利率の基本から、仕事を選ぶ際の判断基準、実際の計算方法、さらに粗利率改善の実践例までをわかりやすく解説します。
粗利率とは?職人社長が知っておくべき基本
粗利率は、以下の式で求められます:
粗利率(%)=(売上 − 原価)÷ 売上 × 100
例えば、ある工事で売上が100万円、原価が70万円だった場合:
粗利=100万円 − 70万円 = 30万円
粗利率=30万円 ÷ 100万円 × 100 = 30%
この30%が高いのか低いのかは、業種や業態によって異なりますが、水道工事業では一般的に30〜40%が目安とされています。
粗利率が高ければ高いほど、会社に残るお金が多くなり、経営が安定しやすくなります。
特に個人事業主や小規模な工事店の場合、粗利率が経営の命綱とも言えます。資金繰りに直結し、月末の支払いに頭を抱えなくて済むようになるためにも、この数字の重要性をしっかり理解しておきましょう。
なぜ粗利率が重要なのか?数字が語る経営のリアル
粗利率を意識することで、以下のような経営判断が可能になります:
- 利益の出る仕事かどうかを見極められる
- 価格交渉やコスト削減の必要性を判断できる
- 将来的な資金繰りや投資計画を立てやすくなる
- 忙しさ=儲かる という錯覚から脱却できる
例えば、粗利率が20%の仕事と40%の仕事があった場合、同じ売上でも手元に残るお金が倍違います。
この差が積み重なると、1年後、3年後の経営状況に大きな差が生まれます。
また、粗利率が低い仕事ばかりを抱えると、忙しい割に利益が出ず、スタッフの疲弊やモチベーション低下にもつながります。
つまり、粗利率を高めることは、経営者の財布だけでなく、会社全体の健康状態を守ることにも直結しているのです。
粗利率で仕事を選ぶ:実践的な判断基準
仕事を受ける際には、以下のポイントをチェックしましょう:
- 原価の把握:材料費、外注費、交通費など、直接かかる費用を正確に見積もる。
- 売上の見込み:工事の規模や内容から、適正な売上を設定する。
- 粗利の計算:売上から原価を引いた粗利を計算し、粗利率を求める。
- 目標との比較:自社の目標粗利率(例:35%)と比較し、受注の可否を判断する。
- リスクの評価:工期の遅延や追加工事リスクなども含めて採算をシミュレーション。
このプロセスを習慣化することで、利益の出る仕事を選びやすくなります。
また、仕事を断る勇気を持つことも大切です。粗利率が明らかに低い案件は、将来の赤字リスクを抱える可能性があるため、短期的な売上にとらわれず、長期的な視点で判断しましょう。
実例:粗利率を意識した仕事選びの成功事例
ある独立2年目の水道工事業の社長さんは、粗利率を意識するようになってから、以下のような変化がありました:
- 以前:とにかく受注を優先し、粗利率20%以下の仕事も多く受けていた。
- 現在:粗利率30%以上を目安に仕事を選ぶようにし、売上は変わらずとも利益が増加。
具体的には、見積り時点でExcelを活用して原価を細かく見積もり、粗利率が基準に満たない案件は値上げ交渉を行うようにしたとのこと。
結果として、1件あたりの利益が増えただけでなく、時間的余裕もでき、社員の残業も減少。お客様対応にも余裕が生まれ、リピート受注率も向上しました。
粗利率を簡単に計算する方法:Excelテンプレートの活用
粗利率の計算を手間なく行うために、Excelテンプレートを活用しましょう。
以下のようなテンプレートを作成すると便利です:
- 入力項目:売上、材料費、外注費、交通費など
- 自動計算:粗利、粗利率を自動で算出
- 比較機能:複数の案件を比較できる
- 条件付き書式:粗利率が目標に満たない場合は色分け表示
このテンプレートを使えば、見積り段階で粗利率を確認し、受注判断がスムーズになります。
また、過去の案件を記録しておくことで、「どの案件がどれくらい利益を生んだのか」「どの得意先は単価が安くなりがちか」などの分析にもつながります。
粗利率を改善するには?現場視点からできる工夫
もし現状の粗利率が低い場合、どのように改善すればよいのでしょうか。 以下のような工夫が有効です:
- 材料の仕入れ先を見直す:同じ材料でも、仕入れルートや数量割引で原価を下げられる。
- 外注費の見直し:協力業者との単価交渉や定期的な見直しを行う。
- 工期の短縮化:段取りや職人の配置を工夫し、稼働日数を減らすことで人件費を削減。
- 業務の効率化:現場調査や見積もり作成の標準化、ツール導入による業務の自動化。
これらの取り組みは、地道ではありますが、着実に粗利率改善に寄与します。自社で取り組めるところから一歩ずつ着手してみましょう。
まとめ:粗利率を味方に、賢い経営を目指そう
粗利率を意識することで、仕事の選び方が変わり、経営の安定化につながります。
最初は難しく感じるかもしれませんが、習慣化すれば自然と身につきます。
「高粗利の仕事=いい仕事」ではありませんが、「粗利率が低い=危険信号」と捉えることで、健全な経営判断ができるようになります。
自社の利益を守るためにも、今日から粗利率をチェックする習慣をはじめましょう。
水道工事と粗利率のよくある質問
Q1. 粗利率はどれくらいを目安にすればいいですか?
A1. 水道工事業では、一般的に粗利率30〜40%が目安とされています。30%を下回ると資金繰りが厳しくなりやすいため、見積りや受注判断の際は粗利率を必ず確認することが重要です。
Q2. 忙しいのに利益が残らないのはなぜですか?
A2. 粗利率が低い仕事を多く抱えていることが原因の一つです。売上があっても原価が高いと手元にお金が残らず、結果的に「働いても儲からない」状態になります。受注の段階で粗利率を計算し、低い案件は見直す必要があります。
Q3. 粗利率を改善するにはどうすればいいですか?
A3. 材料の仕入れルートの見直しや外注費の交渉、工期の短縮、業務の効率化などが効果的です。小さな工夫を積み重ねることで、着実に粗利率を改善し、経営の安定につながります。
独立って何から始めればいい?経営者になるための教科書公開中
「とりあえず独立したけど、営業や経営は初めてで手探り状態…」
そんな独立1〜3年目の水道工事業の社長に向けて、仕事を安定させる前段階から役立つ情報をまとめたページをご用意しました。
このページでは、
- まず何を準備すればいいか
- お客様をどう見つけ、どう信頼を得るか
- 少しずつ仕事を増やしていく方法
など、職人から経営者へとステップアップするための具体的なヒントを解説しています。
独立したてで「これからどう動けばいいか」に悩んでいる方はぜひご覧ください。
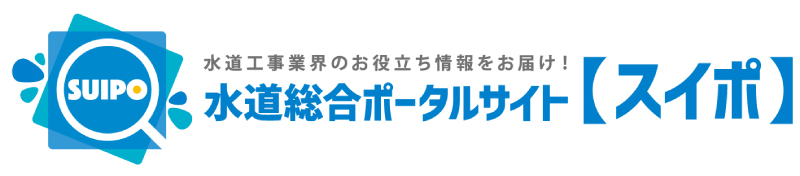



\【スイポ】サイトへのご意見募集してます/ 「こんなこと知りたい」、「ここが使いにくい」などの貴重なご意見を募集しております。