新規案件の獲得に追われ、ふと「もっとリピートのお客様を増やせないだろうか?」と考えていませんか?
お客様に喜んでもらえれば、自然とリピートや紹介が増えるはずだと感じつつも、具体的に何をすれば良いのか、どのようにすればお客様が真に満足してくれるのか、明確な答えが見つからずお困りではないでしょうか。
この記事では、建設業における顧客満足度向上がなぜ重要なのか、そしてどのようにすれば顧客満足度を高め、リピートに繋げられるのかを具体的な方法と共にご紹介します。
この記事を読めば、価格競争に巻き込まれることなく、お客様から選ばれ続ける会社になるための具体的なヒントが得られるでしょう。
原価高騰で価格以外の価値が経営の生命線になっている時代
近年、建設業界では、材料費の高騰が著しく、ウッドショックやアイアンショックに代表されるように、木材や鉄鋼製品の価格が大幅に上昇しています。
これに加えて、燃料価格の高騰は輸送費に直結し、工事現場への資材運搬コストを押し上げています。
さらに、建設技能労働者の高齢化と人手不足は、人件費の上昇を招き、外注費も増加の一途を辿っています。
これらの原価高騰は、元請け企業だけでなく、下請け企業においても深刻な影響を与えており、多くの建設会社が利益率の圧迫という“板挟み”状態に陥っています。
このような状況下で、価格競争に終止符を打つことが急務となっています。
もはや「値下げ」だけでは企業経営を維持することが難しくなり、限界を迎えています。
だからこそ、価格以外の要素で顧客に選ばれる会社こそが、今後も成長し続けることができるのです。
つまり、新規案件を追い求めるばかりでリピートが少ない会社は危険信号と捉えるべきでしょう。
本記事の結論として、激化する競争環境において唯一の安定策は、「顧客満足の仕組み化」にあると言えます。
建設業における「顧客満足」とは?
建設業における顧客満足とは、顧客が抱いていた「期待」と、実際に体験した「実際の体験」との間に生じるギャップの大小によって決まります。
具体的には、工事の品質が高いことはもちろん重要ですが、それだけでは十分ではありません。
顧客満足は、契約前の打ち合わせから始まり、施工中の進捗報告、そして引き渡し後のアフターサポートに至るまで、顧客が建設会社と関わるすべてのプロセスが評価対象となります。
例えば、契約前の見積もり提示が迅速であったか、施工中の現場が常に整理整頓されていたか、引き渡し後の不具合に対して誠実に対応してくれたかなど、あらゆる局面での対応が顧客の心象を左右するのです。
顧客が本当に求めているのは、工事品質という“モノ”だけでなく、それを通じて得られる“安心”や“信頼”といった感情です。
顧客満足は、一度の「感動」よりも、むしろ顧客が抱く「不安」を取り除き、「安心」と「信頼」を地道に積み重ねていくことで築かれるものと言えるでしょう。
このような顧客管理の徹底が、最終的に顧客からの信頼を厚くし、リピートや紹介へと繋がるのです。
なぜ今、顧客満足が経営に直結するのか?
現代の建設業において、顧客満足の向上は単なるサービス向上以上の意味を持ちます。
それは企業の存続と成長に直結する重要な経営戦略であり、主に3つの理由からその重要性が高まっているのです。
原価高騰が続く中で、価格競争に頼らない経営を実現するためには、顧客満足を追求し、顧客から選ばれ続ける企業になることが不可欠と言えるでしょう。
理由1:値上げしても納得感を持ってもらえる会社の条件
顧客が「この会社なら任せても大丈夫」と信頼を寄せるためには、日々の積み重ねが重要です。
価格だけで他社と比較されてしまうと、利益が減少し、結果として会社の存続が危ぶまれる可能性があります。
顧客が最終的に判断するのは、会社の規模や実績だけではなく、担当者の人柄や誠実な対応、そして提供されるサービスに対する安心感です。
これらの要素が充実している会社こそが、価格を値上げしても顧客からの納得と支持を得られる条件を備えていると言えるでしょう。
理由2:薄利の時代ほどリピート・紹介が利益の源泉
原価高騰が続く時代において、新規顧客の獲得にかかるコストは、既存顧客の維持と比較して高くなる傾向があると言われています。
複数の情報源によると、新規顧客獲得にかかるコストは、既存顧客を維持するコストの約5倍であるとされています。
そのため、安定した利益を確保し、経営を盤石なものにするためには、いかに既存顧客との関係を強化し、リピートや紹介を増やしていくかが重要です。
顧客満足度を高めることは、価格競争から抜け出し、価格以外の価値で選ばれる企業になるための現実的な方法の一つです。
顧客が満足すれば、自然とリピートや紹介が増え、結果として新規獲得コストを抑えながら利益の最大化に繋がります。
理由3:どの会社も価格が上がっている今、差別化は「対応品質」
どの建設会社も価格高騰の影響を受けている今、価格だけで差別化を図ることは非常に困難です。
そのため、顧客からの信頼と満足を得るためには、「対応品質」が重要な差別化要因となります。
具体的には、顧客への説明を丁寧に行い、現場での細やかな対応を心がけ、引き渡し後のアフターフォローを充実させることが不可欠です。
これらの対応は、直接的なコストをほとんどかけずに実施できるにもかかわらず、顧客からの評価を大きく向上させ、結果としてリピートや紹介に繋がりやすいという大きな効果が期待できます。
顧客が建設会社に本当に求めている金額以外の価値
建設会社に工事を依頼する顧客は、単に工事が完成することだけでなく、そのプロセス全体を通して「安心感」や「信頼」を求めています。
例えば、丁寧で分かりやすい説明は、工事内容への理解を深め、不安を軽減するものです。
また、工事の進捗状況が写真や動画、報告書などで透明性を持って共有されることで、顧客はいつでも状況を把握でき、精神的な安定に繋がります。
連絡の早さも重要で、疑問や不安が生じた際に迅速な返答があれば、顧客は「大切に扱われている」と感じるでしょう。
さらに、現場の清潔感や近隣への配慮は、建設会社のプロ意識を示すとともに、顧客の日常生活への影響を最小限に抑えることになります。
万一、トラブルが発生した際にも、迅速かつ正直な報告と対応があれば、顧客は会社への信頼を失うことなく、むしろ誠実さを評価します。
引き渡し後のきめ細やかなフォローも、長期的な安心感を提供し、顧客が価格以上に「安心感」と「信頼」を重視していることが伺えます。
今日からできる!建設業の顧客満足の具体的な実践策
建設業における顧客満足度を高める具体的な実践策は、契約前、施工中、引き渡し後の3つのフェーズに分けて考えることが重要です。
それぞれの段階で顧客の期待を上回り、安心と信頼を提供することで、リピートや紹介へと繋がるでしょう。
今日から実践できる具体的なステップを、次の項目から詳しく解説していきます。
契約前
契約前における顧客満足度向上の鍵は、顧客の不安を解消し、期待値を適切に調整することです。
まず、顧客がどのような点に不安を感じているのかを把握するために、事前ヒアリングの型化を進めましょう。
例えば、「以前の工事で不満だった点はありますか?」や「今回の工事で特に気になっていることは何ですか?」といった質問テンプレートを用意することで、潜在的な不安要素を早期に引き出すことができます。
次に、期待値のすり合わせシートを活用し、工事の範囲、期間、予算、品質基準などを顧客と詳細に確認し、書面で共有することで、認識のズレを防ぎます。
特に、建設業では図面や見積もりが専門的で分かりにくいと感じる顧客も少なくありません。
そこで、素人にも理解できるよう、パース図や3Dモデルの活用、専門用語を避けた説明、写真付きの資料などを用いて、視覚的に分かりやすく提示することが重要です。
また、原価高騰による値上げが避けられない場合でも、その理由を丁寧に説明するためのテンプレートを用意しましょう。
例えば、「資材の高騰」だけでなく、「具体的にどの資材が、なぜ、どの程度上がっているのか」を明確に伝えることで、顧客は納得感を得やすくなります。
これらの取り組みは、顧客との信頼関係を構築し、トラブルを未然に防ぐだけでなく、最終的な顧客満足度を大きく向上させることに繋がるでしょう。
施工中
施工中の顧客満足度を高めるためには、透明性の確保とコミュニケーションの最適化が不可欠です。
まず、進捗報告のルール化を徹底しましょう。
具体的には、週に1回の頻度で、工事の進捗状況を写真や動画を用いて報告します。
その際、「どこを、どのように進めているのか」「今後の工程はどうなるのか」を具体的に説明し、顧客が工事の全体像を把握できるように努めます。
写真の基準としては、作業前後の比較がわかるアングルや、特に変化があった箇所のクローズアップなどを設定し、顧客が変化を実感できるよう工夫することが重要です。
次に、連絡レスポンスの基準化も欠かせません。例えば、「問い合わせには24時間以内に必ず返信する」といった明確なルールを設け、顧客の不安を速やかに解消する体制を整えます。
連絡手段も、電話だけでなく、メールやチャットアプリなど、顧客が利用しやすい方法を複数用意すると良いでしょう。
現場の“見える化”アプリの活用も有効な手段です。クラウド型の施工管理アプリを導入することで、顧客は自身のスマートフォンからいつでも工事の進捗状況や写真を確認でき、安心感に繋がります。
また、現場清掃・整理整頓のルールを明確にし、朝礼時に徹底を促すことで、常に清潔で安全な現場を維持することも重要です。
例えば、「作業終了時には必ず工具を片付け、ゴミは分別して廃棄する」といった具体的な行動規範を定めます。
さらに、近隣挨拶マニュアルを作成し、工事着工前と完了後に丁寧な挨拶を実施することで、近隣住民とのトラブルを未然に防ぎ、顧客の心配事を減らすことができます。
万が一トラブルが発生した際には、説明テンプレートを活用し、迅速かつ誠実に状況を説明し、今後の対応策を提示することで、顧客からの信頼を損なうことなく、むしろ誠実な対応として評価に繋がるでしょう。
引き渡し後
引き渡し後の顧客満足度を高めるためには、定期的なアフターフォローと、顧客の声を収集する仕組みが不可欠です。まず、引き渡し後1ヶ月、6ヶ月、1年といった節目で定期点検を仕組み化し、顧客宅を訪問することで、施工後の不具合を早期に発見し、対応することができます。
また、定期的に電話やLINEで顧客の状態を伺うことで、小さな不具合や疑問点も気軽に相談できる関係性を築き、顧客の不安を解消します。小さな不具合は迅速に対応できるよう、対応基準を明確に定め、顧客が不満を抱く前に解決できる体制を整えましょう。
さらに、満足度アンケートなどを活用して顧客の声を定期的に収集し、サービス改善に繋げることも重要です。
これらの取り組みを通じて、顧客が自然と口コミや紹介をしてくれるような導線づくりを進めることで、長期的な顧客との関係を構築し、会社のファンを増やしていくことができます。
顧客満足を仕組み化して誰でも同じ品質を提供する方法
顧客満足を仕組み化するためには、まず業務フローに顧客対応の品質基準を組み込むことが不可欠です。
担当者個人のスキルや経験に依存する属人化を排除し、誰が対応しても一定以上の品質を提供できる体制を構築します。
具体的には、問い合わせ対応から見積もり作成、現場での作業、引き渡し後のアフターフォローに至るまで、各プロセスにおける顧客対応の共通ルールを明確に定めます。
例えば、「お客様からの問い合わせには〇時間以内に一次回答を行う」「現場作業前には必ず近隣の方へご挨拶に伺う」といった具体的な行動指針をマニュアル化し、全従業員に周知徹底させることが重要です。
さらに、顧客満足度を向上させるためのPDCAサイクルを定期的に回す仕組みも不可欠です。
例えば、顧客満足度アンケートを定期的に実施し、結果を分析することで、改善点や課題を洗い出します。
特に、クレームが発生した際には、単なる個別対応で終わらせるのではなく、クレーム内容を詳細に分析し、その原因を特定することが重要です。再発防止策を立案し、業務フローや共通ルールに反映させることで、同様のクレームが二度と発生しないよう仕組みを改善していくのです。
また、DX(デジタルトランスフォーメーション)を活用して顧客満足度を向上させることも有効です。
例えば、工事の進捗状況を顧客とリアルタイムで共有できる写真共有ツールや、迅速なコミュニケーションを可能にするチャットツールを導入します。
工程管理システムを活用すれば、顧客はいつでも工事の進捗を確認でき、安心感に繋がります。
これにより、電話やメールでのやり取りの手間が省け、顧客も会社側も効率的に情報を共有できるようになります。
一方で、過剰なサービスは会社の負担を増やすだけでなく、顧客の期待値を過剰に高めてしまい、結果的に満足度を下げる可能性もあります。
そのため、サービス範囲を明確に線引きし、顧客に提供できる価値とできない価値を事前に明確に伝えることが重要です。
例えば、「標準工事に含まれる範囲」と「追加費用が発生するオプション」を具体的に提示し、顧客が納得した上で契約を進めるようにします。
このように、適切なサービスレベルを設定し、それを安定的に提供できる仕組みを構築することで、過剰サービスを避けながらも顧客満足度を最大化し、長期的な信頼関係を築くことができるでしょう。
原価高騰の時代でも選ばれ続ける会社になる顧客満足モデル
顧客満足モデルの構築は、原価高騰が続く現代において、建設会社が選ばれ続けるための重要な戦略です。
このモデルは、顧客の不安や期待を明確に把握し、それに応えるための具体的な行動を体系化することで成り立ちます。
まず、ステップ1として、事前ヒアリングやアンケートを通じて、顧客が抱える漠然とした不安や、工事に対する具体的な期待を徹底的に可視化することが重要です。
例えば、「過去の工事で嫌だったことは何か」「今回の工事で特に重視したい点は何か」といった質問で顧客の本音を引き出します。
次に、ステップ2では、現場の「見える化」と丁寧なコミュニケーションを徹底します。工事の進捗状況を写真や動画で定期的に報告したり、質問には迅速かつ分かりやすく回答したりすることで、顧客は常に安心感を得られます。
ステップ3は、引き渡し後のアフターフォローで信頼を積み重ねることです。定期点検や不具合発生時の迅速な対応は、顧客との長期的な関係構築に不可欠です。
ステップ4では、これらの顧客からの声や対応事例を社内で共有し、成功体験を再現できる仕組みを構築します。
これにより、担当者ごとの対応品質のばらつきをなくし、会社全体で顧客満足度を高めることが可能になります。
最終的にステップ5では、このような一連の取り組みを通じて、顧客は価格以外の「安心」「信頼」「高品質な対応」といった価値を感じるようになります。
結果として、仮に原価高騰による値上げが必要になったとしても、顧客は会社の対応品質に納得し、他社に流れることなく、長期的な顧客として定着する可能性が高まります。
この顧客満足モデルを実践することで、建設会社は価格競争から脱却し、持続的な成長を実現できるでしょう。
まとめ:これからの建設業は“価格ではなく満足”で勝つ
建設業界では原価高騰が続く今、価格競争に陥らず顧客に選ばれ続けるためには、顧客満足度の向上が不可欠です。
顧客が本当に求めているのは、工事品質だけでなく、安心や信頼、対応品質といった価格以外の価値だからです。
契約前の丁寧なヒアリングから、施工中の透明性の高い情報共有、引き渡し後のきめ細やかなアフターフォローまで、顧客とのあらゆる接点において満足度を高める取り組みを仕組み化することが重要です。
これにより、値上げが必要な場合でも顧客は納得し、リピートや紹介へと繋がります。価格ではなく「顧客満足」で選ばれる会社こそが、これからの建設業界で勝ち残るための鍵となるでしょう。
建設業の顧客満足に関するよくある質問
Q1. 顧客満足を高めると言われても、まず何から始めれば良いですか?
A. まずは「顧客の不安を把握すること」から始めるのが最も効果的です。
建設業の顧客は、工事が問題なく進むかどうかに不安を感じています。
そのため、事前ヒアリング(不安・要望を聞き出す)→期待値のすり合わせ を行うだけでも、満足度は大きく向上します。
難しいことをいきなりやる必要はなく、
・過去の不満点
・今回の工事で最も心配な点
を聞くだけでも十分スタートになります。
Q2. 工事品質に自信があれば、顧客満足は自然に上がるのでは?
A. 品質だけではリピートにはつながりません。
顧客が評価しているのは「モノの品質」だけでなく、
・説明の分かりやすさ
・進捗報告の丁寧さ
・連絡の早さ
・アフターフォロー
といった “対応品質” です。
実際、建設業でクレームに発展する多くの原因は品質ではなく、コミュニケーション不足から生じる不安 です。
Q3. 進捗報告はどれくらいの頻度で行うべきですか?
A. 週1回程度の「定期報告」が最も効果的です。
毎日の報告は逆に負担が大きくなりますが、週1回の
・写真つき進捗
・翌週の予定
があるだけで、顧客の安心感は劇的に高まります。
報告の“形式を統一”しておくと、担当者が変わっても品質が安定します。
Q4. 値上げの説明が苦手で、納得してもらえる気がしません…どうすればいい?
A. 値上げの「理由」を丁寧に伝えれば、多くの顧客は納得します。
ポイントは、“抽象的な説明ではなく、具体的な根拠” を示すことです。
例)
・木材価格が○%上がっている
・仕入れ先の値上げ通知
・鉄鋼価格の推移
など、理由を明確に伝えることで「誠実な会社」だと感じてもらえます。
値上げで揉める会社の多くは、値上げそのものではなく、説明不足による不信感 が原因です。
Q5. 顧客満足を“属人化”させず、会社として仕組み化するには?
A. 各工程ごとに「やるべき対応」をルール化することが必要です。
例えば、
・問い合わせは○時間以内に一次回答
・進捗報告は週1回、テンプレート化
・現場清掃の基準を明確化
・引き渡し後の定期点検をスケジュール化
など、誰が担当しても同じ品質で提供できるようになります。
属人化がなくなるほど、顧客満足は安定し、リピート率も向上します。
Q6. 顧客満足度を高めると、本当にリピートが増えるの?
A. ほとんどの建設会社で、リピート・紹介が利益の大部分を占めています。
特に原価高騰が続く今、新規顧客だけに頼る経営は非常に危険です。
顧客は「安心」「信頼」「丁寧な対応」を提供する会社を選び、そうした会社に仕事を頼み続けます。
顧客満足は、短期的な売上ではなく、長期的な“選ばれる仕組み”を作るための経営戦略 なのです。
独立って何から始めればいい?経営者になるための教科書公開中
「とりあえず独立したけど、営業や経営は初めてで手探り状態…」
そんな独立1〜3年目の水道工事業の社長に向けて、仕事を安定させる前段階から役立つ情報をまとめたページをご用意しました。
このページでは、
- まず何を準備すればいいか
- お客様をどう見つけ、どう信頼を得るか
- 少しずつ仕事を増やしていく方法
など、職人から経営者へとステップアップするための具体的なヒントを解説しています。
独立したてで「これからどう動けばいいか」に悩んでいる方はぜひご覧ください。
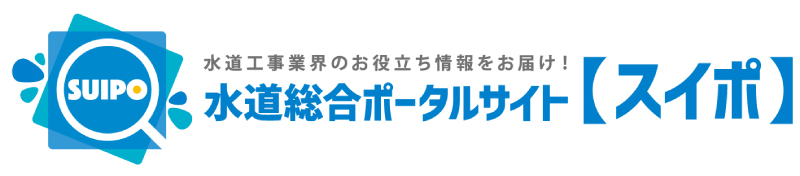



\【スイポ】サイトへのご意見募集してます/ 「こんなこと知りたい」、「ここが使いにくい」などの貴重なご意見を募集しております。